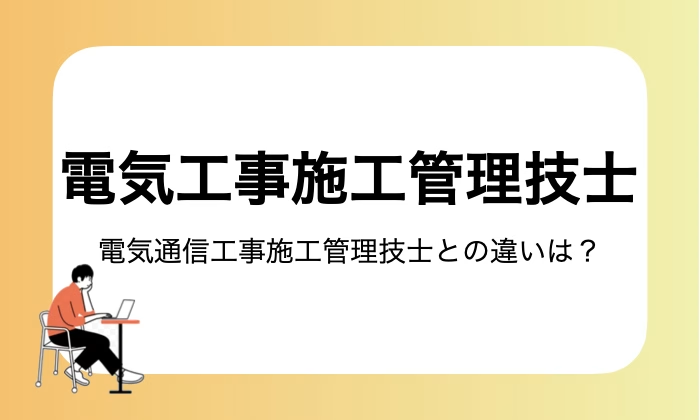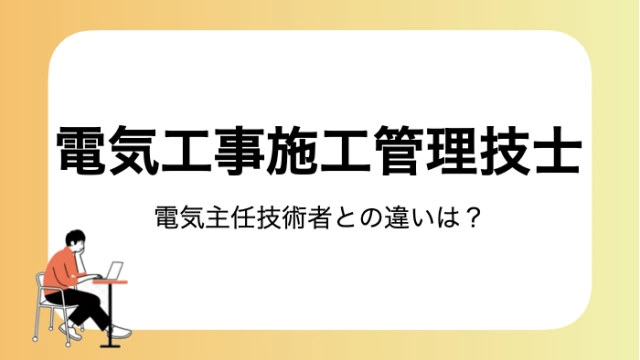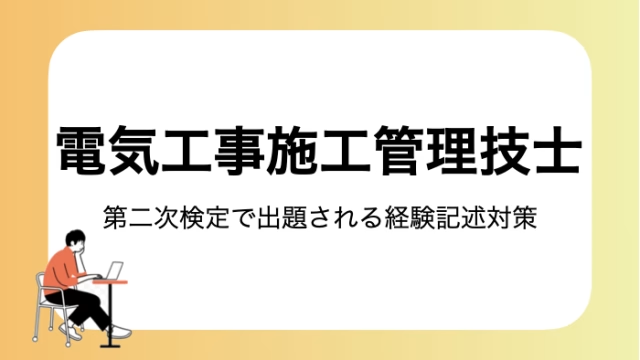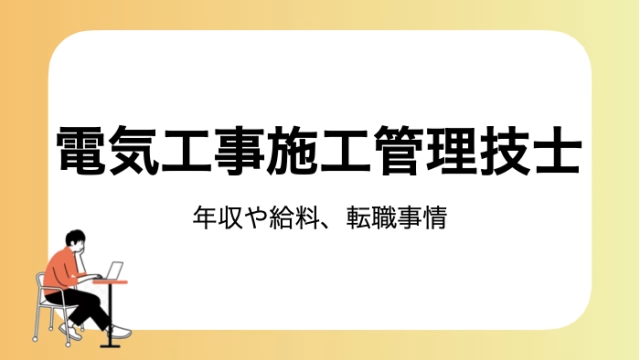「電気工事施工管理技士と電気通信工事施工管理技士、何がどう違うのか分からない…」ということはありませんか?
似た名前の資格でも、実は扱う工事の内容や将来のキャリアに大きな違いがあります。
そこで、今回は電気工事施工管理技士と電気通信工事施工管理技士の違いについて解説します。
この記事を読めば仕事内容・試験内容・活躍できる業界などの違いと、自分に合った資格の選び方がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
取り扱う工事の違い
電気工事施工管理技士と電気通信工事施工管理技士は、どちらも工事の「施工管理」を担う国家資格ですが、扱う工事の内容には明確な違いがあります。
ここでは、それぞれが対象とする工事の分野を具体的に解説します。
電気工事:照明・送電・構内設備など高電圧領域
電気工事施工管理技士が扱うのは、主に電気設備に関する工事で、比較的高電圧の電力を取り扱う領域です。
たとえば、送電線・変電設備・照明設備・コンセント配線・受変電設備・構内電気設備などが該当します。
これらは建物やインフラにとって不可欠な基礎工事であり、安全性や法令遵守が重視される分野です。
また、住宅やビルだけでなく、工場・プラント・公共施設など、多様な建築物の電力供給に関わる工事が中心となります。
特に「電気工事士」の資格とも関連が深く、実務経験を積みながら管理者としてキャリアアップしていくケースが多いのも特徴です。
以下は代表的な電気工事の例です。
| 工事種別 | 内容例 |
| 照明設備工事 | 室内外の照明器具・照明回路の設置 |
| 送電設備工事 | 高圧電線や変電所に関する配線・設置 |
| 受変電設備工事 | 受電設備や変圧器などの構築・点検 |
| 構内電気設備工事 | コンセント、配電盤、スイッチ類の配線工事 |
高電圧を扱う工事であることから、感電や火災などのリスク管理も重要であり、施工管理者の知識と責任が問われる場面が多くあります。
電気通信工事:通信・情報制御・LAN工事など低電圧領域
一方、電気通信工事施工管理技士は、主に「情報のやり取り」に関する設備工事を取り扱います。
こちらは低電圧で動作する設備が中心であり、電話回線・インターネット配線・LANケーブル・防犯カメラ・センサー類・放送設備などが含まれます。
IoT化やスマートビルの普及に伴い、電気通信工事の需要は年々増加しており、特にネットワーク構築や自動制御装置の設置といった「情報インフラ」を支える工事が主軸となっています。
高度な情報技術との接点が多いため、ITやデジタルに関する知識も求められる傾向があります。
以下に、電気通信工事の主な例を示します。
| 工事種別 | 内容例 |
| LAN配線工事 | オフィスや施設内のネットワークケーブルの敷設 |
| 防犯設備工事 | 監視カメラやセンサーの設置、制御システムの構築 |
| 情報通信工事 | 電話・インターホン・インターネット関連の設備施工 |
| 放送設備工事 | 校内放送・館内放送・非常用放送設備などの設置 |
このように、電気通信工事は情報伝達を支える設備に特化しており、日常生活やビジネスに欠かせない通信環境の整備に直結しています。
高電圧を扱う電気工事とは異なり、繊細かつスピーディーな対応が求められる点も特徴です。
試験範囲と内容の違い
電気工事施工管理技士と電気通信工事施工管理技士では、試験の等級構成は似ていても、その内容や出題傾向には大きな違いがあります。
ここでは1級・2級それぞれの試験科目と出題形式、学習内容の特徴について詳しく比較します。
各資格の1級・2級それぞれの試験科目を簡潔に比較
電気工事施工管理技士と電気通信工事施工管理技士の試験は、それぞれ1級と2級に分かれており、共通する項目もある一方で専門分野に応じた出題内容の違いが見られます。
まず、両資格とも1級・2級ともに【学科試験】と【実地試験】の2部構成ですが、学科試験においては「施工管理法」「法規」などの共通科目が存在します。
ただし、専門的な内容には違いがあり、電気工事施工管理技士では高圧受変電設備や配線図、電力系統の知識が問われるのに対し、電気通信工事施工管理技士ではネットワーク構築、伝送設備、電波の基礎などが中心です。
以下に各資格の主な試験科目をまとめた比較表を示します。
| 資格名/等級 | 主な試験科目(学科) |
| 電気工事施工管理技士(1級・2級) | 施工管理法/法規/電気設備一般/電力工学/電気理論など |
| 電気通信工事施工管理技士(1級・2級) | 施工管理法/法規/情報通信工学/ネットワーク技術/電波伝搬など |
実地試験では、工事経験記述や施工の工程、安全管理、品質管理に関する記述式問題が出題されますが、こちらも扱う工事内容に応じて求められる知識・表現に違いがあります。
試験形式(選択・記述)や学習内容の傾向も解説
試験形式については、どちらの資格も学科試験は選択式(マークシート)、実地試験は記述式となっており、大枠の形式は共通しています。
しかし、学習のアプローチには明確な違いがあります。電気工事施工管理技士の試験では、「電気理論」「計算問題(電圧・電流・抵抗など)」が多く出題され、電験三種や第二種電気工事士などで学んだ基礎知識が土台として役立ちます。
そのため、理系寄りの知識と工事管理の両方をバランスよく学ぶ必要があります。
一方、電気通信工事施工管理技士では、情報通信分野の用語やネットワーク構成の理解、電波・信号に関する知識が重要です。LAN配線や無線LAN、映像配信システムなど、よりIT寄りの知識が問われるため、理系というよりは情報系の勉強が多くなるのが特徴です。
また、実地試験における工事経験記述の内容も異なり、電気工事では「高圧受電設備の施工管理」、電気通信工事では「通信ケーブル敷設や無線中継設備の設置管理」など、専門領域に応じた経験と記述力が求められます。
このように、同じ「施工管理技士」でも、試験内容や勉強方法には資格ごとの特性があるため、受験前に自分の適性や業務分野を踏まえて選ぶことが重要です。
合格率と難易度の違い
電気工事施工管理技士と電気通信工事施工管理技士では、合格率や難易度にも違いがあります。
特に、電気通信工事施工管理技士は比較的新しい資格であるため、受験者側にとって不透明な部分も多くあります。
ここでは過去5年間の合格率と難易度について比較・解説します。
過去5年の平均合格率を比較
電気工事施工管理技士の合格率は、1級・2級ともに長年の実績があるため、統計データが豊富に揃っています。
過去5年の平均合格率を見ると、以下のようになります。
| 資格・等級 | 学科試験 合格率(平均) | 実地試験 合格率(平均) |
| 電気工事施工管理技士(1級) | 約55〜65% | 約30〜40% |
| 電気工事施工管理技士(2級) | 約60〜70% | 約35〜45% |
これに対して、電気通信工事施工管理技士は2021年度に創設された新資格のため、まだ合格率の推移が安定しておらず、年によってばらつきがあります。
初年度は受験者数が少ないことも影響し、想定よりもやや高めの合格率が記録されましたが、現在では徐々に難易度が調整されつつある状況です。
特に注意すべきは、実地試験の記述対策であり、実務経験や論理的な記述能力が問われる点は、どちらの資格にも共通する難所といえるでしょう。
新設資格である電気通信工事施工管理技士の難しさも補足
電気通信工事施工管理技士は、2021年から国家資格として新設されたことにより、まだ受験者や教育機関のノウハウが十分に蓄積されていない点が特徴です。
そのため、試験対策教材の少なさや、過去問のデータが少ない点が受験者にとっての大きなハードルとなります。
また、電気通信工事という専門性の高い分野ゆえに、受験者が実務経験を積みにくいという実情もあります。
電気工事施工管理技士に比べ、通信インフラや情報通信ネットワークの知識、光ファイバーや映像配信設備などに関する理解が求められるため、理工系でも特に「情報・通信」寄りの素養がある方が有利です。
一方で、制度自体が新しいため試験制度が整備途上であり、過年度の受験者数が少ない年には「広く合格者を確保する傾向」も見られました。
つまり、今後は受験者の増加に伴い、合格率が下がる可能性もあるため、早めの受験が有利ともいえます。
このように、電気通信工事施工管理技士は新設資格ゆえの不透明さがある一方で、成長中の通信インフラ業界で注目されている資格でもあり、将来性という点では魅力的です。
資格取得後に得られる受験資格の違い
電気工事施工管理技士と電気通信工事施工管理技士では、資格取得後に挑戦できる上位資格やキャリアパスに明確な違いがあります。
ここでは、建築設備士などの上位資格との関係性や、今後のキャリアステップに与える影響を解説します。
建築設備士など上位資格の取得可否
まず、電気工事施工管理技士と建築設備士との関連について見ていきます。
建築設備士は、建築物の設計や監理に携わるための専門資格であり、設備系技術者の上位資格に位置づけられます。
受験資格として「電気工事施工管理技士の1級」を有することで、一定の実務経験とともに申請可能となるケースがあります。
一方、電気通信工事施工管理技士は、通信分野に特化した資格であり、現時点では建築設備士の受験資格と直接的な関連はありません。
建築設備士は建築基準法に基づく資格であるため、建築・電気・空調といった分野を包含する内容となっていますが、電気通信工事はあくまで情報・通信インフラに限定されるためです。
また、国家資格としての歴史の長さや汎用性を考慮すると、電気工事施工管理技士の方が、他の技術系国家資格への受験資格として認められやすい傾向があります。
将来的に電気通信分野においても関連資格が拡充される可能性はあるものの、現状では取得後の横展開には限界があります。
将来のキャリアステップへの影響
資格取得後のキャリア形成においても、両者には明確な違いがあります。
電気工事施工管理技士は、建築工事や公共インフラ、プラント、商業施設など幅広い現場で必要とされるため、ゼネコン・サブコン問わず多くの企業で「現場監督の登竜門」として重視されています。
また、1級取得者であれば監理技術者としての登録も可能になり、より大規模なプロジェクトに携わることができます。
さらに、一定の実務経験を積めば、技術士(電気電子部門)など高度な資格への挑戦も視野に入ってきます。
一方、電気通信工事施工管理技士は、主に通信インフラやデータセンター、放送設備、監視カメラ設置といったICT分野に特化しており、キャリアパスも通信系のSIer、施工会社、インフラ企業などに限られがちです。
専門性は高いものの、まだ業界内での資格認知度が発展途上にあるため、資格を活かすには自ら専門領域での実績を積み、キャリアを切り拓いていく姿勢が求められます。
今後の業界動向や資格制度の整備状況にもよりますが、汎用性・キャリアの広がりという点では、現時点では電気工事施工管理技士に軍配が上がると言えるでしょう。
転職先・活躍できる業界の違い
電気工事施工管理技士と電気通信工事施工管理技士では、資格取得後に活躍できる業界や企業の種類に違いがあります。
ここでは、それぞれの資格がどのような業界で重宝されているのかを具体的に解説します。
電気通信:通信会社・5G・IoT分野
電気通信工事施工管理技士は、主に低電圧領域での通信インフラの構築に関わるため、通信事業者やネットワークインフラ企業に高いニーズがあります。
とくに近年では5Gインフラの整備や、スマートシティに関連した通信網の構築、IoT機器を支えるネットワーク設備の導入において重要な役割を果たします。
これにより、NTTグループやKDDI、ソフトバンクといった大手通信会社、あるいは通信設備工事専門の中小企業において活躍する道が開けています。
また、IoT関連のシステム設計や通信機器の設置・保守といった分野でも、資格者は施工管理の専門家として評価されるケースが増えています。
今後、スマート工場・スマートホームといった分野が拡大する中で、通信インフラの需要はさらに高まり、資格保有者の転職市場価値も高まっていくと予想されます。
電気工事:ゼネコン・鉄道・官公庁関連工事
一方、電気工事施工管理技士は建築物全般の電気設備工事に関わるため、転職先としてはゼネコン(総合建設業者)や電設工事会社、鉄道会社、官公庁発注の公共工事を受託する企業などが中心です。
とくに高電圧設備や照明設備、受変電設備など、建築やインフラに直結する工事分野での需要が高く、業務範囲も広範です。
たとえば、鉄道関連の工事では駅構内の照明や自動改札機の電源工事、送電線工事なども担当でき、国家規模のインフラ整備にも関与することが可能です。
官公庁関連では、学校や病院、庁舎などの電気設備改修においても電気工事施工管理技士の資格が活かされます。
建設ラッシュが見込まれる地域や再開発が進む都市圏では特に求人数が多く、安定したキャリア形成が可能です。
| 資格名 | 主な転職先 | 主な活躍分野 |
|---|---|---|
| 電気通信工事施工管理技士 | 通信会社、ネットワーク工事会社、ITインフラ企業 | 5G整備、IoT導入、スマートシティ構築 |
| 電気工事施工管理技士 | ゼネコン、鉄道会社、官公庁工事請負企業 | 高圧電気工事、送電線設置、公共インフラ整備 |
共通点と取得するメリット
電気工事施工管理技士と電気通信工事施工管理技士は名称こそ異なりますが、どちらも国家資格であり、建設業界において重要な役割を担います。
共通する仕事内容や法的な効力、そして資格取得による実務・経営面でのメリットについて解説します。
共通する仕事内容(工程・品質・安全管理など)
両資格ともに、工事現場での施工管理が主な業務となります。
施工管理とは、工事が計画どおりに、安全かつ高品質に進められるよう管理する仕事であり、大きく「工程管理」「品質管理」「安全管理」の3つが中心です。
これらは建設業の根幹を成す業務であり、対象となる工事が異なるだけで、管理手法や対応する法律・規格には多くの共通点があります。
たとえば、工期を守るためのスケジュール管理、安全教育の実施、作業手順の見直し、工事記録の作成などは、どちらの資格保有者にも共通して求められるスキルです。
そのため、現場での実務経験が豊富な技術者ほど、どちらの資格でも活躍できる場面は多くなります。
主任技術者・監理技術者になれる点
電気工事施工管理技士と電気通信工事施工管理技士のいずれも、一定の条件を満たせば「主任技術者」または「監理技術者」として現場に配置可能です。
主任技術者は、下請契約金額が一定以上となる工事において必要なポジションであり、施工の技術的責任者として工事全体を統括します。
また、監理技術者は、元請けとして複数の下請業者に工事を発注する場合に必須となる職責であり、施工管理の高度な知識と実務経験が求められます。
いずれの資格も1級であれば監理技術者になることができ、現場での地位や収入アップにも直結するため、キャリア形成において非常に大きなメリットとなります。
経営事項審査での加点など
両資格には、経営事項審査(経審)において加点対象となるメリットもあります。
経審とは、公共工事の入札に参加するために必要な評価制度で、技術力や財務状況などを数値化して評価するものです。
施工管理技士の資格保有者が一定人数在籍していることは「技術職員数」の項目で加点され、企業の総合評価点を高める効果があります。
特に、電気・電気通信工事の元請として公共事業を受注する際には、該当分野の資格保有者が在籍しているかどうかが重要視されます。
そのため、企業側としても施工管理技士の資格者を積極的に採用・育成する動きがあり、取得者の市場価値は非常に高いといえます。
| 項目 | 電気工事施工管理技士 | 電気通信工事施工管理技士 |
|---|---|---|
| 共通業務 | 工程・品質・安全・原価管理など | |
| 主任技術者になれる | ○(対象:電気工事) | ○(対象:電気通信工事) |
| 監理技術者になれる(1級) | ○ | ○ |
| 経営事項審査での加点 | 技術職員として加点対象 | 技術職員として加点対象 |
どちらの資格を選ぶべきか?
電気工事施工管理技士と電気通信工事施工管理技士、どちらを取得すべきかは、今後のキャリアや就きたい職種によって判断が分かれます。
以下では、キャリア志向や将来性に応じた選び方を解説します。
キャリア志向・転職先の希望に応じた選び方
まず、自分がどのような業界で働きたいのかを明確にすることが重要です。
電気工事施工管理技士は、ゼネコン、建設会社、鉄道インフラ、官公庁工事など、インフラ整備に直結する仕事で活躍の場が広く、安定性を求める方に向いています。
一方、電気通信工事施工管理技士は、通信会社やIT系企業、データセンター関連など、5G・IoT・AI時代の最先端分野で求められており、技術革新に興味のある方におすすめです。
また、求人市場を見ると、電気工事施工管理技士の方が求人数が多い傾向にありますが、通信分野は今後さらに需要が拡大していく見込みです。
そのため、転職やキャリアチェンジの柔軟性を重視するなら、どちらの分野にも対応できるスキルの習得を視野に入れるのも一つの選択肢です。
将来性の観点からのアドバイス
将来的な業界の動向を踏まえると、電気通信工事施工管理技士のニーズは今後ますます高まっていくと予想されます。
理由は、5G・IoT・クラウドといった通信インフラが急拡大しており、これらの分野では通信工事の専門技術者が不足しているからです。
とくに、スマートシティや自動運転技術の発展に伴い、通信網の整備は国策レベルで推進されているため、長期的な成長が見込めます。
一方で、電気工事施工管理技士も依然として安定した需要があります。
再生可能エネルギー、スマートグリッド、高速道路や空港などの大規模インフラ工事には引き続き不可欠な存在です。
つまり、将来性という視点ではどちらの資格も活用の場はあり、自身の興味関心や働きたい分野によって選ぶのが最も合理的です。
| 選び方の視点 | 電気工事施工管理技士 | 電気通信工事施工管理技士 |
|---|---|---|
| 活躍分野 | インフラ・建築・公共工事 | 通信・IT・IoT・5G |
| 求人数の傾向 | 多い(既存需要) | 増加傾向(新規需要) |
| 将来性 | 安定志向向け | 成長志向向け |
| おすすめの人 | 公共性の高い仕事をしたい人 | ITや通信技術に関心がある人 |
まとめ
今回の記事では、電気工事施工管理技士と電気通信工事施工管理技士の違いについて解説しました。
どちらの資格も将来性がありますが、自分のキャリア志向や働きたい業界を明確にしたうえで選ぶことが大切です。
進みたい分野に合った資格を計画的に取得しましょう。
電気工事施工管理技士や電気通信工事施工管理技士は、現場を支える重要な資格です。
その一方で、
- 責任が重い割に評価が低い
- 長時間労働が常態化している
- 将来の働き方が見えない
と感じている方も少なくありません。
資格を活かしながら無理なく働く選択肢について、転職・副業の両面から無料で相談を受け付けています。