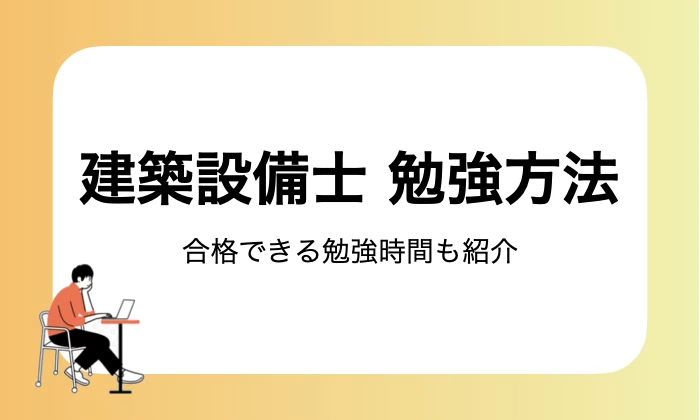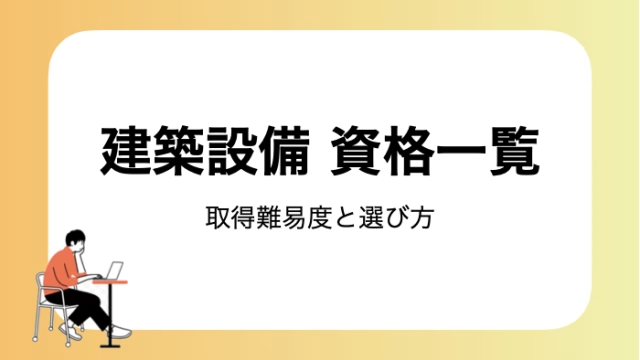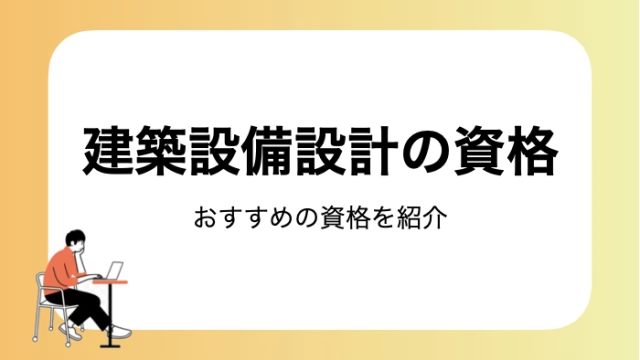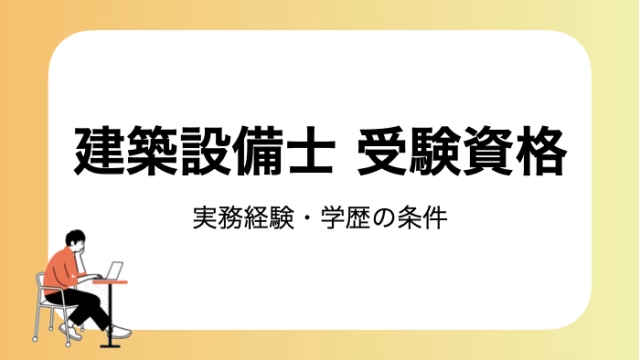「建築設備士の勉強方法がわからない」と悩んでいるのでしょうか?
教材が多すぎて、どれを選んでどの順番で進めればよいか迷ってしまう…そんな悩みを抱える方は少なくありません。
そこで、今回は独学で学科試験に合格するための勉強方法と必要な勉強時間について解説します。
この記事を読めば、効率的な勉強の進め方・おすすめ教材・合格までのスケジュール感がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
建築設備士とは?まず知っておきたい試験概要
建築設備士は、建築物の電気・空調・衛生などの設備設計に携わる専門資格で実務経験を持つ技術者がステップアップするための国家資格です。
ここでは試験の仕組みや難易度、受験資格などの全体像を解説します。
建築設備士の役割と資格の価値
建築設備士は、建築士と連携しながら、建物の設備設計に専門的な視点から助言や提案を行う重要な役割を担います。
空調設備、電気設備、衛生設備などの設計は、快適性・安全性・省エネ性に直結するため、専門知識を持った技術者の関与が不可欠です。
建築設備士の資格を保有することで、これらの設備設計に対する理解と能力が公的に証明されるため、社内での評価向上や転職・独立の場面でも大きな強みになります。
また、国土交通省が認可する国家資格であることからその信頼性と汎用性は高く、設備設計の現場だけでなく、官公庁案件や大型プロジェクトへの参画にも有利です。
試験の構成(学科試験・設計製図試験)
建築設備士試験は「学科試験」と「設計製図試験」の2段階で構成されています。
学科試験では、建築一般知識・法規・建築設備の3分野から出題され、設備に関する広範な知識が問われます。
例年6月に実施され、マークシート形式で解答します。
合格基準は例年6割程度とされており、比較的明確な目標設定が可能です。
学科に合格した者のみが、次の設計製図試験を受験できます。設計製図試験は9月に行われ、与えられた課題に対して図面作成と設計趣旨の記述を行う実技形式です。
図面作成に加え、機器の選定や系統設計といった設備特有の判断力が求められる点が特徴です。この2つの試験を通じて、知識と実務的スキルの両面が問われます。
合格率と難易度の実態
建築設備士試験の合格率は、学科・製図ともに例年20~30%程度とやや低めです。
ただしこれは、受験者の多くが働きながら勉強する実務者であることも影響しています。
特に学科試験については、出題範囲が広く、建築・電気・機械など複数分野をまたぐため、専門外の領域に苦戦する受験者が多いのが現実です。
逆に言えば、しっかりと過去問演習や教材の取捨選択を行えば、独学でも十分に合格可能な試験です。
製図試験は、図面を描くだけでなく、制限時間内に構想・設計し、論理的な構成で答案を仕上げる必要があり、慣れが重要です。
そのため、多くの合格者が講習会の受講を通じて対策をしています。
総じて、片手間では厳しい試験ですが、計画的に学習を進めれば合格を狙える難易度と言えます。
建築設備士の学科試験は独学でも合格できる
建築設備士の学科試験は、適切な教材と戦略を持って取り組めば、資格学校に通わずとも十分に独学で合格が可能です。
ここでは独学合格者の体験をもとに、勉強方法や必要な教材、注意点について詳しく解説します。
独学合格は本当に可能?実際の合格者の声
「独学では難しいのでは?」と感じる方も多いですが、実際には学科試験を独学で突破している受験者は数多くいます。
特に社会人受験者の場合、仕事の合間を縫って効率的に勉強を進める必要があるため、コスト面や柔軟性を重視して独学を選ぶケースが増えています。
合格者の多くが語るのは「過去問を徹底的に繰り返すこと」と「自分に合った教材を選ぶこと」が成功の鍵だという点です。
特に、過去問から出題傾向を把握し、解説を理解しながら学習することで、理解が深まり効率的に得点力を高められます。
資格学校に通わなければ合格できないということはなく、ポイントを押さえれば独学でも十分に通用するのです。
独学合格に必要な勉強時間とスケジュールの立て方
独学で建築設備士の学科試験に合格するために必要な勉強時間は、平均で150~200時間前後とされています。
もちろん、建築や設備の実務経験があるかどうか、他資格の知識があるかによっても前後します。
実務経験がある人なら100時間程度でも合格圏に届く可能性があります。
一方で、専門外の分野に苦手意識がある場合は、200時間以上を見積もっておいたほうが安心です。
スケジュールを立てる際は、3〜4ヶ月前からの学習開始をおすすめします。
1週間あたり10〜15時間の学習時間を確保すれば、無理なく試験当日までに準備が整います。
具体的には、最初の1ヶ月は基礎理解、次の1ヶ月で過去問演習、最後の1ヶ月は模試と復習にあてると効率的です。
独学におすすめの教材と勉強法
独学で合格を目指すなら、教材選びは非常に重要です。
特におすすめされているのが「日建学院出版の建築設備士 学科問題解説集」や「総合資格学院出版の建築設備士 学科試験 問題解説」といった、過去問+解説がセットになった教材です。
これらは問題ごとに丁寧な解説が付いており、初学者でも理解しやすい構成となっています。
勉強方法としては、まず全体像を把握したあと、5年分以上の過去問を繰り返し解くのが基本です。
解説を読み込んで、なぜ間違えたのか、正解はなぜ正しいのかを理解することが合格への近道です。
また、時間がない場合には、理解が難しい問題は丸暗記でも構いません。
得点を重ねることが最優先なので、「完璧」を目指さず「確実に取れる問題を増やす」意識が大切です。
建築設備士の勉強方法【学科試験編】
建築設備士の学科試験は「建築一般知識」「建築法規」「建築設備」の3分野に分かれています。
それぞれに求められる知識や対策法が異なるため、分野ごとの特性を理解し適切なアプローチをとることが合格への近道です。
①建築一般知識の勉強法
建築一般知識では、建築計画・構造・環境などの基礎知識が問われます。
一級建築士試験を簡易にしたレベルとされるため、すでに建築士資格を持っている人にとっては比較的取り組みやすい分野です。
ただし、建築学科以外の出身者や、現場中心の業務に従事している人にとっては、初見の用語や概念が多く、対策に時間を要する可能性があります。
勉強方法としては、過去問演習が最も効果的です。
5年分以上の過去問を繰り返し解き、出題傾向をつかみながら知識を定着させましょう。
特に、「用語の意味」「構造の違い」「設計要件」など、繰り返し問われる内容は確実に押さえる必要があります。
また、初学者の場合は一度テキストで基礎を固めた上で過去問に取り組むと理解度が高まります。
建築一般知識は、学科全体の中でも得点源としやすい分野ですので、早めに対策を始め、確実に得点できるよう準備しておきましょう。
②建築法規の勉強法
建築法規は、法令集を活用しながら解く形式で出題されます。
内容は一級建築士試験の法規よりも簡略化されているものの、設備に特化した条文が多く、普段建築設計中心の業務に携わっている人にとっては注意が必要です。
まず重要なのは、必ず「建築設備関係法令集」の最新版を購入することです。
この法令集は試験当日の持ち込みが可能であり、実際に得点を大きく左右します。
勉強方法としては、過去問を解きながら、出題された条文にマーカーやインデックスを付けて整理していくのが効果的です。
試験当日は時間との戦いになるため、自分だけの「引きやすい法令集」を作っておくことが鍵になります。
例えば、「肯定文=赤線」「否定文=青線」のように色分けしたり、何度も間違えるページにフィルムインデックスを貼っておくと素早く参照できます。
また、出題傾向を把握し、繰り返し出てくる条文は暗記するくらいのつもりで読み込むのが効果的です。
法規は慣れの要素も大きいため、短期間の詰め込みではなく、少しずつ継続的に対策することが成功のコツです。
③建築設備の勉強法
建築設備分野は、建築設備士試験の中で最も難易度が高いと言われています。
出題範囲が電気・空調・衛生設備全般に及び、自身の専門外の分野に関しては特に苦手意識を持つ受験者が多いのが実情です。
そのため、建築設備の勉強法は「捨て問を見極めつつ、得点できる問題を確実に取る」という戦略が求められます。
最も効果的なのは、5年分以上の過去問を繰り返し解くことです。
過去問の解説を読み込んで、内容を理解しながら進めましょう。
ただし、どうしても理解が難しい問題は割り切って、解き方や正解選択肢だけを暗記することも有効です。
合格ラインは6割前後であるため、すべての問題を完璧に理解する必要はありません。
また、過去問を分析していると、一定の周期で出題されるテーマがあることに気づきます。
頻出分野については重点的に対策し、少しでも確実に得点できるようにしておきましょう。
特に、電気系は計算問題も出題されるため、公式の暗記と使い方に慣れておくことが必要です。
設備分野は知識の幅が広いため、地道に反復しながら知識を積み上げていく姿勢が大切です。
建築設備士の勉強時間はどれくらい必要?
建築設備士試験に合格するためには、どの程度の勉強時間が必要なのでしょうか。
ここでは、合格者の平均的な勉強時間をもとに、学科試験・製図試験それぞれに必要な学習量やライフスタイルに応じたスケジュールの立て方について詳しく解説します。
合格者が費やした平均的な勉強時間
建築設備士試験の学科合格者が実際に費やした勉強時間は、一般的に150〜200時間程度が目安とされています。
もちろん個人差があり、建築や設備系の実務経験が豊富な方であれば100時間以下で合格に達するケースもある一方、設備分野が未経験の場合は300時間近くかかることもあります。
製図試験に関しては、図面作成のスキルや表現力が求められるため、80〜150時間程度の準備が推奨されます。
特に独学で対策を進める場合、理解に時間がかかる場面も多いため、余裕を持ったスケジューリングが重要です。
勉強時間を確保できるかどうかが合否を大きく左右しますので、まずは自分にとっての必要時間を正しく見積もり、学習計画を立てましょう。
学科・製図で必要な勉強時間の違い
学科試験と製図試験では、求められるスキルや学習方法が異なるため、当然ながら必要な勉強時間にも差があります。
学科試験は知識の暗記と理解が中心であるため、まとまった時間を集中して確保するよりも、スキマ時間を活用した反復学習が有効です。
例えば、通勤時間や休憩時間を使って過去問演習や解説の読み込みを進めると、トータルで150時間前後を効率よく積み重ねることができます。
一方、製図試験は実際に手を動かして図面を描く訓練が必要であり、1回の学習時間が1〜2時間以上必要になることが多く、週末を使ったまとまった練習が重要になります。
また、製図は「慣れ」が物を言う試験です。
最初は時間内に描き上げられないことも多いため、練習の回数を重ねて図面作成スピードと精度を高めることが合格の鍵となります。
このように、両試験での勉強時間の配分や集中の仕方は異なるため、各フェーズごとに戦略を立てて取り組みましょう。
社会人が効率的に勉強時間を確保するコツ
多くの建築設備士受験者は、仕事と並行して勉強を進める必要があります。
そこで重要になるのが「効率的に勉強時間を確保すること」です。
まずは、平日のスキマ時間を有効活用する習慣を身につけましょう。
例えば、通勤電車で15分間の過去問演習をするだけでも、1週間で1.5時間、1ヶ月で6時間以上の積み上げになります。
また、昼休みの30分を法令集の確認や動画教材にあてるなど、小さな時間を積極的に活用することが重要です。
週末には、2~3時間程度のまとまった時間を取り、製図の練習や総復習に充てると効率的に学ぶことができるので、ぜひ取り組んでみてください。
効率的なスケジュールの立て方
試験日から逆算してスケジュールを立てることが、計画的な学習には不可欠です。
まずは試験日を確認し、そこから3〜4ヶ月前には本格的な勉強を開始できるように設定しましょう。
初月は基礎固めと教材選定に充て、2ヶ月目は過去問演習、3ヶ月目以降は模試形式での演習と弱点克服にフォーカスするのがおすすめです。
週単位で「○○分野を終える」「過去問を○年分解く」といった目標を設定すると、進捗管理もしやすくなります。
また、勉強時間は1日30分〜1時間でも構わないので、無理のないペースを維持することが継続のカギです。
特に仕事が忙しい社会人は、休日に3〜4時間まとめて勉強する「集中日」を設けるのも有効です。
スケジュールには「余白」も持たせ、急な予定変更や体調不良にも対応できるようにしておきましょう。
計画通りに進まないことを前提に、柔軟に修正しながら継続することが、合格を引き寄せる最良の方法です。
製図試験は講習会の活用が効果的
建築設備士の製図試験は、時間内に図面を完成させるスピードと設備設計の総合的な理解が求められるため、独学での合格は難易度が高いと言われています。
そのため、多くの受験者が講習会を活用しています。
なぜ製図試験は独学だと難しいのか
製図試験は、与えられた課題に対して「空調」「衛生」「電気」などの複合的な設備設計を行い、図面を作成する試験です。
限られた時間の中で図面だけでなく、設計趣旨や機器選定の根拠も記述する必要があるため、単に知識を詰め込むだけでは太刀打ちできません。
独学では「設備の配置」「系統のバランス」「記述の一貫性」などの評価基準に対する具体的な指導が受けられないため、自分の図面のどこが減点対象になるのか判断しにくいという課題があります。
さらに、試験では実務とは異なる「採点基準」が存在するため、経験豊富な実務者であっても合格できないケースが少なくありません。
講習会では、過去の出題傾向や合格図面の分析に基づいて、試験で評価される書き方を具体的に指導してもらえるため、合格率の大幅な向上が見込めるのです。
講習会に参加するメリット
講習会の最大のメリットは、「採点基準に沿った図面作成スキル」を効率よく習得できる点にあります。
試験では、実務で優れた設計をしていても、それが試験形式に適していなければ得点に結びつきません。講習会ではその違いを明確に教えてくれるため、無駄のない対策が可能になります。
また、プロの講師による添削やフィードバックを受けることで、自分の弱点を客観的に把握でき、同じミスを繰り返すリスクを減らせます。
講習会によっては模擬試験や時間内での実践トレーニングが組み込まれており、本番の試験に近い環境で経験を積むことができます。
これは独学では得られない貴重な経験です。
さらに、受講生同士の交流や情報交換ができる点も、精神的な支えやモチベーションの維持につながります。
「独学では時間が足りない」「一人だと不安」という方にとって、講習会は非常に有効な選択肢です。
講習会を選ぶ際のポイント
数ある講習会の中から最適なものを選ぶためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
まず注目すべきは、「合格実績が明確に提示されているか」です。信頼性の高い講習会は、過去の合格者数や合格率を具体的に開示しています。
次に確認したいのが「添削サポートの有無」です。
製図試験では、自分の図面を客観的に評価してもらうことが極めて重要であり、丁寧な添削指導を受けられる講座を選ぶことが、実力アップに直結します。
また、「課題の数」や「模擬試験の有無」も大事な指標です。
試験に近い環境での練習量を確保できる講座は、実戦力を高めるのに効果的です。
費用面ももちろん重要ですが、価格の安さだけで選ばず、内容の充実度やサポート体制も含めて総合的に判断することが大切です。
口コミや受講者の声を事前に確認したり、無料体験講座があれば積極的に参加するのも良い方法です。
オンライン講座と通学講座の違い
現在は、通学型の講習会に加え、オンライン型の講座も数多く提供されています。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分のライフスタイルや学習環境に合った形式を選ぶことが重要です。
通学講座は、講師から直接フィードバックを受けられ、即時に質問できる点が大きな強みです。
また、周囲の受講生と一緒に学ぶことで集中力を維持しやすく、実際に手を動かして図面を描く「実技の慣れ」が身につきやすいのも特徴です。
一方、オンライン講座は、場所や時間を選ばずに学べる柔軟性が魅力です。
地方在住の方や多忙な社会人にとっては、移動時間を節約しながら学べる利点があります。
また、講義の録画を繰り返し視聴できるため、理解が浅い部分を何度も復習できるのもポイントです。
ただし、自己管理能力が求められるため、「学習を習慣化できるか」が成功の鍵になります。
どちらが優れているというより、自分の性格やライフスタイルに合った形式を選ぶことが、講習会を最大限に活かすコツです。
過去問の使い方が合否を分ける
建築設備士の試験対策において、過去問は最も信頼性が高くかつ効果的な教材です。
過去問をただ解くだけでなく、正しい使い方を実践することで得点力を飛躍的に高めることができます。
ここでは、合格者が実践している「過去問の活用法」について詳しく解説します。
過去問の解説を理解しながら進める
過去問演習において最も重要なのは、「解説を読みながら学ぶ」という姿勢です。
ただ正解・不正解を確認するだけでは知識は定着しません。
解説文を丁寧に読み込み、「なぜその選択肢が正解なのか」「他の選択肢はなぜ誤りなのか」を一つ一つ理解することが必要です。
特に建築設備士の試験では似たような問題が表現を変えて出題されることが多く、解き方の考え方を身につけることが、応用問題に対応する力になります。
また、使用する過去問集は「解説が詳しいもの」を選びましょう。
日建学院や総合資格学院が出版している問題集は、解説が丁寧で理解しやすく、初学者でも取り組みやすい内容となっています。
間違えた問題はノートに記録して復習したり、自分なりに要点をまとめ直すなど、能動的な学習を意識すると理解度が一段と深まります。
過去問の出題傾向を確認する
建築設備士試験は、過去問の出題傾向を把握することが得点アップの鍵です。
5年〜10年分の過去問を解いていくと、繰り返し出題されるテーマや用語、パターンに気づくようになります。
これらのよく出る問題を確実に得点源にできれば、全体の合格率を大きく引き上げることが可能です。
出題傾向をつかむには、単に「解く」だけでなく、「分析する」姿勢が求められます。
たとえば、「法規分野では○○条が3年連続で出題されている」「衛生設備の○○に関する問題は隔年で登場している」といった出現パターンを記録し、自分専用の傾向リストを作るのも効果的です。
こうした傾向分析は、限られた勉強時間の中で“やるべき問題”と“捨ててもよい問題”の取捨選択にも役立ちます。
合格ラインが6割程度であることを踏まえるとすべてを完璧にする必要はなく、頻出問題を徹底的に対策する方が効率的なのです。
わからない問題は問題と答えや解き方を暗記する
建築設備士試験では、専門性の高い問題や、設備系のバックグラウンドがない人には理解が難しい問題も少なくありません。
そうした「どうしても理解できない問題」に出くわした場合は、思い切って「暗記」に切り替えることも一つの戦略です。
具体的には、問題文と正解の選択肢、さらには選択肢の根拠までを丸ごと覚えてしまうことです。
なぜなら、過去問から類似問題が再出題される可能性は非常に高く、同じ言い回しや構造の問題が本試験で登場することも珍しくありません。
理解できなくても、正解を覚えていれば得点にはつながります。
これは、合格点が6割前後でよいという試験の特性を考えた、非常に合理的なアプローチです。
ただし、やみくもにすべてを暗記するのではなく、「理解できない問題」や「何度も間違える問題」を優先して記憶するのがポイントです。
また、暗記した内容は時間をおいて繰り返し確認することで、試験当日まで忘れずに維持できます。
理解と暗記をバランスよく使い分け、合格に必要な知識を効率よく積み上げていきましょう。
よくある質問(FAQ)
建築設備士の試験勉強に取り組む中で、受験生からよく寄せられる悩みや疑問にお答えします。勉強の進め方やモチベーション維持の工夫、社会人ならではの時間確保術まで、実践的なアドバイスをまとめました。
Q. 学科試験と製図試験の勉強は並行すべき?
結論から言えば、基本的には学科試験に集中し、合格後に製図対策へ移行するのが効率的です。
なぜなら、建築設備士試験は一次(学科)を突破しないと二次(製図)に進めない構造であり、学科に合格しなければ製図の勉強は無駄になってしまうためです。
とはいえ、例外的に「今年こそ絶対に合格したい」「すでに学科の理解に自信がある」場合は製図の概要だけでも早めに触れておくことで、製図の勉強開始時のハードルを下げられます。
特に出題傾向や過去の課題、製図の構成ルールなどを軽くインプットしておくと、学科合格後にスムーズに対策へ移行できます。
ただし、製図対策は時間と労力を要するため、学科と製図を“同じ比重”で並行するのは避けるべきです。
あくまでも学科が最優先。製図は合格後に集中すれば十分間に合います。
焦らず、試験の構造に合わせて、段階的に取り組むのが最も合理的な戦略です。
Q. 独学だとモチベーションが続かない場合の対策は?
独学は自由度が高い一方で、孤独になりやすく、継続が難しいというデメリットもあります。
建築設備士の試験は中長期的な準備が必要なため、モチベーションの維持が合格へのカギになります。
効果的な対策としては、まず「学習の可視化」があります。
具体的には、勉強時間や進捗を記録できるアプリやノートを活用し、日々の達成感を積み重ねていくことです。
たとえば「今週は過去問を○年分終えた」「今日は1時間勉強できた」と記録するだけでも、自分の努力が“見える化”され、やる気が続きやすくなります。
また、SNSやオンラインコミュニティで同じ試験を目指す人たちとつながるのも有効です。
Xやnoteなどでは「#建築設備士勉強垢」のようなタグを使って発信・共有する人も多く、他人の努力を見ることで刺激を受けられます。
さらに、自分へのご褒美制度(例1週間頑張ったら好きな映画を見る)や、勉強する時間帯・場所をルーティン化するなど、仕組みづくりも大切です。
継続には気合より「環境」が大きく影響します。
自分が継続しやすい“ペースと空間”を整えることが、モチベーション維持には欠かせません。
Q. 勉強時間が確保できない社会人へのアドバイス
社会人受験者にとって最大の課題が「勉強時間の確保」です。
仕事や家庭の事情でまとまった時間が取れない中でも、いかにスキマ時間を積み上げられるかが勝負になります。
まずおすすめなのは、1日30分〜1時間の「ミニ勉強」をスケジュールに組み込むことです。
朝起きて15分、昼休みに20分、寝る前に25分といった具合に、日常のすき間に過去問や法令集のチェックを差し込むことで、1日でも1時間前後の学習時間を確保できます。通勤中に解説動画や音声教材を聞くのも良い方法です。
また、週末に2〜3時間の“集中ブロック”を設定するのも効果的です。
「この時間だけはカフェにこもって集中する」「日曜午前は図面練習」と決めておくことで、平日とは違う学習スタイルで補完できます。
家族や同居人がいる場合は、「試験までの○ヶ月だけ協力してほしい」とあらかじめ相談しておくと、生活リズムを無理なく調整できます。
時間がないからといって何もしないと学習ゼロの日が続き、焦りばかりが増してしまいます。
重要なのは“短くても毎日続けること”。継続こそが、忙しい社会人にとって最大の戦略です。
まとめ
今回の記事では、建築設備士に合格するための勉強方法について解説しました。
今回お伝えした内容を参考に、ぜひ建築設備士の取得を目指して頑張ってください。
建築設備士は、本来は設計・計画段階で力を発揮する資格です。
しかし現場では、
- 資格を持っていても業務内容が変わらない
- 責任だけ増えて評価が伴わない
- 転職すべきか、副業という道があるか
といったケースも見られます。
今の環境が適正かどうか、転職・副業を含めた選択肢整理を無料で行っています。