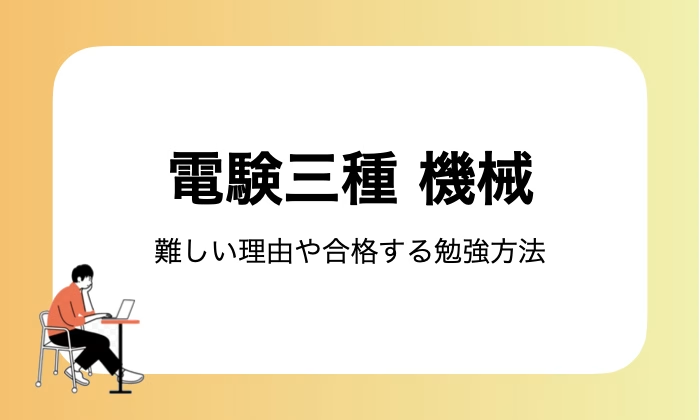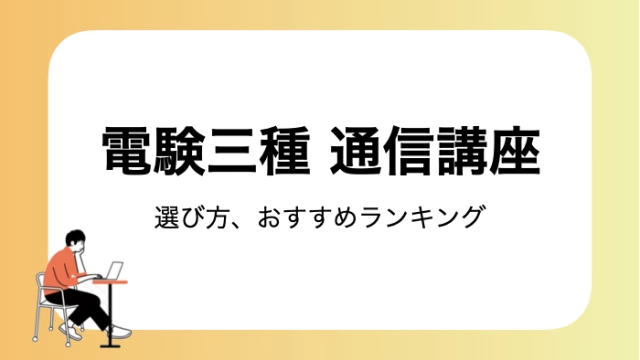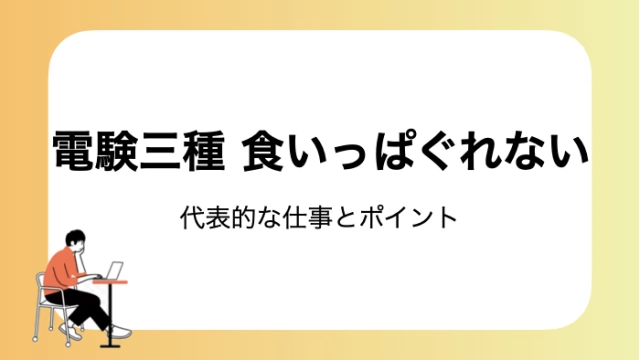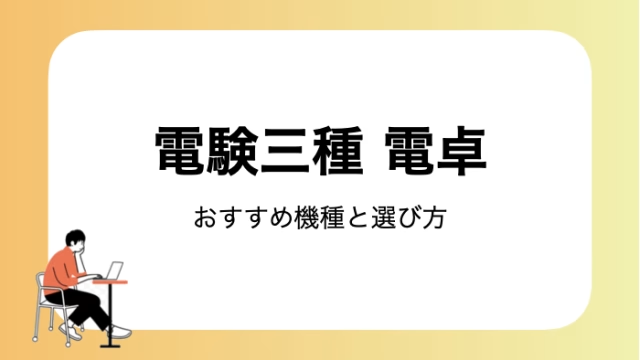「機械科目は暗記も多いし公式も複雑で、他の科目より理解しにくい」と感じている方は多いです。特に独学では、勉強の進め方に悩むのは当然です。
そこで、今回は電験三種の機械科目に特化した勉強法について解説します。
この記事を読めば効率的な暗記のコツや過去問の活用法、頻出ポイントの押さえ方がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
電験三種の機械が難しいと言われる理由
電験三種の「機械」科目は、受験者の中でも特に苦手意識を持たれることが多い分野です。
ここでは、なぜ機械科目が難しいとされるのか、その主な理由を解説していきます。
出題範囲が広く、公式や知識の暗記だけでは対応できない
機械科目の最大の特徴は、その出題範囲の広さです。
電動機や変圧器、パワーエレクトロニクス、制御工学、照明・電熱・空調など、まるで別分野のようなテーマが1科目に詰め込まれています。
そのため、単純な公式暗記や単発の知識だけでは、本質的な理解に至らず、応用問題や複合問題に対応できません。
さらに、問題文では単語や数値だけでなく、設問の意図を読み取る力も問われるため、表面的な学習では不十分です。
例えば「この装置の効率を求めよ」という問題一つとっても、回路図の理解・公式の選択・単位換算・計算過程の正確性など、複数の能力が求められます。
そのため、機械の勉強では、各単元ごとに「なぜその公式が成り立つのか」「その装置の役割は何か」といった根本的な理解を深めることが必要です。
暗記はあくまでも入口にすぎず、それをどう活かすかが問われるのが、機械の難しさです。
計算問題が多く、スピードと正確さが求められる
機械科目は計算問題の比率が非常に高い傾向にあります。
特に誘導機や直流機、変圧器などの電気機器に関する問題は、公式を使って出力や効率、損失などを求めるパターンが頻出です。
問題の中には数値の変換や単位の統一が必要なものもあり、正確な数値処理能力が求められます。
加えて、試験時間内に複数の問題を解ききる必要があるため、解答スピードも重要です。
途中式の見直しや計算ミスの確認にかけられる時間も限られており、「正確さ」と「速さ」の両立が大きなハードルとなります。
また、計算過程においても「式を立てる力」が必要になります。
どの公式を選ぶべきかを判断する読解力と、それを短時間で適用できる実践力の両方がなければ得点につながりません。
機械科目では、単なる計算練習にとどまらず、出題傾向に基づいたパターン別の演習が効果的です。
実物を見る機会が少なく、イメージしにくい分野が多い
電験三種の受験者の多くは、実務経験がない学生や異業種からの転職希望者などです。
そのため、機械科目で登場する「直流機」や「三相誘導電動機」などの機器を、実際に見たことがないという人も少なくありません。
イメージが湧かないまま勉強を進めると、構造や動作原理の理解が曖昧になり、応用問題でつまずく原因になります。
特に、モーターの回転方向や磁界の変化、トルクの概念などは、視覚的な理解がないと非常に抽象的で難解です。
この対策としては、YouTubeなどで公開されている解説動画や、メーカーの資料を活用して視覚的な情報を取り入れることが有効です。
また、技術参考書などに掲載されている図解を用いて、構造や回路の流れを頭の中でシミュレーションする習慣を持つことも重要です。
視覚情報と学習内容を結びつけることで、記憶の定着率も飛躍的に向上します。
「理論」の知識が前提となる問題も多く、基礎の理解が不可欠
機械科目は、単体で独立しているように見えて、実は「理論」科目の知識を前提にしている部分が多く存在します。
例えば、三相交流回路の理解やベクトル図の描き方、電磁誘導や力率の計算などは、理論の範囲でしっかり学んでおくべき基礎知識です。
機械の問題ではこれらの知識を活用して、「この場合の入力電力は?」「回転速度はどうなる?」といった応用的な設問が出されるため、理論があやふやなままだと、機械の学習も進みません。
実際、理論を後回しにして機械に取り組んだ結果、途中で手が止まってしまい、時間だけが浪費されてしまうというケースは多くあります。
逆に、理論をある程度マスターしてから機械に取りかかると、公式の意味や構造の動作がスムーズに理解でき、学習効率が上がります。
したがって、機械対策は単独で完結させるのではなく、まずは「理論」をしっかりと固めた上で進めるという戦略が不可欠です。
基礎がしっかりしていれば、応用にも対応できるようになり、合格への道が大きく開けるでしょう。
機械科目の出題内容とポイント
機械科目は、電験三種の中でも計算問題が多く、理論的な理解と計算スピードが求められる科目です。
出題形式や配点の仕組みを把握し、重点分野を明確にして学習することで、効率的な得点獲得が可能になります。
試験時間・出題形式・合格基準(A・B問題の配点)
電験三種の機械科目は、他の科目と同様に午前または午後の90分間で行われ、A問題(選択式)およびB問題(記述式)で構成されています。
A問題は60点満点で、B問題が40点満点。全体で100点中60点以上で合格と判定されます。
A問題は選択肢から正答を選ぶマークシート形式であり、知識や基本的な計算能力が求められます。
B問題では記述式の設問が中心で、応用的な計算や理論の理解を問われることが多くなります。
B問題は特に配点が大きいため、得点源として活用するためにも出題傾向の把握と練習が欠かせません。
また、機械科目では電気機器、パワーエレクトロニクス、自動制御などの専門的なテーマが出題されることが多いため、広範囲の学習が必要になります。
出題数は例年A問題が10問前後、B問題は3〜5問程度で構成されています。
重点分野:四機(直流機・変圧器・誘導機・同期機)は必ず押さえる
機械科目で特に重要な出題領域が、「四機」と呼ばれる直流機・変圧器・誘導機・同期機の4つの電気機器です。
これらは電気工学の基礎であり、電験三種の機械科目における頻出分野でもあります。
直流機においては、発電機と電動機の基本構造や起電力・トルクの計算、負荷特性などが出題されます。
変圧器では、理想変圧器の等価回路や電圧変動率、損失、効率の計算が中心です。
誘導機は、回転磁界の原理やすべり、トルク計算が問われ、同期機では力率、端子電圧、無効電力などの理解が重要になります。
これら四機の単元は、必ず毎年出題されるわけではありませんが、全体の出題割合として非常に高いため、対策の優先順位は最上位に位置します。
図や等価回路を活用した理解が効果的で、計算問題も頻出であるため、公式を暗記するだけでなく意味や使い方を理解しておくことが求められます。
出題傾向の強いテーマ:パワエレ、自動制御、電熱、電気化学など
機械科目の出題は、四機に加えてパワーエレクトロニクス、自動制御、電熱、電気化学といった分野からも頻繁に出題されます。
これらのテーマは一見バラバラに見えますが、いずれも機械科目の根幹を成す要素であり、特にパワーエレクトロニクスと自動制御はB問題でも頻出です。
パワエレ分野では、ダイオードやトランジスタ、サイリスタを用いた整流回路、インバータ、チョッパ回路などが出題されます。
回路動作の理解と波形計算、平均電圧や電流の計算が求められます。
自動制御では、比例制御(P)、積分制御(I)、微分制御(D)やその組み合わせによるPID制御の原理、伝達関数やブロック線図の読み解きが問われます。
電熱分野は、ジュール熱や熱伝導、電気炉の計算などが主題であり、電気化学では電解、電池(鉛蓄電池、燃料電池など)の仕組みや起電力の計算が問われます。
これらの分野は計算と理論が複雑になりがちですが、パターンを押さえれば安定して得点が見込めるため、過去問演習を通じて出題形式に慣れておくことが重要です。
重要な計算公式とその活用方法
機械科目では、公式の暗記だけでなく「どう使うか」が非常に重要です。
計算問題が多く出題されるため、代表的な公式をすぐに使えるようにしておく必要があります。
例えば変圧器においては「電圧比=巻数比」、「電力=電圧×電流×力率」、「効率=出力÷入力」、「損失=銅損+鉄損」などの公式は頻出です。
誘導機ではトルクT=k×Φ×I(磁束×電流)や、同期機では無効電力Q=V×I×sinθといった公式が重要になります。
パワーエレクトロニクスでは、平均電圧やリップル電圧、整流回路における効率計算など、正弦波と半波・全波整流の関係性を使った式を活用します。
電熱では、ジュールの法則 Q=I²Rt が基本ですが、熱容量や熱伝導率を含む応用問題もあり、単位にも注意が必要です。
公式の丸暗記ではなく、導出の流れや意味、適用条件を理解しておくことで、初見の問題でも応用が利きます。
過去問演習で繰り返し使う中で、自然と使いこなせるようになるのが理想です。
解く上での「ポイント」まとめ(捨て問判断、先に解く問題)
機械科目は計算問題が多く、時間配分と戦略が合否を分ける大きな要素になります。
すべての問題に全力で取り組むのではなく、効率よく得点を積み上げることが大切です。
まず、A問題では確実に得点できる四機や基本的なパワエレ、自動制御の問題から手をつけましょう。
難解な記述問題や時間がかかる図解問題は後回しにし、最後まで時間が余れば挑戦するというスタンスで構いません。
また、「見た瞬間に内容が思い出せない」「計算が複雑そう」と感じた問題は捨て問候補です。
解ける問題を優先し、取りこぼしを防ぐことが合格への近道になります。
B問題は記述式である分、計算の途中式を丁寧に書くことで部分点を得られる可能性があります。
たとえ最終解が間違っても、過程をしっかり示すことで得点できるため、途中式を省かないよう注意しましょう。
日頃から時間を計って過去問演習を行い、「解ける問題を見極める目」を養っておくことで、本番でも落ち着いて対応できるようになります。
電験三種「機械」の効果的な勉強法4選
「機械」は電験三種の中でも特に計算や暗記の両面が問われる難関分野です。
限られた学習時間で効率よく合格点を狙うためには、戦略的な勉強法を実践することが不可欠です。
ここでは具体的かつ再現性の高い勉強法を4つ紹介します。
① インプットとアウトプットの反復
電験三種の「機械」は、知識の暗記だけでなく、それを使いこなす力が求められます。
そのため、テキストを読むだけの学習では不十分であり、「インプットしたらすぐにアウトプット」を徹底することが重要です。
具体的には、1つの単元をテキストで読んだら、すぐに関連する問題を解くようにしましょう。
特に四機(直流機、変圧器、誘導機、同期機)のような頻出テーマは、繰り返し解いて確実に得点できるようにすることがポイントです。
過去問は少なくとも10年分を用意し、3〜5回は繰り返し解くのが理想です。
同じ問題でも時間を空けて何度も解くことで、知識の定着と問題対応力が自然と身につきます。
繰り返す中で、解法のパターンも見えてくるようになります。
② 暗記すべき知識の整理
機械科目では、理論の理解と並行して「覚えるべきこと」を効率よく暗記していく工夫が求められます。
特に、四機の公式、パワエレの波形や電圧の式、自動制御のPID制御の特徴などは頻出であり、確実に暗記しておきたいポイントです。
まず、自分の中で「これは覚えるべきもの」と「これは理解すればよいもの」を分け、ノートや単語帳などに整理しましょう。
例えば、公式だけをまとめた1冊を作成し、見開きで「公式+簡単な例題」を書いておくと、記憶の定着が高まります。
また、スキマ時間の活用にはアプリ学習が便利です。
暗記カード形式のアプリや、過去問演習ができる無料ツールを活用すれば、通勤時間や休憩中にも反復学習が可能です。
毎日5分でも継続すれば、大きな差になります。
③ 過去問分析で出題傾向をつかむ
電験三種の「機械」は出題傾向がある程度決まっており、過去問分析を行うことで効率よく学習できます。
具体的には、直近10年分の過去問を分析し、よく出る分野や問題形式を把握しましょう。
各年の出題テーマを表にしてまとめると傾向が一目でわかります。
頻出テーマに優先して取り組むことで、学習の無駄を省くことができ、得点効率が飛躍的に高まります。
逆に、出題頻度が低く、難易度が高いテーマは思い切って後回しにするのも戦略のひとつです。
特にB問題では、パターンが似た出題が繰り返される傾向があるため、過去問の繰り返し学習が合格への最短ルートと言えるでしょう。
④ 通信講座・動画・参考書を併用
独学での理解が難しい分野に対しては、通信講座や解説動画、わかりやすい参考書をうまく活用することが突破の鍵になります。
機械科目は、電気回路だけでなく、機構や物理的な動きに関する理解も必要なため、文章だけではイメージしづらい場面が多いのが特徴です。
そこでおすすめなのが、YouTubeなどで無料公開されている解説動画や、図解中心で直感的に理解できる参考書の併用です。
特に「イラストでわかる電験三種 機械」や「完全マスターシリーズ」は、初学者にもわかりやすく、苦手意識の克服に効果的です。
また、ユーキャンなどの通信講座は、動画と問題演習がセットになっているため、効率よく学習を進めたい方には最適です。
自分に合った教材を選ぶことで、モチベーションを維持しながら学習を継続できます。
「機械」を攻略するための勉強スケジュール例
電験三種の「機械」科目は、分野が広く、電気以外の知識(力学、材料、制御など)も求められるため、独学者にとって特に難関とされています。
ここでは、3か月・6か月の学習期間別におすすめのスケジュールを紹介します。
【3か月プラン】週4日の学習で合格を目指すモデル
3か月という短期で「機械」科目の合格を目指す場合は、限られた時間の中で効率よく重要単元を攻略する必要があります。このプランでは、週に4日(1日2〜3時間)を目安に、トータルで約150〜200時間の勉強時間を確保することを目標にします。
まず、1か月目は「機械」の全体像を把握しながら、頻出分野である「変圧器」「誘導電動機」「直流機」などの電気機器を重点的に学習します。過去問を活用して出題パターンを把握し、インプットとアウトプットを並行して進めましょう。
2か月目は、「パワーエレクトロニクス」や「自動制御」「照明・電熱」「力学」など、比較的苦手とされがちな周辺分野をカバーします。この時期からは苦手意識を克服することを重視し、基礎の再確認にも時間をかけてください。
3か月目は過去問演習に集中し、出題傾向を掴んで得点力を磨くフェーズです。本番を想定したタイムアタック形式で解くことで、試験当日の時間配分の練習にもなります。
【6か月プラン】毎日コツコツ型の学習プラン
時間にゆとりのある6か月プランでは、1日1時間程度の学習を継続しながら、300時間前後を目安に学習を進めることができます。ゆっくり確実に理解を深められるため、未経験者や文系出身者にもおすすめです。
1〜2か月目は、教科書や参考書を使って「機械」の全範囲を一通り学びます。特に、出題数の多い電気機器に時間をかけて、仕組みや動作原理を理解することを心がけましょう。
3〜4か月目は、前半で学んだ内容をもとに過去問や問題集で演習を繰り返します。分からない部分はすぐに参考書に戻って復習することで、知識を定着させていきます。また、苦手な単元は早めに把握し、重点的に補強しておくことが大切です。
5〜6か月目は、応用問題への対応力を養いながら、総仕上げとして模試や総合問題を解いて実戦力を高めます。本番形式に慣れることも、この時期の重要なポイントです。
勉強時間の目安:100〜300時間(学歴・経験により異なる)
「機械」科目に必要な勉強時間は、個人のバックグラウンドによって大きく異なります。理系出身者や業務で関連知識がある方なら、100〜150時間程度でも合格圏内を目指せます。一方、初学者や文系出身者は200〜300時間を目安に考えるとよいでしょう。
目安としては、以下のようになります。
| 学歴・経験 | 想定勉強時間 | ポイント |
|---|---|---|
| 理系(電気系)出身 | 100〜150時間 | 過去問中心でスピード合格を狙える |
| 文系・初学者 | 200〜300時間 | 基礎理解+演習でじっくり対策が必要 |
勉強時間は「量」だけでなく「質」も重要です。インプットとアウトプットのバランスを意識し、単元ごとに「理解→問題演習→復習」のサイクルを繰り返すことで、確実に力をつけていきましょう。
先に「理論」を合格してから「機械」に取り組む方法もアリ
電験三種では、1科目ずつ合格を積み重ねていくスタイルも認められています。特に「理論」は他科目の基礎にもなるため、先に理論をクリアしてから「機械」に進む戦略は非常に有効です。
理論を先に学ぶことで、「機械」の電気機器に関する理解がスムーズになり、特に回路図や計算問題の対応力が上がります。また、理論で学んだ公式や考え方がそのまま「機械」でも応用できるため、効率よく学習を進められるというメリットがあります。
さらに、理論合格後は「自分は合格できる」という自信にもつながり、モチベーションの維持にも効果的です。1年で全科目合格を目指すのが難しい場合には、戦略的に「理論→機械→電力・法規」とステップを踏んでいく分割学習法を検討してみましょう。
苦手な人は「科目別合格制度」を活用
電験三種の試験は4科目あり、すべてを一度に合格するのは大変です。
そんなときに役立つのが「科目別合格制度」。この制度を上手に活用すれば、苦手な科目を後回しにして計画的に合格を目指すことが可能です。
機械をあえて後回しにする戦略
電験三種の中でも「機械」は苦手と感じる受験者が多い科目です。
扱う内容が幅広く、電気回路だけでなく、モーターや発電機、電子回路などの知識も問われるため、物理や工学的な理解が求められます。
そのため、最初から全科目を同時に合格しようとするのではなく、「機械」だけを後回しにして他の科目に集中する戦略が有効です。
とくに文系出身者や、電気分野が未経験の人にとっては、「理論」「電力」「法規」の3科目で得点源を作ってから、「機械」に時間をかけて取り組む方が効率的です。
また、「機械」以外の3科目は出題傾向や対策パターンが比較的安定しており、独学でも取り組みやすいメリットがあります。
このように、苦手意識のある科目は無理に一度で合格を目指さず、戦略的に後回しにすることで、結果的に最短合格につながる可能性が高くなります。
合格した科目は最大連続5回まで免除
「科目別合格制度」では、一度合格した科目は、最大連続5回の試験で免除される仕組みになっています。
※ただし、有効期間は3年間です。電験三種試験は年2回実施されるため、3年間で最大5回まで免除可能ということです。
これにより、得意な科目や比較的取り組みやすい科目から優先して勉強し、確実に合格していくことが可能です。
たとえば、初年度に「理論」「法規」の2科目に集中して合格し、次年度に残りの「電力」「機械」を受験するという分割戦略を取れば、精神的にも負担が軽減されます。
また、年ごとのスケジュール調整もしやすく、働きながら学習を続ける社会人にとっても非常に有効です。
注意点として、免除制度を活用するには年に1回は受験申し込みを行う必要があるため、うっかり申込を忘れると合格の権利が失効してしまいます。
合格した科目の有効期限や受験回数のカウント方法を事前に確認し、計画的に受験を続けることが重要です。
初回は「理論」「法規」に集中 → 翌年に「機械」
電験三種において最も基本となる科目が「理論」、そして出題傾向が安定していて比較的得点しやすいのが「法規」です。
この2科目を初年度に集中して学習することで、まずは土台を固めることができます。
「理論」は電験三種の基礎的な知識を網羅しており、他の科目の理解にも直結するため、最初に攻略しておくと効率的です。
「法規」は暗記中心の科目ですが、過去問の傾向が比較的変わりにくく、学習時間に対して成果が出やすいのが特徴です。
初年度でこの2科目に合格すれば、翌年は「電力」と「機械」の2科目に専念できます。
特に「機械」は一筋縄ではいかない科目なので、1年分の時間を割いて集中的に取り組むのが得策です。
このように「理論」と「法規」→「電力」と「機械」というステップで学習を分割すると、合格までの見通しが立てやすく、モチベーションも維持しやすくなります。
まとめ
今回の記事では、電験三種の機械科目の勉強方法について解説しました。
今回お伝えした内容を参考に、ぜひ電験三種の取得を目指して頑張ってください。
実際、電験三種は、取得するだけでも大きな価値があります。
一方で、その価値が十分に評価されるかどうかは、働く環境次第です。
- 今の職場で資格がどう扱われているか
- 将来的にどんな選択肢があるか
- 転職すべきか、副業という道があるか
無理な提案は行わず、電験三種を持つ方向けの選択肢整理を無料で行っています。