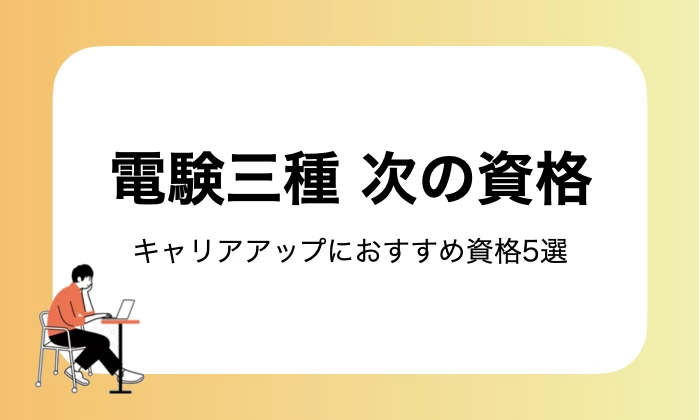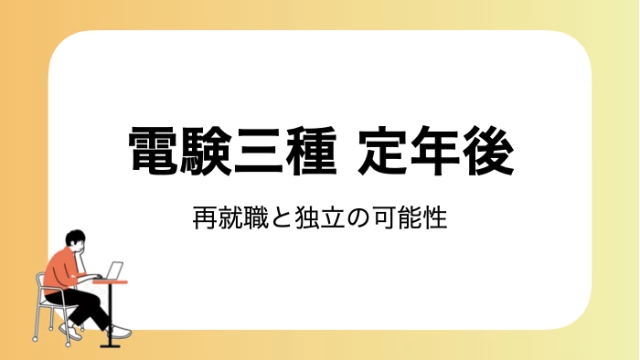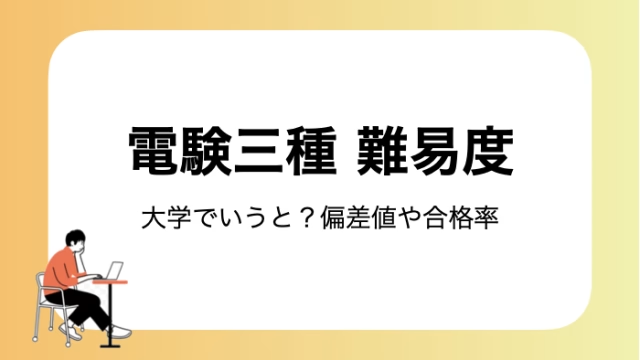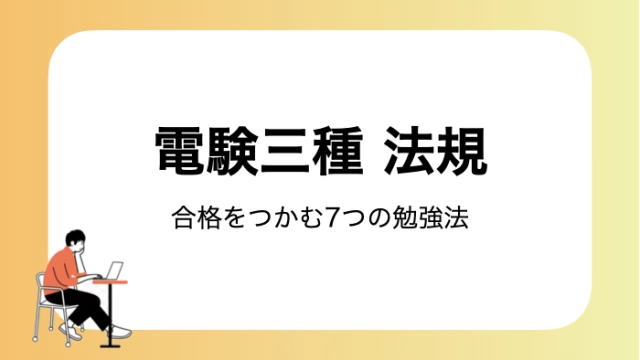「電験三種を取ったけど、次に取る資格で迷っている」ということはありませんか?
そこで、今回は電験三種取得後におすすめの次の資格と、その選び方について解説します。
この記事を読めば、電験三種と相性の良い資格や免除制度、キャリアアップに直結する資格選びのポイントがわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
電験三種の次におすすめの資格5選
電験三種を取得した後にさらにキャリアを伸ばすには、関連性の高い資格を組み合わせて取得することが効果的です。
ここでは電験三種と相性が良く、業務の幅や待遇改善につながるおすすめ資格を5つ紹介します。
電験二種(電気主任技術者として上位資格)
電験二種は電験三種の上位資格にあたり、取り扱える電圧の上限が大きく拡大するため、活躍の場が飛躍的に広がります。
例えば、電験三種では5000ボルト未満の電気設備が主な対象ですが、二種を取得すると5万ボルト未満の大規模設備を扱うことが可能になります。
そのため、工場や発電所、鉄道関連施設など大規模インフラを扱う現場での需要が高く、電気主任技術者としての責任ある役割を担うことができます。
また、企業によっては電験二種保有者に対して資格手当が支給されるほか、昇進条件として必須とされる場合もあります。
難易度は高いですが、その分得られるメリットは大きく、電験三種取得後のステップアップとして最も王道の選択肢といえます。
電気工事士(第一種・第二種)
電気工事士は、実際の電気工事を行うために必要な国家資格です。
電験三種が「監督・管理」を中心とする資格であるのに対し、電気工事士は「施工」を担う資格となります。
第一種を取得すれば最大500キロワット未満の受電設備に関わる工事が可能となり、第二種であっても住宅や小規模な施設の配線工事を手掛けることができます。
電験三種と組み合わせることで、設計・監督から施工まで一貫して対応できるため、現場での即戦力性が格段に高まります。
また、実務での活用範囲が広く、需要も安定しているため転職や独立を考える人にとっても有利です。
さらに、電験三種保有者は学科試験が免除される制度があるため、効率的に資格取得を進められる点も魅力です。
電気工事施工管理技士(1級・2級)
電気工事施工管理技士は、電気工事の現場において工程管理や安全管理を行うための資格です。
1級を取得すれば、国や自治体が発注する公共工事において主任技術者や監理技術者として従事することが可能になります。
2級でも民間工事を中心に現場を任されるため、キャリア形成に大きな役割を果たします。
電験三種が「設備管理の専門家」であるのに対し、施工管理技士は「現場統括のプロフェッショナル」として評価されるため、両方を揃えることで大規模な工事現場から設備管理までをトータルにカバーできます。
企業にとっては一人で複数の役割を任せられるため評価が上がり、転職市場でも大きな強みとなります。
実務経験を積めば受験資格が得られるため、現場でキャリアを積みながら狙うのが現実的です。
消防設備士
消防設備士は、消防法に基づいて火災報知器や消火設備などの点検や設置を行う資格です。
建物の安全を守るためには定期的な点検が不可欠であり、この資格を持つことでビル管理や設備メンテナンス業界での活躍の場が広がります。
電験三種と組み合わせることで、電気設備だけでなく防災設備の面からも建物全体を総合的に管理できるようになり、ビルメンテナンス業務における付加価値が高まります。
特に大規模な商業施設や病院、オフィスビルなどでは消防設備士の需要が高く、安定した需要が期待できます。
また、資格を持つことで法律に基づいた点検業務を受託できるため、独立開業を目指す場合にも大きな強みとなります。
電験三種取得者であれば学習内容が重なる部分も多いため、比較的取り組みやすい資格といえるでしょう。
エネルギー管理士
エネルギー管理士は、省エネ法に基づき工場やビルなどにおけるエネルギー使用状況を管理する資格です。
電験三種の知識と大きく重なる分野が多く、試験科目にも共通部分があるため効率的に学習できます。
省エネやカーボンニュートラルが重視される現代においては需要が非常に高く、特に製造業や大規模ビルの管理部門では必須人材として扱われるケースも少なくありません。
資格を取得することで、省エネ計画の立案や設備改善の提案など、より高度なマネジメント業務を担えるようになります。
また、エネルギー管理士は国家資格であり、企業によっては資格手当が付与される場合もあります。
電験三種と組み合わせることで「設備の安全を守る力」と「効率を高める力」を兼ね備えた人材となり、長期的にキャリアの安定性と市場価値を高めることができます。
電験三種取得者が免除対象になる資格一覧
電験三種を取得すると、関連資格の一部で試験免除や受験資格の優遇を受けられる制度があります。
これを活用すれば効率的に複数資格を取得でき、キャリアの幅を広げることが可能です。
ここでは代表的な免除対象資格について解説します。
第一種・第二種電気工事士(学科試験免除あり)
電気工事士は電気設備の施工に必要な国家資格で、第一種は最大500kW未満の受電設備を含む幅広い工事が可能、第二種は一般住宅や小規模施設が対象です。
電験三種を取得している場合、学科試験が免除され、技能試験のみの受験で済みます。
これは、電験三種で習得した電気理論や法規の知識が電気工事士の学科内容と重複しているためです。
実務に直結する技能資格を短期間で取得できるのは大きなメリットであり、現場での施工業務に直接携わることができるようになります。
また、技能試験に集中できるため合格率も高まりやすく、効率的にキャリアアップを目指せます。
電気工事施工管理技士(実務経験で二次試験から受験可能)
電気工事施工管理技士は、大規模な電気工事現場の施工計画、安全管理、品質管理を担う国家資格です。
通常は一次試験からの受験が必要ですが、電験三種取得者は一定の実務経験を積むことで一次試験が免除され、二次試験から受験可能となります。
この制度により、効率よく上位資格を狙えるのが特徴です。
施工管理技士を取得すれば公共工事の主任技術者や監理技術者を務められるため、企業内での評価も高まり、昇進や待遇改善にも直結します。
電験三種の知識を土台としながら、現場管理のスキルを追加できるため、キャリアの幅が大きく広がるのが魅力です。
建築設備士(受験資格の付与)
建築設備士は、建物における電気・空調・給排水などの設備設計に関与する専門資格です。
本来は大学で建築学や設備工学を専攻した者に受験資格が与えられるケースが多いですが、電験三種を持つことで受験資格が付与される特例があります。
この制度により、学歴や専攻に制約がある人でも受験が可能となり、キャリアの選択肢が広がります。
建築設備士は建築士と設備設計の橋渡しをする役割を担い、建築物の省エネ設計や安全性の確保において重要なポジションを占めています。
電験三種を基盤にしつつ、建築関連の知識を身につけることで、ゼネコンや設計事務所、ビル管理会社などで活躍の場を広げることができます。
消防設備点検資格者(講習受講資格あり)
消防設備点検資格者は、消防法に基づいて設置された消火器や自動火災報知設備などの定期点検を行える資格です。
通常は一定の実務経験や専門知識が必要ですが、電験三種を取得していれば講習の受講資格が与えられます。
これにより、短期間の講習を受けるだけで資格取得が可能となり、業務領域を広げられます。
特にビルメンテナンス業界や設備保守業務に携わる人にとっては、電験三種と組み合わせることで電気設備と消防設備の両方を管理できるようになるため、企業からの評価が高まります。
さらに、法定点検業務を受託できるようになることで独立開業の可能性も広がり、安定した需要を背景に長期的なキャリア形成が期待できます。
| 資格名 | 免除条件 | 免除内容 | 申請方法 |
|---|---|---|---|
| 第一種・第二種電気工事士 | 電験三種取得 | 学科試験免除 | 受験申込時に免状の写しを提出 |
| 電気工事施工管理技士 | 電験三種取得+実務経験 | 一次試験免除、二次試験から受験可能 | 受験申請時に資格証明と実務経歴書を提出 |
| 建築設備士 | 電験三種取得 | 受験資格の付与 | 受験申込時に免状の写しを提出 |
| 消防設備点検資格者 | 電験三種取得 | 講習受講資格が与えられる | 講習申込時に免状の写しを提出 |
電験三種の次に資格を取る際の選び方
電験三種を取得した後にどの資格を狙うかは、人によって最適な答えが異なります。
将来のキャリアビジョンや働き方、収入面での希望によって選ぶべき資格は変わってきます。
ここでは資格選びの基準を整理し、自分に合った道を見極めるためのポイントを解説します。
将来のキャリアプランから逆算する
資格選びでまず重要なのは、自分のキャリアプランを明確にすることです。
たとえば、大手電力会社やプラント企業で技術者としてキャリアを積みたい場合は、電験二種や電験一種といった上位資格を目指すのが有効です。
一方で、現場での施工や工事業務に携わりたい場合は、電気工事士や電気工事施工管理技士が適しています。
さらに将来的に独立を考えるなら、消防設備士やエネルギー管理士など、法定点検やコンサル業務につながる資格が役立ちます。
キャリアプランを軸に考えることで、必要なスキルを効率的に積み上げられ、資格取得が単なるコレクションではなく実務や収入に直結するものとなります。
逆算的に選ぶことで、長期的に無駄のない成長を実現できます。
仕事の幅を広げたいか、専門性を深めたいか
資格を取る目的が「仕事の幅を広げる」ことなのか、「特定分野で専門性を高める」ことなのかを明確にするのも大切です。
幅を広げたい人は、電験三種と組み合わせて電気工事士や消防設備士を取得すれば、設計・施工・保守といった複数領域をカバーでき、現場で即戦力性が高まります。
一方、専門性を深めたい人は、電験二種やエネルギー管理士のように難易度の高い資格を選び、特定領域で強みを発揮する方向が適しています。
幅広さは柔軟なキャリア展開を可能にし、専門性は高度なポジションや専門職に直結します。
自分がどちらを優先したいのかを判断することで、取得する資格の優先順位が見えてきます。
迷ったときは「現職で求められていること」を基準に選ぶのも効果的です。
資格手当・独立可能性・需要を基準に選ぶ
資格取得には労力と時間がかかるため、将来的にどのようなリターンがあるのかも重要な判断基準です。
資格手当が支給される職場であれば、取得することで安定した収入増が見込めます。
また、独立を視野に入れるなら消防設備士やエネルギー管理士といった資格が有効で、法定点検や省エネコンサルといった業務に直結します。
さらに、社会的需要の高さも選ぶ基準の一つです。
再生可能エネルギーや省エネ分野の拡大に伴い、エネルギー管理士や上位の電験資格は将来的にも需要が続く見込みがあります。
このように、資格手当・独立の可能性・需要という3つの観点で比較することで、実際のメリットを数字や将来性で判断しやすくなり、より効果的な資格選びにつながります。
まとめ
今回の記事では、電験三種取得後の次の資格について解説しました。
すでに電験三種を取得している場合には、ぜひ今回の記事を参考にして、次の資格取得を目指してください。
もしまだ電験三種を取得していない場合は、まずは電験三種を早く取得できるように取り組んでいきましょう。
実際、電験三種は、取得するだけでも大きな価値があります。
一方で、その価値が十分に評価されるかどうかは、働く環境次第です。
- 今の職場で資格がどう扱われているか
- 将来的にどんな選択肢があるか
- 転職すべきか、副業という道があるか
無理な提案は行わず、電験三種を持つ方向けの選択肢整理を無料で行っています。