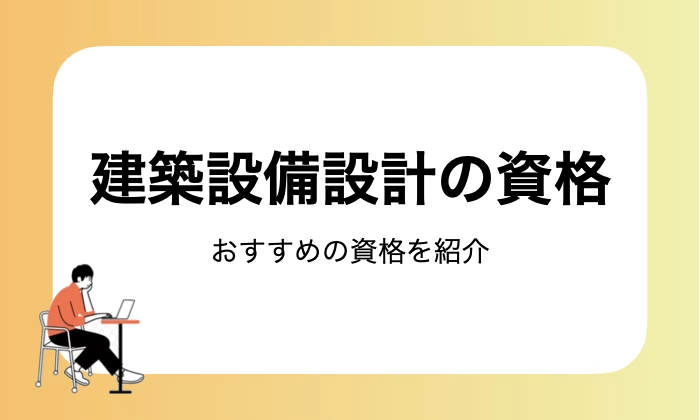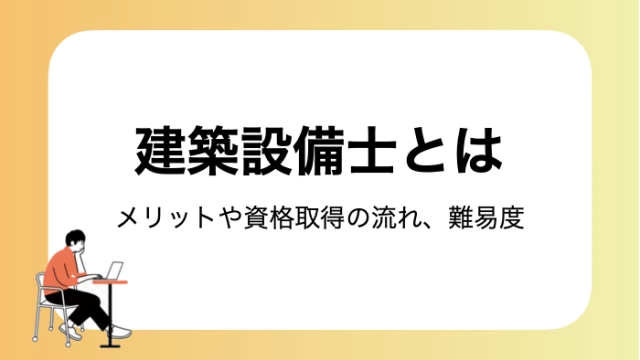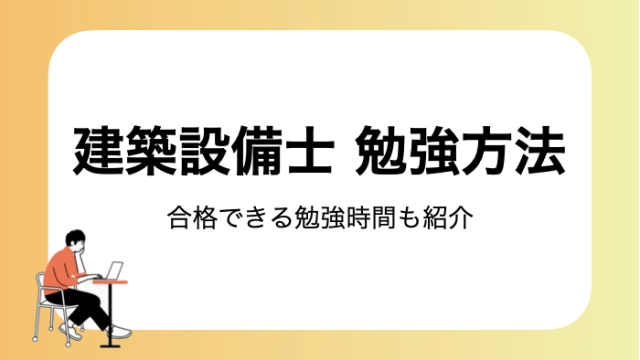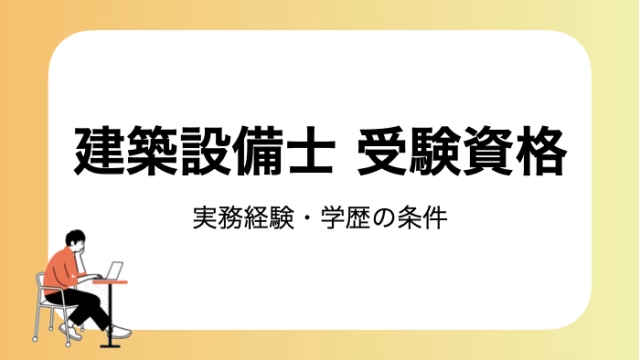「建築設備の設計にはどんな資格が必要なの?」という疑問を抱えていませんか?
そこで、今回は建築設備の設計に関わる主な資格について解説します。
この記事を読めば、建築設備士や設備設計一級建築士、電験三種、技術士などの資格の違いや建築設備の設計職に就くためのステップがわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
建築設備とは?設計との関係性
建築設備とは、建物内で人々が快適かつ安全に過ごすために必要な「空調・電気・給排水・防災・通信」などのインフラ設備を指します。
これらを建物の設計に組み込む業務が「設備設計」であり、意匠設計・構造設計と並ぶ建築設計の重要な分野です。
建築設備の役割とは
建築設備は、単なる機器や配線の設置ではなく、建物全体の機能性と快適性を左右する極めて重要な要素です。
たとえば、空調設備は室内温度の快適性を担い、電気設備は照明や動力の供給、水道設備は衛生環境の維持に直結しています。
こうした設備が適切に設計・配置されていなければ、いくら建物の外観や構造が優れていても、実際に使う人にとって不便で不快な空間になってしまうでしょう。
建築設備の目的は「建物を使いやすくすること」に尽きます。
さらに、近年はエネルギー効率や環境配慮、IoT化といった要素も求められるため、設備設計の専門性はますます高まっています。
建築設計における設備設計の位置づけ
建築設計は大きく分けて「意匠設計」「構造設計」「設備設計」の3つに分類されます。
意匠設計は建物のデザインや使い勝手を、構造設計は建物の強度や耐震性を、そして設備設計は人が生活するうえで必要なインフラを整える役割を担います。
特に設備設計は、建物の見えない部分に関わるため軽視されがちですが、実際には利用者の快適性・安全性・効率性を支える基盤となる重要な業務です。
また、これら3つの設計は独立しているわけではなく、互いに密接に連携しながら進める必要があります。
たとえば、空調機器の設置位置が意匠設計に影響することもあれば、重量物の配置が構造設計に干渉することもあります。
つまり、設備設計は建築全体の完成度を左右する「裏方の要」とも言えるのです。
設備設計の仕事に必要な資格一覧
設備設計の仕事を担ううえで、資格は必ずしも必要ではありませんが、一定の規模や法的要件がある案件では保有が義務付けられることがあります。
ここでは、設備設計の現場で評価されやすい主な資格を紹介します。
建築設備士
建築設備士は、建築士法に基づく国家資格であり、建築士に対して設備設計や工事監理に関するアドバイスを行う専門職です。
受験には指定学科を卒業後、一定の実務経験が求められます。
大学卒で2年以上、短大や高専で4年以上、高校卒であれば6年以上の実務経験が必要です。
この資格を取得することで、設備設計分野での専門性が証明されると同時に、将来的に建築士(一級・二級・木造)を目指す際に、実務経験が免除されるメリットもあります。
特に、設計事務所やゼネコンの設備部門で高く評価される資格の一つです。
なお、建築設備士は設計そのものを独占するわけではありませんが、高度な設備設計や審査への対応などで重要な役割を果たします。
設備設計一級建築士
設備設計一級建築士は、2005年の耐震偽装問題を契機に新設された資格で、大規模建築物の設備設計に必須となる国家資格です。
受験には「一級建築士の資格」と「5年以上の設備設計実務経験」が求められます。
さらに、所定の講習会(3日間)を受講し、修了考査に合格する必要があります。
この資格が求められるのは、3階建て以上・延べ床面積5,000㎡超の建築物に関する設備設計業務であり、その設計を行うか、あるいは設計内容の適合性を確認する責任を負います。
建築確認申請の際には設備設計一級建築士の関与が義務付けられているため、大手設計事務所や総合建設会社では欠かせない存在です。
取得の難易度は高いものの、設備設計における最高峰の資格として位置づけられており、キャリアアップや信頼性の面でも大きなアドバンテージとなります。
技術士(建設部門)
技術士は、科学技術に関する高度な専門知識と応用力を証明する国家資格で、建設業界では「建設部門」が該当します。
設備設計において直接的に設計業務を独占する資格ではありませんが、計画や評価、マネジメントの面で強い説得力を持ち、行政や発注者からの信頼も得やすくなります。
技術士になるには、一次試験と二次試験を経る必要があり、特に二次試験は一級建築士と同等レベルの難関です。
また、建設業法上、営業所における「専任技術者」として認定されることから、会社としても採用に積極的な傾向があります。
設備設計の現場では、特に品質管理・コスト管理・省エネ対応などの観点から技術士の知見が活かされる場面が多く、プロジェクト全体の監修的立場で活躍することも可能です。
電験三種(第三種電気主任技術者)
電験三種は、電気主任技術者として認定される国家資格で、主に電気設備の保守・運用を担う人材に求められます。
設備設計そのものを行ううえで必須ではありませんが、電気系統の安全性・信頼性の確保という観点から、設備設計職にとって非常に有利な資格です。
特に、電気設備を多く扱う大規模施設(工場・病院・商業施設など)では、電験三種の知識がそのまま設計業務の質向上につながります。
受験資格に制限はなく、誰でも受けられるため挑戦しやすい一方、合格率は10〜15%前後と低く、基礎からしっかり学ぶ必要があります。
建築設備の設計業務においては、受変電設備や非常用電源系統、系統連系設計などの場面で、電験三種の知識が現場で強く求められるでしょう。
資格取得により、設計と保守の両面で活躍できるスキルセットが構築できます。
建築設備の設計職に就くためのステップ
建築設備の設計職に就くには、必要な知識・スキルの習得と実務経験の積み重ねが重要です。
加えて、キャリアアップに有利な資格取得も将来性を広げるカギとなります。
以下では、就職までに踏むべき具体的なステップを順を追って解説します。
- 建築設備設計の基礎を学ぶ
- 実務経験を積む
- 設計職に有利な資格を取得する
- 就職・転職活動を行う
建築設備設計の基礎を学ぶ
建築設備の設計職を目指すには、まず基礎知識の習得が欠かせません。
建築設備とは、空調・給排水・電気・通信・防災などのインフラ設備全般を指し、建物内の快適性や安全性を支える非常に重要な分野です。
これらの知識は独学でも可能ですが、より体系的に学ぶためには大学・専門学校などで建築・設備・電気・機械系の学科を履修するのが一般的です。
加えて、建築基準法や電気設備技術基準、省エネルギー法といった関連法規の理解も必要です。
特に建築設備設計は、設計した設備が法令に適合していなければ建築確認が下りないため、単なる技術だけでなく「法規を守る設計」が求められます。
また、設計ソフト(AutoCADやRebro、Tfasなど)の操作スキルも現場では重宝されるため、学生のうちからCADソフトに触れておくと実務への適応がスムーズになります。
実務経験を積む
学んだ知識を実務に活かす段階では、設備設計事務所、建設会社、設計部門を持つゼネコンなどでの就業が一般的です。
特に新卒者の場合、設備設計職としての募集は限られることもあるため、設計補助や現場管理職などで経験を積んでから、設計職に移行するケースも多くあります。
設備設計の実務では、建築主や意匠設計者との打ち合わせ、図面作成、各種計算、設備機器の選定、法令チェックなど多岐にわたる業務に関わることになります。
これにより、単に図面を引くだけでなく、「設備をどう配置すれば、最も合理的で安全か」という判断力も養われていきます。
また、建築設備は複数の分野が複雑に絡み合うため、空調・電気・給排水それぞれの専門家と連携する調整能力も求められます。
一定の実務経験を積むことで、業界での評価や信頼も高まり、より大きなプロジェクトや責任あるポジションを任されるようになります。
特に資格取得を視野に入れるなら、この実務経験が受験資格の要件にもなってくるため、若いうちから意識的に経験を重ねることが重要です。
設計職に有利な資格を取得する
建築設備設計の職に就き、キャリアを高めるには資格の取得が大きな武器となります。
まず設備設計に特化した国家資格として「建築設備士」があります。
この資格は、建築士への助言を行う専門家としての証であり、一定の実務経験と学歴を満たせば受験可能です。
建築設備士を取得することで、建築士の受験時に実務経験が一部免除されるなどのメリットもあります。
より高度な資格としては「設備設計一級建築士」があり、こちらは一級建築士の保有と設備設計の実務経験が5年以上あることが条件です。
3階建て以上かつ延べ床面積5,000㎡超の大規模建築物を設計する場合、必ず関与が義務付けられており、設計職としての社会的信用度は非常に高くなります。
また、電気設備設計に関心があるなら「第三種電気主任技術者(電験三種)」の取得もおすすめです。
特にビルや工場など電力需要が大きい建築物を扱う場合には、電気設備に対する深い理解が求められ、資格者として高く評価されます。
他にも「技術士(建設部門)」などの資格も、設備設計における指導的立場やマネジメント職を目指すうえで有利に働きます。
就職・転職活動を行う
必要な知識と経験、資格を身につけたら、いよいよ就職または転職のステップに入ります。
新卒であれば、大学の就職課や合同企業説明会を活用して、設備設計職を募集している企業を探すとよいでしょう。
一方で、中途採用を狙う場合は、建築・設備系に特化した転職エージェントを利用することで、よりマッチした求人に出会いやすくなります。
面接や書類選考では、どのような案件を担当したか、どの分野に強いか、CADソフトの使用経験やプロジェクトでの役割などを具体的にアピールすることが求められます。
また、建築設備士や電験三種などの資格を保有していると、その時点で書類選考の通過率が上がることも多いです。
特に近年は、ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)設計や再生可能エネルギーとの連携、BIMの活用といった先進的な設計への関心も高まっており、それらの知識・経験がある人材は各社が積極的に採用したいと考えています。
今後、建築設備設計の現場はますます進化していくため、柔軟に学び続ける姿勢と実践力が大きな強みになります。
まとめ
今回の記事では、建築設備設計をおこなううえでの資格について解説しました。
資格がなくても設計業務に携われますが、担当できる業務や信頼性には限界があります。
将来的なキャリアの幅を広げるためにも、実務経験を積みながら資格取得を積極的に目指しましょう。
なお、建築設備士は、本来は設計・計画段階で力を発揮する資格です。
しかし現場では、
- 資格を持っていても業務内容が変わらない
- 責任だけ増えて評価が伴わない
- 転職すべきか、副業という道があるか
といったケースも見られます。
今の環境が適正かどうか、転職・副業を含めた選択肢整理を無料で行っています。