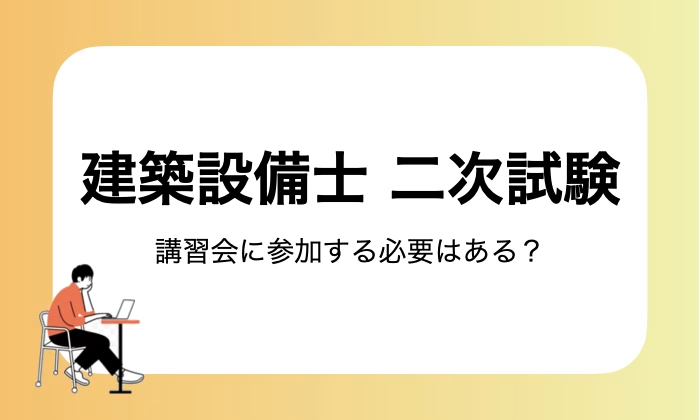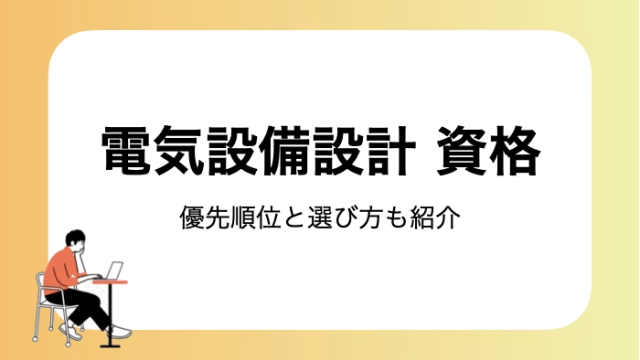「講習会に参加すべきか迷っている」ということはありませんか?
建築設備士の二次試験を受けるにあたって、講習会への参加が本当に必要なのか迷う人は多いです。
そこで、今回は講習会の必要性や内容、参加時の注意点について解説します。
この記事を読めば、講習会に参加するメリットや活用方法、独学との違いがわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
建築設備士の二次試験と講習会の関係
建築設備士の二次試験対策として注目されるのが、講習会の活用です。
一次試験と異なり、実技を含む二次試験には特有の準備が必要であり、そのために講習会が存在します。
ここでは、二次試験の概要や講習会の主催者、開催時期・会場・受講料について詳しく解説します。
そもそも二次試験とは?一次試験との違い
建築設備士試験は、一次試験と二次試験の二段階で構成されています。
一次試験は主に学科試験で、建築設備に関する幅広い知識を問うマークシート形式です。
一方、二次試験は記述式および製図試験で、より実務的な知識と応用力が求められます。
とくに製図問題では、空調・衛生・電気設備といった各分野における実践的な設計力が試されるため、単なる暗記では太刀打ちできません。
また、二次試験に関しては市販の対策教材がほとんどなく、情報源が限られているのが実情です。
そのため、独学だけでは対応が難しいと感じる受験者も少なくありません。
講習会は、こうした課題に対応するための重要な手段であり、実際に合格者の多くがこの講習会を利用して学習を進めています。
講習会は誰が主催しているのか
日建学院など資格学校でも二次試験の対策をおこなっていますが、建築設備士の二次試験講習会というと一般的に、「日本設備設計事務所協会連合会(JESDO)」が主催しているもののことを指します。
この団体は、建築設備の設計・技術力向上を目的に、全国の設備設計事務所で構成されている専門機関です。
毎年、建築設備士の試験対策を目的とした公式な講習会を企画・実施しており、多くの受験生が参加しています。
この講習会では、空調・衛生・電気設備それぞれの専門家による講義が行われ、二次試験で求められる設計図作成や記述対策に直結する実践的な知識が得られます。
また、参加者には専用のテキストが配布されますが、このテキストが実質的に「唯一の対策教材」となる点も重要です。
市販されているわけではなく、講習会に参加しないと入手が難しいため、多くの受験者にとって価値ある情報源となっています。
講習会の開催時期・会場・受講料
講習会は例年5月下旬に日本設備設計事務所協会連合会の公式サイトで案内され、6月上旬から申し込み受付が開始されます。
一次試験の合格発表前から申し込めるため、一次試験に自信がある人や免除者は早めの申し込みが推奨されます。
定員制のため、締切前に満席になるケースもあるので注意が必要です。
開催地は全国4都市(札幌・東京・大阪・福岡)で、アクセスしやすい会場が選ばれています。
受講料は25,000円(税込)で、これにはテキスト代も含まれています。
1日で3つの分野(空調、衛生、電気)をカバーする集中講義形式で、9時から19時までびっしりと組まれたスケジュールです。
なお、参加が難しい人向けにテキストのみの購入が可能な年もありますが、発送が遅れる・情報の正誤表対応が必要などのデメリットがあります。
やはり直接参加することで、講師からの直接解説や質疑応答の機会を得られる点が大きなメリットです。
建築設備士講習会に参加するメリット
建築設備士の二次試験において、講習会は独学では得られない多くのメリットを提供してくれます。
特に、試験対策用テキストの入手や講義の質、参加者限定の情報など、合格に直結する内容が豊富です。
ここでは講習会参加の具体的な利点を詳しく解説します。
テキストが重要な理由
建築設備士の二次試験において最大の課題は、市販の問題集や参考書がほとんど存在しない点です。
そのため、講習会で配布されるテキストは、事実上「唯一の実践的教材」と言えます。
このテキストは、日本設備設計事務所協会連合会が試験の傾向や出題パターンを踏まえて作成しており、合格に必要な知識や製図例が網羅されています。
また、過去に出題された問題に対する模範解答や考え方の解説も含まれているため、単なる知識の暗記ではなく、実際に使えるスキルを養うことができます。
加えて、講習会で解説される内容と連動しており、講義を聞いたあとに自宅で復習する際の学習効率も大幅に向上します。
ただし、テキストにはごくまれに誤植や内容の誤りが含まれる場合があり、後日公式サイトに正誤表が掲載されることもあるため確認は必須です。
とはいえ、その情報価値は非常に高く、これを持たずして合格を目指すのは困難だと言っても過言ではありません。
講義内容と当日の流れ
講習会当日は、朝9時から夕方19時までの長時間にわたり、3つの主要分野(空調設備・衛生設備・電気設備)について順に講義が行われます。
スケジュールは非常にタイトですが、それぞれの分野に精通した講師による専門的な解説が受けられるため、密度の濃い一日になります。
午前中は空調設備、昼過ぎから衛生設備、夕方から電気設備の講義が組まれており、それぞれの講義は約3時間ずつです。
講義はスライドとプロジェクターを用いて進行し、図面や試験例題をもとにした解説が中心となります。
また、出題傾向や採点基準、減点されやすいポイントなど、試験に直結する実務的な情報も紹介されます。
テキストと連動した内容が中心であるため、事前に目を通しておくことで理解度が高まります。
加えて、参加者同士の雰囲気から受験へのモチベーションが高まるという心理的な効果も期待できます。
時間的にはハードですが、1日で全体像を把握できる非常に有益な場です。
質疑応答や独学との違い
講習会に参加する最大のメリットのひとつが、講師との「直接のやり取り」ができる点です。
講義の最後には質疑応答の時間が設けられており、受講者が抱える疑問点に対して講師が丁寧に解説してくれます。
この場での質問は、他の参加者にとっても有益で、独学では得られない「現場の知恵」が得られる瞬間でもあります。
また、独学では理解が難しい製図の細かいポイントや、設備間の配置バランス、納まりなどの実務的な知識も、図面を使いながら視覚的に学ぶことができます。
これにより、試験本番での図面作成にも自信をもって臨めるようになります。
独学では時間配分や優先順位の判断も難しく、結果として学習のムラが出ることもありますが、講習会ではその心配がありません。
受講者全体の理解度を意識しながら講義が進むため、自分が見落としていた視点や課題にも気づけます。
実際に合格者の多くが「講習会が合格の決め手になった」と振り返るのも、このような実用性の高さに理由があります。
講習会に参加しない選択肢もある?
建築設備士の二次試験対策において、多くの受験者が講習会の参加を検討しますが、状況や環境によって参加が難しいケースもあります。
この見出しでは、講習会に参加しない選択肢として「テキストのみ購入」「資格学校との比較」「独学による合格可能性」について詳しく解説します。
テキストだけ購入できる場合も
講習会に参加できない、あるいは参加を見送る場合でも、講習会で配布されるテキストだけを入手するという方法があります。
日本設備設計事務所協会連合会では、毎年ではないものの、テキスト単体での販売を実施する年があります。
これは、会場に足を運べない受験者にとってはありがたい制度であり、最低限の情報収集手段として活用できます。
ただし、テキストのみ購入した場合、発送時期が講習会後となるため、講習会参加者に比べて入手が遅れる傾向があります。
そのため、学習スケジュールに余裕を持たせることが重要です。
また、内容に誤りが含まれていることもあるため、正誤表を公式サイトで確認しながら学習を進める必要があります。
テキストは講義と連動した設計になっているため、解説がない状態では一部理解が難しい箇所もあります。
したがって、十分な予備知識がある、あるいは過去問の出題傾向を把握している受験者にとっては有効な手段ですが、初学者にはややハードルが高く感じるかもしれません。
資格学校との違いと比較
講習会に参加しない場合のもう一つの選択肢が、日建学院などの資格学校に通うという方法です。
資格学校は、通年で受講できるカリキュラムを提供しており、個別指導や添削サービスが充実している点が特徴です。
一方で、費用面では講習会(約25,000円)に比べ、資格学校は10万円〜20万円と大きく上回るため、予算に制限がある方には不向きな場合もあります。
また、資格学校は長期間の学習を前提としているため、短期間で集中して対策したいという受験者には不向きなケースもあります。
特に実務経験があり、ある程度の基礎知識が備わっている受験者にとっては、講習会のような1日集中型の方が効率的と感じることもあります。
一方で、資格学校の強みは、個別対応によるフィードバックと、添削課題の提出による実力チェックができる点です。
講習会では一方的な講義が中心となるため、自分の理解度を客観的に把握したい人にとっては、資格学校のサポートは有効です。
自身のスケジュール・学習スタイル・予算に応じて、どちらを選ぶべきか慎重に判断しましょう。
独学での合格は可能か
建築設備士の二次試験を独学で突破することは可能です。
ただし、相応の準備と工夫が必要になります。
市販の教材がほとんど存在しないため、講習会テキストを入手できない場合は、過去の試験問題や受験体験記、ネット上の情報を駆使して、自分なりの勉強法を確立する必要があります。
特に製図に関しては、出題形式や図面のルールに慣れていないと、何から手を付ければよいか迷うことも多く、初学者にとっては難易度が高い分野です。
独学で合格した人の多くは、過去問を繰り返し練習し、時間配分や図面の完成度を意識して演習を重ねています。
また、情報の信頼性を見極める力も重要です。
ネットには多くの断片的な情報が存在しますが、内容が古かったり、試験傾向とズレていたりすることもあるため、最新情報に基づいて学習を進める工夫が求められます。
独学はコストを抑えられる反面、孤独な戦いでもあります。
モチベーションを維持するために、SNSや勉強会などを活用して情報交換をするのも一つの手です。
独学でも十分に合格は可能ですが、自分に合った学習環境を整えることが最大のポイントとなります。
講習会を受ける前の準備と注意点
建築設備士の講習会は、内容が非常に濃く合格に直結する重要な機会です。
その効果を最大限に引き出すためには、事前の準備と当日の行動に注意が必要です。
この見出しでは、申し込み時期・当日の行動・予習の重要性について詳しく解説します。
申込はいつから?すぐ満席になる理由
建築設備士の講習会は例年6月上旬頃から申し込みがスタートします。
しかし、募集開始から短期間で定員が埋まってしまうケースが多いため、早めの対応が必須です。
特に一次試験後の自己採点で合格の見込みがあると判断した方々が一斉に申し込むため、枠の争奪戦になります。
また、一次試験免除の方や受験経験者の中には、一次試験前から講習会への申込みを行うケースもあります。
つまり、試験結果を待ってから申し込もうとすると、すでに希望の会場が満席になっている可能性があるのです。
そのため、早期申込ができる人は試験前に申込を済ませておくと安心です。
募集状況や開催スケジュールの詳細は、日本設備設計事務所協会連合会の公式ホームページにて公開されます。
講習会は全国で限られた都市(札幌・東京・大阪・福岡)のみで開催され、各会場の定員も限られているため、申込みのタイミングを逃さないように注意しましょう。
早めに会場入りすべき理由とは
講習会当日は、講義開始が午前9時からと早く、長丁場となるため、余裕をもって会場に到着することが非常に重要です。
理由のひとつは「座席の位置」にあります。
指定席ではないため、到着が遅れると会場の後方にしか座れず、講義中のスクリーンやプロジェクターの文字が見えづらくなる可能性があります。
また、後方の席では講師の声が聞き取りにくいといった問題も生じやすく、集中力を欠く原因にもなります。
特に建築設備士の講習会は専門的かつ実務的な内容が多いため、聞き逃しや視認性の悪さは理解度に大きく影響します。
早めに着くことで、テキストや筆記用具の準備、トイレや軽食などの確認も余裕をもって済ませられます。
周囲の参加者とも情報交換ができるかもしれません。
貴重な1日を最大限に活かすためにも、講義開始の30分前には会場に到着しておくのが理想です。
予習で講義の理解度が大きく変わる
講習会の内容をしっかりと理解し、自分の学習に活かすためには、事前の予習が極めて効果的です。
テキストは事前送付されないため、配布されるまでは過去問や前年度の問題を見ながら試験形式に慣れておくことをおすすめします。
特に、製図問題に触れておくことで、講義で解説される図面や記述のポイントがスムーズに理解できます。
また、予習によって「自分が何を理解していないか」「どこが曖昧なのか」といった弱点が明確になり、講義中に重点的に聞くべきポイントが整理されます。
これは受講の質を大きく左右する重要な準備です。
講義は専門的な用語や手法が多く登場するため、ある程度の知識を持って臨むことで、講師の説明が「初見情報」にならず、理解が深まりやすくなります。
結果として、講義後の復習にもスムーズに取り組めるようになります。
受講料の25,000円を最大限に活かす意味でも、予習は不可欠といえるでしょう。
建築設備士の二次試験合格を目指すなら
建築設備士の二次試験は、実践力と継続的な学習が求められる難関試験です。
講習会の活用を含め、正しい学習法とモチベーション維持が合格のカギを握ります。
ここでは、テキストの使い方・製図学習・継続学習のコツについて詳しく解説します。
講習会のテキストを最大限に活用する方法
講習会で配布されるテキストは、建築設備士二次試験対策における最重要教材です。
市販の教材が存在しない中で、このテキストは過去問の出題傾向、図面の記載方法、記述式対策などが網羅されており、独学受験者にとっては合格への指針となります。
効果的に活用するには、まず全体を通読し、構成と出題意図を把握しましょう。
そのうえで、過去問題と照らし合わせながら内容を実践に落とし込むことで、単なるインプットから応用力を身につけることができます。
また、各ページにメモを書き込んだり、自分なりの補足を加えたりすることで、復習のたびに理解が深まり、記憶の定着にもつながります。
特に、講習会での解説とテキストの内容が密接にリンクしているため、講義当日にしっかりとノートを取り、後日見返す習慣をつけましょう。
講習会を受けただけで満足せず、テキストを繰り返し使い込む姿勢が、最終的な合格率を大きく左右します。
製図と暗記を繰り返す学習が合否を分ける
建築設備士の二次試験では、製図力と専門知識の暗記力が問われます。
とくに製図は「見て覚える」「描いて覚える」作業の繰り返しが重要です。
講習会で得た知識を元に過去問の製図問題を何度も模写し、図面の構成や寸法感覚、各設備の配置バランスを体で覚えていくことが合格への近道です。
さらに、暗記分野では空調・衛生・電気設備に関する記述問題が出題されるため、講習会テキストや自作ノートを使って定期的に復習しましょう。
特に減点されやすいミス(記述の漏れ・用語の誤用など)を洗い出し、ミスノートを作成することも効果的です。
製図と暗記は、それぞれ独立したスキルのように見えますが、実際には密接に関係しています。
たとえば、空調機器の配置を理解するには原理の暗記が不可欠であり、記述問題を理解するには図面の知識が求められます。
これらを意識的に結び付け、反復することで知識の定着と実践力の向上を図りましょう。
継続的な学習とモチベーション維持がカギ
建築設備士の二次試験は、試験範囲が広く、かつ実技要素も含まれるため、短期集中型の学習では合格が難しい傾向があります。
したがって、毎日の積み重ねによる継続的な学習が合否を分ける重要な要素となります。
モチベーション維持のためには、「学習の見える化」が効果的です。
たとえば、カレンダーに製図の練習日を記録したり、学習時間や到達目標を一覧化することで、進捗を客観的に把握できます。
また、SNSや勉強仲間と進捗を共有するのも、やる気を保つ手段として有効です。
さらに、「なぜ建築設備士を目指すのか」という目的を定期的に振り返ることも大切です。
目的意識が曖昧になると、学習が惰性になりがちです。
小さな成功体験(図面を1枚描き切った、記述を暗記できた等)を積み重ねることで、前向きな気持ちを維持しやすくなります。
合格までの道のりは決して短くありませんが、日々の努力を継続し、講習会で得た知識を活かして学習を継続すれば確実に合格に近づけるでしょう。
まとめ
今回の記事では、建築設備士の二次試験対策の講習会について解説しました。
今回お伝えした内容を参考に、ぜひ建築設備士の取得を目指して頑張ってください。
建築設備士は、本来は設計・計画段階で力を発揮する資格です。
しかし現場では、
- 資格を持っていても業務内容が変わらない
- 責任だけ増えて評価が伴わない
- 転職すべきか、副業という道があるか
といったケースも見られます。
今の環境が適正かどうか、転職・副業を含めた選択肢整理を無料で行っています。