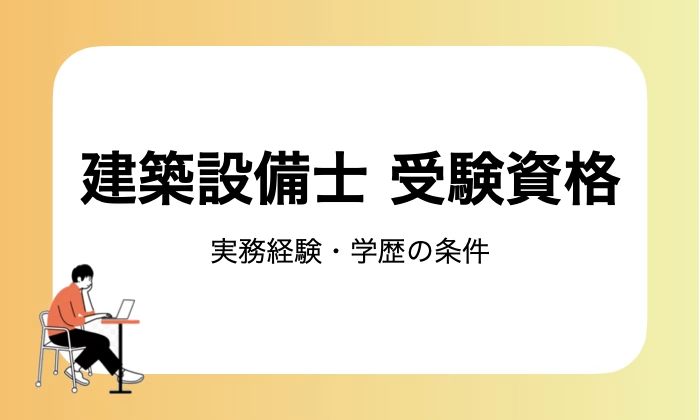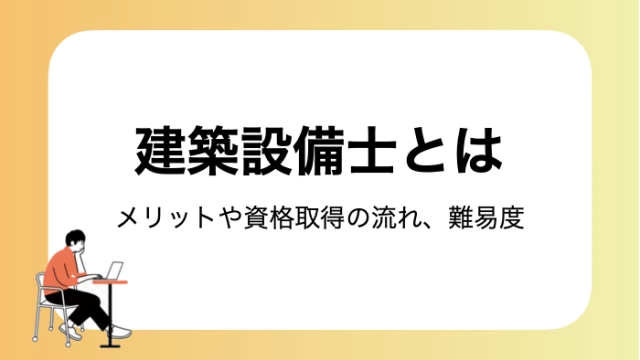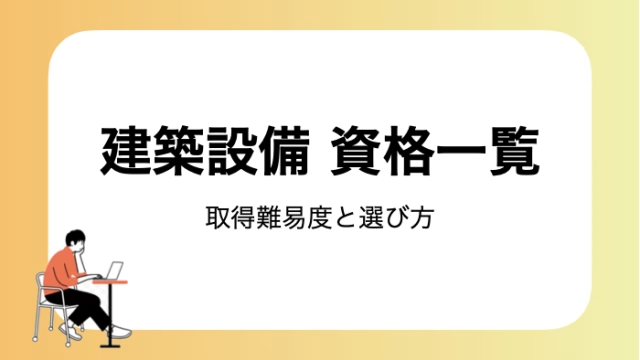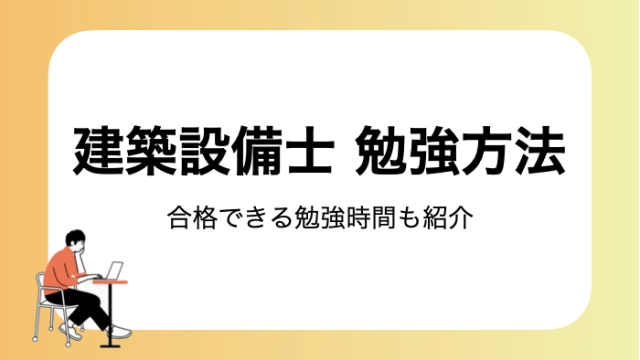「建築設備士の受験資格、実務経験が足りるか不安…」ということはありませんか?
建築設備士を受験する資格を満たしているか自信が持てない方は少なくありません。
特にビルメンテナンス業務や補助作業しか経験していない場合、「本当に受験資格があるのか?」と不安になるものです。
そこで、今回は建築設備士の受験資格に必要な実務経験や学歴、資格による緩和条件の考え方について解説します。
この記事を読めば自分の職歴や学歴で受験資格があるかどうかを確認でき、今後のキャリアプランを立てやすくなりますので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
建築設備士の受験資格とは?
建築設備士の資格を取得するためには、特定の学歴や資格に加え、実務経験が必要です。
特に実務経験の内容や年数は、学歴や保有資格によって条件が大きく異なります。
建築設備士 受験資格 実務経験の基本
建築設備士の受験資格で最も重要なのが「実務経験」です。
これは建築設備に関する実務に携わった年数を指しますが、すべての業務が該当するわけではありません。
実務経験として認められるのは、建築設備の設計や施工管理、保全、積算など、専門的な内容に限られます。
例えば、設計事務所や建設会社、設備工事会社などで建築設備に直接関与していた業務は実務経験として認められます。
一方、トレース作業や機器の運転、記録作業など、補助的な作業にとどまるものはカウントされないのでご注意ください。
建築設備士の受験資格に必要な実務経験
建築設備士の受験資格を得るためには、所定の実務経験を積むことが必須です。
必要な年数は学歴や所持資格によって異なり、また実務経験として認められる業務の内容にも明確な基準があります。
ここでは、実務経験の判断基準や注意点について詳しく解説します。
実務経験の年数と判断基準
建築設備士の受験資格において求められる実務経験の年数は、学歴や保有資格によって細かく定められています。
たとえば、大学で建築・電気・機械などの学科を卒業した場合は、卒業後2年以上の実務経験が必要です。
短期大学や高等専門学校卒業者は4年以上、高等学校卒業者であれば6年以上の実務経験が求められます。
一方で、1級建築士や1級電気工事施工管理技士、電気主任技術者(第1〜第3種)など、一定の国家資格を保有している場合は、学歴に関係なく2年以上の実務経験で受験資格を得ることが可能です。
これを「緩和措置」と呼びます。
また、学歴や資格がない場合でも、9年以上の実務経験を積むことで受験資格を得られる制度もあります。
ただし、この場合も業務内容が適切である必要があるため注意が必要です。
実務経験に該当する業務とは
建築設備士の受験資格で実務経験として認められるのは、「建築設備に直接関わる業務」に限られます。
具体的には、建築設備の設計業務、工事監理、施工管理、積算、維持管理、保全、改修、教育、研究などが該当します。
これらの業務を行っていることが、実務経験として認められる最低条件です。
勤務先の例としては、設計事務所、建設会社、設備工事会社、設備機器メーカー、不動産管理会社、大学や研究機関、官公庁などが挙げられます。
ただし、注意点として、建築業界で働いていても、単に設備機器を運転したり、設計図をトレースするだけの補助業務では実務経験として認められません。
ビルメンテナンス業務に従事している方の場合、「建築設備の保全・改修」にあたる業務であれば実務経験としてカウントされる可能性があります。
ただし、日常点検や清掃のような作業は該当しないため、具体的な業務内容をよく確認する必要があります。
自己申告制と記入の注意点
建築設備士の受験申込時には、実務経験を所定の申告フォームに記入する必要があります。
これは自己申告制であり、建築士試験のように第三者による証明書の提出は求められません。
しかしながら、だからといって自由に記載してよいというわけではなく、虚偽の申告があった場合には後々のトラブルにつながる可能性もあります。
たとえば、試験実施機関が申告内容に疑問を感じた場合、追加の説明を求められたり、補足書類の提出が必要になったりすることがあります。
そのため、実際に携わった業務内容を正確かつ具体的に記載することが重要です。
特にビルメン業務や設備保守の職歴を記載する場合には、「改修工事の立案に関わった」「空調設備の更新計画を作成した」など、建築設備に関わったことを示す具体的な記述が求められます。
曖昧な表現や形式的な職種名だけでは不十分なので、実務経験が受験資格に該当するかどうか不安な場合は、公式サイトの情報を参照したり、相談窓口に問い合わせたりすることもおすすめです。
建築設備士の受験資格における学歴要件
建築設備士試験の受験には、実務経験に加えて学歴が関係するケースが多くあります。
どの学校を卒業したか、どの分野の課程を修了したかによって、求められる実務経験年数が異なるため、学歴要件は非常に重要です。
以下では、学歴ごとの受験条件や注意点を詳しく解説します。
大学・短大・高専・高校卒業者の要件
建築設備士の受験資格では、卒業した学校の種別に応じて、必要な実務経験年数が定められています。
たとえば、大学で建築・機械・電気などの関連学科を卒業した場合、必要な実務経験は2年以上です。
短期大学や高等専門学校を卒業している場合は、4年以上の実務経験が求められます。
また、高等学校卒業者であれば6年以上の実務経験が必要です。
これらの学歴に共通して重要なのは、「建築・機械・電気またはこれらに準ずる課程を修了していること」です。
たとえば文系学部やまったく無関係な分野の学歴では、たとえ大学卒であっても受験資格に該当しない可能性があります。
また、受験申込時には卒業証明書の提出が必要になります。
証明書の発行には時間がかかることがあるため、出願期限に間に合うよう早めに準備を進めておくことが重要です。
特に、卒業から年数が経っている場合は、大学等に問い合わせる時間も見込んでおきましょう。
他資格による受験資格の緩和措置
建築設備士の受験資格には学歴や実務経験の他に、特定の国家資格を保有していることで実務経験年数が短縮される「緩和措置」が設けられています。
ここでは対象となる資格や緩和の内容、注意点について詳しく解説します。
受験資格が緩和される対象資格
建築設備士の受験資格における実務経験年数は、学歴のみで判断する場合と比較して、一定の資格を保有していると緩和されます。
たとえば、次のような資格が対象です。
- 1級建築士
- 1級電気工事施工管理技士
- 1級管工事施工管理技士
- 空気調和・衛生工学会設備士
- 電気主任技術者(第1種〜第3種)
これらの資格を保有している場合は、学歴に関わらず2年以上の実務経験を積めば、建築設備士の受験資格が得られるとされています。
つまり、大学や高専を卒業していない場合でも、これらの資格を持っていれば通常よりも短い期間で受験資格を取得できるのです。
このような「建築設備士 受験資格 緩和」制度は、既に専門性の高い資格を持っている人が、より効率的にキャリアアップを図れる仕組みとして活用されています。
特に実務経験が長く、すでに他資格を取得済みの方には大きなメリットとなるでしょう。
電気主任技術者と受験資格の関係
「建築設備士 受験資格 電気主任技術者」として検索されることも多いように、電気主任技術者の資格を持っていると、受験資格の緩和対象になります。
これは、第1種から第3種までいずれの区分でも対象とされており、保有していれば実務経験2年以上で受験可能です。
ただし、注意すべき点は「建築設備に関する実務経験」が必須であることです。
電気主任技術者としての実務経験があっても、その内容が発電所や工場の電気系統の管理であり、建築設備(空調・給排水・電気設備など)に直接関わっていない場合は、建築設備士の受験資格にカウントされない可能性があります。
したがって、資格を取得しているだけではなく、その後にどのような業務を行ってきたかが重要となります。
設備設計事務所や建築設備を扱う現場での経験があれば、よりスムーズに受験資格を得ることができるでしょう。
ビルメンテナンス業務は受験資格に含まれる?
建築設備士試験の受験を考える中で、ビルメンテナンス業務に従事している人が「自分の職歴が受験資格として認められるのか?」と不安に思うケースは多くあります。
ここでは、ビルメン業務が実務経験として認められる条件や判断のポイントについて解説します。
ビルメン業務の中でも該当する業務とは
ビルメンテナンス業務と一口に言っても、その内容は多岐にわたります。
建築設備士の受験資格において実務経験として認められるのは、建築設備の「保全」や「改修」を行う業務です。
たとえば、空調や給排水、電気設備の修繕計画の立案や、実際の更新工事への関与などが該当します。
公益財団法人 建築技術教育普及センターの基準によると、「維持管理会社等での建築設備の保全、改修を伴う業務」が対象であると明記されています。
これに該当するような、設備機器の更新提案や見積書作成、改修工事の監理といった業務を日常的に行っている場合は、受験資格として認められる可能性が高いです。
ただし、日常点検や清掃、報告書の記録、巡回などのルーチン作業のみでは「建築設備に関する専門的な実務」とはみなされません。
このような補助的・作業員的な業務にとどまる場合は、年数を積んでいても受験資格としてはカウントされないため注意が必要です。
ビルメン業務で実務経験を証明するには
ビルメン業務が建築設備士の受験資格として認められるかどうかは、実務内容をどれだけ明確に説明できるかにかかっています。
建築設備士試験では実務経験は「自己申告制」となっており、申込時に所定の実務経歴フォームへ職歴の詳細を入力する必要があります。
ここで、単なる職種名や業務範囲だけを記載するのではなく、具体的な業務内容を明記することが求められます。
たとえば、「空調機器の更新に関する現場調査・設計補助・発注手続きまで担当」や、「給排水設備の老朽化に伴う改修計画を立案し、施工会社との調整を行った」などのように、どの設備に、どのように関与したのかを具体的に記述することが重要です。
また、勤務先の実績や社内での担当範囲なども明示できると信頼性が増します。
企業によっては、社内での職務記録や業務報告書、案件リストなどを保管している場合もあるため、こうした資料をもとに正確に申告内容を作成するのが望ましいでしょう。
実務経験がない人はどうすればよいか?
建築設備士の受験には、学歴や資格の有無にかかわらず「実務経験」が必須条件です。
そのため、現時点で実務経験がない方は、まず実務経験を積むための行動が必要になります。
以下では、未経験者が受験資格を得るまでに踏むべきステップについて解説します。
実務経験を積むための職場選び
実務経験がない場合、まず重要なのは建築設備に関わる業務に従事できる職場へ就職または転職することです。
実務経験として認められる業務は、建築設備の設計、工事監理、施工管理、積算、保全、改修などであり、勤務先としては設計事務所、設備工事会社、建設会社、ビルメンテナンス会社、官公庁などが該当します。
なかでも未経験者にとっては、アシスタント業務や補助からスタートし、徐々に設計や管理などの中核業務に関わることで、受験資格につながる経験を積むことが可能です。
求人票や面接時には「建築設備に関する業務に携われるか」「設計や施工管理などに関われる可能性があるか」を必ず確認しましょう。
また、ビルメンテナンス業務であっても「保全・改修」に関わる業務内容であれば実務経験として認められるケースがあります。
自分がどのような業務に従事できるか、就業先と相談しながらキャリアを積み上げていくことが重要です。
学歴や資格と実務経験の関係を理解する
実務経験を積む際には、自分の学歴や保有資格に応じて、必要な経験年数が異なることを理解しておく必要があります。
たとえば、建築・機械・電気系の大学を卒業していれば、2年以上の実務経験で受験資格が得られます。
一方で、高校卒業の場合は6年以上、学歴が該当しない場合は9年以上の実務経験が必要です。
また、他の国家資格を取得している場合(例:電気主任技術者、1級施工管理技士など)は、受験資格が緩和され、2年程度の実務経験で受験できるケースもあります。
そのため、まずは自分がどの区分に該当するのかを把握し、それに応じた実務経験年数の目標を立てましょう。
特に、受験資格を得るまでに時間がかかることがわかっている場合は、早期にキャリアプランを立てることが大切です。
いずれ受験を目指すのであれば、日々の業務を「実務経験として証明できるように記録しておく」意識を持つことが、将来的な申請をスムーズにします。
必要に応じて、上司や職場に記録の保管を相談しておくのも一つの方法です。
まとめ
今回の記事では、建築設備士の受験資格について解説しました。
学歴や実務経験、他資格によって条件が異なるため、必ず公式情報を確認し、自身の経歴に合った要件を整理しておきましょう。
また、ぜひ建築設備士の取得を目指して頑張ってください。
建築設備士は、本来は設計・計画段階で力を発揮する資格です。
しかし現場では、
- 資格を持っていても業務内容が変わらない
- 責任だけ増えて評価が伴わない
- 転職すべきか、副業という道があるか
といったケースも見られます。
今の環境が適正かどうか、転職・副業を含めた選択肢整理を無料で行っています。