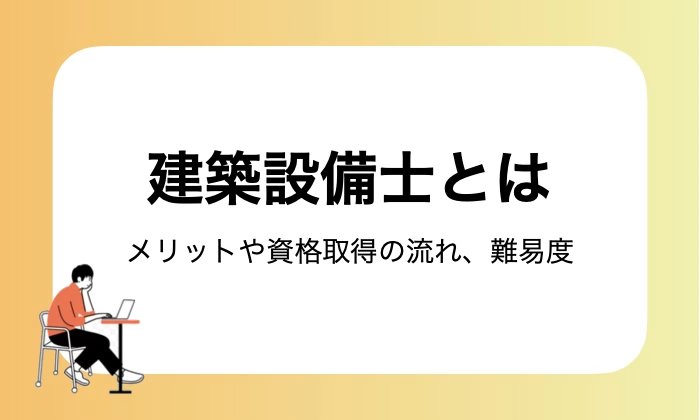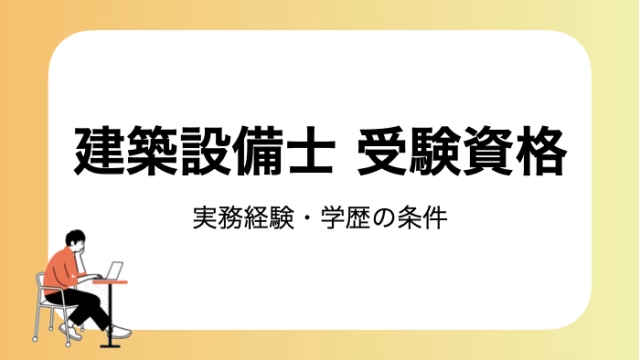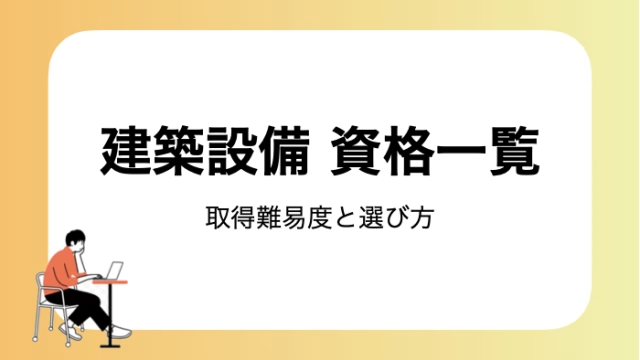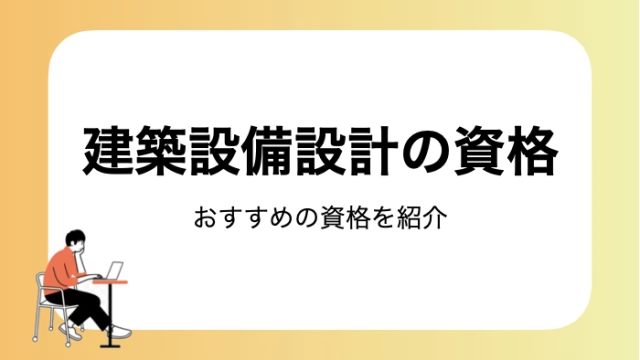「建築設備士とは何か」「どんなメリットがあるのか」など、資格取得を検討しているものの、具体的な内容や難易度、合格率がわからず不安に感じている方は多いのではないでしょうか。
そこで、今回は建築設備士とは何か、資格取得のメリットや流れ、難易度について解説します。
この記事を読めば、建築設備士という資格の全体像や、取得に向けて何をすべきかがわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
建築設備士とはどんな資格?
建築設備士とは、建築士と連携して空調・電気・給排水などの設備設計に専門的な助言を行う国家資格です。
建築基準法に明記された技術者であり、設備の法適合性や性能の向上を担う重要な役割を果たします。
建築設備士の定義と法律上の位置づけ
建築設備士とは、建築物の設備(空調・換気・給排水・電気など)の専門家であり、建築士が作成する設計図書のうち「設備に関する設計図書」の説明に責任を持つ国家資格者です。
その根拠は「建築士法第20条の2」にあり、特定建築物の設備設計において、建築士が建築設備士から説明を受けることが義務付けられています。
つまり建築設備士は、設備設計の品質と法的適合性を担保するための専門的立場として、法的に認められた存在です。
また、資格取得後は「建築設備士証」が交付され、建築設備設計における一定の信頼性・権限が認められます。
このように、建築設備士は単なる実務技術者ではなく、法律上も建築設計の一翼を担う国家資格者として制度上明確な役割を持っています。
建築士との違い、設備設計一級建築士との関係
建築士と建築設備士の大きな違いは、設計対象の領域です。建築士は建築全体(意匠・構造・法規など)を包括的に設計できる資格ですが、建築設備士は建築設備に特化した知識と責任を持ち、設計そのものというより「建築士への設備設計の説明と助言」に特化しています。
また、近年創設された「設備設計一級建築士」との違いについても混同されがちですが、明確に役割は分かれています。
| 項目 | 建築設備士 | 設備設計一級建築士 |
| 根拠法令 | 建築士法第20条の2 | 建築士法第20条の3 |
| 必要資格 | 特になし(受験資格あり) | 一級建築士の登録 |
| 主な役割 | 設備設計図の説明・助言 | 特定建築物の設備設計を行う建築士 |
| 登録主体 | 建築技術教育普及センター | 国土交通省所管の建築士登録制度 |
つまり、設備設計一級建築士は「建築士の資格を持つ上で、設備に強い人」、一方、建築設備士は「建築士とは別の資格で、設備に特化した助言者」という立ち位置です。
双方が連携することで、より高度で安全な建築物の設備計画が可能になります。
担当する業務(空調・電気・衛生設備など)
建築設備士が担当する主な業務は、建築物における設備設計・計画・法令適合の助言です。
具体的には、以下のような建築設備全般に関わります。
- 空調設備(冷暖房・換気・湿度制御)
- 給排水衛生設備(水道・下水・給湯・衛生器具)
- 電気設備(照明・コンセント・受変電設備・防災電源)
- 昇降機・避難設備(エレベーター・非常用照明など)
例えば、ある建築物に空調システムを導入する際、建築設備士は必要な換気量・熱負荷・ダクト経路を設計図面に反映し、建築士へその内容を説明します。
また、消防法や建築基準法、エネルギー消費性能基準に適合するよう調整するのも建築設備士の重要な役割です。
これらの業務は、安全性・快適性・環境負荷・ランニングコストに大きく影響するため、建築設備士の技術判断が建物全体の質を左右するといっても過言ではありません。
そのため、設計段階から施工、維持管理フェーズに至るまで、建築設備士の専門知識が求められ続けます。
建築設備士 資格取得の流れと必要条件
建築設備士資格の取得には、受験資格の確認から試験、講習、登録手続きまで一連の流れがあります。
ここでは、学歴・実務経験による受験要件、一次試験と二次試験の違い、合格までのスケジュール例、そして最終的な免許登録の流れを詳しく解説します。
受験資格(学歴・実務経験など)
建築設備士試験を受験するには、所定の学歴と実務経験が必要です。
受験資格は以下のように学歴に応じて実務年数が異なります。
| 学歴区分 | 実務経験年数 |
| 大学(建築・設備系)卒業 | 2年 |
| 短大・高専(建築・設備系)卒業 | 3年 |
| 高校(建築系)卒業 | 5年 |
| 上記以外・実務経験のみ | 8年 |
また、「設備設計・工事監理」などの建築設備に関する実務経験が必要とされており、単なる現場作業や施工管理では認められない場合もあります。
実務経験の内容は、願書提出時に職務経歴証明書で証明が必要です。
所属企業や元上司に記載してもらう必要があるため、余裕をもって準備を進めることが大切です。
なお、詳しい受験資格については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。
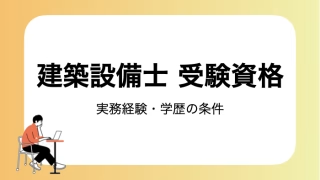
一次試験と二次試験の構成と違い
建築設備士試験は一次試験(学科)と二次試験(設計製図)の2段階で構成されています。
それぞれの内容と難易度の違いは以下の通りです。
【一次試験(学科)】
- 試験形式:マークシート(多肢選択式)
- 主な科目:建築一般、建築設備、建築法規、設備計画・設計など
- 合格率:約30〜45%
- ポイント:広範囲な知識を問われる。特に法規や計画分野が頻出
【二次試験(設計製図)】
- 試験形式:記述式+製図作業
- 出題内容:具体的な建築条件をもとに、空調・電気・給排水の計画図を作図
- 合格率:約40〜50%(一次試験合格者が母数)
- ポイント:図面の整合性、合理性、機器配置の適切さなどが評価対象
一次試験に合格しなければ二次試験を受験できない「段階式」試験となっており、一次と二次を分けて受験することはできません。
ただし、一度一次に合格すれば一定期間(例年2年)その合格が保持される制度があります。
合格までの標準的なスケジュール(例:実務→一次→講習→二次)
建築設備士資格を取得するまでの流れは1年以上に及ぶことが多く、スケジュール管理が重要です。
以下に一般的な例を示します。
| 時期 | 内容 |
| 4月〜6月 | 受験申込(願書提出) |
| 7月下旬 | 一次試験(筆記) |
| 9月上旬 | 一次試験合格発表 |
| 10月〜11月 | 二次試験(製図) |
| 翌1月頃 | 二次試験合格発表 |
| 翌2〜3月 | 建築技術教育普及センター主催の講習(必須)受講 |
| 翌4月以降 | 登録申請・建築設備士証交付 |
重要なのは、二次試験合格後に必ず講習の受講が必要な点です。
講習を受けなければ資格登録ができないため、仕事の都合などで参加できる日程を確認しておきましょう。
また、勉強は少なくとも半年〜1年を見込むのが一般的です。
働きながら資格取得を目指す方は、1日1〜2時間の学習時間をコツコツと積み重ねる必要があります。
登録・免許申請の手続きの流れ
建築設備士試験に合格しても、それだけでは資格は得られません。
正式に「建築設備士」として活動するには、登録申請と免許証の交付が必要です。流れは以下の通りです。
1. 講習受講(修了証取得)
二次試験合格後、建築技術教育普及センターの指定講習を受講し、修了証を取得します。
2. 登録申請書の提出
必要書類(講習修了証・住民票・証明写真など)を添えて、登録申請を行います。
3. 登録完了・免許証の交付
書類審査を経て、登録が認可されると「建築設備士証」が交付されます。
【登録に必要な主な書類】
- 登録申請書
- 講習修了証(写し)
- 住民票(6ヶ月以内)
- 証明写真(2枚)
- 登録手数料(約1万5千円)
登録が完了すれば、晴れて「建築設備士」として名乗ることが可能になります。
これにより、建築士に対して設備設計図書の説明・助言ができる法的な立場を得られます。
特に、設計事務所や設備会社では「登録済み」であることが採用や昇進の条件となっている場合もあるため、登録手続きを忘れず早めに進めることが重要です。
建築設備士の難易度と合格率
建築設備士は建築士法に基づく国家資格であり、合格には相応の専門知識と実務理解が求められます。
試験は一次(学科)と二次(製図+講習)に分かれており、それぞれに特徴的な難易度があります。
一次試験の合格率(過去データから)
建築設備士の一次試験は、マークシート方式の学科試験であり、建築・設備全般の広範な知識を問われます。
近年の一次試験の合格率は30%台後半〜40%台前半で推移しています。
以下は過去5年間の合格率の推移です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2023年 | 約5,500人 | 約2,200人 | 約40.0% |
| 2022年 | 約5,800人 | 約2,300人 | 約39.7% |
| 2021年 | 約5,900人 | 約2,150人 | 約36.4% |
| 2020年 | 約6,000人 | 約2,100人 | 約35.0% |
| 2019年 | 約6,300人 | 約2,250人 | 約35.7% |
出題内容は「建築設備に関する一般知識」「建築法規」「設備計画と設計」などに分かれ、単なる暗記では通用しません。
特に設備分野に関する実務的な問題が多く、建築士とは異なる視点が必要です。
また、マークシートでありながら思考力が問われる設問も多く、実務経験の浅い人には難しく感じる内容も多く含まれます。
難しいポイント(計算問題・記述・実務の理解)
建築設備士試験の難易度が高いとされる主な要因は、以下の3点に集約されます。
1. 計算問題の多さと難易度
空調負荷、換気量、水道管径、電気容量など、建築設備では多くの数値計算が発生します。
試験ではそれらを正確に理解し、条件に基づいて導き出す力が問われます。
特に空調や給排水の問題では単位換算や比例計算を含むため、数学的処理能力が不可欠です。
2. 記述式問題の専門性
一次試験では一部記述問題も含まれ、設備の改善案や設計意図の説明など、単なる知識では対応できません。
二次試験の図面作成では記述も求められる場合があり、機器選定の根拠や空間との関係などを論理的に説明できる能力が試されます。
3. 実務理解がないと難しい出題傾向
建築設備士試験は、実務経験が一定あることを前提とした設問構成となっており、教科書や参考書だけの勉強では対応できないこともあります。
例えば「既存建物に対する設備更新提案」「法改正後の適用判断」など、実務的判断が必要な問題が出されます。
このように知識・計算力・実務判断が三位一体で求められる点が、試験を難しくしている最大の理由です。
合格に向けた勉強法のポイント
建築設備士に合格するためには、戦略的な学習と過去問対策が不可欠です。
以下に有効な勉強法のポイントをまとめます。
1. 過去問題を繰り返す
一次試験は出題傾向が安定しているため、過去問演習を繰り返すことが最も効率的です。
特に「法規」や「計画」は同じテーマが繰り返し出題される傾向にあるため、過去5年分を徹底的に解きましょう。
2. 弱点分野をピンポイントで強化
計算が苦手な人は空調負荷や電力量の公式をまとめ、パターン化することが効果的です。
逆に法令に弱い場合は建築基準法や消防法を重点的に押さえ、条文の根拠を明確にしておきましょう。
3. 製図は手で描く練習を積む
二次試験の製図は手描きが基本です。
普段CADで仕事をしている人でも、手描き特有のスピード感や線の引き方に慣れておく必要があります。
また、過去の設計課題をもとに実際に描いて、時間内に仕上げる練習が重要です。
4. 市販テキスト・通信講座の活用
独学での合格も可能ですが、効率的に進めたい場合は通信講座の活用も有効です。
特に初学者にとっては「出題範囲の全体像」「頻出ポイントの要点整理」が役立ちます。
講義動画や添削サービスを活用することで、学習の質を一段上げることができます。
なお、より詳細な勉強方法については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。
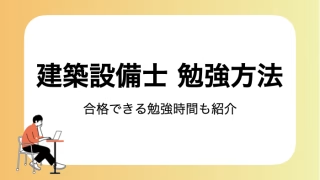
建築設備士 資格取得のメリットとは?
建築設備士を取得することで、法的に設備設計に関する助言・説明ができる立場となり、キャリアや待遇面でも大きな恩恵があります。
ここでは主な4つのメリットについて解説します。
設備設計の責任者としての立場が得られる
建築設備士の資格を取得すると、建築士に対して設備設計図書の内容について助言・説明を行える、いわば「設備設計の責任者」としての立場を持つことができます。
これは建築士法第20条の3で定められた正式な役割であり、資格を持たない者では対応できません。
特に、大規模施設や特殊建築物など、設備の専門性が高くなる現場では、建築設備士の存在は極めて重要視されます。
建築士と対等に意見交換を行える資格者として、社内外からの信頼も厚くなり、設備担当としての発言権も増します。
さらに、意匠設計や構造設計とは異なる「設備設計」という独自領域において、責任者のポジションを得られるため、現場の主導権を握ることにもつながります。
建築確認申請においての有利性
建築設備士は、建築確認申請においても有利に働くことがあります。
建築基準法上、設備設計図書の作成責任は基本的に建築士が担いますが、設備内容が複雑な場合や高度な判断が求められる場合、建築主事(確認申請を審査する側)から補足説明や技術的根拠の提示を求められることがあります。
このとき、建築設備士が関与していることは、提出書類の信頼性や妥当性の裏付けとなります。
とくに、消防設備、排煙設備、換気、給排水、電気容量など、法令上の安全性に関わる重要項目については、資格を持つ技術者の意見が強く尊重される傾向にあります。
実務上でも、建築設備士による「設計図書への所見記載」や「確認申請前の事前協議」でスムーズな審査につながるケースが多く、建築設備士の存在は実質的な申請リスクの軽減にも寄与します。
昇進・転職・独立へのプラス効果
建築設備士の資格取得は、キャリアアップにおいて強力な武器となります。
とくに、設備設計事務所・ゼネコン・設計部門のある建設会社などでは、主任・課長・設計統括などの昇進条件として建築設備士の保有が求められるケースも増えています。
また、転職市場においても「建築設備士保有者」は引き合いが多く、年収600万円以上のポジション提示や、管理職採用の条件として提示されることが多くなっています。
独立を視野に入れる場合でも、建築設備士という国家資格があることで「設計補助者」ではなく、正式な「設計責任者」として仕事を請け負うことが可能になります。
下記は求人サイトでの条件例です。
| 求人分類 | 年収例 | 必須資格 |
| 設備設計(主任クラス) | 550〜700万円 | 建築設備士 |
| 設備設計(所長候補) | 700〜900万円 | 建築設備士 ※建築士(あったら尚良し) |
このように、昇進・転職・独立と、どのフェーズにおいてもプラス効果のある資格であることがわかります。
資格手当や年収アップの可能性
建築設備士を取得することで、収入面でのメリットも期待できます。
企業によっては資格手当が月5,000円〜20,000円程度支給されるほか、賞与や昇給に反映されることもあります。
とくに設計・技術職においては「資格=社内の専門性証明」として高く評価されるため、責任ある案件を任されるようになり、結果的に報酬の増加にもつながります。
以下は、資格取得による年収アップの例です。
| 取得前年収 | 資格手当(月額) | 昇進後年収 |
| 約480万円 | 月1万円(年間12万円) | 約550万円 |
また、地方自治体や公共団体と関わる業務においても、建築設備士の資格があると入札資格や選定評価で加点される場合があり、間接的な収入増の要因にもなります。
このように、建築設備士の資格取得は一過性の資格手当だけでなく、長期的な収入向上につながる重要なキャリア投資といえるでしょう。
建築設備士を目指す人が知っておくべきこと
建築設備士を目指すにあたっては、受験資格となる実務経験や学習方法の選定、さらに他資格との相乗効果について理解しておくことが大切です。
どのような実務経験が必要か
建築設備士の受験には、建築設備に関する一定の実務経験が求められます。
具体的には、大学・短大・高専などで所定の課程を修了した後、2年以上の実務経験が必要です(課程により年数は異なる)。
実務の内容は「建築設備の設計・工事監理・施工」などに関わる業務でなければなりません。
注意したいのは、単なる建築現場の作業員や補助的業務ではカウントされないケースがある点です。
受験申込時には「実務経験証明書」の提出が必要で、勤務先の上司または代表者からの記名・押印が必須となります。
また、確認審査では職務内容の詳細な記述が求められるため、日頃から関わっている業務をしっかり記録・整理しておくことも大切です。
下表に一般的な受験資格の早見表をまとめました。
| 学歴・課程 | 必要な実務経験年数 | 主な対象業務内容 |
| 建築系大学卒 | 2年以上 | 設備設計、工事監理、施工管理など |
| 高専卒(5年制) | 3年以上 | 同上 |
| 建築設備職業訓練校卒 | 4年以上 | 同上 |
学習に必要な教材・通信講座の例
建築設備士試験は、一次試験(学科)と二次試験(設計製図)に分かれており、それぞれに合った教材・講座の活用が合格への鍵となります。
一次試験対策では、建築基準法・電気設備・衛生設備・空調換気設備など幅広い知識が問われるため、市販の過去問集や予想問題集を中心に、繰り返し学習が効果的です。
一方、二次試験は設備設計図の作成と記述問題が中心となるため、実技指導を受けられる通信講座や通学講座の活用が有効です。
特に図面の描き方や表現方法には独自のルールがあるため、独学では限界がある場合も少なくありません。
以下は代表的な教材・講座の例です。
| 種類 | 主な教材・講座名 | 特徴 |
| 市販教材 | 建築設備士受験テキスト(オーム社) | 網羅的な理論解説+問題演習 |
| 通信講座 | 日建学院「建築設備士講座」 | 添削指導付き・図面対策あり |
| 通学講座 | 総合資格学院「建築設備士対策」 | 模試・演習・講義サポートが充実 |
独学での学習が難しいと感じる場合は、模試や講座を活用してペースを保ち、合格を確実に狙う学習スタイルをおすすめします。
他の建築系資格との相乗効果(例:一級建築士とダブル資格)
建築設備士は、それ単体でも非常に専門性の高い資格ですが、他の建築系国家資格と組み合わせることでさらに価値が高まります。
特に「一級建築士」とのダブルライセンスは、設計全般において非常に強力な武器となります。
たとえば、一級建築士は建築物の設計全体に責任を持つ立場であり、建築設備士はその中でも空調・電気・給排水などの「設備」に特化したプロフェッショナルです。
両資格を持つことで、設計のトータルマネジメントが可能となり、ゼネコンや大手設計事務所での評価が格段に上がります。
また、以下のような組み合わせによる相乗効果もあります。
| 資格の組み合わせ | メリット |
| 一級建築士+建築設備士 | 設計・申請・監理すべてを網羅できる |
| 建築設備士+電気工事士 | 電気設備の詳細設計・施工にも対応可 |
| 建築士+建築設備士+省エネ適合判定員 | ZEB・省エネ設計案件への関与が可能に |
近年では、建築物のエネルギー効率や環境性能が重視される傾向にあるため、複数資格を活かして多角的に提案・監理ができる人材の需要が高まっています。
将来性を考えるうえでも、建築設備士は他資格との相乗効果を狙いやすい資格といえるでしょう。
まとめ
今回の記事では、建築設備士について解説しました。
今回お伝えした内容を参考に、ぜひ建築設備士の取得を目指して頑張ってください。
建築設備士は、本来は設計・計画段階で力を発揮する資格です。
しかし現場では、
- 資格を持っていても業務内容が変わらない
- 責任だけ増えて評価が伴わない
- 転職すべきか、副業という道があるか
といったケースも見られます。
今の環境が適正かどうか、転職・副業を含めた選択肢整理を無料で行っています。