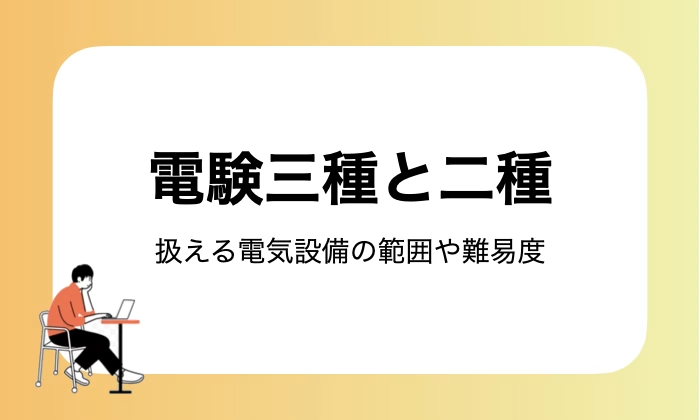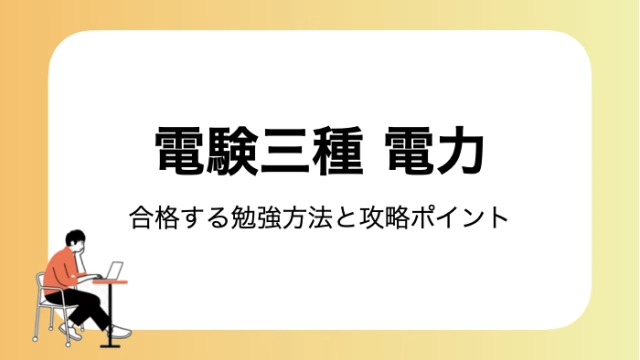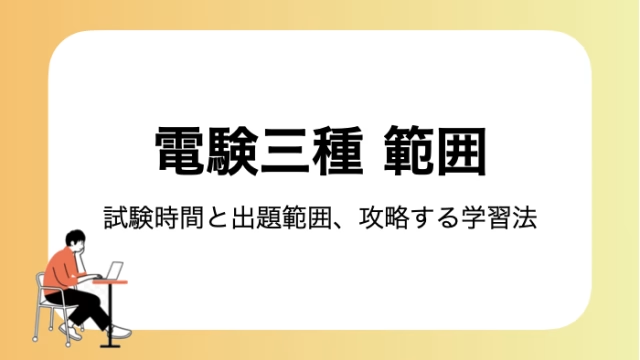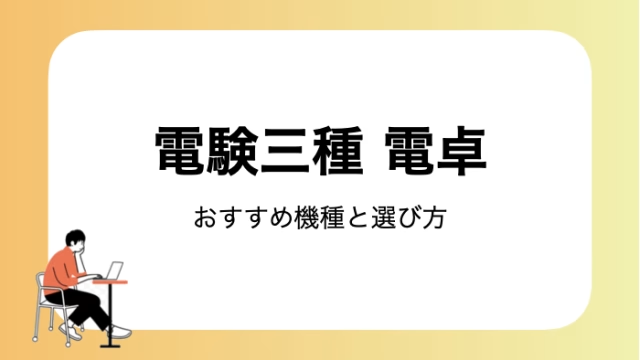電験三種と電験二種で試験制度や難易度、将来性などがごちゃごちゃになっていて、どちらを受けるべきか迷ってしまう方も多いはずです。
そこで、今回は電験三種と電験二種の違いや試験制度、併願の可否、難易度の比較について解説します。
この記事を読めば両者の違いを明確に理解でき、自分に合った受験戦略やキャリアの方向性がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
電験三種と電験二種の取り扱い範囲の違い
電験三種と電験二種は、どちらも電気主任技術者として必要な国家資格ですが、扱える電気設備の範囲や電圧に明確な違いがあります。
ここでは、その取り扱い範囲の違いを中心に解説します。
取り扱える電圧と設備の違い
電験三種と電験二種の最も大きな違いは、取り扱える「電圧」と「設備の規模」にあります。
電験三種の資格で対応できるのは、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物です。
ただし、出力5,000キロワット以上の発電所については対象外となっています。
このため、主にビルの受変電設備や、小規模な発電設備、商業施設の電気設備の保安監督などが業務の中心になります。
一方、電験二種になると、取り扱える範囲は一気に広がります。
電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物が対象となり、大型の発電所・変電所・配電所・大規模工場といった、高圧設備を含む大規模インフラの保安監督業務が可能になります。
以下の表は、両者の対応範囲の違いをまとめたものです。
| 資格区分 | 対応電圧 | 取り扱い可能な設備 |
|---|---|---|
| 電験三種 | 5万ボルト未満 | ビル・中小規模施設、小規模発電所(出力5,000kW未満) |
| 電験二種 | 17万ボルト未満 | 発電所、変電所、配電所、大規模工場など |
このように、電験二種の取得により、より高度で社会的インパクトの大きい設備を扱うことができるようになります。
これは、技術者としてのキャリアにおいて大きな飛躍と言えるでしょう。
仕事のフィールドの広がり
取り扱える電圧や設備が広がることで、電験二種を取得した場合には、就職先や活躍できるフィールドも大幅に広がります。
電験三種を保有していると、ビルメンテナンス会社や中小規模の工場、商業施設などでの電気主任技術者としての需要があります。
安定した職場環境で働くことができ、特に都市部では求人数も安定しています。
一方で、電験二種を取得すると、より高圧で大規模な設備を管理できるため、電力会社、重工業系の大手企業、大規模インフラ関連企業などへの就職・転職の選択肢が広がります。
また、エネルギー業界や再生可能エネルギーの分野でも、より重要なポジションに就くことが可能です。
さらに、二種の資格を活かして独立開業(電気管理技術者としての登録)を目指す道も見えてきます。
自営で顧客を持ち、複数の施設の電気設備を保守・点検することで、自由度の高い働き方も実現できます。
このように、電験三種と二種の取り扱い範囲の違いは、単に電圧だけでなく、その後のキャリアや働き方にまで大きく影響を及ぼす重要な要素です。
自身の目指す働き方や業界に応じて、どちらの資格がより適しているかを見極めることが重要です。
試験制度の違い|一次・二次の構成比較
電験三種と電験二種は、いずれも電気主任技術者の資格ですが、試験制度には大きな違いがあります。
特に注目すべきは、電験二種に「二次試験」がある点です。
ここでは、電験三種と電験二種の試験制度について解説します。
三種と二種の試験構成と出題形式の違い
電験三種は「理論・電力・機械・法規」の4科目のみで構成されており、試験形式はすべてマークシート方式です。
五肢択一の出題形式となっており、出題傾向は比較的定型化されています。
受験者は限られた選択肢から正解を選ぶ形式のため、知識の有無がダイレクトに結果に反映されやすい特徴があります。
一方、電験二種では、同じ4科目による一次試験に加えて、合格後に記述式の二次試験があります。
二次試験は「電力・管理」と「機械・制御」の2科目で構成されており、選択肢を選ぶのではなく、自ら論述や計算の過程を記述する形式です。
そのため、知識の理解度だけでなく、応用力・思考力・説明力も問われる高難度の試験といえます。
このように、三種と二種では「マーク式か記述式か」「一次のみか二次もあるか」など、試験制度の設計思想が異なります。
以下に両試験の構成をまとめた表を記載します。
| 資格 | 試験構成 | 出題形式 |
|---|---|---|
| 電験三種 | 理論・電力・機械・法規(4科目) | マークシート式(五肢択一) |
| 電験二種 | 一次:同上 二次:電力・管理、機械・制御(2科目) |
一次:マーク式 二次:記述式 |
出題レベルと試験制度の違い
電験三種と電験二種では、試験内容の深さにも違いがあります。
三種の問題は基礎的な電気理論や法規の理解を中心とした内容ですが、二種は同じ科目名でも出題範囲が広く、より深い専門知識が求められます。
特に二次試験は、単なる暗記だけでは対応できません。
現場の応用やトラブル対処に必要な思考力、実務に即した解決能力が求められる問題が多く出題されます。
また、解答には記述力も必要なため、論理的に説明する力も問われます。
つまり、電験三種は「広く浅く」が求められる試験であるのに対して、電験二種は「深く応用的な」理解と表現力が求められるのです。
そのため、単なる勉強時間の差だけでは対応できず、実務経験や工学的な思考力が重要になります。
この違いは、単に試験制度の違いというよりも、資格取得後に担う責任や業務の重さに対応した設計であるといえるでしょう。
科目合格制度の違いと有効期間
科目合格制度は、長期的な計画で合格を目指す受験者にとって非常に重要な制度です。
電験三種と二種の両方にこの制度はありますが、その適用範囲と有効期限に違いがあります。
電験三種では、4科目のうち合格した科目については、申請を行うことで「最大5回」まで免除されます。
たとえば、1科目だけ落ちた場合でも、他の3科目は次回以降の試験で再受験する必要がありません。
これにより、計画的に1科目ずつクリアしていく戦略が取りやすくなっています。
一方、電験二種でも一次試験については科目合格制度が適用されますが、有効期限は「3年以内に4科目すべて合格すること」が条件です。
つまり、合格科目を次年度以降に引き継げる点は同じですが、三種よりも有効期間が短いため、より集中的な計画が必要になります。
なお、電験二種の二次試験には科目合格制度は適用されていません。
つまり、一次試験に合格しても、二次試験で不合格となれば、翌年に再度チャレンジが必要です。
ただし、翌年は一次試験が免除されるという救済措置があるため、1年間は二次試験に集中できます。
このように、科目合格制度は両資格に用意されていますが、その運用ルールや有効期間には明確な差があるため、自分のライフスタイルや学習計画に合った戦略を立てることが重要です。
難易度の違い|合格率と受験者層から分析
電験三種と電験二種では、試験の合格率や出題範囲、求められる実務的な理解度が異なります。
ここでは、合格率の数値と受験者層の違いに注目し、それぞれの資格がどのようなレベル感なのかを詳しく分析します。
電験三種の合格率と受験者の特徴
電験三種(第三種電気主任技術者試験)は、電気主任技術者の登竜門ともいえる資格であり、受験者の多くは学生・社会人を問わず幅広い層です。
合格率は年度によって前後しますが、おおむね10〜15%前後で推移しています。2023年度の合格率は約11.2%で、例年通り厳しい試験となっています。
この試験の特徴として、文系出身者や独学で受験する人が多く、受験生の背景は多様です。
また、試験内容には数学・物理・電気回路・法規などの基礎的な工学知識が問われるため、理系的な思考力が必要です。
特に理論科目でつまずく人が多く、基礎学力の有無が合否に直結する傾向があります。
また、近年では参考書・過去問・YouTubeなどの教材も豊富に揃っており、独学でも対応しやすい環境になっています。
とはいえ、全科目に合格するためには継続的な学習と、体系的な知識の定着が必要です。
電験二種の一次・二次の合格率
電験二種は、電験三種の上位資格として位置づけられており、その分、難易度は格段に高くなります。
試験は一次試験と二次試験に分かれており、それぞれに合格する必要があります。
一次試験の合格率は、年度にもよりますが15〜25%程度とやや高めに見えるかもしれません。
しかし、二次試験では10%未満となることが多く、全体としては極めて厳しい試験です。
2023年度の実績では、一次試験の合格率が約20.6%、二次試験は9.7%という結果でした。
受験者の大半は、電験三種の合格者や電気系の実務経験者です。
試験範囲は三種と重なる部分もありますが、より高度な電気理論や設計・運用に関する知識が問われるため、単なる暗記では対応できません。
論述式の問題もあるため、理解したうえで自分の言葉で説明する力が求められます。
合格率だけで比較できない理由
合格率の数字だけを見ると、電験二種と三種の差が単純に10%前後に見えるかもしれません。
しかし、これをそのまま「難易度の差」として捉えるのは適切ではありません。
なぜなら、合格率はあくまで「受験者の中での合格者の割合」であり、受験者の質や背景が大きく異なるからです。
電験三種は幅広い層に開かれており、初学者や文系出身者なども含まれています。
そのため、合格率が低くても、実際には基礎力があれば合格できる可能性は高い試験です。
一方、電験二種の受験者は、三種の合格者や電気分野での実務経験者が多く、一定レベル以上の知識がある人が挑戦していることが多いです。
このように、受験者の層や試験の性質が異なるため、合格率だけを比較して「こっちの方が難しい」と判断するのは早計です。
試験に必要な学習時間や、理解・思考力の深さなど、総合的に見て判断することが重要です。
求められる知識・経験の差
電験三種と電験二種では、出題される知識の深さや範囲、さらには実務的な理解度に大きな違いがあります。
電験三種は主に電気主任技術者としての基礎的な知識を問うものであり、発電・変電・送電・配電といった分野の基本事項を押さえていれば対応できます。
計算問題もありますが、比較的基礎的な公式の理解とその運用で解けるものが中心です。
一方、電験二種では、設計や運用に関する判断力、応用的な電気理論、より高圧な電力設備の知識などが求められます。
さらに、二次試験では記述式が採用されており、自分の理解を論理的に展開する力も必要になります。
つまり、単なる暗記では対応できず、「なぜそうなるのか」を説明できるレベルの理解が不可欠です。
また、現場経験があると、出題意図を読み取る力や、論述において具体的な例を挙げやすくなるため有利になります。
このように、電験三種と二種では、知識の深さ・応用力・経験の必要性に大きな差があることを認識しておくべきです。
併願は可能?スケジュールと勉強法の注意点
電験三種と電験二種の併願は可能ですが、試験形式や学習量に大きな差があるため、事前の理解と準備が不可欠です。
以下では、併願に関する具体的な条件やスケジュール管理、適性、効率的な勉強法について詳しく解説します。
CBT方式なら併願可能
2022年度以降、電験三種はCBT(Computer Based Testing)方式を採用しており、これにより試験の実施日程が大幅に柔軟になりました。
従来は年1回の筆記試験だったため、電験二種との併願はほぼ不可能でしたが、CBT方式の導入により、電験三種の試験日程を自分で選択できるようになり、同年の電験二種との併願も現実的となりました。
ただし、CBTの予約枠は先着順で埋まるため、希望する時期に受験できるとは限りません。
特に併願を考えている人は、電験二種の試験日程を先に確認した上で、電験三種の受験予約を早めに済ませる必要があります。
また、電験二種は依然として年1回の筆記試験であり、一次試験と二次試験に分かれている点も留意が必要です。
このため、CBTを利用した電験三種の受験スケジュールを適切に組まないと、二種の対策に支障が出る可能性があります。
試験日程と注意点
併願を検討する上で、試験日程の把握は極めて重要です。電験三種のCBTは4〜11月の間に複数の受験期間が設けられています。
一方で、電験二種の一次試験は例年9月上旬、二次試験は12月に行われます。
この日程を踏まえると、電験三種の受験は遅くとも7月中旬までに済ませておくのが理想です。
そうすることで、8月以降は電験二種の一次試験に集中でき、スムーズな学習スケジュールを確保できます。
| 試験 | 実施時期 | 形式 |
|---|---|---|
| 電験三種 | 4月〜11月(複数期間) | CBT方式 |
| 電験二種(一次) | 9月上旬 | 筆記試験 |
| 電験二種(二次) | 12月上旬 | 筆記試験(論述) |
注意点として、CBTの申込開始は受験希望日の2か月前から可能ですが、枠の埋まり具合にばらつきがあるため、希望日に確実に受けるには余裕を持ってスケジュールを立てることが不可欠です。
併願に向いている人・向いていない人
併願が向いているかどうかは、学習の習慣や目的、基礎知識の有無によって大きく左右されます。
まず、併願に向いているのは、以下のようなタイプです。
- すでに電験三種の合格レベルに達している
- 理論科目や数学に強い
- 1日3時間以上の学習時間を継続できる
- 長期的な資格取得プランを持っている
一方、以下のようなタイプは併願に向いていません。
- 電験三種を初学者としてゼロから学ぶ人
- 本業が忙しく学習時間が確保できない
- 論述問題に苦手意識がある
- 直近で資格取得の実績がない
電験三種と電験二種では難易度に大きな開きがあり、二種は単なる「三種の延長線」ではありません。
二次試験の論述式問題には、実務的な思考力や文章構成力も求められるため、三種合格の経験だけでは太刀打ちできない場面も多く存在します。
効率的な併願対策の進め方
併願対策を成功させるには、段階的な学習計画と科目ごとの戦略が必要です。
まずは電験三種の全体像を3か月ほどで把握し、主要科目(理論・電力)を優先的に固めましょう。
これらの科目は電験二種の一次試験にも共通して出題されるため、基礎固めがそのまま併願対策となります。
電験三種の受験を7月までに終える場合、8〜9月は電験二種の一次試験対策に専念できます。
理論・電力に加え、機械・法規の応用力も求められるため、問題演習中心の学習にシフトしましょう。
一次試験後、合格していれば10〜12月は論述対策に切り替えます。ここでは過去問分析と答案作成の練習が不可欠です。
また、併願者はスケジュールの可視化も重要です。
週単位で目標を設定し、どの科目にどれだけの時間を投下するかを管理しましょう。
タスク管理ツールや学習記録アプリの活用も効果的です。
併願は難易度こそ高いものの、しっかりとした計画と自己管理があれば、十分に合格を狙える選択肢です。
電験三種合格後に電験二種を目指すメリット
電験三種に合格した後、さらなるステップアップとして電験二種を目指すことには多くのメリットがあります。
ここでは「年収」「学習効率」「独立性」という3つの観点から、その利点を具体的に解説します。
年収アップ・キャリアの広がり
電験二種に合格すると、電験三種と比較して、より高度な業務に従事できるようになります。
例えば、電気主任技術者として選任できる事業用電気工作物の規模が拡大するため、管理できる設備の範囲も大きくなります。
これにより、年収ベースでも大きな差が生まれます。
実際に、求人サイトなどを確認すると、電験三種の資格者が対象の求人は年収400万〜600万円程度が相場ですが、電験二種保有者では600万〜800万円、あるいはそれ以上の提示がされていることもあります。
特に大手インフラ系企業やプラント管理業務では、二種以上の資格が昇進条件となっていることも少なくありません。
さらに、キャリアの広がりという点でも、電験二種を持っていることで技術管理職や設計部門などへの転職・異動のチャンスが増えます。資格があることで業界内での信用も高まり、専門性を活かした仕事を選べる幅が広がるのです。
試験範囲が重なるため学習効率が良い
電験三種と電験二種の試験科目は、「理論」「電力」「機械」「法規」と共通しています。
ただし、難易度は当然ながら二種の方が高くなりますが、試験の出題範囲そのものに大きな違いはありません。
そのため、三種の学習で得た知識を土台として、効率的に二種の学習へと進められるのが大きなメリットです。
特に、「理論」と「法規」に関しては、三種と二種の問題内容が類似しているため、復習の延長線上で対策が可能です。
また、電験三種の勉強を通じて電気工学全般の基礎体力がついているため、二種の応用的な問題に対しても臆することなく取り組むことができます。
さらに、試験の形式(選択式・マークシート)や科目合格制度の運用についても共通点があるため、試験慣れという意味でも三種の経験は大きなアドバンテージとなります。
独立・フリーランスとしての将来性
電験二種を取得することで、企業に属さない「電気のプロフェッショナル」として独立・フリーランスで活動する選択肢も現実味を帯びてきます。
特に、電験二種以上を必要とする大規模施設や高圧受電設備を持つ工場・ビルなどでは、外部委託で主任技術者を選任するケースも多く、個人事業主として契約することが可能になります。
また、複数の施設と契約し、年間数百万円以上の報酬を得ている電験二種保有者も少なくありません。
地域によっては電験二種以上の有資格者が不足しており、スケジュールが合えば好条件での契約も見込めます。
加えて、電気設備の保守・点検・コンサルティング業務なども展開可能であり、技術と知識を活かした高単価なサービス提供も実現可能です。
将来的に会社を設立し、技術者を雇用して事業拡大する道も開けており、まさに「資格を使って人生を変える」ことができる資格といえるでしょう。
まとめ
今回の記事では、電験三種と電験二種の違いについて、取り扱い範囲・試験制度・難易度・併願の可否まで徹底的に比較しました。
資格の選択は今後のキャリアに大きく関わるため、電験三種と二種の違いを正しく理解した上で、自分の目標や状況に合った道を選びましょう。
実際、電験二種や三種は、取得するだけでも大きな価値があります。
一方で、その価値が十分に評価されるかどうかは、働く環境次第です。
- 今の職場で資格がどう扱われているか
- 将来的にどんな選択肢があるか
- 転職すべきか、副業という道があるか
無理な提案は行わず、電験三種を持つ方向けの選択肢整理を無料で行っています。