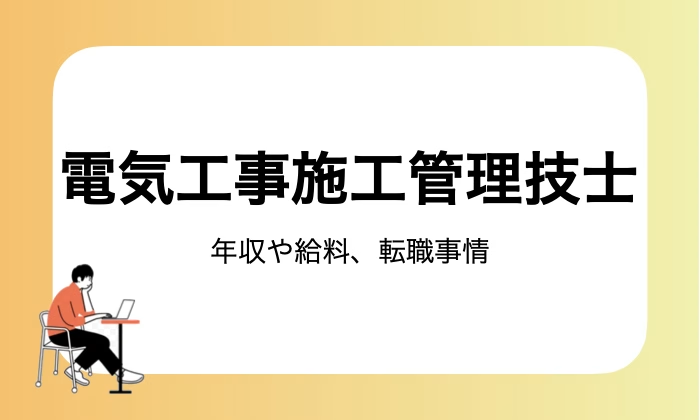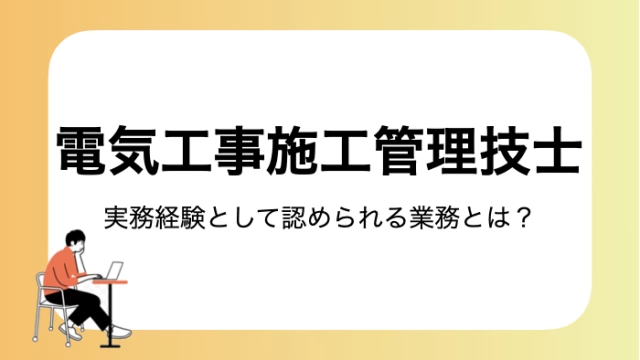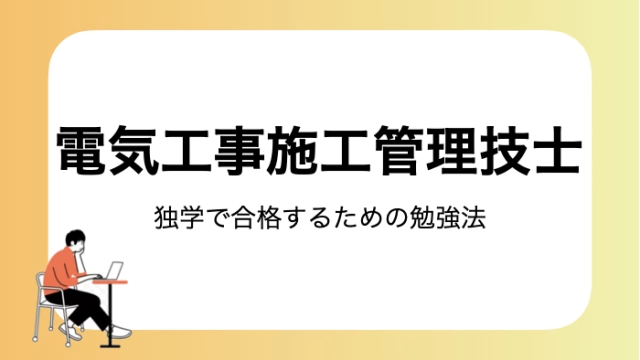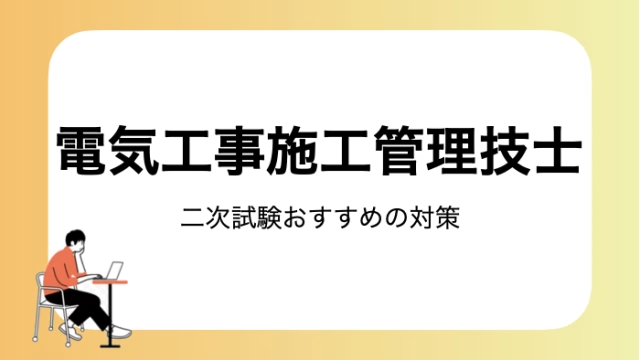「電気工事施工管理技士の年収って実際どうなの?」と疑問に思っていませんか?
資格を取っても、将来の給料や転職先での待遇に不安を感じている方も多いはずです。
そこで、今回は電気工事施工管理技士の年収事情や給料相場、年収を上げるための具体的な方法について解説します。
この記事を読めば、雇用形態・地域・年齢別の平均年収の違いや、年収アップにつながる転職・資格取得のポイントがわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
電気工事施工管理技士の年収は本当に高い?
電気工事施工管理技士の年収は高いと言われますが、その実態を正確に把握している人は少ないかもしれません。
ここでは、平均年収や初任給、月給相場に触れながら、なぜこの資格が高収入とされているのか、その理由をわかりやすく解説します。
平均年収は約496万円|初任給や月給の相場も解説
電気工事施工管理技士の平均年収は約496万円とされています。
これは国税庁が発表している日本人全体の平均年収約441万円を上回っており、比較的高収入の部類に入ります。
月給に換算すると約41万円前後、初任給は20万円台が相場です。特に経験を積んだ50代では年収600万円近くまで上がる傾向があります。
以下に、電気工事施工管理技士の雇用形態別の平均年収・時給をまとめた表を掲載します。
| 雇用形態 | 平均年収・時給 | 備考 |
|---|---|---|
| 正社員 | 約496万円 | 安定的に昇給・昇格が見込める |
| 派遣社員 | 時給約1,797円 | 専門技術により高時給 |
| アルバイト・パート | 時給約1,202円 | 資格があれば高時給 |
このように、正社員だけでなく派遣やアルバイトでも高めの時給が設定されており、資格の価値が高いことがわかります。
特に電気工事施工管理技士の派遣社員として働くという方法を取ったとしても、安定した収入を確保できる点は、他職種と比較しても優位性があります。
日本人の平均年収と比較して高い理由
電気工事施工管理技士の年収が高い背景には、いくつかの明確な理由があります。
まず、電気工事というインフラを支える業務であり、専門性と責任が非常に高い点が挙げられます。
現場では、安全管理・品質管理・工程管理など、幅広い管理業務を担うため、業務の難易度が高く、結果として給与水準も上がります。
さらに、電気工事施工管理技士は国家資格であり、資格手当が支給される企業も多く存在します。
これは資格を持つこと自体に経済的価値があることを示しています。
また、特定建設業では、1級資格者でなければ従事できない現場もあるため、企業側からのニーズも非常に高い状況です。
こうした背景から、電気工事施工管理技士は一般的なサラリーマンよりも高い給料を得られる職種として注目されているのです。
年収に影響する3つの要素|雇用形態・地域・年齢
電気工事施工管理技士の年収は一定ではなく、働き方や勤務地、年齢によって大きく異なります。
ここでは、雇用形態・地域・年齢という3つの観点から、年収にどのような違いが出るのかを詳しく解説します。
正社員・派遣・アルバイトでどう変わる?
雇用形態によって電気工事施工管理技士の年収は大きく変動します。
正社員の場合、年収は約496万円が平均とされ、昇給・昇格のチャンスもあるため安定的に年収アップが狙えます。
これはキャリアを積むほどに給与水準が上がる構造のため、将来性を見据えるなら最も有利な雇用形態です。
一方で派遣社員は時給制が一般的ですが、平均時給は約1,797円と高めに設定されており、短期間での収入を重視する人にとっては効率の良い働き方とも言えます。
アルバイトやパートの場合でも、平均時給は約1,202円と高水準です。
ただし、収入の上限はどうしても低くなりがちで、キャリアアップの機会も限定的です。
安定した年収や将来の昇進を目指すなら、正社員としての就業が望ましいでしょう。
以下に雇用形態別の年収・時給をまとめた表を掲載します。
| 雇用形態 | 平均年収・時給 | 特徴 |
|---|---|---|
| 正社員 | 約496万円 | 昇給・昇格による収入増が期待できる |
| 派遣社員 | 時給約1,797円 | 即戦力として高時給、柔軟な働き方が可能 |
| アルバイト・パート | 時給約1,202円 | 資格があれば高時給だが昇進の機会は少ない |
関東・関西 vs 地方の地域差とは?
地域によっても、電気工事施工管理技士の年収には差があります。
最も平均年収が高いのは関東エリアで、約506万円と全国平均を上回っています。
次いで関西(497万円)、九州・沖縄(484万円)と続きます。
都市部では大規模なインフラ整備や再開発案件が多いため、高額な報酬が提示される傾向があります。
一方、地方エリアでは年収がやや低めに設定されており、例えば甲信越・北陸では447万円、四国では464万円となっています。
ただし、生活コストが低いため、実質的な生活水準は都市部と大きく変わらない場合もあります。
また、地方でも公共工事や電力系のプロジェクトに携われば高年収を得られる可能性があります。
以下の表は、地域ごとの平均年収を比較したものです。
| 地域 | 平均年収 | 特徴 |
|---|---|---|
| 関東 | 約506万円 | 案件数が多く、年収水準が高い |
| 関西 | 約497万円 | 再開発案件が豊富 |
| 九州・沖縄 | 約484万円 | 工業地帯や都市開発が進行中 |
| 甲信越・北陸 | 約447万円 | 求人はやや少なめ |
| 四国 | 約464万円 | 地方でも比較的安定している |
地域によって年収に差はありますが、大きな開きがあるわけではなく、地方でも450万円前後の水準は十分に狙えます。
20代と50代の年収の差
年齢も年収に大きな影響を与える要素です。
電気工事施工管理技士は経験や現場スキルが重視される職種であるため、年齢とともに収入が上がっていく傾向があります。
20代の平均年収は約454万円と、同年代の他業種と比べても高めです。
資格を取得していることで、若いうちから責任あるポジションを任されるケースもあり、キャリアの早期形成が可能です。
一方で、50代になると平均年収は約599万円にまで上昇します。
長年の現場経験とマネジメントスキルが評価され、管理職や上級技術者として活躍する人が多いためです。
実力次第では年収700万円以上を目指すことも不可能ではありません。
このように、電気工事施工管理技士は年齢と経験が正当に評価される職種であり、長く働くほどに収入も安定しやすくなります。
若年層から始めれば、将来的な年収アップの余地は大きいといえるでしょう。
他の施工管理系資格と年収比較
電気工事施工管理技士の年収が他の施工管理資格と比べてどの程度の位置にあるのかを知ることで、その資格の価値やキャリアの選択肢が明確になります。
ここでは主要な施工管理系資格と比較して解説します。
電気工事士や土木施工管理技士との比較
電気工事施工管理技士とよく比較される資格に、「電気工事士」や「土木施工管理技士」があります。
いずれも建設・インフラ分野で需要の高い資格ですが、それぞれ年収面では違いが見られます。
まず電気工事士は、現場での実務が中心であり、平均年収は約444万円前後とやや控えめです。
現場の作業員として働くケースが多く、資格手当などはあるものの、施工管理のポジションと比べると給与水準は低めです。
一方、土木施工管理技士は公共工事などの案件で活躍することが多く、年収は約518万円と電気工事施工管理技士(約496万円)より若干高い傾向にあります。
ただし、管理対象が大規模であることから責任や労働時間の負担が大きく、仕事の厳しさも相応に高いです。
電気工事施工管理技士はインフラやビル設備、再生可能エネルギー関連の需要拡大により、今後さらに年収水準の向上が期待される資格です。
設備寄りの専門性を活かしながら安定した年収を得たい方には非常に有利な選択肢と言えます。
| 資格名 | 平均年収 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 電気工事施工管理技士 | 約496万円 | 設備・電力インフラの需要が高く、将来性もあり |
| 電気工事士 | 約444万円 | 現場作業中心、実務経験が求められる |
| 土木施工管理技士 | 約518万円 | 公共工事が中心、大規模案件が多く責任も大きい |
管工事施工管理技士との違い
管工事施工管理技士は、空調・給排水・衛生設備といった「配管工事」の現場管理を行う資格で、ビル建設や公共インフラに欠かせない存在です。
この資格の平均年収は約492万円と、電気工事施工管理技士(約496万円)とほぼ同水準に位置しています。
両者の違いは、扱う専門分野です。電気工事施工管理技士が「電気・通信・防災システム」などを担当するのに対し、管工事施工管理技士は「水回り・空調・配管」などの設備分野を専門とします。
実務内容としては、いずれも図面の確認や工事計画の立案、現場の工程管理、安全管理などに共通点が多く、建築現場においては両者が協力して工事を進める場面も少なくありません。
需要という観点では、どちらも都市再開発や災害対策、老朽設備の更新に伴い案件が安定しており、将来性は高いといえます。
年収もほぼ同等のため、どちらの資格を選ぶかは「どの分野の仕事に興味があるか」が分かれ目となります。
電気や通信に関心があるなら電気工事施工管理技士、水回り・空調設備に興味があるなら管工事施工管理技士を選ぶと、自身のスキルや適性をより活かすことができるでしょう。
| 資格名 | 平均年収 | 主な分野 |
|---|---|---|
| 電気工事施工管理技士 | 約496万円 | 電気・通信・防災設備 |
| 管工事施工管理技士 | 約492万円 | 給排水・空調・配管工事 |
仕事の内容から見る年収の妥当性
電気工事施工管理技士は高度な専門知識と現場責任を求められる職種です。
その仕事内容と他職種との比較から、現在の年収水準が妥当かどうかを検討します。
電気工事施工管理技士の仕事内容(施工計画・工程・安全・品質管理)
電気工事施工管理技士の業務は、単なる現場作業にとどまらず、プロジェクト全体のマネジメントに関わる高度な内容です。
主な業務は大きく分けて「施工計画の立案」「工程管理」「安全管理」「品質管理」の4つに分類されます。
まず、施工計画では、設計図や仕様書をもとに、施工の順序や工法、必要な人員・資材の調整を行います。
この段階でプロジェクト全体のスケジュールと予算に大きな影響を与えるため、高い判断力と計画力が求められます。
工程管理では、工事が予定通り進行しているかを常に監視し、遅延が発生しないように調整を行います。
資材の納入や他工事との調整もここに含まれます。
安全管理では、労働災害を防ぐための安全対策を徹底します。
現場の巡回、安全ミーティング、作業員への指導などが含まれます。安全性の確保は法令遵守とも深く関わり、非常に重要な任務です。
品質管理では、完成した設備が設計図通りの性能を発揮しているかを確認し、必要に応じて是正を行います。
不具合が後に発覚すれば大きな損害につながるため、非常にシビアな対応が求められます。
このように、施工管理技士の仕事は広範かつ高い専門性と責任を伴うものであり、年収が500万円前後であることは、仕事内容に見合った水準と言えるでしょう。
ビルメン(ビル設備管理)との業務範囲や責任の違い
同じ「電気設備」に関わる職種として比較されやすいのが、「ビルメン」と呼ばれるビル設備管理の職種です。
ビルメンの主な業務は、既存のビルや施設における設備(電気・空調・給排水など)の維持管理や定期点検、簡易な修繕対応です。
一方で、電気工事施工管理技士は、ビルや施設が新設・改修される段階での工事計画と実行を担います。
つまり、「作る」工程を管理するのが施工管理技士、「維持する」のがビルメンという違いがあります。
責任の大きさにも差があります。
ビルメンは日常的な対応が中心で、突発的なトラブル対応などもありますが、比較的ルーチン業務が多く、技術的な判断は上位者や専門業者に委ねることも多いです。
対して電気工事施工管理技士は、プロジェクト全体の品質・安全・進捗に責任を持ち、施工ミスや工程遅延が発生すれば企業に大きな損害を与えるリスクもあります。
そのため、意思決定や管理能力が求められ、精神的プレッシャーも大きい職種です。
年収面では、ビルメンが約350万~400万円程度であるのに対し、電気工事施工管理技士は約500万円前後となっており、業務内容と責任範囲の差がそのまま反映された形となっています。
したがって、年収面での差異は業務の性質や責任を考慮すれば妥当だといえるでしょう。
| 職種 | 主な業務 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 電気工事施工管理技士 | 施工計画・工程/安全/品質管理 | 約496万円 |
| ビルメン(ビル設備管理) | 設備の点検・保守・修繕 | 約370万円 |
電気工事施工管理技士で年収アップする方法3選
電気工事施工管理技士として年収を上げるには、資格のランクアップや関連資格の取得、転職・独立など複数の選択肢があります。
ここでは代表的な3つの方法を紹介します。
2級→1級のステップアップ
最も基本的かつ確実な年収アップの方法が、2級から1級へのステップアップです。
2級電気工事施工管理技士の資格では中規模以下の工事に携わることが多く、年収の相場も400万円台前半が主流です。
一方、1級の資格を取得すると大規模工事の主任技術者や監理技術者として現場の責任者を任されるようになり、プロジェクト単位での報酬も大きくなります。
企業によっては、1級資格者に対して資格手当を月数万円支給するところもあり、年間で数十万円の年収増加につながるケースもあります。
また、施工体制台帳上での配置義務があるため、1級所持者は企業にとって不可欠な人材となり、昇進・昇給のスピードも早まる傾向にあります。
実務経験と学科・実地の試験合格が必要ですが、資格を取得することでキャリアの可能性が大きく広がるため、1級取得は年収アップを目指すうえで外せない選択肢といえるでしょう。
関連資格(電気主任技術者など)を取得する
電気工事施工管理技士に加えて、関連資格を取得することでスキルの幅を広げ、より高収入のポジションを狙うことができます。
中でも特に有利なのが「電気主任技術者(第三種〜第一種)」です。
電気主任技術者は、ビル・工場・病院などにおける受変電設備の保守・管理を行う専門職で、法令により設置が義務づけられている施設も多く、需要が安定しています。
この資格を保有していることで、ビルメンテナンス業界や製造業の設備保全などへの転職も有利になり、平均年収も500〜700万円台が見込まれます。
また、電気工事士やエネルギー管理士などの資格も業務領域を拡大でき、企業からの評価につながります。
これらの資格を複合的に保有することで「電気の総合技術者」としてのポジションが確立し、転職や独立においても大きな強みとなるでしょう。
転職や独立でキャリアの幅を広げる
年収アップを現実的に狙うなら、転職や独立も強力な選択肢です。
現在の職場で評価されにくい環境にいる場合、資格や経験を活かしてより待遇の良い企業に転職することで、年収が100万円以上アップするケースも珍しくありません。
特にゼネコンや大手電気設備会社では、1級電気工事施工管理技士を持つ人材に対して高額の報酬を用意していることがあります。
また、福利厚生や賞与の充実度も高く、トータルでの収入が大きく改善することもあります。
一方で、十分な経験と人脈がある場合は、独立して個人事業主や法人として工事を請け負う道もあります。
元請けとして工事を獲得できれば、年収1,000万円を超えることも可能です。
ただし、営業・資金繰り・法的対応など、現場以外のスキルも求められるため、慎重な準備が必要です。
キャリアの幅を広げることで、単なる年収の増加にとどまらず、仕事のやりがいや自由度も大きく向上するため、自身のライフスタイルに合った選択を検討するとよいでしょう。
今後の将来性と需要|AI時代でも安定収入は可能?
AIや自動化が進む中でも、電気工事施工管理技士は現場対応力やインフラ需要に支えられ、将来にわたり高い安定性が見込まれます。
特に再生可能エネルギーや公共工事の分野で需要が拡大しています。
AIでは代替しにくい現場対応力
AIの進化によって多くの業務が自動化される中でも、電気工事施工管理技士の現場対応力は依然として高く評価されています。
施工管理の仕事には「現場特有のトラブルへの臨機応変な対応」「複数業者間の調整」「天候や地盤状況に応じた判断」など、AIでは判断が困難な業務が多く含まれます。
また、現場の安全管理や工程調整は、単に計画通りに進めるだけではなく、作業員とのコミュニケーションを通じて初めて成立するものです。
こうした人間特有の感覚や経験に基づく判断は、今後もAIでは完全に代替できない領域といえます。
さらに、建設業界では現場ごとに状況が異なるため、パターン認識だけで仕事を進めることができず、実際に現地を見て判断しなければならないことも多々あります。
そのため、電気工事施工管理技士のような現場型の専門職は、AI時代でも必要不可欠な職種として安定した地位を維持することが予測されます。
インフラ整備や再エネ分野での需要増
国や自治体によるインフラ整備の継続と、再生可能エネルギー分野の拡大により、電気工事施工管理技士の需要は今後も安定的に続く見通しです。
日本では老朽化した道路・橋梁・上下水道・電力設備などの更新が急務となっており、それに伴う工事現場では電気施工管理技士の役割が欠かせません。
また、再生可能エネルギーの普及政策が進むなか、太陽光発電設備や風力発電施設の設置工事においても電気施工管理の知識と経験が求められます。
これらの工事は通常の建築電気工事とは異なる専門的な知識が必要とされるため、有資格者は高い市場価値を持ちます。
今後は電気自動車の普及にともなう充電インフラ整備、スマートシティ構想に伴う先進的な配電・制御システムの設計・管理など、より高度なスキルを必要とするプロジェクトが増えると見込まれています。
こうした流れの中で、電気工事施工管理技士のニーズは中長期的に拡大していくでしょう。
安定した資格である理由
電気工事施工管理技士が安定した資格である最大の理由は、国家資格として法的な地位が確立されている点にあります。
特定の規模以上の電気工事では、法令に基づいて有資格者を「主任技術者」や「監理技術者」として配置しなければならず、この制度により、企業側も継続的に資格保有者を必要とする構造ができています。
さらに、施工管理技士の資格は更新制ではなく一度取得すれば永久に有効であるため、長期的なキャリア形成に有利です。
就業先の変更や定年後の再就職においても、この資格を持っていることで大きなアドバンテージになります。
また、電気工事の現場は日本全国に存在し、地域ごとの再開発や設備更新の波があるため、特定地域に限らず全国的に需要があるのも安定性の一因です。
AIやITの進化により働き方は変わっていくかもしれませんが、現場を支えるこの資格の重要性は今後も揺らぐことはないといえるでしょう。
まとめ
今回の記事では、電気工事施工管理技士の年収について解説しました。
今回お伝えした内容を参考に、ぜひ電気工事施工管理技士の取得を目指して頑張ってください。
電気工事施工管理技士は、現場を支える重要な資格です。
その一方で、
- 責任が重い割に評価が低い
- 長時間労働が常態化している
- 将来の働き方が見えない
と感じている方も少なくありません。
資格を活かしながら無理なく働く選択肢について、転職・副業の両面から無料で相談を受け付けています。