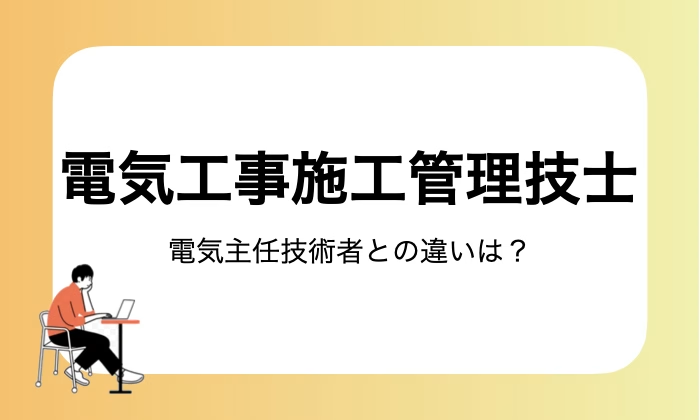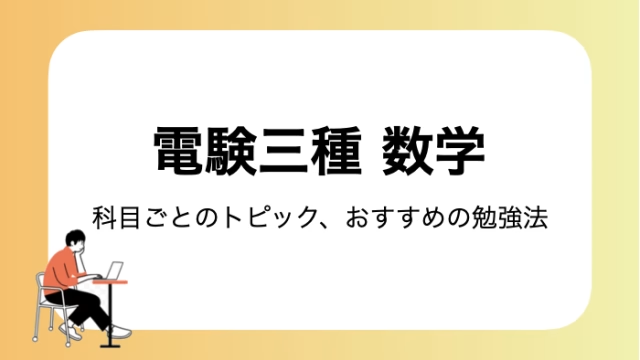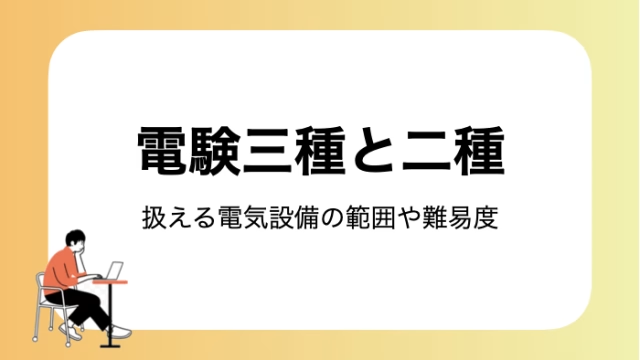電気工事施工管理技士と電気主任技術者、どちらも将来性のある資格ですが、仕事内容や年収、試験の難易度などが異なるため、自分に合った資格がわからず悩んでいる方も多いでしょう。
そこで、今回は電気工事施工管理技士と電気主任技術者の違いについて解説します。
この記事を読めば両資格の特徴や向いている人のタイプ、どちらを取得すべきかの判断基準がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
資格の基本概要
電気工事施工管理技士と電気主任技術者は、どちらも電気設備に関わる国家資格ですが、役割や活躍の場が大きく異なります。
ここでは、それぞれの資格の定義や特徴、目的の違いについて詳しく解説していきます。
電気工事施工管理技士とは
電気工事施工管理技士は、建設現場などにおける電気工事の施工計画から工程管理、安全管理、品質管理までを統括する管理職的な役割を担う国家資格です。
電気工事を「実際に行う人」ではなく、「監督・管理する人」として工事全体を指揮します。
この資格は、国土交通省が所管する「施工管理技士」の一種であり、1級と2級に分かれています。
1級は大規模な現場の専任技術者や主任技術者としても活躍でき、2級は中小規模の工事を担当することが多いです。
試験は「第一次検定(筆記試験)」と「第二次検定(記述式)」に分かれており、実務経験が一定以上必要とされるため、現場経験者向けの資格といえます。
電気工事業界では、元請け企業やサブコンなどで施工管理技士の資格を持つ人材の需要が非常に高まっています。
電気主任技術者とは
電気主任技術者は、発電所や工場、大型商業施設などで使用される高圧・特別高圧電気設備の保安・維持管理を担う国家資格で、「電験(でんけん)」の略称でも知られています。
経済産業省の管轄で、第一種・第二種・第三種の3つの区分に分かれています。
資格の等級によって取り扱える電気設備の規模が異なり、第三種では比較的小規模なビルや工場、第一種では大規模な発電設備や大規模プラントまで管理可能です。
特に事業用電気工作物には、法的に電気主任技術者の選任が義務づけられており、非常に重要な役割を担っています。
試験は一次試験(理論・電力・機械・法規)と、第一種・第二種では加えて二次試験(管理・制御)も必要となり、合格率も1桁台と難関です。
誰でも受験可能な点が特徴で、電気保安に関わるキャリアを目指す方にとっては最適な資格です。
それぞれの目的と役割の違い
電気工事施工管理技士と電気主任技術者の最大の違いは、「工事の監督者」と「設備の管理者」という立ち位置です。
前者は建設工事において、電気設備の新設・改修などの工程を安全かつ効率よく進めるために全体を管理します。
一方、後者は完成した電気設備を安全に運用し、トラブルが起きないよう保守・点検を行うのが主な仕事です。
具体的には、以下のように業務内容が分かれます。
| 資格名 | 主な役割 | 活躍の場 |
| 電気工事施工管理技士 | 電気工事現場の管理・監督 | ゼネコン、サブコンなど |
| 電気主任技術者 | 電気設備の保守・管理・監督 | 工場、商業施設など |
つまり、電気工事施工管理技士は「建設フェーズ」の管理者であり、電気主任技術者は「運用フェーズ」の責任者です。
どちらも電気設備において不可欠な存在ですが、関わるタイミングと責任範囲がまったく異なります。
そのため、自身のキャリアビジョンに応じて、どちらの資格を目指すかを判断することが重要です。
仕事内容の違い
電気工事施工管理技士と電気主任技術者は、どちらも電気設備に関わる資格ですが、その仕事内容はまったく異なります。
ここでは、工事現場での監督業務と運用中の設備保守管理という観点から、それぞれの業務内容と向いている人物像を詳しく比較していきます。
工事の監督と設備保守、業務内容の比較
電気工事施工管理技士と電気主任技術者では、関わるフェーズと業務範囲に明確な違いがあります。
電気工事施工管理技士は「施工段階」における管理者であり、現場の進行状況や安全、品質などを総合的に管理します。
電気工事が計画どおりに進行および安全に完了するよう監督し、作業員や関連業者と調整しながら工事全体をまとめあげます。
一方で電気主任技術者は、電気設備が完成した後の「運用段階」において保守・管理を担います。
工場やビル、発電所などにおける高圧電気設備の法定点検、トラブル発生時の原因特定、保安規定の策定・運用などが主な業務です。
電気事故を未然に防ぎ、設備を安定稼働させることが重要な責務です。
以下は両者の業務内容を比較した表です。
| 資格名 | 主な業務内容 | 活躍のフェーズ |
| 電気工事施工管理技士 | 電気工事の工程・安全・品質・予算管理/現場監督 | 計画〜施工段階 |
| 電気主任技術者 | 電気設備の点検・保守/障害対応/保安規定の作成と運用 | 設備運用〜維持段階 |
このように、電気工事施工管理技士は“工事を成功させる”ために動き、電気主任技術者は“電気を安全に使い続ける”ために存在する資格です。
どちらも現場に不可欠な役割であり、専門性の高い仕事であることに変わりはありません。
向いている人の特徴
電気工事施工管理技士と電気主任技術者は、仕事内容が大きく異なるため、向いている人物像もまったく異なります。
まず、電気工事施工管理技士に向いているのは「人と関わるのが好き」「現場を動かすリーダーシップがある」「物事を段取りよく進めるのが得意」といったタイプです。
複数の関係者とコミュニケーションを取りながら、工期や安全、品質のバランスを取りつつプロジェクトを推進していく力が求められます。
一方で電気主任技術者に向いているのは、「一つの物事を深く突き詰めるのが好き」「数値や理論に強い」「慎重で冷静な判断ができる」といったタイプです。
定期点検やトラブル対応では正確さと緻密さが求められるため、コツコツと地道な作業を続けられる粘り強さが大切になります。
以下に、向いている人物像の違いをまとめた表を示します。
| 資格名 | 向いている人の特徴 |
| 電気工事施工管理技士 | 現場での調整が得意/リーダータイプ/段取り力がある/対人能力が高い |
| 電気主任技術者 | 理論や数値が好き/慎重な性格/集中力がある/一人での作業が苦にならない |
どちらの資格も責任は重いですが、自分の性格やキャリア志向に合ったものを選ぶことで、長く充実した働き方が実現できます。
どちらを選ぶか迷ったときは、自分が「現場を動かしたいのか」「設備を守りたいのか」という視点で判断すると良いでしょう。
年収・待遇の違い
電気工事施工管理技士と電気主任技術者は、どちらも電気系の国家資格として高い専門性が求められますが、年収や昇給、待遇面には明確な違いがあります。
ここでは、平均年収の比較と、それぞれのキャリアパスにおける昇給や待遇の違いを詳しく解説します。
平均年収の比較
電気工事施工管理技士と電気主任技術者の平均年収は、概ね同水準とされているものの、実際には業務内容や所属企業、地域、経験年数によって差が生じます。
以下は参考となる年収の目安です。
| 資格名 | 平均年収(概算) | 備考 |
| 電気工事施工管理技士 | 400万~500万円程度 | 現場責任者や経験者は700万円以上も可能。プロジェクト規模により変動。 |
| 電気主任技術者 | 400万~500万円程度 | 第一種取得者や大規模施設勤務者は600万〜800万円以上も。 |
電気工事施工管理技士の場合、大手ゼネコンやサブコンの現場で1級資格者として勤務すれば年収600万円以上を目指すことが可能です。
一方、電気主任技術者は第一種の資格を有し、大規模発電所やプラントなどで勤務することで高年収を得やすくなります。
また、残業の多さや休日の取りやすさといった待遇面では、電気主任技術者の方が比較的落ち着いた勤務体系を取りやすい傾向にあります。
現場管理が主業務となる電気工事施工管理技士は、どうしても繁忙期や工程の遅延があると休日出勤や残業が増える傾向があります。
昇給・キャリアアップの違い
キャリアアップの道筋においても、両者には違いがあります。
電気工事施工管理技士は、現場経験を重ねていくことでより大規模な案件の主任技術者や工事部門のマネージャーへと昇進でき、社内評価や役職手当によって年収が大きく伸びるケースがあります。
また、1級取得によって建設業法に基づく専任技術者・監理技術者としての登録も可能になり、業界内での市場価値が高まります。
一方で、電気主任技術者は第一種・第二種といった上位資格を取得することで、より高圧・大規模な設備の管理が可能になります。
これにより、大手メーカーの電力部門やインフラ企業への転職、または電気保安法人での責任者ポジションへのキャリアアップが狙えます。
以下に、昇給・キャリアアップの特徴をまとめた表を示します。
| 資格名 | 昇給・キャリアアップの主な道筋 |
| 電気工事施工管理技士 | 現場責任者 → 主任技術者 → 工事部長や技術部門の管理職 |
| 電気主任技術者 | 第三種 → 第二種 → 第一種 → 電力会社や大規模設備の責任者・技術顧問など |
また、両資格ともに経験を積めばフリーランスとして独立する道もあり、特に電気主任技術者は需要の高い保安管理分野で個人契約や委託業務が可能です。
施工管理技士もまた、施工管理会社の設立や請負契約を通じて高年収を目指せる職域です。
キャリアの方向性に応じて、安定志向か挑戦志向かを見極め、適した道を選ぶことが重要です。
試験の難易度と合格率の違い
電気工事施工管理技士と電気主任技術者の試験は、対象となる業務内容が異なるため、出題範囲や難易度、合格率に大きな違いがあります。
ここでは、両者の試験内容の比較、合格率と難易度の差、そして効果的な勉強方法のポイントについて解説します。
試験内容の比較(1級・2級、第一〜第三種)
試験内容は、資格の種別ごとに求められる知識と技能が異なります。
以下に主な試験内容を表でまとめました。
| 資格 | 試験内容(要約) |
| 1級・2級 電気工事施工管理技士 | 【一次】電気工学、施工管理法、法規など(マークシート) 【二次】施工管理法(記述式) |
| 第一種 電気主任技術者 | 【一次】理論、電力、機械、法規 【二次】電力・管理、機械・制御 |
| 第二種 電気主任技術者 | 第一種と同様(範囲やレベルが若干異なる) |
| 第三種 電気主任技術者 | 理論、電力、機械、法規(全てマークシート) |
電気工事施工管理技士は、実務を想定した「施工管理」に関する知識が中心ですが、電気主任技術者は理論物理や電気機器、法令の理解が問われる「座学中心」の構成です。
特に第一種や第二種では、二次試験での記述解答が求められ、実務的かつ高度な知識が必要となります。
一方、第三種電験は四科目のマークシート式で構成されており、受験しやすい反面、合格に必要な理解力は高く、単なる暗記では太刀打ちできません。
施工管理技士は実務と直結した出題が多いため、現場経験がある人ほど有利です。
合格率と難易度の差
試験の難易度は、出題範囲や合格率からも読み取れます。
以下に代表的な資格の合格率を比較します。
| 資格 | 合格率の目安 |
| 1級 電気工事施工管理技士 | 約29% |
| 2級 電気工事施工管理技士 | 約27% |
| 第一種 電気主任技術者 | 約8% |
| 第二種 電気主任技術者 | 約9% |
| 第三種 電気主任技術者 | 約10% |
このように、電気主任技術者のほうが圧倒的に難易度が高いと言えます。
特に第一種と第二種は一次・二次ともに高難度であり、理論と応用力が問われる試験内容です。
一方、電気工事施工管理技士は、試験形式の変更や受験者層の影響により、近年やや合格率が上昇傾向ですが、二次試験での記述式回答が苦手な受験者も多く、しっかりした対策が必要です。
「誰でも受験できる」第三種電験は参入障壁が低い分、初学者も多く、結果的に合格率が低くなっています。
つまり、電験は“簡単に受けられるが、受かりにくい”試験であると言えるでしょう。
勉強方法のポイント
試験対策の要は「過去問の繰り返し」と「理解の積み重ね」です。
どちらの資格も、市販のテキストと過去問題集を活用した独学が可能ですが、資格ごとの性質に合わせた勉強が求められます。
電気工事施工管理技士の勉強法
- 一次試験対策として、マークシート式の出題範囲(法規・施工管理・電気工学)を反復学習
- 二次試験の記述対策は、過去問を写経しながら文章の構成や要点を身につける
- 模試や予備校の通信講座を活用して添削指導を受けるのも効果的
電気主任技術者の勉強法
- 一科目ずつ独立して合否判定されるため、得意科目から合格を目指す「科目合格制度」を活用
- 計算問題が多いため、理論・電力・機械の各単元で“原理の理解”を重視
- 法規は頻出条文の暗記より、出題パターンの把握が鍵
いずれの資格でも、最低でも「過去5年分×5周」が基本となります。
理解が曖昧な部分は動画講座や参考書を併用し、できるだけ“自分の言葉で説明できる”状態を目指しましょう。
また、スケジュール管理と継続的な学習が合格の近道です。
週ごとの目標を定めて計画的に進めれば、働きながらでも十分合格を狙えます。
受験資格の違い
電気工事施工管理技士と電気主任技術者では、受験に必要な条件が大きく異なります。
とくに「実務経験の有無」や「年齢・学歴制限の有無」が資格取得のハードルを左右します。
ここでは、それぞれの受験資格について具体的に比較し、どの資格が取得しやすいのかを明らかにします。
実務経験の有無と制限の違い
電気工事施工管理技士は、等級によって受験資格が異なり、とくに1級は厳しい実務経験が求められます。
以下の表をご覧ください。
| 資格種別 | 年齢条件 | 学歴・実務経験などの条件 |
| 1級 電気工事施工管理技士 | 満19歳以上 | 最終学歴に応じた実務経験が必要(例:高卒→11年以上、専卒→9年以上) |
| 2級 電気工事施工管理技士 | 満17歳以上 | 最終学歴+実務経験 or 施工管理技士補資格など |
このように、施工管理技士試験は“誰でも受けられる”ものではなく、一定の実務経験をクリアしなければなりません。
たとえば、高卒で1級を目指すには11年以上の実務経験が求められるなど、かなりの長期キャリアが必要です。
また、2級に合格してもすぐに1級を受験できるわけではなく、合格後の経験年数も受験要件に含まれます。
逆に、電気主任技術者はこの点が大きく異なります。
誰でも受験できる資格は?
電気主任技術者(第一種〜第三種)は、基本的に学歴・年齢・実務経験に関係なく誰でも受験可能です。
この“門戸の広さ”が、多くの社会人や異業種からのチャレンジを可能にしている理由でもあります。
| 資格種別 | 年齢制限 | 学歴制限 | 実務経験 | 備考 |
| 第三種 電気主任技術者 | なし | なし | 不要 | もっとも受けやすい |
| 第二種 電気主任技術者 | なし | なし | 不要 | 難易度は上がる |
| 第一種 電気主任技術者 | なし | なし | 不要 | 最難関の試験 |
このように、電験は「知識さえ身につければ受けられる」制度設計となっており、電気業界未経験者や理系学生にも門戸が開かれています。
特に第三種電験は、年齢・学歴・経験に縛られず、通信講座や独学で挑戦する人も多く見られます。
ただし、合格率が10%前後と低いため、学習には強い意志と継続力が必要です。
一方、電気工事施工管理技士は「現場経験者向け」の色が強く、現場に即した知識・スキルが前提とされるため、資格制度自体が現場主義といえます。
まとめると、「誰でも受験可能でチャンスが広い」のが電気主任技術者、「キャリアの積み重ねが前提」の実務者向け資格が電気工事施工管理技士という違いがあります。
主な就職先・キャリアパスの違い
電気工事施工管理技士と電気主任技術者では、活躍できる職場やキャリアの築き方に大きな違いがあります。ど
ちらの資格も電気分野では重要なポジションを担いますが、その後の転職や独立にも影響を与えるため、将来のビジョンに合わせて選ぶことが重要です。
それぞれの活躍の場とは?
電気工事施工管理技士は「施工管理者」として、工事現場で工程・品質・安全などの管理を担当するポジションです。
主な就職先は、以下のような企業が中心になります。
| 資格 | 主な就職先例 |
| 電気工事施工管理技士 | 電気工事会社、ゼネコン、サブコン、プラントエンジニアリング会社、設備工事会社など |
| 電気主任技術者 | 発電所、電力会社、ビル・商業施設・工場の設備管理部門、再生可能エネルギー関連企業など |
一方、電気主任技術者は「保安監督者」として、電気設備の維持管理、安全確保、保守計画の立案などを行うのが主な業務です。
特に一定規模以上の事業所では、選任が法律で義務づけられており、その専門性と責任の高さが特徴です。
どちらの資格も需要が安定しており、都市開発や再エネ拡大に伴ってさらなる活躍の場が広がっていますが、現場型か施設管理型かで求められるスキルセットが異なる点に注意が必要です。
転職・独立で有利になるのは?
転職や独立を視野に入れるなら、それぞれの資格の「汎用性」と「専門性」に注目しましょう。
電気工事施工管理技士は、特にゼネコン・サブコン業界でのニーズが高く、1級保持者は現場代理人として高年収を狙えるため、転職市場では非常に有利です。
さらに、複数の施工管理技士資格を掛け合わせることで、マネジメント領域へ進む道も開けます。
また、工事会社を立ち上げて独立する例も少なくありません。
一方、電気主任技術者は「選任制度」によって事業所に必ず必要な人材であり、そのためビルメンテナンス業界やインフラ系企業への転職で非常に重宝されます。
とくに第一種・第二種を保有していれば、特高設備を扱う企業から高待遇で迎えられることもあります。
また、独立系ビル管理会社や自営での「技術者派遣」の道も選べます。
| 項目 | 電気工事施工管理技士 | 電気主任技術者 |
| 転職の有利さ | 現場管理経験が評価され、ゼネコン・サブコンで有利 | 発電所・ビル設備の保安監督で重宝 |
| 独立のしやすさ | 工事会社設立などの道がある | フリーランス技術者やコンサル業も可能 |
| 市場での希少価値 | 1級取得で現場責任者として重宝 | 上位資格保持者は特高設備で高待遇 |
結果として、どちらが有利かは「目指すキャリア像」によります。
工事現場でリーダーシップを発揮したいなら電気工事施工管理技士、設備管理やインフラに関わる安定キャリアを求めるなら電気主任技術者が適しています。
両方の資格を取得することで、転職・独立の幅をさらに広げることも可能です。
両方の資格を取得するメリット
電気工事施工管理技士と電気主任技術者の両方を取得することで、電気設備の「施工」と「運用・保守」の両面に対応できるスキルを持つ専門家として、高く評価される存在になれます。
特に企業からは「一人で完結できる人材」として重宝され、キャリアの幅が広がります。
電気設備のトータル管理が可能に
両資格を持つことで、電気設備の計画から施工、引き渡し後の運用・保守まで一貫して関われるようになります。
たとえば、工事段階では電気工事施工管理技士として工程・品質・安全管理を行い、設備の稼働後は電気主任技術者として定期点検や保安管理を担当することが可能です。
この「工事と保守を理解している」点が大きな強みとなり、設備の全体最適やトラブルの早期対応にもつながります。
また、設備全体の技術的理解が深まることで、設計段階から効率的な仕様を提案できるなど、プロジェクト全体に貢献できる場面も増えます。
特に中小企業や地方工場では、1人の技術者に多様な役割が求められることが多いため、両資格保有者は極めて重宝されます。
| 資格の役割 | 主な対応範囲 |
| 電気工事施工管理技士 | 工事計画・進捗管理・品質・安全管理 |
| 電気主任技術者 | 設備点検・保安監督・法定管理 |
| 両資格を保有 | 計画〜施工〜運用・保守まで一貫対応可能 |
結果として、両方の知識があることで、現場判断の精度が上がり、プロジェクト全体の生産性向上にも貢献できます。
企業からの評価と重宝される理由
企業にとって、両資格を持つ人材は「即戦力+マルチプレイヤー」という極めて貴重な存在です。
現場管理もできるし、設備の保安責任者にもなれる。つまり、一人で複数ポジションを兼任できるため、人材コストの削減にもつながります。
特に以下のような理由から高評価を得ています。
- 工事の背景や意図を理解したうえで、運用上のリスクに対応できる
- 法令遵守と技術的実現性の両立が可能
- トラブル時に、どこに問題があるか迅速に特定・対応できる
- 工事中から運用後までの一貫した説明責任を果たせる
このような実用性の高さから、プロジェクトリーダーや施設全体の統括管理者としての登用も期待され、昇進や高年収のチャンスにも恵まれやすくなります。
また、発注者側にまわるキャリアも築きやすく、発注仕様書の精度向上や設備投資の最適化といった業務にも携われます。
特に、以下のような企業からは強いニーズがあります。
| 企業タイプ | 両資格者に期待される役割 |
| サブコン・電気工事会社 | 現場責任者+設備管理者の兼任 |
| 工場・製造業のインフラ部門 | 工場内の新設・更新工事と設備保守の全体統括 |
| 再エネ・発電関連企業 | 発電所建設時の施工管理と稼働後の法定管理対応 |
| 設備保全会社・ビルメン会社 | 受託業務全体を一人でカバー、トラブル対応力向上 |
このように、両資格保有者は企業の合理化やリスクマネジメントに貢献する存在として、高い評価と待遇を受けることが可能です。
自らの価値を最大化したい方には、両資格の取得は大きな投資価値があるといえるでしょう。
他の電気系資格との違いも確認
電気工事施工管理技士や電気主任技術者は、電気系の中でも管理職・責任者的な役割を担う資格です。
一方で、電気工事士や電気通信工事施工管理技士など、似た分野の資格も存在します。
それぞれの違いを把握することで、自分に合ったキャリアパスや受験計画を立てやすくなります。
電気工事士、電気通信工事施工管理技士との違い
電気工事士は、実際に電気設備の工事を行う「作業者」に必要な資格であり、特に住宅やビル、工場などの電気設備の配線・設置において義務付けられています。
対して、電気工事施工管理技士は、工事現場の管理者として、工事の計画・工程・品質・安全を管理する立場にあります。
つまり、作業を「する人」と「管理する人」で役割が異なります。
また、電気通信工事施工管理技士は、LAN配線や電話回線、光ファイバーなどの通信インフラの工事を監督する資格です。
こちらも「施工管理技士」ではありますが、対象となる設備が電力ではなく通信である点が特徴です。
以下の表で役割を比較してみましょう。
| 資格名 | 主な対象設備 | 役割 | 必要性 |
| 電気工事士(第1種・第2種) | 電灯・動力設備など | 作業者(施工者) | 作業実施に必須 |
| 電気工事施工管理技士 | 建築物の電気工事全般 | 施工管理(管理者) | 現場監督や請負工事で重要 |
| 電気主任技術者(1〜3種) | 高圧・特高電気設備 | 保守管理・監督者 | 法定で選任が義務付けられる |
| 電気通信工事施工管理技士 | 通信設備・配線 | 施工管理(通信工事) | 通信インフラ工事で必要な管理者資格 |
このように、それぞれの資格には「対象設備」と「業務の性質」に明確な違いがあり、自身のキャリアに応じた選択が重要です。
資格選びで失敗しないためのポイント
資格選びを間違えると、取得後に「想定していた仕事と違った」「活かせる場面が少ない」と後悔することがあります。
失敗を避けるには、以下のようなポイントを事前に確認することが大切です。
①目指す職種に直結するかどうか
たとえば、将来的に現場監督になりたいなら電気工事施工管理技士、設備の責任者を目指すなら電気主任技術者が適しています。
②資格の法的効力や必須性
電気工事士は作業者として必須、電気主任技術者は一定規模以上の電気設備における法定管理者として必要です。
法令による義務かどうかも確認しましょう。
③将来性や転職市場での価値
資格の取得に対する企業のニーズや求人市場での需要を調べておくと安心です。
特に両資格保持者は重宝され、収入面やポジション面で有利になる可能性があります。
④難易度と勉強時間のバランス
取得にどのくらいの時間と労力が必要かも選定基準になります。
働きながら取得する場合は、合格率や学習ボリュームも現実的に検討しましょう。
| 選定基準 | 電気工事士 | 電気工事施工管理技士 | 電気主任技術者 |
| 現場作業希望 | ◎ | △ | × |
| 管理職希望 | △ | ◎ | ◎ |
| 法的義務がある業務 | ◎(作業) | △ | ◎(設備保安) |
| 難易度(平均的な評価) | やや易しい | 普通 | やや難しい〜難しい |
| 将来性・汎用性 | △ | ◎ | ◎ |
このように、自分のキャリアビジョンと照らし合わせて資格を選ぶことが、後悔しないための最大のポイントです。
興味や得意分野だけで判断せず、「どんな業務に就きたいのか」「資格が活きる職場はどこか」を明確にしたうえで、最適な選択を目指しましょう。
どちらを選ぶべきか?タイプ別に解説
電気工事施工管理技士と電気主任技術者はどちらも電気系の国家資格ですが、目指すキャリアや働き方のスタイルによって向き・不向きがあります。
ここでは「現場志向か技術志向か」「将来どのような働き方をしたいか」によって、それぞれの資格がどんな人に向いているかを解説します。
現場志向 vs 技術志向
「体を動かす現場作業が好き」「現場で人をまとめるのが得意」といった現場志向の方には、電気工事施工管理技士が向いています。
この資格は、工事現場において施工の計画や進捗、安全管理、品質管理を担当し、実際の施工スタッフと連携しながらプロジェクトを動かすポジションです。
特に建設業や設備工事の現場に常駐しながら働きたい方には適しています。
一方で、「設備の仕組みや電気理論に興味がある」「高圧・特別高圧設備の技術的な責任者になりたい」といった技術志向の方には、電気主任技術者が向いています。
こちらは、工場やビルなどの受変電設備の維持管理やトラブル対応など、電気設備の安定稼働を支えるための知識と判断力が求められます。
以下の表は、タイプ別の適性を比較したものです。
| 指向性 | 向いている資格 | 理由 |
| 現場志向 | 電気工事施工管理技士 | 現場管理業務が中心、体力とコミュニケーション力が重要 |
| 技術志向 | 電気主任技術者 | 電気理論や保守管理に重点、高度な知識が求められる |
どちらの指向に近いかを見極めることで、自分に合ったキャリア選択が可能になります。
将来のキャリアで選ぶ資格
将来的に「工事現場の責任者として働きたい」「施工会社やゼネコンでキャリアアップしたい」という方には、電気工事施工管理技士がおすすめです。
1級取得後は監理技術者として大規模工事に携わることも可能で、ゼネコンやサブコンでの昇進・昇給にも有利に働きます。
一方で、「ビルや工場などの設備管理に携わりたい」「インフラを陰で支える立場で活躍したい」という方には、電気主任技術者が適しています。
こちらは、法律で一定の設備には有資格者の配置が義務付けられているため、求人ニーズが安定しており、将来的に独立して保安管理業務を請け負う道もあります。
以下に、将来像別の資格選びをまとめた表を示します。
| 将来のキャリア像 | 向いている資格 | 理由 |
| ゼネコンで現場責任者になりたい | 電気工事施工管理技士 | 施工管理の経験・資格が出世や現場責任者への登用に直結する |
| 工場・ビルの保守担当として安定勤務したい | 電気主任技術者 | 法定資格であり、需要が安定。長く働き続けることができる |
| 将来は独立して技術顧問になりたい | 電気主任技術者 | 保安協会や法人設立を通じて、設備管理業務を外部受託できる可能性がある |
このように、自分が描くキャリアに合った資格を選ぶことが、後悔のない選択につながります。
将来の自分を明確にイメージし、どちらが理想に近いかをしっかり見極めましょう。
まとめ
今回の記事では、電気工事施工管理技士と電気主任技術者の違いについて解説しました。
資格を選ぶ際は、将来の働き方や興味のある業務内容に合わせて選ぶことが重要です。
安易に決めず、自分のキャリアビジョンに合った資格を選びましょう。
実際、電気工事施工管理技士と電気主任技術者は、取得するだけでも大きな価値があります。
一方で、その価値が十分に評価されるかどうかは、働く環境次第です。
- 今の職場で資格がどう扱われているか
- 将来的にどんな選択肢があるか
- 転職すべきか、副業という道があるか
無理な提案は行わず、電気工事施工管理技士や電気主任技術者を持つ方向けの選択肢整理を無料で行っています。