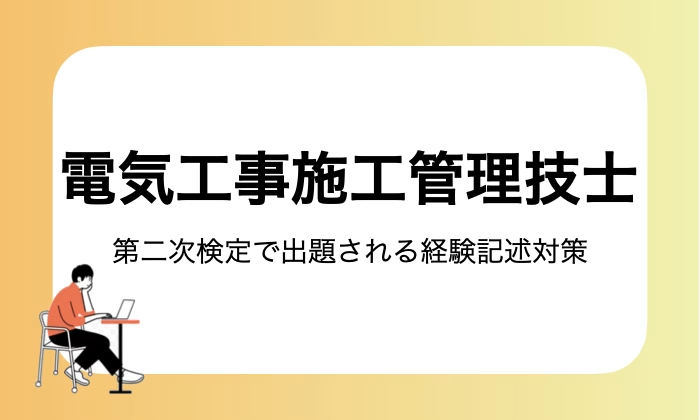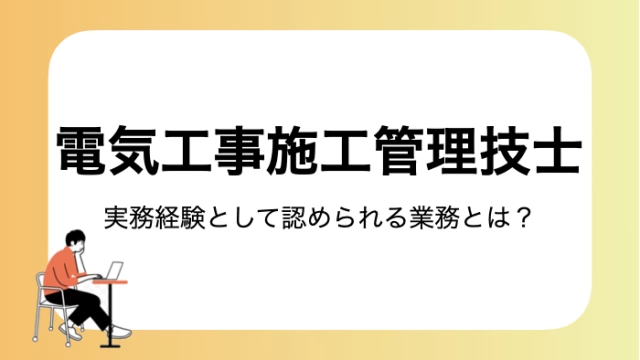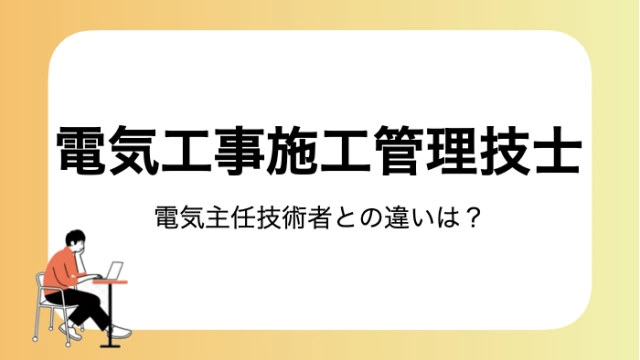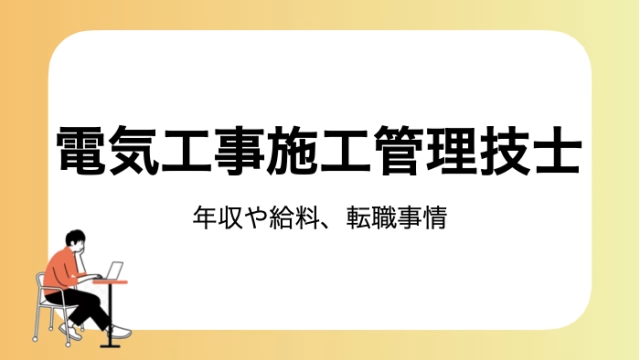電気工事施工管理技士の第二次検定では、工程管理をはじめとする経験記述問題が合否を大きく左右します。
新しい出題形式への対応も求められ、戸惑っている方も多いでしょう。
そこで、今回は電気工事施工管理技士の経験記述対策と工程管理の書き方について解説します。
この記事を読めば試験で評価される経験記述の構成・表現・具体例がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
試験制度の変更と最新の出題傾向
令和6年度から電気工事施工管理技士の試験制度が見直され、特に第二次検定では経験記述の出題形式が大きく変更されました。
これにより、従来の暗記中心の対策では対応が難しくなり、実務に基づいた柔軟な記述力が求められています。
以下で、変更点とその背景、対応策を詳しく解説します。
令和6年度からの出題形式の変更点
令和6年度からの試験制度変更では、電気工事施工管理技士の第二次検定において「記述問題の出題形式」が抜本的に見直されました。
従来は自らの経験を自由記述で問われるスタイルが主流でしたが、2024年度からは選択式の要素が加わり、「条件付きで書かせる」出題形式へと変化しています。
具体的には、以下のような変更があります。
| 従来形式 | 令和6年度以降 | 受験者への影響 |
|---|---|---|
| 自由記述形式 | 選択+条件付き記述 | 内容の的確さと構成力が必要 |
| 出題テーマは明示されない | 複数テーマから選択 | 事前準備がしやすくなる |
この変更は、より実践的な判断力と表現力を評価するために導入されたものであり、実務経験が浅い受験者にとってはやや厳しい側面もあります。
一方で、構造的な書き方を身につければ、以前よりも高得点を狙える可能性が高くなったともいえるでしょう。
暗記対策では通用しない理由
新形式では、いわゆる「ひな形の丸暗記」や「ネットに落ちている例文の使い回し」では通用しません。
なぜなら、問われるのは具体的な施工経験に基づく記述であり、かつその記述がテーマや条件に沿って適切であるかが重視されるからです。
たとえば、「工程管理に関する経験を、品質・安全との関連に触れて書け」といった条件がつく場合、単に工程管理の手順だけを書いても不合格となるリスクがあります。
加えて、現場でのトラブルや対応策、改善点といった要素も盛り込む必要があり、受験者自身の経験を客観的に整理・言語化する力が求められます。
このように、「書き方を覚えて使い回す」対策から、「状況に応じて構成を変える」柔軟なスキルへの転換が不可欠です。
逆に言えば、きちんとした構成パターンを習得すれば、初見の問題にも対応できるようになります。
経験記述の選択式・条件付き出題の特徴
令和6年度から導入された「選択式・条件付き出題」には、以下のような特徴があります。
- 複数の設問テーマ(例:品質管理、安全管理、工程管理など)から1つを選ぶ
- 選んだテーマについて、指定された要素(例:課題・対策・効果など)を盛り込んで記述する
- 字数制限や段落構成の指定がある場合もある
この形式のポイントは、「自分の経験をテーマと条件に適合させて再構成する力」です。
例えば、工程管理の経験があったとしても、「品質との関連性を述べよ」という条件がある場合、その関連性を掘り下げて書かなければなりません。
また、条件が複数重なることで、受験者が何を求められているかを正確に読み取る読解力も問われます。
記述力だけでなく、設問の意図を正確に捉える力がなければ、点数を取りこぼしてしまうのです。
こうした変化に対応するためには、テンプレート的な暗記から脱却し、自身の経験を「条件に沿って語る」練習を積むことが合格への近道となります。
経験記述問題の出題形式と配点の仕組み
経験記述問題は、施工管理技士試験の中でも特に実務能力を評価する重要なパートです。
問1と問2に分かれており、それぞれ異なるテーマと出題形式で出題されます。
ここでは、それぞれの問題形式と配点の仕組みについて詳しく解説します。
問1:工程管理・安全管理に関する選択問題
問1では、受験者のこれまでの経験を踏まえた「工程管理」または「安全管理」のいずれかを選んで記述する形式が採用されています。
設問では、まず「あなたが担当した工事の概要(工事名、工期、施工場所など)」を簡潔に説明することが求められ、その後に「工程管理の工夫点と効果」あるいは「安全管理の取り組みと効果」など、実務での具体的な取り組みについて記述するよう指示されます。
記述内容では、「なぜその工夫や対策を行ったのか」という背景や理由が重視されており、単なる作業内容の羅列では評価されません。
例えば「天候による遅延が予想されたため、資機材の調整を前倒しで行った」といったように、状況判断と対応策、そして結果としての効果までを論理的に説明する力が必要です。
用語の正確な使い方や、業務フローの理解が問われるため、単なる丸暗記では太刀打ちできません。
また、工事の種類や規模、担当フェーズによって、適したテーマの選択が合否を分けることもあります。
自分の経験の中で、より具体的かつ成果のあるエピソードを選ぶことが重要です。
問2:品質管理とその理由・対策の記述
問2では、主に「品質管理」に関する実体験をもとに、トラブルを防ぐために講じた対策や、品質向上のために工夫したことなどを記述します。
問1と異なり、選択ではなく全員が同じテーマでの記述となります。
与えられた設問に対して、自分が関わった具体的な工事を想定し、その中で品質をどのように確保・改善したかを論理的に説明する必要があります。
設問では「発生し得る品質問題」「それに対して取った予防措置」「その効果や成果」などの観点から記述するよう求められます。
例えば「配管工事における寸法精度確保のため、施工前に墨出し工程を3段階に分けてチェックした」など、実務に即した具体性のある記述が評価されます。
重要なのは、ただ問題を挙げるのではなく、その背景にある「原因の分析」と「対策立案の理由」、そして「結果としてどうなったか」というストーリーを構築することです。
これにより、品質管理に対する意識の高さや実践力が評価されます。
施工管理においては、品質の確保が最終的な顧客満足や信頼につながるため、技術的な理解だけでなく、マネジメント的視点も盛り込んだ記述が理想です。
各問題の配点と合格基準
経験記述問題は、全体の中でも重要な得点源であり、それぞれの設問には明確な配点が設定されています。
問1・問2それぞれに40点、合計80点満点の構成となっており、合格のためにはこの記述問題で一定以上の得点を獲得する必要があります。
合格基準としては、一般的に各問で60%以上(24点以上)を獲得することが望ましいとされますが、近年では採点がより厳格化されており、論理性や一貫性のない記述は容赦なく減点される傾向にあります。
特に、経験の裏付けが曖昧だったり、課題と対策のつながりが弱い場合は高得点が望めません。
以下の表は、経験記述問題の配点と評価ポイントをまとめたものです。
| 設問 | 配点 | 評価ポイント |
|---|---|---|
| 問1(工程管理または安全管理) | 40点 | 選択の妥当性・論理構成・具体性・成果の有無 |
| 問2(品質管理) | 40点 | 問題提起・原因分析・対策理由・実施効果 |
つまり、単に自分の業務経験を羅列するだけでは不十分であり、論理的思考と実務への理解、そして文章構成力が問われる問題といえます。
事前にテーマを想定し、何度も書き直しながら練習することが、合格への近道となるでしょう。
経験記述を書くための5つの基本ルール
経験記述問題では、実務経験をもとに自らの業務遂行力を論理的に説明することが求められます。
ここでは、経験記述を書く際に必ず押さえておくべき5つの基本ルールについて解説します。
実体験をベースに構成する重要性
経験記述において最も重要なのは、自身の実体験をもとに記述を構成することです。
抽象的な内容や他人の経験を借りたような記述では、読み手に信頼性を与えることができません。
実際に担当した工事や現場での取り組みをベースに、時系列や因果関係を明確にしながら記述を展開しましょう。
たとえば、「〇年〇月に着工したRC造の3階建て共同住宅工事において、躯体工事の進捗が1週間遅れた際には、作業工程を再調整し、電気・配管業者との工程を前倒しする調整を行いました」など、事実を具体的に記すことが重要です。
体験に基づいたリアルなエピソードこそが、評価者に高く評価される文章の基盤となります。
工程管理に関する具体的な対策と数値の活用
工程管理の記述では、対策を講じた理由や、その効果を数値で示すことが非常に有効です。
単に「工程を調整した」と書くよりも、「当初予定より3日遅れた工程を2日分前倒しするために、鉄筋工事の作業人員を5人から8人に増員した」といった、具体的な行動と数値を含めた記述が求められます。
また、日程変更の際に使用したツール(工程表、ガントチャートなど)や、業者間の調整方法(週次会議、LINE連絡網など)も記述に含めると説得力が増します。
さらに、「結果として、全体工程に影響なく、当初の引き渡し予定日通りに竣工できた」という効果も忘れずに書きましょう。
数字や事実に基づく論理展開は、記述内容の信頼性を高める鍵です。
誤字・脱字、行数、専門用語の使い方
経験記述問題では、文章表現そのものも評価の対象です。
まず、誤字・脱字は減点対象になるため、提出前の確認は必須です。
読みやすく、端的に伝わる表現を心がけ、無駄な修飾や冗長な言い回しは避けましょう。
行数についても、問題ごとに指定された行数を埋めることが重要です。
大幅に行数が足りないと、実務経験が浅いと見なされる可能性があります。
専門用語については、過度な使用は避けるべきですが、工事種別や作業内容に応じた適切な用語(例:根切り、型枠支保工、躯体、仮設足場など)は使用し、必要に応じて補足説明を加えると親切です。
文章の精度と読みやすさは、記述全体の印象を左右する要素であることを意識してください。
経験記述の文章構成と書き方の手順
経験記述では、読み手が内容を理解しやすく、かつ論理的に伝わる構成が求められます。
特に導入から効果までの一貫した流れを意識し、背景や制約条件、取り組んだ工夫などを明確に書くことで、文章全体の説得力が高まります。
以下にその具体的な書き方を示します。
導入 → 問題点 → 理由 → 対策 → 効果の流れ
経験記述の文章は、まず「導入」で業務の概要や背景を説明し、その中で直面した「問題点」を明確にします。
次にその問題が起きた「理由」を客観的に分析し、それに対して自分が講じた「対策」を記述します。
そして、最終的に得られた「効果」や成果を具体的に述べて、読み手に自分の取り組みの価値を伝えます。
この5つの要素を順番に記述することで、文章全体に一貫性と説得力が生まれます。
たとえば、「工程の遅延」という問題があった場合、単に「対策を講じた」だけでなく、なぜ遅延が発生したのか、どのような状況だったのかを具体的に書くことが重要です。
また、対策の内容は「打ち合わせ回数を増やした」といった表面的なものではなく、「業者間の工程を見直し、工程表を再編成した」など、読み手がその有効性を判断できるような記述が求められます。
工事の背景・制約条件を的確に表現するコツ
経験記述で差が出やすいのが、工事の背景や制約条件の記述です。
ここを曖昧にすると、問題点や対策の妥当性が伝わらず、説得力が低下してしまいます。
したがって、背景や制約条件は具体的かつ簡潔に、必要な情報を過不足なく伝えるように意識しましょう。
たとえば、「駅前の商業施設での改修工事」という記述があるなら、「昼間の工事が制限されるため、夜間施工で対応」といった制約があるはずです。
このような制約を明確に書くことで、「なぜそのような工程を組んだのか」という理由が読み手に自然と伝わります。
また、「作業エリアが狭く、資材の仮置きスペースが確保できなかったため、段階的な搬入計画を立てた」といった記述も、現場対応力を具体的に伝えることができます。
制約条件の記述には、地理的条件、施工時間、近隣との関係、工期、予算、安全性など、複数の視点からの検討が必要です。
それぞれの要素が、あなたの判断や工夫にどのように影響したかを意識して記述することで、経験の深さが伝わる文章になります。
読み手に伝わる文章力の磨き方
読み手に伝わる文章とは、単に正しい日本語で書かれたものではありません。
情報の優先順位が明確で、具体性があり、かつ論理的な流れがある文章が求められます。
読み手が「なぜそのように判断したのか」「どんな結果が得られたのか」を自然に理解できるような書き方を意識することが重要です。
そのためには、主語と述語の対応、接続詞の適切な使用、冗長な表現の排除を意識して文章を見直す習慣をつけましょう。
たとえば、「私はA工事に従事した。B工事では苦労した」という記述は主語が変わってしまっているため、文脈が混乱します。
正しくは「私はA工事およびB工事に従事し、特にB工事では○○に苦労した」とまとめると、読みやすくなります。
また、文章構成の訓練には、「誰に・何を・どう伝えるか」の視点を持つことが効果的です。
記述の目的を明確にし、それに沿って構成を組み立てることで、無駄のない読みやすい文章になります。
さらに、実際に書いた文章を第三者に読んでもらい、わかりやすさや伝わり方のフィードバックを受けることも、文章力向上に大いに役立ちます。
工程管理の経験記述:具体例と注意点
工程管理の経験記述では、ただ作業日程を説明するのではなく、「どのような課題に直面し、それにどう対応したのか」を論理的に展開する必要があります。
特に施設運用中の工事や狭隘な現場では、制約条件や安全面のリスクが多く、工程管理者としての判断力と対応力が問われます。
以下では、具体的な問題例や注意点、そして効果的な記述方法を紹介します。
「施設運用中」の工事で起きやすい問題とは
施設が稼働している状態での工事では、利用者や管理者の活動に配慮しながら作業を進める必要があります。
特に、病院や学校、商業施設などでは工事による騒音、振動、粉塵の発生が業務や学習、サービス提供の妨げとなる可能性があるため、工程の制約が非常に大きくなります。
さらに、工事中の動線確保や設備停止に伴う影響範囲も予測しづらく、事前の調整や説明が不十分だとクレームや工事中断に直結します。
このようなケースでは、工程の組み方そのものに工夫が必要であり、例えば「夜間工事を主体とした工程組み」や「作業単位を細分化して短時間で完了させる」などの対応が求められます。
経験記述では、これらの制約をどう整理し、誰とどのように調整して工程を成立させたかまでを、具体的に書くと説得力が増します。
狭い空間での工程管理とリスク回避
狭隘な現場では作業員の移動や資機材の搬入・設置に時間がかかる上、同時作業が難しくなることから、工程の重複がリスクになります。
特に既設建物内のリニューアル工事などでは、他業種との干渉が頻発し、工程のずれが全体遅延につながりやすい状況です。
このような環境では、まず空間ごとの作業内容を事前に可視化し、1日の作業量や順序、職種の配置を細かく管理することが基本です。
たとえば「1区画ごとの日単位管理」や「工具・資材の事前配置」「仮設養生・清掃の工程内組み込み」など、狭さを前提にした段取りを記述に盛り込みましょう。
また、実際に発生したトラブル(例:搬入作業中の接触事故)などがあれば、それに対してどう工程や管理体制を見直したかを記すことで、管理能力の高さをアピールできます。
問題ごとの具体的な対策の書き方
工程管理の記述では、「問題が発生した」「工程に遅れが生じた」といった事実だけで終わらせず、必ず「どのような対策を取ったか」「その効果はどうだったか」まで踏み込んで書くことが重要です。
たとえば、「配管工事の工程が遅延した」という問題に対しては、「作業班を2分割して並行作業できる区画を設け、夜間作業を増やした」「各業者との朝礼で日次計画を共有する体制を導入」などの対策を明記します。
その結果、「予定より2日短縮できた」「業者間の作業重複が解消された」といった効果も示すことで、工程調整力の高さが伝わります。
また、記述の際には「誰と」「どのように話し合い」「どの判断を下したか」というプロセスの流れも忘れずに書きましょう。
文章としては「問題→原因→対策→効果」という流れを徹底することが、評価される経験記述につながります。
よくある失敗例とその回避法
ここでは、電気工事施工管理技士の経験記述における失敗例や対策について解説します。
模倣文のリスク
インターネット上に公開されている実務経験記述の例文をそのまま模倣することは、非常にリスクが高い行為です。
なぜなら、オリジナリティがないと判断されるだけでなく、内容と実際の職務経験が一致しない場合には、虚偽の記載とみなされる可能性があるからです。
また、模倣された文章には、その現場や業務に対する具体的な関与が見られず、評価者から「この人が本当に経験した内容か?」という疑念を持たれてしまいます。
対策としては、例文を参考にするのは構いませんが、自分が実際に体験した工程や判断、トラブルとその対応を思い出し、できる限り具体的に記述することが求められます。
たとえば「納期遅延を防ぐため、施工業者との日次進捗ミーティングを導入した」といったように、行動と目的をセットで書くことでオリジナリティが自然と生まれます。
模倣文ではなく「経験の棚卸し」を徹底することが、合格レベルの記述への第一歩です。
抽象表現・誤用・一貫性の欠如
実務経験記述において、「施工管理を的確に行いました」「安全に配慮しました」などの抽象的な表現は避けるべきです。
これらは具体性がなく、どのような行動をとったのか、どんな工夫があったのかが伝わらないため、評価に結びつきません。
また、専門用語の誤用や日本語の曖昧な使い方も、記述内容の信頼性を損ないます。
さらに、文章の前半と後半で内容が食い違う、あるいは工程の時系列が混乱しているといった「一貫性の欠如」も減点対象になります。
これらの失敗を防ぐには、まず自分の記述を第三者の目線で読み直すことが重要です。
「この内容で初見の第三者に状況が伝わるか?」「一貫した流れになっているか?」という観点で点検しましょう。
また、各段落のはじめに「背景・問題」、中盤で「対応策」、終わりに「結果」を明示する構成を意識すると、自然と一貫性と具体性が整います。
問題点と対策の不一致パターン
記述の中で頻繁に見られるミスの一つに、「問題」として書かれている内容と、「対策」として述べている行動が一致していないケースがあります。
たとえば、「工期が短く、工程調整が困難だった」と書いたにもかかわらず、対策として「現場の安全確認を徹底した」と記述されていると、評価者は「工程問題への対応が記述されていない」と判断します。
これは単なる構成ミスではなく、実際の業務理解が浅いと受け取られかねない重大な失点要素です。
対策としては、「問題—原因—対策—結果」の流れをセットで考えることです。
工期に関する問題であれば、その原因(業者の遅れ、天候、資材納品の遅れなど)を明示し、そのうえでどのような行動でスケジュールを調整したか(工程の前倒し調整、応援要員の投入、夜間作業の許可取得など)を具体的に記述します。
そして結果として「計画通りの工期で竣工した」などの結論で締めることで、論理的で一貫性のある文章となります。
この一連の流れが正しく構成されていれば、評価者にも「現場をよく理解して業務を遂行している人物」という印象を与えることができます。
実務経験が浅い方への対策と情報収集法
実務経験が浅い方でも、工夫次第で知識や理解を深めることは十分可能です。
以下では、現場の観察や先輩からの学び、書籍や問題集の活用法、そして模擬問題を通じた実践的なトレーニング方法について解説します。
現場見学・先輩の体験談から学ぶ方法
実務経験が少ない方にとって、現場の空気感や実際の作業の流れを知ることは非常に重要です。
机上の学習だけではイメージしづらい作業手順や安全対策なども、現場見学を通じて視覚的に理解できます。
たとえば、配線経路や機器設置の方法を自分の目で確認することで、施工図の読み方や設計意図もより具体的にイメージできるようになります。
また、先輩や上司に対して「この設備の設計意図は何ですか?」「トラブルが起きたときはどう対応しますか?」といった質問をすることで、現場での判断基準や過去の成功・失敗事例など、貴重なノウハウを吸収することができます。
情報収集の姿勢としては、「教えてもらう」のではなく「学び取る」意識が大切です。
訪問先や話を聞いた内容をメモし、後から自分なりに整理して復習することで、理解が深まります。
複数の現場を見ることで共通点と違いも見えてくるため、継続的な現場観察をおすすめします。
専門書や過去問の活用ポイント
専門書や過去問は、知識の整理と体系的な理解を深めるための強力なツールです。
ただし、分厚い専門書を頭から読むのではなく、「目的別に必要な箇所を拾い読みする」読み方が効果的です。
たとえば、施工計画について理解したい場合は、該当の章だけを集中的に読み、内容をノートにまとめることで理解が定着します。
また、過去問は知識の応用力を養うのに最適です。
同じテーマでも出題の角度が異なる問題を複数解くことで、知識が浅くても「どこを問われやすいか」「どんな表現で問われるか」が見えてきます。
間違えた問題は必ず解説を読み、正答の理由を言語化する癖をつけましょう。
さらに、専門書と過去問を組み合わせることで相乗効果が生まれます。
過去問で理解できなかった箇所は専門書で補い、逆に専門書で得た知識を過去問で確認する流れが理想です。
この繰り返しにより、理解の「幅」と「深さ」をバランスよく強化できます。
模擬問題で書く練習を積むコツ
知識を持っているだけでは、実際の試験で合格点に達することはできません。
特に、記述式問題では「書く力」が重要です。模擬問題を活用してアウトプットの練習を積むことで、記述力を高めましょう。
最初は過去問を参考にしながら、問題に対して自分の言葉で答える練習から始めます。
1回目はうまく書けなくても構いません。
大切なのは、「なぜそのように書いたか」を自己分析することです。
例えば、「配線の施工方法を説明せよ」といった問題に対して、実務経験がないと抽象的な表現に頼りがちになりますが、模範解答と照らし合わせることで「どこが具体性に欠けていたか」が見えてきます。
また、書いた答案は第三者に見てもらうのが効果的です。
可能であれば先輩や講師に添削を依頼し、フィードバックを得ることで、自分では気づけない弱点が明らかになります。
さらに、時間を測って答案を作成することで、本番さながらの緊張感の中で文章構成力と表現力を鍛えることができます。
毎週1問ずつ取り組むなど、継続的に取り組む姿勢が記述力向上への近道です。
まとめ
今回の記事では、電気工事施工管理技士の第二次検定で必要な経験記述について解説しました。
今回お伝えした内容を参考に、ぜひ電気工事施工管理技士の取得を目指して頑張ってください。
電気工事施工管理技士は、現場を支える重要な資格です。
その一方で、
- 責任が重い割に評価が低い
- 長時間労働が常態化している
- 将来の働き方が見えない
と感じている方も少なくありません。
資格を活かしながら無理なく働く選択肢について、転職・副業の両面から無料で相談を受け付けています。