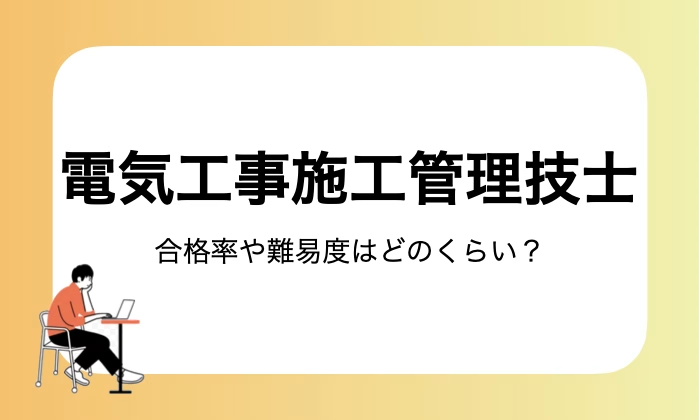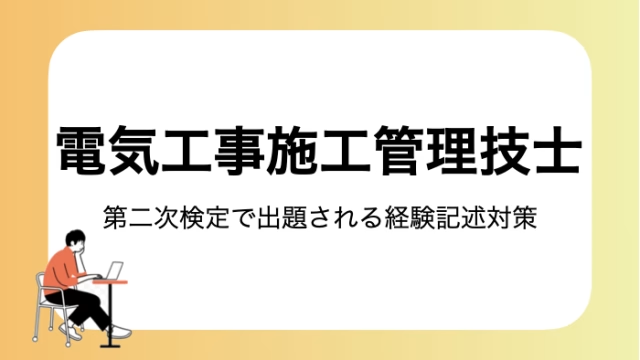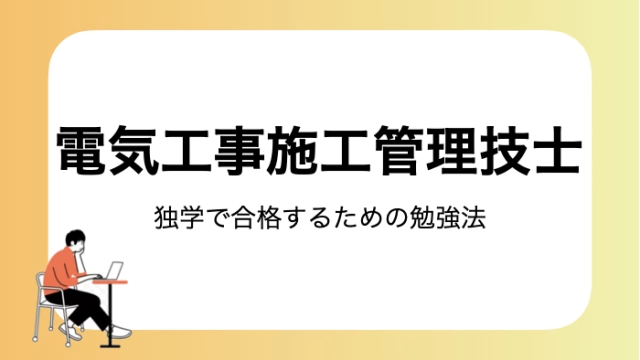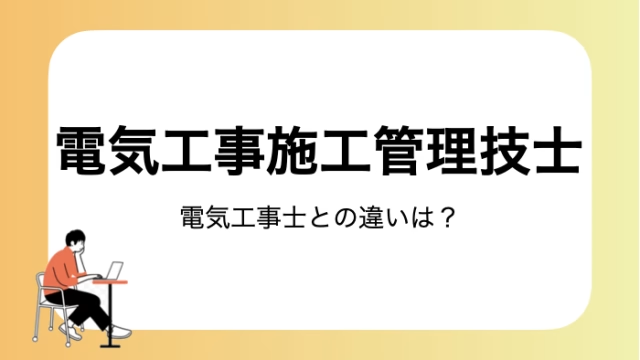電気工事施工管理技士の合格率が気になる方に向けて、今回は電気工事施工管理技士の合格率や試験の難易度、他資格との比較について解説します。
この記事を読めば1級・2級それぞれの合格率の傾向や、難易度・偏差値の目安、効率的な学習法がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
電気工事施工管理技士とは
電気工事施工管理技士は、国土交通省が所管する「施工管理技術検定」によって認定される国家資格です。
建設業法に基づき、一定規模以上の電気工事を行う際には、施工管理技士の配置が義務づけられています。
この資格を有していることで、専任技術者や主任技術者として現場に配置されることが可能になります。
1級と2級の違い
電気工事施工管理技士には1級と2級があり、それぞれに対応する業務範囲と責任の重さが異なります。
以下の表は、1級と2級の業務範囲の違いをまとめたものです。
| 業務内容 | 2級電気工事施工管理技士 | 1級電気工事施工管理技士 |
|---|---|---|
| 一般建設業における専任技術者 | 従事できる | 従事できる |
| 特定建設業における主任技術者 | 従事できない | 従事できる |
| 監理技術者としての従事 | 不可 | 可能 |
このように、1級資格はより高い責任と裁量が与えられる分、取得には実務経験や高度な知識が求められる点も特徴です。
【1級・2級別】合格率の推移と最新データ
電気工事施工管理技士の1級・2級それぞれの合格率は、受験者にとって非常に気になるポイントです。
ここでは、最新の合格率データや過去の推移、合格基準の仕組みについて詳しく解説します。
1級・2級それぞれの合格率の比較
電気工事施工管理技士には1級と2級がありますが、その難易度は大きく異なります。
試験範囲や求められる実務経験年数にも差があり、当然ながら合格率にも差が出ます。
以下の表は、直近3年間の1級と2級の学科試験・実地試験の合格率を比較したものです。
| 試験区分 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 1級(学科) | 44.3% | 42.7% | 43.1% |
| 1級(実地) | 37.2% | 34.5% | 35.8% |
| 2級(学科) | 59.4% | 61.0% | 60.2% |
| 2級(実地) | 48.6% | 50.1% | 49.3% |
全体として2級の方が合格率が高く、1級は実地試験が特に難関であることがわかります。
年度別の合格率推移
合格率は年度ごとに変動があり、難易度の指標として活用できます。
例えば、出題形式の変更や受験者数の増減、業界動向の変化などが影響します。
以下は過去5年間の1級と2級の合格率推移です。
| 年度 | 1級(実地) | 2級(実地) |
|---|---|---|
| 2019 | 39.5% | 51.2% |
| 2020 | 36.8% | 52.5% |
| 2021 | 37.2% | 48.6% |
| 2022 | 34.5% | 50.1% |
| 2023 | 35.8% | 49.3% |
近年では大きな変動は見られず、1級は30%台後半、2級は50%前後で推移しています。
これにより、合格に必要な準備の指針が立てやすくなっています。
合格基準の詳細(6割基準など)
電気工事施工管理技士試験の合格基準は「正答率60%以上」が一般的なラインとされています。
ただし、年度や試験内容によっては基準が若干調整されることもあります。
学科試験は選択問題が多いため、正答数が明確に決まっています。一方で、実地試験は記述式のため、評価がやや不透明に感じられることがあります。
また、1級と2級で合格基準に違いはありませんが、実地試験における記述内容の専門性や論理性は1級の方が求められるレベルが高いです。
実務経験に基づいた内容が問われるため、単なる知識だけでなく、現場での対応力や技術者としての視点が必要です。
合格するためには、過去問対策だけでなく、自身の実務経験をうまく言語化できるトレーニングが重要になります。
合格率から見る試験の難易度と偏差値
電気工事施工管理技士試験の合格率から見た難易度や、他資格との比較、偏差値的な目安について解説します。
社会人が働きながら挑戦する際の現実的な対策も取り上げています。
合格率と難易度の関係性
電気工事施工管理技士の合格率は、試験の難易度を示す一つの目安になります。
1級と2級の両方において、合格率は年度によって上下しますが、平均すると2級が約50~60%、1級が約30~40%となっています。
この数字からわかるように、2級はある程度の学習時間を確保すれば合格できる可能性が高く、1級は実務経験や応用力が求められる難易度の高い試験です。
特に1級の実地試験は記述式であり、実務経験に基づいた具体的な記述が求められるため、合格率が低めに推移する傾向があります。
単に知識だけでなく、業務に対する理解と表現力が問われる点が、難易度の高さに直結しているのです。
そのため、合格率を見る際は、試験の形式や内容とセットで捉えることが重要です。
「電気工事施工管理技士の偏差値」はどのくらい?
国家資格において偏差値という概念は公式には存在しませんが、目安として大学入試のように合格率を元に偏差値的な位置づけを考えることは可能です。
一般に合格率が30%程度であれば、偏差値は約60〜65と見なされることが多く、1級電気工事施工管理技士はそれに相当します。
一方、2級の偏差値は合格率が50〜60%であるため、概ね偏差値50〜55程度とされます。
この偏差値的な目安は、あくまで一般的な尺度に当てはめたものであり、資格取得の価値や難易度を一律に評価するものではありません。
しかし、自分の現在の学習状況や目標設定の参考にはなります。
特に1級を目指す場合には、難関大学入試に近い準備が必要とされる点を意識して取り組むと良いでしょう。
他の電気系資格との比較(例:電気工事士、工事担任者 など)
電気工事施工管理技士は、他の電気系資格と比較しても、実務経験や総合的な知識が求められるため、難易度は高めに位置づけられます。
以下に主な電気系資格とその特徴を比較した表を示します。
| 資格名 | 平均合格率 | 特徴 |
|---|---|---|
| 第二種電気工事士 | 60〜70% | 初心者向け。筆記と実技がある |
| 工事担任者(AI・DD総合種) | 35〜45% | 通信設備の専門資格 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 30〜40% | 施工計画・工程管理など総合力が必要 |
この比較からも分かるように、電気工事施工管理技士は施工管理やマネジメントの知識が問われるため、他資格よりも実務との連動性が強く、試験対策も多角的になります。
知識だけでなく、経験や思考力も試される資格だといえるでしょう。
社会人が働きながら取得する難しさと対策
社会人が電気工事施工管理技士の資格を目指す場合、最大の壁は「時間の確保」です。
特に1級の場合は出題範囲が広く、実務に基づいた記述式の問題対策も必要となるため、仕事と学習の両立が困難だと感じる人も多いでしょう。
加えて、家庭やプライベートとのバランスを取る必要もあり、計画的な学習が求められます。
その対策としては、スキマ時間を有効活用することがカギになります。
例えば通勤時間に講義動画を視聴したり、昼休みに過去問を解いたりといった工夫が効果的です。
また、記述対策については添削サービスや勉強会の活用が推奨されます。
さらに、試験日から逆算して「何を、いつまでに終えるか」を明確にすることで、焦りを減らし効率的な学習が可能になります。
社会人にとっては時間もエネルギーも限られていますが、計画的かつ実践的な学習を行えば、十分に合格を狙える資格です。
電気工事施工管理技士の難易度を左右する3つの要素
電気工事施工管理技士の試験は単なる知識だけでなく、実務経験や記述力も求められるため、一筋縄ではいかない難しさがあります。
そんな電気工事施工管理技士試験の難易度を左右する3つの要素について紹介します。
①試験範囲の広さと出題形式(記述式など)
電気工事施工管理技士試験の難易度を大きく左右するのが、その広範囲にわたる出題内容と出題形式の多様さです。
第一次検定では、法規・電気設備・施工管理に関する幅広い知識が問われ、マークシート形式であっても油断できません。
また、第二次検定では択一問題に加えて記述問題もあり、ただ用語を知っているだけでは通用しない構造になっています。
問題文を正確に読み取り、自分の言葉で的確に答える能力が問われるため、普段から文章表現の練習も必要です。
さらに、最新の法改正や施工基準に関する知識も出題されるため、情報収集力と応用力が求められるのが特徴です。
②第二次検定の記述問題の壁
第二次検定の記述式問題は、多くの受験者にとって最大の難関です。
というのも、実務経験に基づいた記述が求められるため、単なる知識では通用せず、実務を経験していない人にとっては対策が困難だからです。
例えば「安全管理」や「工程管理」に関する記述問題では、具体的な現場経験を交えて論述する必要があります。
また、論理的かつ簡潔にまとめる文章構成力も評価対象となるため、単に経験があるだけでは不十分です。
模範解答の写し書きでは対応できないため、自分の体験をもとに、説得力のある文章を書く訓練が合格のカギとなります。
③ 実務経験の有無による差
電気工事施工管理技士の試験では、実務経験の有無が合否に大きく影響します。
特に第二次検定では、現場での経験を前提とした問題が出題されるため、経験者と未経験者とではスタートラインが異なります。
たとえば、電気設備の工程計画や施工方法に関する問題では、実際に現場で指示を出した経験があれば、自然と説得力のある答案が書けるでしょう。
一方で、実務経験がない場合は、参考書や講義だけでは限界があり、知識が机上の空論になりがちです。こ
の差を埋めるためには、模擬現場の事例に基づいた勉強や、実務者の添削指導を受けるなど、現場感覚を養う工夫が必要です。
合格に必要な学習時間と効果的な勉強法
電気工事施工管理技士の試験に合格するためには、目安として約200時間の学習が必要とされています。
限られた時間を効率よく使うためには、学習方法の選択が極めて重要です。
ここでは、学習時間の目安や、自分に合った勉強法を見極めるヒント、過去問や参考書の活用法について詳しく解説します。
合格までに必要な目安時間(約200時間)
電気工事施工管理技士の試験に合格するために必要な学習時間は、一般的に一次・二次試験を合わせて約200時間とされています。
ただし、個人の理解力や基礎知識の有無によっても大きく前後する点には注意が必要です。
電気の基礎知識がある人であれば150時間前後で済むこともありますが、まったくの初心者であれば300時間近く必要となることもあります。
特に一次試験は選択式のため比較的取り組みやすい一方、二次試験では記述式の問題が出題されるため、単なる暗記では対応しきれません。
したがって、学習時間のうち50時間以上は記述練習に割くことをおすすめします。
仕事や家庭の時間を確保しながら、1日1〜2時間をコツコツ継続することが、合格への近道となるでしょう。
独学・通信講座・講習会それぞれのメリット
電気工事施工管理技士の勉強方法には、大きく分けて独学・通信講座・講習会の3つがあります。
それぞれにメリット・デメリットがあり、自分のライフスタイルや学習スタイルに合わせた選択が大切です。
独学は最もコストを抑えられる方法で、自分のペースで進められる点が魅力です。市販の参考書と過去問題集があれば、基本的な知識を習得することができます。
ただし、疑問点を自力で解決しなければならないため、途中でつまずきやすい傾向があります。
一方、通信講座は、プロが作成したカリキュラムに沿って学べるため、効率的な学習が可能です。
分からない箇所を質問できるサービスや、記述添削サポートなどが用意されていることもあり、独学よりも安心して取り組めます。
講習会は、短期間で集中して学びたい人に適しています。
リアルタイムで講師の解説を聞けるため、理解が深まりやすく、モチベーションの維持にもつながります。
ただし、費用が高めで、スケジュールが制限される点には注意が必要です。
過去問と参考書の活用法
電気工事施工管理技士の合格を目指すなら、過去問と参考書をうまく活用することが不可欠です。
まずは市販の参考書を一通り学習し、試験の全体像と基礎知識を把握しましょう。
参考書選びでは、イラストや図解が多く、初心者にもわかりやすいものを選ぶのがポイントです。
参考書で知識をインプットした後は、必ず過去問に取り組みましょう。
5年分以上の過去問に繰り返し挑戦することで、出題傾向が把握でき、苦手分野も明確になります。
詳しい勉強法については、以下のページでも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
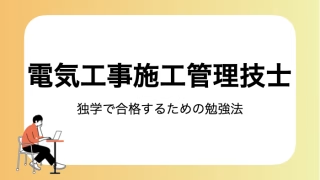
まとめ
今回の記事では、電気工事施工管理技士の合格率について解説しました。
今回お伝えした内容を参考に、ぜひ電気工事施工管理技士の取得を目指して頑張ってください。
電気工事施工管理技士は、現場を支える重要な資格です。
その一方で、
- 責任が重い割に評価が低い
- 長時間労働が常態化している
- 将来の働き方が見えない
と感じている方も少なくありません。
資格を活かしながら無理なく働く選択肢について、転職・副業の両面から無料で相談を受け付けています。