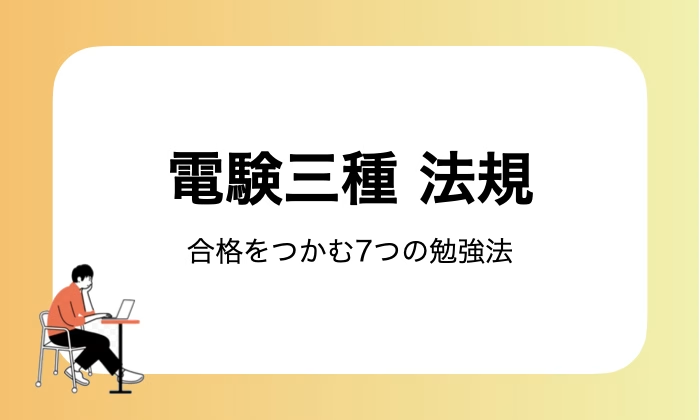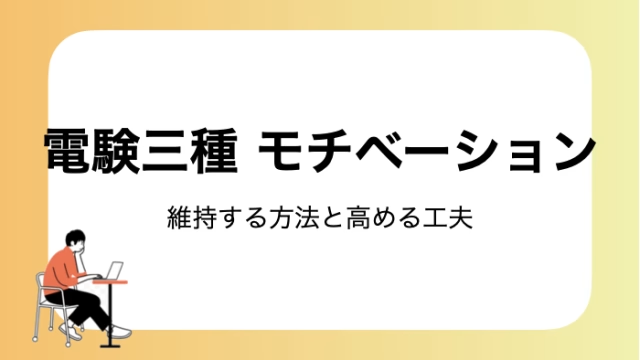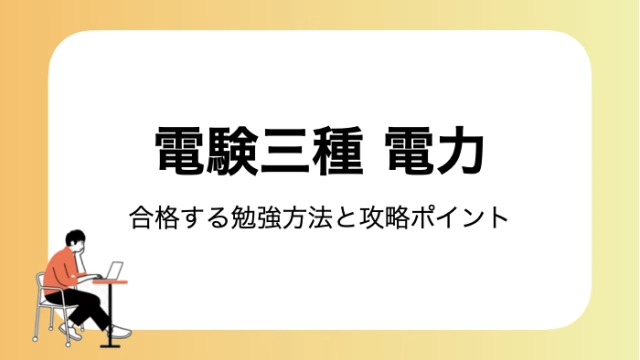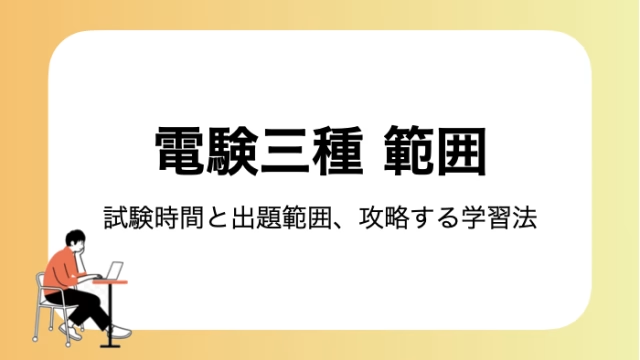「法規の覚え方が全然身につかない…」ということはありませんか?
電験三種の法規は、試験範囲が広く、計算と暗記のバランスも難しいため、どう勉強すればよいか迷ってしまう方が多いです。
そこで、今回は電験三種の法規に特化した覚え方と勉強法について解説します。
この記事を読めば、法規の出題傾向や効率的な覚え方、過去問やアプリの活用法がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
電験三種の法規とは?試験の特徴と出題傾向
電験三種の法規は、電気法規および電気施設管理に関する内容が問われる科目です。
暗記だけでなく計算力も必要とされ、他科目より難易度が高いのが特徴です。
ここでは試験の内容や配点、他科目との比較を詳しく解説します。
法規の試験内容と出題範囲
電験三種の「法規」では、電気の安全や管理に関わる法令に関する知識が求められます。
試験範囲は主に以下の3分野に分けられます。
- 電気関係法規
- 電気設備技術基準とその解釈
- 電気施設管理
これらは、すべての範囲からバランスよく出題される傾向にあります。
そのため、「ここだけ覚えれば大丈夫」といった学習は通用せず、幅広く学ぶ必要があります。
また、法規には知識問題だけでなく、計算問題も含まれている点が他の法令系資格試験と異なります。
計算問題はおおよそ全体の40%を占めており、得点源にしやすい反面、計算力がなければ合格は難しいという特徴があります。
法規科目は「穴埋め問題」「正誤判定問題」「計算問題」など多様な形式で構成されており、単なる暗記では太刀打ちできません。
法令の仕組みを理解し、実務との関連性まで把握した上で演習を重ねることが重要です。
電験三種 法規の配点と合格基準
電験三種の法規では、全体で65分間の試験時間の中で13問が出題されます。
他の3科目(理論・電力・機械)が各90分で17問構成であるのに対し、法規だけ短く、問題数も少ないのが特徴です。
問題構成は以下の通りです。
| 問題形式 | 出題数 | 配点 |
|---|---|---|
| A問題(知識) | 10問 | 各6点 |
| B問題(計算) | 3問 | 13点×2問、14点×1問 |
合計100点満点中、60点以上が合格基準点とされています。
ただし、実際の試験では難易度によって科目間調整が入るため、合格ラインが若干前後することもあります。
過去には54点でも合格とされた年もありました。
計算問題の配点が大きいため、ここを落とすと一気に点数が伸びなくなります。
逆に言えば、計算問題をしっかり得点できれば、合格にぐっと近づくでしょう。
勉強する際は、B問題のパターンを掴み、重点的に対策を進めるのが効果的です。
他科目と比較した法規の難易度
法規は、電験三種の4科目の中でも特に難易度が高いとされます。その理由は以下の5つです。
- 問題数が少ないのに1問あたりの配点が高く、ミスが致命的になる
- 試験時間が他科目より25分短く、時間配分の難易度が高い
- 出題範囲が広く、毎年まんべんなく全分野から出題されるため山を張りにくい
- 過去問と類似した問題が出にくく、予測がしづらい
- 試験の最後に実施されるため、集中力が落ちた状態で取り組まざるを得ない
実際の合格率にもその難しさが表れています。以下は最近の試験の合格率の一例です。
| 年度 | 法規 | 理論 | 電力 | 機械 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年下期 | 24.4% | 29.2% | 25.3% | 24.9% |
| 2024年上期 | 27.3% | 23.2% | 25.2% | 26.3% |
このように、法規の合格率は常に他科目と比較して低めであり、対策の難しさが浮き彫りになります。
特に暗記だけに頼った学習では通用しないため、理解・計算・応用力の三拍子が揃った対策が求められる科目です。
なぜ法規が難しい4つの理由を解説
電験三種の法規は、他の科目とは異なる難しさが存在します。
以下で、法規が難しいとされる4つの主な理由を解説します。
問題数が少なく1問の配点が高い
電験三種の法規は問題数が他科目に比べて少なく、1問ごとの配点が非常に高いという特徴があります。
例えば、1問の正誤で数点が動くため、わずかなミスが合否を分ける結果になることも珍しくありません。
このような構造の試験では、1問の重みが大きいために心理的なプレッシャーも強まり、慎重になりすぎて解答時間を圧迫する原因にもなります。
また、確実に得点できる問題を見極める力や、ケアレスミスを減らす注意深さが求められるため、ただ知識があるだけでは得点につながらない難しさが存在します。
従って、点数配分を理解し、重要度の高い分野を優先的に学習する戦略が必要です。
試験時間が短くケアレスミスが起きやすい
法規は試験時間が60分と限られており、内容に対して時間がタイトに設定されています。
このため、計算問題や文章問題に時間をかけすぎると、後半の問題に手が回らなくなる可能性があります。
特に、文章読解力や条文の正誤を判断する問題では、設問の意図を正確に読み取る必要があるため、焦ると読み間違いを起こしやすくなります。
さらに、複雑な単位の変換や電気設備に関する計算では、ちょっとした符号や小数点の扱いを誤るだけで失点につながります。
こうしたケアレスミスを防ぐためには、過去問演習を通じてスピードと正確さを同時に鍛えることが不可欠です。
模擬試験などで実戦感覚を養うことも有効な対策となります。
出題範囲が広く出題傾向が分散
法規の出題範囲は、電気事業法、電気設備技術基準、消防法、労働安全衛生法など非常に多岐にわたります。
また、実務寄りの法令知識から電気設備の技術的な知識まで問われるため、学習対象が幅広く、効率的な勉強が難しいと感じる受験生も多いです。
さらに、近年は出題傾向が分散しており、同じ分野が毎年繰り返し出題されるとは限らないため、「これだけやれば大丈夫」という学習方法が通用しにくいのも特徴です。
このように、法規の出題範囲の広さと不安定な傾向は、計画的な学習を難しくし、試験対策における大きな壁となっています。
そのため、過去問だけに依存せず、全体を網羅する学習スケジュールの構築が求められます。
過去問の再現率が低い理由
電験三種の他の科目と比べて、法規は過去問と類似した問題の出題率が低い傾向があります。
これは、法令の改正や技術基準の更新が頻繁にあるため、問題が年々変化しやすいという背景があります。
特に、最新の条文や改正ポイントを把握していないと、過去問の知識だけでは対応しきれないケースが発生します。
加えて、文章問題では表現が変わることで設問の意図が変わり、単純な暗記では対応できないこともあります。
過去問を解いても点数が伸びにくいと感じるのは、この再現率の低さに起因しているのです。
したがって、過去問演習と並行して、参考書や最新情報を取り入れたアップデート学習が必要不可欠です。
電験三種 法規の覚え方|合格者が実践する7つの勉強法
電験三種の法規科目は、暗記と理解、そして過去問対策のバランスが求められる独特な科目です。
合格者が実際に効果を実感した7つの勉強法を紹介します。
①法規の勉強は後回しにしすぎない
法規は暗記中心の科目であるため、「直前に詰め込めばいい」と考えがちです。
しかし、実際には法令の理解や計算問題の演習が求められるため、早期からの学習が有利になります。
特に条文の言い回しや数字の暗記には時間がかかるため、他科目の学習に並行して少しずつ取り組むことが重要です。
後回しにすると、試験直前に「何から手をつけるべきかわからない」という状況になりがちです。
法規は、最初から「コツコツ型」で計画的に学習すれば得点源になります。
最初の段階で法規を「難しい」と思わず、他科目と同じように扱うことが合格への近道です。
②電験三種 法規 計算問題を優先的に攻略する
法規というと暗記科目というイメージが強いですが、実際の試験では計算問題も出題されます。
そして、この計算問題は暗記では対応できない分、得点差がつきやすいポイントです。
電気設備の設計に関する内容や、電力損失の計算など、基礎的な電気理論を活用する問題が多く出ます。
理論や電力といった他科目の知識が法規にも活きてくるため、まずは計算問題を攻略することで学習効率も向上します。
計算問題を重点的に演習することで、選択肢の絞り込みにも有利に働き、全体の得点力を底上げできます。
過去問を解く際も、まずは計算問題に注目して解法のパターンを定着させるようにしましょう。
③電験三種 法規 過去問を10〜15年分解く
法規の出題は一見ランダムに見えて、実際には一定のパターンがあります。
過去問を10〜15年分しっかり解くことで、よく出る法令や計算問題の傾向を把握でき、対策の精度が格段に上がります。
特に同じ法律や条文が形を変えて繰り返し出題されるケースが多いため、繰り返しの演習が知識の定着に直結します。
また、過去問を解くことで出題形式にも慣れ、本番でも冷静に対応できます。
模擬試験の代わりとしても活用でき、苦手分野の発見にも有効です。
ただし、単なる解答の暗記ではなく、出題の意図や根拠まで意識して解くことが重要です。
理解を伴った繰り返しで、得点力は確実に伸びていきます。
④電験三種 法規 アプリでスキマ時間を活用
法規は暗記量が多いため、スキマ時間の活用が非常に効果的です。
通勤時間や昼休み、ちょっとした待ち時間などに、法規専用の学習アプリを使えば効率的にインプットが可能です。
最近では電験三種専用の問題集アプリや一問一答形式の暗記アプリが多数あり、音声読み上げ機能や確認テスト機能が充実しています。
短時間でも繰り返し触れることで、記憶の定着が促進されます。
特に、法規で頻出の数字や名称などは、繰り返し見聞きすることで自然と頭に入ってくるものです。
紙のテキストだけでなく、アプリを活用することで学習のハードルが下がり、日常の中で無理なく継続できるのがメリットです。
⑤出題率の高い法令に絞って暗記
法規では数多くの法律や条文が出題範囲となっているため、すべてを網羅しようとすると膨大な労力がかかります。
そこで有効なのが、出題頻度の高い法令に絞って学習する方法です。
たとえば「電気事業法」「電気設備技術基準」「消防法」「建築基準法」などは高頻度で出題されます。
これらを優先的に学習し、まずは合格に必要な得点ラインを確保することが大切です。
また、同じ法令でも、特に問われやすい条項や数字に注目することで、さらに学習効率が上がります。
過去問を分析しながら「出るところだけ覚える」意識を持つことで、限られた時間を有効に使えるようになります。
⑥条文の丸暗記は避け、内容理解を重視
法規の条文は独特の言い回しが多く、丸暗記しようとすると膨大な時間がかかるうえ、応用がきかなくなります。
条文の一語一句を覚えるのではなく、「この法律は何のためにあるのか」「この条文はどのような内容を規定しているのか」といった本質を理解することが重要です。
内容を理解していれば、多少言い回しが違っても問題に対応できるようになります。
また、図やイラストを使って視覚的に把握することで、理解と記憶の両方が定着しやすくなります。
さらに、似たような条文や法律を比較しながら覚えることで、混乱を防ぐことができます。
理解に基づいた暗記が、法規攻略の鍵となります。
⑦苦手分野は通信講座で補うのも一手
どうしても法規の学習が進まない、苦手意識が拭えないという場合は、通信講座の活用も検討すべきです。
最近の通信講座は動画解説やテキストだけでなく、質問対応や進捗管理までサポートが充実しています。
特に法規に特化した講座では、重要な法令や計算問題の対策に特化したカリキュラムが組まれており、独学では気づけないポイントや理解のコツが効率よく学べます。
費用はかかりますが、短期間で得点力を伸ばしたい人にとっては非常に効果的な選択肢です。
自分の弱点に合わせて講座を選ぶことで、苦手分野を克服し、全体の得点バランスを取ることが可能になります。
電験三種 法規を効率よく学ぶための3つのポイント
電験三種の法規対策では、時間と労力をかける場所を見極めることが合格の鍵です。
以下の3つの視点から、効率よく学習を進める方法を解説します。
法令①「電気設備技術基準」は後回しでもOK
電験三種の法規にはさまざまな法令が登場しますが、中でも「電気設備技術基準」に関する出題は近年やや減少傾向にあります。
そのため、学習初期の段階では無理にこの法令から取り組む必要はありません。
むしろ、出題率の高い電気事業法や電気工事士法、消防法、労働安全衛生法などから手を付けた方が得点につながりやすく、効率的です。
「電気設備技術基準」は内容が技術的かつ抽象的な条文が多く、初学者にとっては難解です。
時間が限られている中では、得点源になりやすいテーマから攻略し、直前期にまとめて「電気設備技術基準」に触れる方が理解も定着しやすくなります。
試験では法令を丸暗記するより、選択肢の中から正誤を見抜く判断力が問われます。
最初からすべてを完璧に覚えようとせず、優先順位をつけて進めるのが合格への近道です。
条文番号の暗記は不要
法規では多くの法令や条文が登場しますが、条文番号そのものを覚える必要はほとんどありません。
試験では「第○○条」という表記がそのまま出ることは少なく、内容の理解が問われる問題が中心です。
むしろ、条文番号の暗記に時間を使ってしまうと、他の重要な学習がおろそかになりかねません。
実際の問題は、条文に含まれるキーワードや規定の趣旨、禁止事項・義務の内容などを問う形式が主です。
そのため、「この条文は○○について述べている」という内容の理解が重要であり、実務的な視点で学ぶことが効果的です。
たとえば、「感電防止措置に関する条文」や「高圧機器の点検義務に関する規定」といったように、テーマごとに分類して学習すると記憶の定着が良くなります。
あくまで“内容の理解”を優先し、条文の番号暗記に時間を費やさないようにしましょう。
法規1科目にかける目安時間は約250時間
電験三種の法規に必要な勉強時間は、おおよそ200〜300時間とされています。
個人差はありますが、平均すると250時間前後を目安にするとよいでしょう。
法規は暗記と計算が混在するため、他の科目と比べても独特な学習スタイルが求められます。
250時間を確保するには、1日2時間の学習であれば約4ヶ月、1日1時間なら8ヶ月ほどの準備期間が必要です。
この学習時間の中には、過去問演習や復習の時間も含まれます。
最初の100時間は基礎理解と法令の概要把握に、次の100時間は過去問演習と計算問題対策、残りの50時間で復習と苦手分野の補強という配分が効果的です。
特に直前期には、過去問を中心に問題演習の時間を多くとることで、実戦力がついてきます。
勉強時間は長ければ良いというものではなく、限られた時間をどれだけ集中して使えるかが重要です。
学習スケジュールを立て、定期的に進捗を確認しながら取り組みましょう。
電験三種 法規の勉強に役立つおすすめアプリ2選
電験三種の法規は暗記量が多く、勉強に苦手意識を持つ受験者が多い分野です。
しかし、最近は効率的な学習を支えるアプリも充実してきており、うまく活用することで独学でも合格レベルに到達することが可能です。
ここでは、暗記と問題演習に特化したおすすめアプリを2つ紹介します。
それぞれの特徴を活かせば、通勤時間やスキマ時間をフル活用した効率的な学習が実現できます。
暗記アプリ|おまかせ出題で効率的に学習
暗記分野に特化したアプリは、法規の重要条文や用語の記憶に非常に役立ちます。
中でも「おまかせ出題」機能があるアプリは、自分がまだ覚えていない部分を優先的に出題してくれるため、学習の無駄がありません。
これにより、「覚えていることを繰り返すだけの時間」を減らし、記憶の定着に必要な反復学習が短時間で可能になります。
また、単語カード形式や選択肢式での暗記ができるアプリを使えば、通勤中の5分でも集中して取り組めるのがメリットです。
さらに、学習の進捗管理や目標設定ができるものもあり、モチベーションの維持にもつながります。
反復の頻度や出題の順番が自動最適化されるため、自分で学習計画を細かく立てなくても効果的な暗記が進む点も魅力です。
問題演習アプリ|ミス問題復習やレベル別学習が可能
法規の得点力を高めるためには、条文の理解だけでなく、出題形式に慣れることが欠かせません。
問題演習に特化したアプリでは、過去問ベースの出題ができるだけでなく、ミスした問題を自動で記録し、重点的に復習できる機能が搭載されています。
たとえば「レベル別モード」では、初級・中級・上級と段階的に問題を解くことで、自分の理解度に合ったステップアップが可能です。
また、時間制限付きの演習機能もあるため、試験本番に近い感覚で問題を解く練習にもなります。
間違えた問題だけを抽出する復習モードは、苦手分野を集中的に補強するのに非常に有効です。
さらに、最新の法改正に対応した問題が配信されるアプリもあるため、常に最新の内容で勉強を進められるのも大きなメリットといえるでしょう。
学習履歴の分析や正答率の推移がグラフで確認できるアプリもあるため、自分の成長を実感しながら継続学習がしやすくなります。
法規を短期集中で合格するためのスケジュール例
電験三種「法規」は範囲が広く、暗記も多いため、計画的な学習が合格の鍵を握ります。
ここでは、短期集中で成果を出すための勉強スケジュール例を紹介します。
3ヶ月で250時間確保する勉強計画
「法規」は法律知識だけでなく計算問題も含むため、まとまった学習時間が必要です。
合格ラインを目指すなら、最低でも3ヶ月で250時間を目安に勉強時間を確保することが現実的です。
1日あたりの学習時間で換算すると、平日は2時間、週末は3〜4時間のペースが求められます。
効率よく学ぶには、月ごとのテーマを決めて進めるのが効果的です。
【1ヶ月目】:法規の全体像をつかむインプット期(テキスト読解+法令の暗記)
【2ヶ月目】:過去問・問題集でアウトプット強化
【3ヶ月目】:苦手分野の洗い出しと反復演習+模試で総仕上げ
スケジュール通りに進めるためには、学習管理アプリやカレンダーを活用して、毎日の進捗を「見える化」しておくのがポイントです。
計画倒れを防ぐには、毎週の振り返りと軌道修正も忘れずに行いましょう。
法規単体受験 or 他科目と組み合わせる戦略
電験三種では、科目ごとの合格制度があるため、「法規だけ」先に合格しておくという戦略も可能です。
しかし、それが必ずしも最適とは限りません。法規は「電力」や「機械」との関連性があるため、併願による相乗効果も見込めるからです。
単体受験を選ぶ場合、すべての集中力を法規に向けられるメリットがあります。
記憶系のインプットに集中できる反面、モチベーションの維持が課題になることも。
他方、他科目との併願なら時間配分が難しくなりますが、学習のリズムを崩さず維持しやすいという利点があります。
受験スタイルは、自分の得意不得意や勉強時間の確保状況に応じて最適化すべきです。
たとえば、時間の確保が難しい社会人受験生であれば、法規単体受験→翌年他科目という段階的戦略も合理的でしょう。
疲労対策と試験本番での注意点
3ヶ月の集中学習期間は、精神的にも身体的にも負荷がかかります。
特に平日の夜に勉強時間を捻出している人は、慢性的な疲労が蓄積しやすく、パフォーマンスの低下にもつながります。
勉強の合間には、ストレッチや短時間の仮眠を取り入れてリフレッシュする習慣を作りましょう。
また、試験本番では知識量だけでなく「コンディション」も合否を分ける要素です。
前日は徹夜を避け、6〜7時間の十分な睡眠を取りましょう。
当日は、時計を持参し、1問あたりの制限時間を意識しながら進めることで、時間切れを防げます。
試験中に焦って思考が停止してしまうのを防ぐためにも、事前に模試を受けて「時間配分」と「出題傾向」に慣れておくのが有効です。
過去問だけでなく、模擬試験を通じて本番と同様の環境を経験しておくことが、冷静な対応力につながります。
まとめ
今回の記事では、電験三種の勉強方法について初心者向けに解説しました。
今回お伝えした内容を参考に、ぜひ電験三種の取得を目指して頑張ってください。
実際、電験三種は、取得するだけでも大きな価値があります。
一方で、その価値が十分に評価されるかどうかは、働く環境次第です。
- 今の職場で資格がどう扱われているか
- 将来的にどんな選択肢があるか
- 転職すべきか、副業という道があるか
無理な提案は行わず、電験三種を持つ方向けの選択肢整理を無料で行っています。