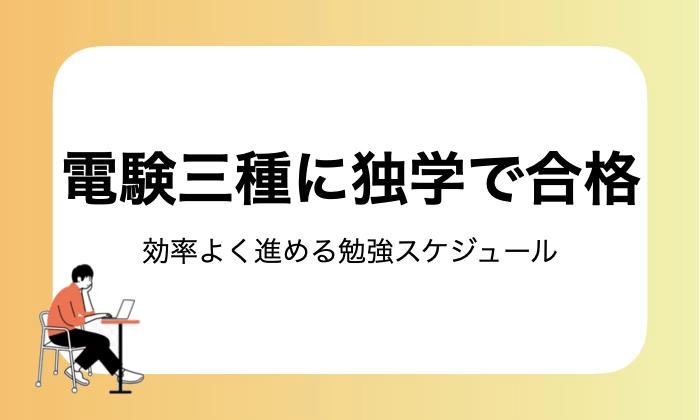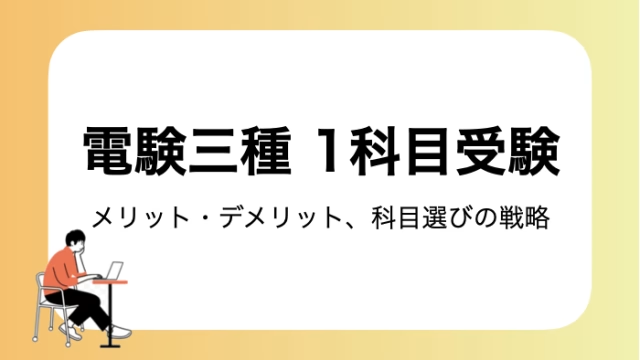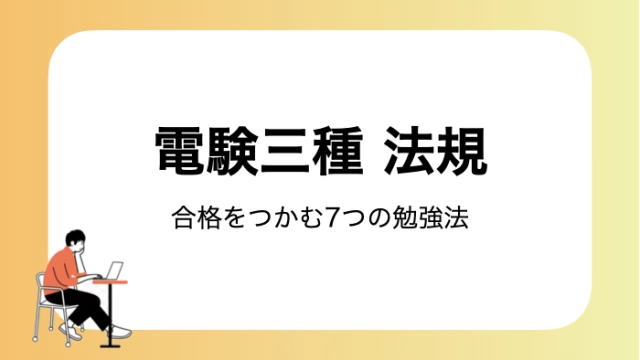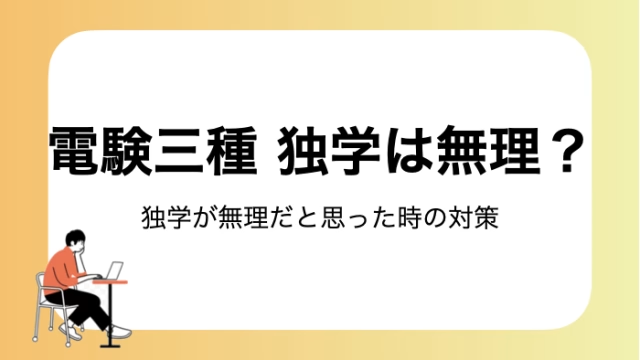「独学で電験三種に挑戦したいけど、独学での進め方がわからず、スケジュールが立てられない」「仕事が忙しくてどうやって取り組めば良いかわからない」と悩んでいませんか?
そこで、今回は電験三種を独学で合格するためのスケジュールの立て方や勉強方法について解説します。
この記事を読めば、自分に合った勉強計画の立て方や、科目ごとの学習順序・勉強時間の目安がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
電験三種は独学でも合格できる?
第三種電気主任技術者、通称「電験三種」は合格率が低く難関資格とされていますが、適切な対策をすれば独学でも合格は可能です。
合格率は例年15〜20%前後で、決して簡単とはいえない水準です。
試験科目は「理論」「電力」「機械」「法規」の4科目で、それぞれが専門的な知識を問う内容になっています。
しかも、各科目の出題範囲が広く、単なる暗記だけでは太刀打ちできません。
理解力や応用力が必要な計算問題も多く含まれており、一定以上の学習時間と計画的な学習戦略が求められます。
また、電験三種には「科目合格制度」があり、1科目でも合格すれば次回以降にその科目の受験を免除されるため、長期的な学習計画も立てやすい試験です。
これにより、一度にすべての科目に合格しなくても、段階的にクリアすることが可能です。
難易度は高いものの、しっかりと準備を進めれば独学でも合格を狙える資格といえるでしょう。
電験三種を独学で合格するための勉強時間の目安
電験三種に独学で合格するためには、計画的な勉強時間の確保が重要です。
ここでは、必要な総勉強時間やライフスタイル別のスケジュール例、科目ごとの時間配分などを具体的に解説します。
合格までに必要な総勉強時間はどのくらい?
電験三種の合格に必要な総勉強時間は、一般的に「400〜600時間」と言われています。
これは、理系出身か文系出身か、または電気に関する実務経験の有無によっても変動します。
理系出身や実務経験者であれば400時間前後でも合格可能ですが、電気に初めて触れる文系出身者であれば600時間以上を想定しておくと安心です。
また、1日あたりの学習時間に応じて、合格までの期間も変わってきます。
たとえば、1日2時間なら半年〜1年、1日1時間なら1年半以上は見積もるべきです。
重要なのは、漫然と時間を使うのではなく、効率よく学習を進めるための「戦略」を持つことです。
そのためにも、次の章で紹介するライフスタイルに応じたスケジュール例を参考にしてください。
ライフスタイル別・勉強時間スケジュール例
学習時間は「自分の生活に無理なく組み込めること」が最重要です。
ここでは、代表的なライフスタイル別に、合格までのスケジュール例を紹介します。
| ライフスタイル | 1日の学習時間 | 合格までの目安期間 |
|---|---|---|
| 社会人(フルタイム勤務) | 1〜1.5時間 | 10〜12ヶ月 |
| 学生・パート勤務 | 2〜3時間 | 6〜8ヶ月 |
| 専業受験生 | 4〜5時間 | 3〜5ヶ月 |
たとえば、フルタイムで働く社会人の場合、平日は1時間・週末に3時間程度学習すれば、1週間で約10時間の勉強時間が確保できます。
これを40週(約10ヶ月)続ければ400時間に達する計算です。
重要なのは、自分のペースを把握し、学習の「ルーティン化」を図ることです。
朝の通勤前や昼休み、夜寝る前など、スキマ時間を活用すると効率的です。
科目ごとの時間配分とポイント
電験三種の試験科目は、「理論」「電力」「機械」「法規」の4科目です。
それぞれ難易度や出題傾向が異なるため、均等に時間を割くよりも、苦手科目や配点の高い科目に重点的に取り組むべきです。
以下に、一般的な時間配分の目安を示します。
| 科目名 | 配分目安(400時間中) | 勉強のポイント |
|---|---|---|
| 理論 | 120時間 | 基礎計算力と公式の理解が鍵。全体の土台となる。 |
| 電力 | 90時間 | 発電・送電などの系統理解が重要。図解で整理すると効果的。 |
| 機械 | 110時間 | 分野が広く複雑。過去問中心で頻出テーマを重点対策。 |
| 法規 | 80時間 | 条文の暗記と計算問題の両立が必要。スキマ学習に最適。 |
特に理論は、他3科目の理解にも影響するため、最初に集中して学習すると他科目の勉強がスムーズになります。
また、法規は一見簡単に思えますが、意外と落としやすいため、軽視せず継続的に復習しましょう。
各科目の難易度や自分の得手不得手を踏まえながら、柔軟に配分を見直していく姿勢が合格への近道です。
独学での勉強スケジュールの立て方
電験三種を独学で合格するには、計画的なスケジュール設計が不可欠です。
ここでは、試験日から逆算して学習計画を立てる方法や、自分に合った学習スタイルの見極め方、途中で挫折しないための工夫について解説します。
試験日から逆算するスケジュール設計法
独学で電験三種を目指す人にとって、スケジュール設計は学習効率を左右する最重要項目です。
最初に行うべきは、試験日を明確に把握し、そこから逆算して各科目にかける時間を割り出すことです。
電験三種は理論・電力・機械・法規の4科目から成り、それぞれに難易度の差があります。
苦手な科目には多めの時間を確保し、得意分野は復習中心に配分するのが基本です。
たとえば、試験日まで180日あるとすれば、初期の30日をインプット期間、中盤の90日を問題演習、残りの60日を過去問と復習に充てるといったステップが理想です。
日々の学習には「今日は理論を3ページ」「明日は電力の問題を5問」など、具体的な目標を設定すると進捗管理もしやすくなります。
短期集中型 vs 長期積み上げ型
スケジュールの立て方には、大きく分けて「短期集中型」と「長期積み上げ型」の2種類があります。
どちらが適しているかは、あなたのライフスタイルや集中力の持続時間によって変わってきます。
短期集中型は、仕事や学校が比較的落ち着いている時期に一気に詰め込む学習スタイルです。
1日5〜6時間の学習を継続できるなら、3ヶ月の集中で合格圏内に届くことも可能です。
ただし、燃え尽き症候群や中だるみに注意が必要です。
一方、長期積み上げ型は、1日1〜2時間を地道に積み重ねていくスタイルです。
半年〜1年かけて少しずつ知識を吸収するため、学習が習慣化しやすく、安定した成績を残しやすいというメリットがあります。
途中で生活スタイルが変わっても柔軟に対応しやすいのも特徴です。
途中で挫折しないための工夫
独学は自由度が高い反面、モチベーションの維持が最大の課題です。途中で挫折してしまう人の多くは、学習の目的や進捗を見失ってしまう傾向にあります。
これを防ぐためには、「見える化」と「報酬設計」が有効です。
まず、進捗を見える化するために、学習スケジュールをExcelやGoogleスプレッドシートで管理しましょう。
1日ごとの目標と達成状況を記録していくことで、達成感が得られ、モチベーションの維持に繋がります。
さらに、学習の区切りごとに自分へのご褒美を設けるのも効果的です。
「一週間続けられたら好きなスイーツを食べる」「3科目終わったら半日オフにする」といった小さな報酬を用意することで、脳が「また頑張ろう」と感じやすくなります。
加えて、SNSや勉強記録アプリで他の受験者とつながるのも一つの方法です。
孤独になりがちな独学を、仲間意識と刺激によって乗り越えることができます。
電験三種の独学勉強法と科目の勉強順
電験三種を独学で突破するには、効果的な勉強順と学習方法の理解が不可欠です。
ここでは、推奨される科目の勉強順と、独学に適した基本的な学習スタイルについて解説します。
おすすめの勉強順番
電験三種の4科目は、単独で勉強するよりも、科目間の関連性を意識して順序立てて進めることで理解が深まります。
おすすめの順番は「理論 → 電力 → 機械 → 法規」です。
最初に理論を学ぶ理由は、他の科目の基礎となる電気の計算や法則が集中しているからです。
理論を押さえることで、電力や機械の内容がスムーズに頭に入ります。
次に電力を選ぶのは、理論の知識を活かして実務的な送電・配電の知識を理解しやすくなるからです。
続いて学ぶ機械は、発電・モーター関連の知識が中心ですが、電力とセットで覚えると効率がよくなります。
最後に法規を学ぶのがベストです。
法規は丸暗記の要素が強いため、他の3科目が仕上がった後に短期集中で一気に取り組むと合格しやすくなります。
電験三種独学の基本勉強方法
独学で電験三種に挑戦する場合、最も重要なのは「学習の習慣化」と「基礎の徹底」です。
特に、いきなり過去問に手を出すのではなく、教科書レベルの内容をしっかり理解することが合格への第一歩です。
基本的な勉強方法は、①教科書でインプット → ②確認問題で理解度チェック → ③過去問で実戦力を養う、という3段階を意識しましょう。
最初のインプットでは、通勤時間や空き時間に動画や音声教材を活用するのも効果的です。
確認問題は章末の例題やネット上の無料問題集を使っても良いでしょう。過去問は、最初は解けなくても構いません。
解説を読み込むことで「試験で問われるポイント」がつかめてきます。
また、1日30分でも毎日継続することが成功の鍵です。
週末にまとめて勉強するスタイルより、毎日触れるほうが記憶が定着しやすく、理解のスピードも格段に上がります。
過去問・インプット・アウトプットのバランス
電験三種の学習では、インプットとアウトプットのバランスが非常に重要です。
どちらかに偏ると、知識の定着や応用力に大きな差が出てきます。
インプットに偏ると、「わかった気になる」だけで終わりがちです。
逆にアウトプットばかりだと、基礎が抜けたままなので応用問題に対応できません。
理想的なバランスとしては、「インプット3:アウトプット7」程度を意識しましょう。
つまり、ある程度知識を入れたら、実際に手を動かして問題を解く時間を多く取ることがポイントです。
また、アウトプットの中でも過去問演習は特に重要です。
電験三種では過去問の類似問題が頻繁に出題されるため、直近10年分を3周以上繰り返すと得点力が大きく伸びます。
なお、1周目は正答率にこだわらず、問題の傾向や解説の読み込みに集中すると効果的です。
最後の仕上げでは時間を計って模試形式で解くことで、本番さながらの実戦力が養えます。
効率よく学ぶための参考書と無料ツール活用法
電験三種を独学で突破するには、時間と労力の使い方がカギを握ります。
特に参考書の選び方や学習補助ツールの活用次第で、学習効率は大きく変わります。
ここでは、独学者でも実践しやすく、かつ成果につながりやすい方法を紹介していきます。
独学者におすすめの参考書シリーズ
電験三種の独学においては、参考書選びが合否を分けると言っても過言ではありません。
なぜなら、電験三種の出題範囲は広く、参考書によって解説の深さや問題の難易度に大きな差があるからです。
初心者にとっておすすめなのは、「みんなが欲しかった!シリーズ」や「これだけシリーズ」です。
前者はイラストや図解が豊富で理解しやすく、後者は要点がコンパクトにまとまっているため、時間のない社会人にも向いています。
さらに、一通り基礎を固めた後は、「完全マスターシリーズ」などの専門的な参考書で応用力を養うのも効果的です。
特に過去問とのリンクが強い参考書は、実践力を鍛えるうえで重宝されます。
購入時には、最新版であることと、解答・解説の分かりやすさを確認しましょう。
中古書籍では解説が古いことがあるため注意が必要です。
YoutubeやSNSで学習効率を上げる方法
電験三種の学習では、動画やSNSを活用することで、独学のハードルを大きく下げられます。
近年は、電験三種に特化したYouTubeチャンネルが充実しており、視覚と音声で理解を深めることができます。
たとえば、「電験三種ちゃんねる」や「オーム社公式チャンネル」では、専門用語をかみ砕いて解説する動画が豊富です。
これらを通勤中や就寝前などのスキマ時間に活用すれば、学習時間の確保にもつながります。
また、X(旧Twitter)やInstagramでも、電験三種に関する学習アカウントが増えており、他の受験者の学習ペースや使っている教材の情報を得られます。
仲間の存在を感じられることは、モチベーション維持にも効果的です。
ただし、SNSの情報には誤りや古い情報もあるため、あくまでも補助的に活用する姿勢が重要です。
信頼できる発信者をフォローし、情報の取捨選択を意識しましょう。
無料の過去問サイトやアプリの活用術
独学者にとって、過去問演習は必須のステップです。
近年では、無料で使える過去問サイトやアプリが多数登場しており、コストを抑えつつ効果的な学習が可能です。
おすすめのサイトには「電験三種 過去問.com」や「工学基礎.com」などがあり、年度別・科目別に問題を絞って解くことができます。
また、解答だけでなく、解説まで丁寧に記載されているため、理解を深めながら学習を進められます。
スマホアプリでは「電験三種 一問一答」や「ポケット電験三種」などが人気です。
特にアプリは通知機能や復習タイマーが付いているものも多く、継続学習の習慣化に向いています。
下記は主なツールの特徴比較表です。
| ツール名 | 特徴 | 対象科目 |
|---|---|---|
| 電験三種 過去問.com | 過去20年分を無料で掲載、解説あり | 理論・電力・機械・法規 |
| ポケット電験三種(アプリ) | スマホで手軽に一問一答形式 | 理論中心 |
| 工学基礎.com | 図解付きで理解しやすい | 機械・電力に強み |
無料ツールを使う際は、定期的に進捗を記録し、自分の苦手分野を可視化することがポイントです。
闇雲に解くのではなく、「間違えた問題の復習」に重点を置きましょう。
独学で合格するために大切な3つのポイント
電験三種は独学でも合格可能な資格ですが、途中で挫折する人も少なくありません。
そこで大切になるのが、学習の継続・考え方の転換・モチベーション維持の3つです。
ここでは、独学で合格するために大切な3つのポイントをご紹介します。
勉強習慣をつける
独学での合格を目指すなら、まずは毎日机に向かう「習慣化」が最優先です。
どれだけ質の高い教材を持っていても、継続しなければ意味がありません。
勉強時間は1日30分でも構いません。
まずは「毎日やること」に体を慣らしていきましょう。
おすすめの方法は、勉強する時間帯を固定することです。
朝起きてすぐ、昼休み、帰宅後の30分など、生活の一部として勉強を組み込むと、習慣化しやすくなります。
また、勉強の記録をつけるのも効果的です。日々の積み重ねが可視化されることで、自信にもつながります。
さらに、毎回の勉強で「今日は何をやるか」を明確にしておくと、取り組むハードルがぐっと下がります。
迷いがなくなり、自然と手が動くようになります。
習慣づくりに悩んでいる方は、まずはこの点から見直してみてください。
60点合格を意識してハードルを下げる
電験三種は各科目60点以上で合格となります。
つまり、満点を目指す必要はありません。
それなのに「すべて理解しないと不安」「全問題解けないとダメ」という思い込みで、挫折してしまう方も多いのが実情です。
ここで大切なのは、合格ラインをしっかり認識し、完璧主義を手放すことです。
60点=6割の得点でいいと割り切ることで、心の負担が軽くなります。
難しい問題を飛ばす勇気を持つことで、効率よく得点源を見つけることができるのです。
また、過去問を分析すると、よく出るパターンや分野が見えてきます。
そこに的を絞って学習することで、最短ルートで合格点を狙えます。
「全部やろう」ではなく「合格するために必要な部分をやろう」と考えることで、独学でも十分に戦える勉強法となります。
モチベーション維持の方法
独学の最大の敵は「孤独」と「中だるみ」です。
特に長期間の勉強が必要な電験三種では、やる気が続かないという壁に誰もが直面します。
このモチベーション維持こそが、独学合格のカギを握ります。
まず取り入れたいのは、小さな目標の設定です。
「1週間で公式を覚える」「1日1問だけ解く」など、実行可能な目標を立てて、達成感を得ることが重要です。
達成したら、自分にちょっとしたご褒美を与えるのも効果的です。
また、SNSや掲示板などで、同じく電験三種を目指している仲間とつながることもおすすめです。
リアルな交流が難しくても、ネット上での励ましや情報交換が大きな支えになります。
「自分だけじゃない」と感じるだけで、心が軽くなるものです。
さらに、モチベーションが下がったときには「なぜこの資格を取りたいのか」を改めて書き出してみましょう。
目的が明確になると、もう一度やる気を取り戻すきっかけになります。
途中で止まってしまったときこそ、この方法を試してみてください。
まとめ
今回の記事では、独学で電験三種に合格するためのスケジュールについて解説しました。
限られた時間の中でも、無理なく続けられる計画を立てることが合格の鍵です。
ぜひ電験三種の取得を目指して頑張ってください。
実際、電験三種は、取得するだけでも大きな価値があります。
一方で、その価値が十分に評価されるかどうかは、働く環境次第です。
- 今の職場で資格がどう扱われているか
- 将来的にどんな選択肢があるか
- 転職すべきか、副業という道があるか
無理な提案は行わず、電験三種を持つ方向けの選択肢整理を無料で行っています。