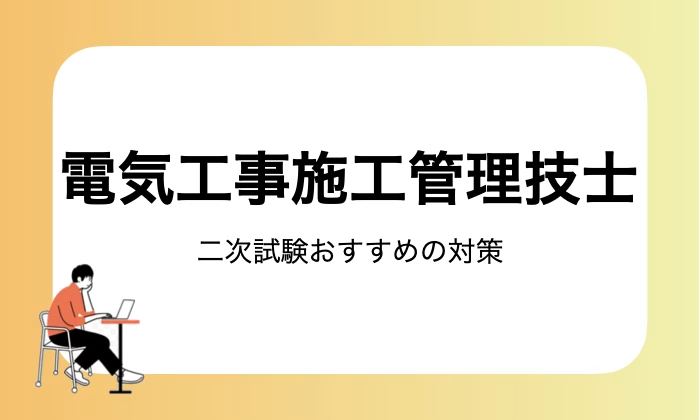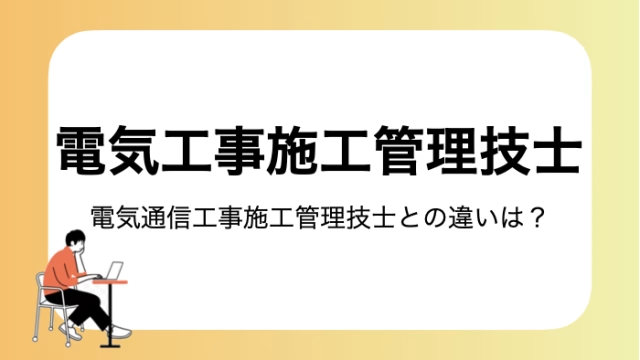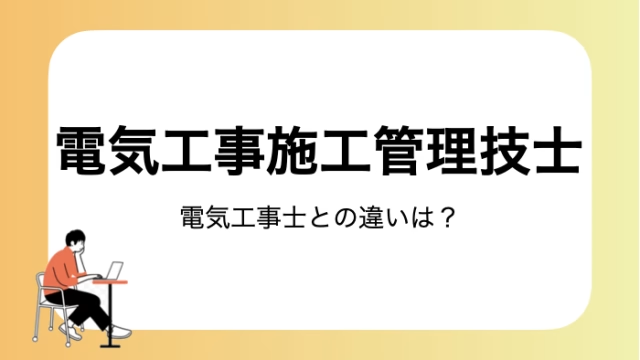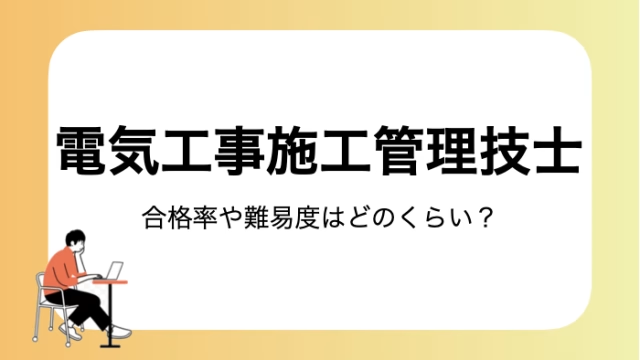「電気工事施工管理技士の二次試験、何から対策すればいいかわからない」ということはありませんか?
記述式が中心で、出題範囲も広く、一次試験よりも難易度が上がることで悩む方は少なくありません。
そこで、今回は電気工事施工管理技士 二次試験の出題傾向や配点の目安、効果的な対策法について解説します。
この記事を読めば、試験の全体像や重要ポイント、過去問の活用法や通信講座の使い方がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
電気工事施工管理技士の二次試験とは
電気工事施工管理技士の資格を取得するには、一次試験と二次試験の両方に合格する必要があります。
ここでは、一次試験との違いや、二次試験の流れやスケジュールについて詳しく解説します。
一次試験との違い
電気工事施工管理技士の一次試験と二次試験は、出題形式や評価の観点が大きく異なります。
一次試験は主に選択式の知識問題を中心に構成されており、暗記や知識の正確さが求められる内容です。
一方、二次試験は、記述式を中心とした実務経験に基づく問題が出題される点が最大の違いです。
二次試験では、工事現場での具体的な経験や判断力、工程管理・安全管理に対する理解が問われます。
例えば、自身の実務経験をもとに、工事上の課題やその対策について論述する問題が出題されます。
単なる知識だけでなく、現場での経験をいかに言語化し、理論的に説明できるかが重要です。
また、設計図書から必要な情報を読み取り、施工図に反映できる能力も問われるため、より実務に近いスキルが求められます。
加えて、二次試験には計算問題(電力計算など)や法律の穴埋め問題も含まれており、広範囲な内容への対応が必要です。
つまり、電気工事施工管理技士の二次試験は、単に暗記では突破できず、実務能力を証明する試験であるといえます。
記述に苦手意識のある方は、早めの対策と記述練習を意識して取り組むことが求められます。
試験日程と流れ
電気工事施工管理技士の試験は、一次と二次に分かれていますが、それぞれが独立しているわけではありません。
一次試験の合格を経て、二次試験に進むという流れになっており、そのスケジュールには注意が必要です。
まず、一次試験の実施後、例年7月から8月にかけて合格発表があります。
その後、合格者は約2週間以内に二次試験の受験料を支払う必要があります。
この支払いを行わないと二次試験の受験資格を失うため、特に注意が必要です。
受験料の納付が完了すると、受験票が発行され、いよいよ二次試験の受験となります。
試験の実施時期は、一次試験の合格発表から約3か月後、例年10月から11月ごろに行われます。
そして、さらに3か月ほど経過した1月から2月頃に二次試験の合格発表が行われます。
その後、合格者は「合格証明書」の交付申請を行うことで、正式に「電気工事施工管理技士」としての資格を取得することができます。
なお、令和6年度からは、受験資格として必要な実務経験年数が変更されており、1級では一次試験合格後5年、2級では一次試験合格後3年の実務経験が必要となります。
このように、一次試験から合格証明書の取得までには数か月から半年以上の時間を要します。
スケジュールを逆算しながら計画的に準備を進めることが、合格への第一歩となるでしょう。
電気工事施工管理技士の二次試験の出題傾向
電気工事施工管理技士の二次試験では、実務経験を基にした記述問題や法規、計算問題など、多様な形式で6つの大問が出題されます。
全体の構成や配点の考え方を把握することで、効率的な学習計画が立てられます。
出題形式の概要
二次試験の形式は、選択式ではなく記述式を中心に構成されている点が特徴です。
試験時間は3時間と長めで、大問6つが出題されます。
各問題には「記述問題」「穴埋め問題」「語句説明問題」などの形式があり、幅広い知識と論述力が求められます。
例えば、大問1では受験者自身の工事経験をもとに、現場で直面した課題とその対応策を記述する問題が出題されます。
これは、実務経験を問うと同時に、その経験をいかに論理的に文章で表現できるかも評価対象になるため、文章構成力や表現力も重要です。
また、大問5ではRLC直列回路の有効電力のような計算問題も出題されるため、基礎的な電気理論の理解も欠かせません。
加えて、大問6の法規問題は五肢択一の穴埋め形式で出題され、建設業法や電気事業法の知識が問われます。
このように、電気工事施工管理技士の二次試験は多角的な出題内容となっており、単に暗記に頼るのではなく、応用力や実務能力を試される試験となっています。
事前に各形式の問題に慣れておくことが、合格への近道といえるでしょう。
各大問の内容と傾向
電気工事施工管理技士の二次試験は、大問1〜大問6までの6題構成で、各問題が異なるテーマと形式で出題されます。
各大問の内容とその傾向を正しく理解することで、重点的に学習すべきポイントが明確になります。
まず、大問1は記述問題で、受験者の実務経験に基づく工程管理や安全管理について問われます。
1級では「工程管理・安全管理」が、2級では「工程管理」が中心です。
単なる事実の記述ではなく、管理上の問題点やその理由、対策を含めた論理的な説明が求められます。
大問2では品質管理について問われます。
施工現場での品質確保のための留意点や、具体的な対策を記述する必要があります。
建築物の安全性や機能性を左右する重要なテーマのため、実務経験と照らし合わせて考える力が必要です。
大問3は労働災害防止策についてです。
特定の作業内容(例:高所作業、配線作業など)を2つ選び、それぞれに対して適切な災害防止策を記述します。
労働安全衛生に関する理解と、現場での対策実践力が問われます。
大問4では、電気設備に関する用語の技術的説明が求められます。
具体的には、「用途」「定義」「特徴」「施工上の留意点」など、多面的に理解しておく必要があります。
施工経験だけでなく、理論的知識も必要とされます。
大問5は、配電線路の線間電圧やRLC直列回路の計算などが問われる計算問題です。
数式の理解や、単位の正確な取り扱いが必要です。電気理論の基礎を復習しておくと安心です。
最後に、大問6は法規に関する問題です。
建設業法や電気事業法に関する五肢択一形式の穴埋め問題が出題されます。
条文の丸暗記ではなく、法の趣旨を理解しておくことが重要です。
このように、各大問にはそれぞれ特徴があるため、自分の得意・不得意を把握し、バランスよく対策を立てることが求められます。
配点の考え方と注意点
電気工事施工管理技士 二次検定においては、配点の詳細は公表されていません。
これは、記述式問題が中心であるため、年度や問題の内容によって評価基準が柔軟に変化するためと考えられます。
そのため、どの問題にどれだけの配点があるかを事前に知ることはできません。
ただし、「受験の手引き」などによると、合格基準は60%以上の得点とされています。
したがって、合格を目指すには最低でも6割以上の得点を取る必要がありますが、全体のバランスを重視する出題傾向を踏まえると、特定の問題だけに集中するのは危険です。
例えば、大問1のような記述問題では、論理性・具体性・経験の正確性が重視されます。
仮にそこに自信があったとしても、大問5の計算問題や大問6の法規問題で大きく失点すると、合格ラインを割ってしまう可能性があります。
そのため、各大問すべてに取り組み、まんべんなく得点を重ねることが安全策といえます。
特に記述問題では、簡潔かつ論理的に書く練習を重ねることが、高得点につながるポイントです。
配点が公開されていないことに不安を感じる受験者も多いですが、それを逆手に取って、全体の完成度を上げる学習を心がければ、結果として合格に近づくことができます。
事前の過去問演習と模範解答の分析を繰り返し行い、バランス重視の対策を徹底しましょう。
電気工事施工管理技士の二次試験のおすすめ対策法
電気工事施工管理技士の二次試験は、記述問題や実務に基づく出題が中心であるため、単なる知識の暗記では対応できません。
ここでは、合格に近づくための効果的な学習方法を3つに分けて紹介します。
過去問を使った学習
二次試験の対策において最も基本かつ重要なのが、過去問の活用です。
二次試験の過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や問題形式に慣れることができます。
特に二次試験では記述式問題が中心となるため、単に正誤を確認するだけではなく、模範解答と比較して「どのように書けば得点につながるか」を学ぶ姿勢が必要です。
出題されやすいテーマにはパターンがあるため、過去問を通してそれを把握することで、準備すべき内容が明確になります。
また、過去問を繰り返し解くことにより、記述の構成力や時間配分の感覚も身につきます。
実際の試験時間は3時間ですが、長文記述が複数出題されるため、書き慣れていないと時間が不足する可能性もあります。
したがって、過去問演習は本番を想定したタイムトライアル形式で実施すると効果的です。
さらに、過去問には「品質管理」「労災対策」「技術用語」など毎年のように登場する定番テーマがあります。
これらの問題に的を絞り、繰り返し練習することで得点源として確保することができるでしょう。
記述対策は実務経験をもとに練習
二次試験の最大の特徴は、実務経験に基づく記述問題が出題される点です。
特に大問1では、1級では「工程管理・安全管理」、2級では「工程管理」について、自身の工事経験をもとに記述する必要があります。
この記述には、単に経験を書き連ねるのではなく、「どのような課題があったか」「なぜそのような課題が発生したのか」「どのような対策を講じたのか」を論理的に構成する力が求められます。
そのためには、事前に自分の実務経験を棚卸しし、工事の目的・工程・問題点・対策を整理しておくことが効果的です。
具体的には、これまで携わった工事をいくつかピックアップし、それぞれの現場での管理項目(工程、安全、品質など)をノートにまとめておくと、記述問題への対応がスムーズになります。
また、実際に文章に起こす練習を繰り返すことで、制限時間内に要点を簡潔にまとめる力が養われます。
さらに、よくある記述テーマに対して、自分なりの「テンプレート」を作成しておくのも有効です。
導入→問題点→理由→対策→結果といった構成で書く練習を行えば、試験本番でも安定した答案が書けるようになります。
通信講座の活用
独学での対策に不安を感じる方には、通信講座の活用を強くおすすめします。
特に、添削サービスが付いている講座であれば、自分の記述に対して専門家からのフィードバックを受けられるため、実践力を効率的に高めることができます。
近年の通信講座では紙ベースの教材だけでなく、動画講義やEラーニングを組み合わせた学習スタイルが主流となっており、理解が難しい項目も視覚的に学べる点が大きなメリットです。
記述対策に特化した講義や、模擬試験を通じた実力チェックなども取り入れられているため、試験本番に向けて体系的な学習が可能です。
また、インターネットを通じて学習サポートを受けられる講座も増えており、講師への質問やモチベーション維持のための面談サービスなど、学習環境を整えた上で進められるのも大きな強みです。
特に仕事と両立しながら受験を目指す方にとっては、自分のペースで進められる通信講座は非常に相性が良いといえるでしょう。
講座選びの際は、「添削あり」「記述対策に強い」「サポート体制が整っている」などのポイントを重視し、自分の学習スタイルに合ったサービスを選ぶことが重要です。
適切な通信講座を活用することで、合格への距離はぐっと近づきます。
令和6年度からの制度変更と注意点
令和6年度から、電気工事施工管理技士の試験制度に大きな変更が加えられました。
特に「受験資格の実務経験年数」と「二次試験の出題内容」に関しては受験者全員が押さえておくべき重要ポイントです。
受験資格の実務経験年数の変更
令和6年度より、1級・2級いずれの電気工事施工管理技士試験においても、二次試験の受験資格が「一次試験合格後の実務経験年数」に変更されました。
これまでは一次試験・二次試験を同時に受験できる制度でしたが、今後は一次試験合格後に所定の実務経験年数を積まなければ、二次試験の受験資格を得ることができません。
具体的には、1級では5年、2級では3年の実務経験が必要です。
ただし、「特定実務経験」とされる内容(管理技術者補佐業務など)を有する場合は、年数が短縮される場合があります。
この変更により、特に実務経験が浅い方や、経験年数のカウントに不安がある方は注意が必要です。
例えば、大学卒で1級を目指していた場合、これまでなら一次・二次の同時受験が可能でしたが、今後は一次合格後にさらに5年の実務経験を積む必要があります。
したがって、今後受験を検討している方は、自身の職歴や業務内容を正確に把握し、どのタイミングで二次試験の受験資格が得られるのかを事前に確認しておくことが不可欠です。
試験内容の変更点
令和6年度からのもう一つの大きな変更点は、二次試験の出題内容です。
これまで二次試験の大問1では「工事概要」など、やや抽象的な記述が中心でしたが、今年度からは明確に「実務記述」へと内容が改められました。
この変更により、出題の主旨は「どれだけ実務を理解しているか」から「どれだけ実務経験を積み、言語化できるか」へと移行しています。
つまり、単なる知識の暗記では対応できず、受験者本人の現場経験や課題対応能力、マネジメントスキルを踏まえた記述力が問われるようになります。
たとえば、「工程管理におけるトラブルとその対処法を実務に基づいて記述せよ」といった問題が出題される可能性が高く、抽象的な回答では得点に結びつきません。
求められているのは、「どんな現場で」「どのようなトラブルが起き」「それに対してどんな具体策を講じたか」といった、リアルな経験に基づく論理的な文章です。
この変更により、受験者にとっては事前準備の方向性が大きく変わります。
過去問を参考にするだけでは不十分で、自分自身の経験をもとに複数のテーマに対応できるよう、あらかじめ記述パターンを作成・練習することが求められます。
現場経験が浅い場合でも、上司や先輩の指導の下で実務を積極的に振り返ることが重要です。
このように令和6年度からの試験は、より「実践力」を重視する内容へと明確にシフトしているため、対策の質が合否を大きく左右することになります。
電気工事施工管理技士の二次試験に合格するための勉強スケジュール例
電気工事施工管理技士の二次試験に合格するためには、限られた時間の中で効率よく対策を行うことが不可欠です。
ここでは、3ヶ月前から計画的に進めるためのスケジュール例と、仕事と両立しながら学習時間を確保する方法について解説します。
3ヶ月前からの対策プラン
試験の約3ヶ月前から始める対策は、効率性と継続性が鍵です。特に働きながら勉強する社会人の場合、時間的制約を考慮した現実的なプランを立てることが合格への第一歩となります。
以下に、月別の学習内容とその目的、実行のポイントをまとめます。
| 時期 | 学習内容 | 重点ポイント |
|---|---|---|
| 試験3ヶ月前 |
|
|
| 試験2ヶ月前 |
|
|
| 試験1ヶ月前 |
|
|
このように、月ごとに目的を分けることで無理なく学習が継続できます。
また、記述力を鍛えるには「書いて、見直して、改善する」の繰り返しが欠かせません。
書いた内容を第三者に見てもらうことで、自分では気づけない表現のあいまいさや論理の飛躍を修正できます。
さらに、仕事と勉強を両立させるためには、時間の「見える化」が有効です。
具体的には、1日のスケジュールを15分単位で区切って記録し、どこに学習時間を確保できるかを明確にします。
たとえば、通勤中に暗記項目を確認し、昼休みに要点整理、夜に記述練習というように、細切れ時間を活用する工夫が重要です。
また、休日には2時間以上のまとまった学習時間を設けて、総復習や模擬試験に取り組むのが理想的です。
早朝学習も集中力が高まるためおすすめです。
重要なのは「勉強する習慣を毎日続けること」であり、毎日30分でも継続できれば、3ヶ月後には大きな力となります。
このように試験までの期間を逆算し、仕事とのバランスを取りながら段階的に対策を進めることが合格への近道となります。
まとめ
今回の記事では、電気工事施工管理技士の二次試験について解説しました。
今回お伝えした内容を参考に、ぜひ電気工事施工管理技士の取得を目指して頑張ってください。
電気工事施工管理技士は、現場を支える重要な資格です。
その一方で、
- 責任が重い割に評価が低い
- 長時間労働が常態化している
- 将来の働き方が見えない
と感じている方も少なくありません。
資格を活かしながら無理なく働く選択肢について、転職・副業の両面から無料で相談を受け付けています。