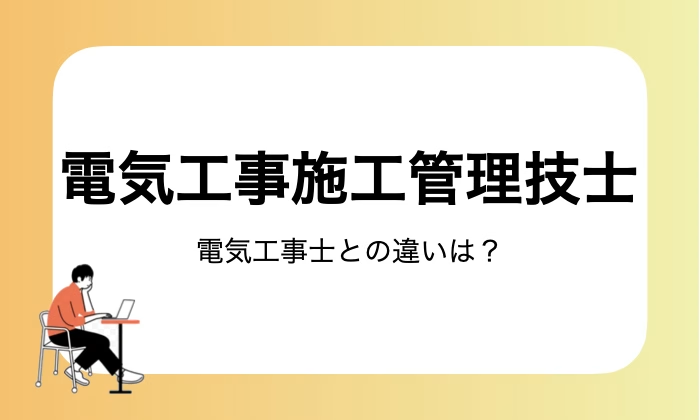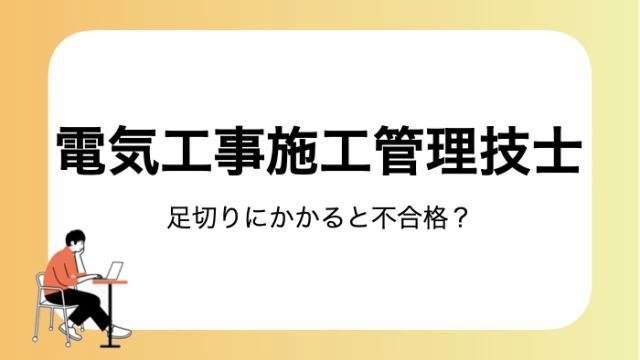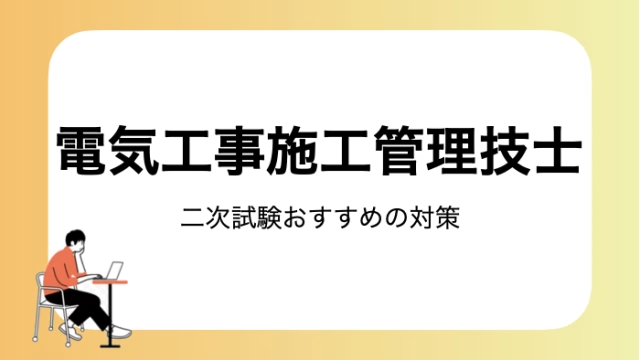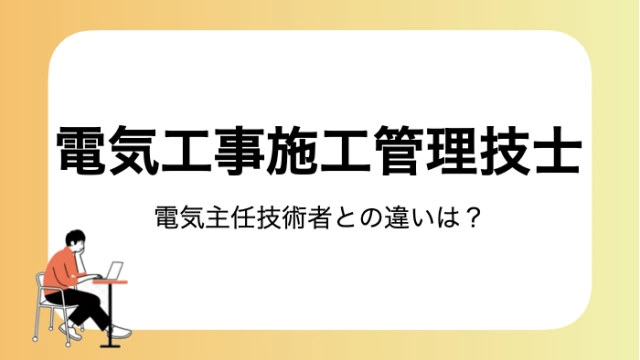「電気工事士と電気工事施工管理技士、どっちを取れば良いかわからない」と悩んでいませんか?
この2つの資格は似ているようで、仕事内容や年収、受験資格に大きな違いがあります。
だからこそ、どちらを目指すべきか悩んでしまう方が多いのです。
そこで、今回は電気工事士と電気工事施工管理技士の違いについて解説します。
この記事を読めば仕事内容・難易度・年収・受験資格の違いと、それぞれの向いている人の特徴がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
電気工事施工管理技士とは?工事を管理する責任者
電気工事施工管理技士とは、電気工事の現場において工事の進行を管理し、品質・原価・安全など多岐にわたる要素を統括する専門資格です。
ここでは、その資格の種類や仕事内容、対応する現場の規模について解説します。
資格の種類(1級・2級)
電気工事施工管理技士の資格は、「1級」と「2級」に分かれており、それぞれに担える業務範囲と責任の重さが異なります。
2級は比較的小規模な工事現場で主任技術者として活動できるのに対し、1級は大規模工事の監理技術者としても活躍できる国家資格です。
1級電気工事施工管理技士を取得すると、建設業法上、4,500万円以上の下請工事において必要な「監理技術者」として配置される資格要件を満たすことができます。
これにより、ゼネコンや大手電気工事会社では1級保有者が重宝され、昇進や年収アップにもつながるケースが多く見られます。
また、1級と2級では受験資格にも違いがあり、1級は一定年数以上の実務経験を必要とします。
令和6年度からは、一次検定については年齢制限のみで受験可能となりましたが、第二次検定には引き続き実務経験が必要です。
以下は、1級と2級の比較表です。
| 資格区分 | 対応現場 | 資格取得後の業務 |
|---|---|---|
| 2級 | 小~中規模の現場 | 主任技術者として配置可能 |
| 1級 | 大規模な現場 | 主任技術者および監理技術者として配置可能 |
主な仕事内容(工程・品質・原価・安全管理など)
電気工事施工管理技士の主な役割は、工事をスムーズかつ安全に進めるための「4大管理業務」です。
これには「工程管理」「品質管理」「原価管理」「安全管理」が含まれ、それぞれが密接に関係し合いながら、現場の最終的な成果物の品質と安全性に直結します。
工程管理では、スケジュール通りに工事を進めるための調整や作業の指示、業者との打ち合わせなどが求められます。
特に工期に遅れが出ないよう、日々の進捗を細かく把握し、対応策を講じる能力が重要です。
品質管理では、設計図や仕様書通りに工事が行われているかを確認し、問題があれば修正を指示します。
原価管理では、材料費や人件費などが予算内に収まるように調整し、コストオーバーを防ぎます。
安全管理も極めて重要な業務で、作業員が事故や災害に遭わないよう、安全教育や現場巡視、KY(危険予知)活動などを行います。
近年は、安全に関する法規制も強化されており、書類作成や監査対応も業務の一環です。
このように電気工事施工管理技士は、現場全体の“指揮官”として、幅広いマネジメントスキルが求められるポジションです。
対象となる現場規模
電気工事施工管理技士が対応する現場の規模は、資格の等級によって異なります。
2級の資格を保有している場合は、小規模から中規模の建設現場において、主任技術者としての配置が可能です。
これは、戸建住宅や中小規模の工場・店舗などが対象となります。
一方で、1級の資格を持つ技術者は、大型の商業施設や公共インフラ、大規模な工場・プラントなどの現場で活躍することができます。
さらに、1級取得者は監理技術者としても配置が可能であり、国や自治体が発注する高額な公共工事や、大手ゼネコンが手がける複雑な建設プロジェクトでは必須の存在です。
以下に、資格ごとの対応現場規模をまとめた表を示します。
| 資格等級 | 対応現場の規模 | 具体的な例 |
|---|---|---|
| 2級 | 小規模~中規模 | 住宅、店舗、小規模工場など |
| 1級 | 大規模 | 大型ビル、商業施設、インフラ関連工事など |
このように、現場規模によって資格の必要性が異なるため、キャリアプランに応じた等級の取得が重要です。
特に将来的に大規模案件の監督や管理職を目指す場合は、早期に1級取得を視野に入れて行動することが望ましいでしょう。
電気工事士とは?現場で活躍する電気のプロ
電気工事士は、住宅やビル、工場などの電気設備工事を直接担当する「現場のプロフェッショナル」です。
ここでは、電気工事士の資格の種類や仕事内容、施工できる工事の範囲について詳しく解説します。
資格の種類(第一種・第二種)
電気工事士の資格は「第一種電気工事士」と「第二種電気工事士」に分かれており、扱える電気設備の規模や範囲に違いがあります。
第二種電気工事士は、一般住宅や小規模な店舗など、600V以下の電圧で受電する設備の工事に従事できる国家資格です。
比較的取得しやすく、実務未経験でも受験が可能なため、入門資格として人気があります。
一方、第一種電気工事士は、第二種の工事範囲に加えて、工場やビルなどの高圧受電設備(最大500kW未満)にも対応できます。
受験資格に制限はありませんが、免状の交付には実務経験が必要なため、キャリアアップの位置づけとして取得されることが多いです。
以下は、第一種と第二種の違いをまとめた表です。
| 資格区分 | 対応電圧 | 対象設備 |
|---|---|---|
| 第二種電気工事士 | 600V以下 | 一般住宅・小規模店舗 |
| 第一種電気工事士 | 600V超(最大500kW未満) | 工場・ビル・高圧受電設備 |
主な仕事内容(配線・設置工事など)
電気工事士の主な業務は、建物内外の配線工事や電気設備の設置・交換・保守といった作業です。
住宅であれば照明器具やコンセントの設置、分電盤の取り付けなどを行います。
商業施設やビルでは、電動機の配線や防災設備、制御盤の設置など、より専門性の高い作業を求められるケースもあります。
また、現場によっては、配線のルート設計や施工図の確認、安全対策の実施なども求められ、単なる作業者ではなく「施工の質」を担う技術者としての責任が伴います。
さらに、近年では省エネ機器やスマート家電などの普及により、IoT設備への対応力も求められるようになっています。
業務中は電気を扱うため感電や火災のリスクがあり、常に法令や技術基準に従った安全な作業が必要です。
そのため、国家資格としての知識・技能の習得が必須であり、定期的な技術更新や講習受講も重要です。
工事可能な範囲
電気工事士の工事可能な範囲は、資格の種類によって法的に定められています。
第二種電気工事士は、600V以下の電圧で受電する一般住宅や小規模施設の屋内配線・照明・コンセントなどの設置・変更が可能です。
これにより、戸建て住宅のリフォームや小規模店舗の内装電気工事などで活躍できます。
第一種電気工事士は、それに加えて高圧(600V超)で受電する設備や最大500kW未満の工場や大型施設の工事も担当できます。
つまり、第二種では対応できない業務も担えるため、電気工事の受注範囲が格段に広がります。
以下に、資格ごとの工事範囲の違いを表にまとめます。
| 資格 | 対応電圧 | 工事可能な施設例 |
|---|---|---|
| 第二種電気工事士 | 600V以下 | 戸建住宅、集合住宅、小規模店舗 |
| 第一種電気工事士 | 600V超~最大500kW未満 | 中規模ビル、工場、高圧設備 |
このように、工事可能な範囲は電気工事士の資格等級によって大きく異なるため、自分の目指す仕事や働きたい現場に合わせた資格選びが重要です。
また、現場によっては電気工事施工管理技士との兼任が求められるケースもあり、双方の役割を理解しておくことがキャリア構築において大きな武器となります。
電気工事施工管理技士と電気工事士の違い
電気業界でキャリアを考える上で、多くの人が迷うのが「電気工事士」と「電気工事施工管理技士」のどちらを目指すかという点です。
ここでは両者の違いを概説します。
- 仕事内容の違い
- 資格取得の難易度・合格率の違い
- 受験資格・年齢制限・実務経験の違い
- 資格でできることの違い
- 年収・キャリアアップの違い
①仕事内容の違い|職人と管理者の明確な線引き
電気工事士は、実際に電線をつなぐ、配線を施す、機器を取り付けるなど、電気設備工事を「手を動かして行う職人」です。
一方、電気工事施工管理技士は、工程や原価、安全、品質などを「現場全体を監督・管理する立場」で対応します。
つまり、電気工事士が「工事を実行する人」であるのに対し、施工管理技士は「工事を計画・監督する人」となります。
両者は現場において密接に連携しますが、果たす役割は明確に分かれており、どちらが欠けても工事は成り立ちません。
特に近年は、安全管理や品質管理の重要性が増しており、施工管理技士の果たす役割はますます広がっています。
現場の経験からキャリアアップを目指す場合、工事士から施工管理技士へステップアップするケースも多く見られます。
②資格取得の難易度・合格率の違い
電気工事士と電気工事施工管理技士では、資格取得の難易度にも大きな差があります。
第二種電気工事士は受験資格がなく、実務経験がなくても誰でも受験可能なため、合格率は60%前後と比較的高めです。
第一種電気工事士は実務経験が必要で、合格率は30%台〜40%程度と難易度が上がります。
一方で、電気工事施工管理技士は、学歴や実務経験による受験資格の制限があり、さらに筆記試験・実地試験(1級のみ)を突破する必要があります。
2級は合格率40〜50%程度、1級は筆記試験が30〜40%、実地試験が50%前後とされており、全体としての難易度は高い傾向です。
| 資格名 | 主な試験内容 | 合格率の目安 |
|---|---|---|
| 第二種電気工事士 | 筆記+技能 | 約60% |
| 第一種電気工事士 | 筆記+技能 | 約30〜40% |
| 2級電気工事施工管理技士 | 学科+実地 | 約40〜50% |
| 1級電気工事施工管理技士 | 学科+実地 | 約30%(学科) 約50%(実地) |
③受験資格・年齢制限・実務経験の違い
電気工事士は、年齢や学歴に関係なく誰でも受験可能な資格であり、特に第二種は未経験者や異業種からの転職にも適しています。
一方、電気工事施工管理技士には、実務経験や学歴によって細かく受験資格が設定されています。
たとえば、1級電気工事施工管理技士では、大学(指定学科)卒業者で3年以上、指定学科以外で5年以上の実務経験が必要です。
学歴がない場合は、10年以上の実務経験が必要になります。
年齢制限そのものはありませんが、施工管理技士を目指すには一定のキャリアを積んでからでないと受験ができないため、スタートできる時期には差が出ます。
この点で言えば、電気工事士は「早く始められる資格」、施工管理技士は「キャリアを積んでから挑戦する資格」と位置づけることができます。
④資格でできることの違い
電気工事士の資格は、電気工事そのものを実際に行うために必要な資格です。
資格を持たずに電気工事を行うことは法律で禁止されており、電気工事士免状の交付が必須となります。
一方、電気工事施工管理技士は、電気工事を「施工計画」「工程管理」「品質管理」「安全管理」といった面で指導・監督するための資格であり、現場代理人や主任技術者としての配置要件を満たします。
つまり、施工管理技士がいなければ、大規模現場では工事そのものが許可されないこともあります。
このように、両者の資格は「現場作業」と「管理職務」という異なる役割に特化しており、実務上は相互補完的に機能しています。
⑤年収・キャリアアップの違い
年収面では、電気工事施工管理技士のほうが高い傾向にあります。
電気工事士の平均年収はおよそ400万〜500万円前後ですが、施工管理技士になると500万〜700万円、1級取得者や大手企業勤務者では800万円超の事例もあります。
キャリアの面でも、電気工事士は「技術を磨く職人型」、施工管理技士は「マネジメント型」のルートが用意されており、将来的に独立や役職登用を狙いたい場合は施工管理技士が有利です。
ただし、電気工事士として経験を積み、第一種取得後に施工管理技士資格を取得することで、両資格を活かしたハイブリッド型のキャリア形成も可能です。
実際、現場での実務経験を重ねてから施工管理職へと転向するケースは非常に多く、安定したキャリアパスと収入向上が期待できます。
このように、自身の将来像に応じてどちらを選ぶか、あるいは両方取得するかを検討するのが理想的です。
資格取得のメリットとキャリア戦略
電気工事士と電気工事施工管理技士の両資格を活かすことで、現場作業から管理職まで幅広い活躍が可能になります。
ここでは、ダブルライセンス取得によるメリットや、就職・転職市場での評価、そして年収アップにつながるキャリア戦略について解説します。
ダブルライセンスで広がる活躍の場
電気工事士と電気工事施工管理技士の両方の資格を持つことで、現場実務と施工管理の両方を担当できるようになり、活躍の幅が大きく広がります。
たとえば、現場での作業中にトラブルが起きた場合も、電気工事士としての技術と施工管理技士としてのマネジメント能力を併せ持つことで、即座に判断・対応が可能です。
さらに、現場の職長や主任技術者としての役割も担えるため、現場における存在感が高まり、キャリアアップのスピードも加速します。
特に中小企業や個人事業主の場合、ダブルライセンス保有者は非常に重宝される人材です。
資格を分けて取得するには時間と労力がかかりますが、実務経験を活かして段階的に取得することで、堅実かつ安定したキャリア構築が可能になります。
長期的には、独立や法人化といった道も視野に入れることができるでしょう。
ゼネコン・電気設備会社での評価
電気工事業界において、ゼネコンや大手電気設備会社では「資格保有者数」が企業の技術力や信頼性を示す指標とされます。
特に施工管理技士は、建設業法に基づいて現場ごとに一定数の配置が義務づけられているため、1級・2級を問わず重宝される存在です。
加えて、電気工事士を併せ持つことで、「設計・施工・管理の三位一体」が実現できる人材として、現場責任者候補や幹部候補としての評価が高まります。
特に大規模プロジェクトを受注する際には、専任技術者や監理技術者の配置が求められるため、資格者の在籍は競争力強化にもつながります。
ゼネコンにおいては、1級電気工事施工管理技士が管理職登用の必須条件となっているケースもあり、資格の有無がキャリアの分岐点となることも珍しくありません。
年収アップ・転職市場での優位性
ダブルライセンスを持つことによる年収アップの効果は非常に大きく、資格手当や職能給が加算されるケースが多く見られます。
たとえば、電気工事士のみ保有者の年収が400〜500万円前後であるのに対し、施工管理技士とのダブルライセンス保持者は600〜800万円超の求人も珍しくありません。
また、転職市場においても、ダブルライセンスは「即戦力」としての評価を得やすく、年齢に関係なく高待遇での採用が期待できます。
特に地方の中堅企業やインフラ関連企業では、施工管理と作業の両方に精通した人材を求めているケースが多く、キャリアの幅が大きく広がります。
以下の表に、資格別の年収目安をまとめました。
| 資格 | 年収の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 電気工事士(単体) | 400万〜500万円 | 現場作業中心。転職はやや限定的 |
| 電気工事施工管理技士(単体) | 500万〜700万円 | 現場責任者・監理技術者として活躍 |
| ダブルライセンス | 600万〜850万円以上 | 管理+実務で高評価。独立も視野 |
このように、将来性や収入面での優位性を考えると、段階的に両資格を取得することは非常に理にかなったキャリア戦略と言えるでしょう。
よくある質問
読者からよく寄せられる疑問に資格の順番や未経験からの挑戦、取得後の働き方など、実際のキャリア選択に直結するリアルな質問に答えます。
Q:電気工事施工管理技士と電気工事士、どっちを先に取るべき?
結論から言えば、未経験や実務経験が浅い方には「電気工事士」の取得を先におすすめします。
理由は、電気工事施工管理技士の受験には一定の実務経験が必要であり、まずは現場での経験が求められるためです。
第二種電気工事士であれば、筆記と技能の両試験がありながらも独学でも合格可能で、取得後は電気工事業に従事することができ、実務経験を積む足がかりになります。
一方、施工管理技士は現場を統括・管理する立場であり、実際に現場作業の流れや課題を理解していないと現実的なマネジメントは難しいです。
そのため、まずは電気工事士として現場に入り、経験を積みながら将来的に施工管理技士を目指すステップアップが現実的かつ確実です。
Q:未経験でも電気工事施工管理技士を目指せる?
未経験から電気工事施工管理技士を目指すことは可能ですが、いくつかの前提条件があります。
まず、1級・2級ともに受験には「電気工事に関する一定年数の実務経験」が必要です。
学歴や資格の有無により、必要な年数は異なりますが、実務経験がゼロの状態では受験資格を満たしません。
そのため、未経験者が最短で施工管理技士を目指すには、電気工事士資格を取得し、電気工事会社などで現場経験を積むルートが一般的です。
2〜5年程度の経験を積むことで受験資格を満たせるケースが多いため、将来的な目標として施工管理技士を掲げつつ、現場経験を積むことが現実的なアプローチです。
また、施工管理補助などのポジションからスタートすれば、働きながら実務経験を積み、受験資格取得を目指すことも可能です。
企業によっては資格取得支援制度を設けている場合もありますので、求人選びの際に注目しておくとよいでしょう。
Q:電気工事士の資格は、電気工事施工管理技士の一次試験免除になる?
電気工事士の資格(第一種・第二種)をもっていてもには電気工事施工管理技士の一次試験免除なりません。
また、電気主任技術者(第一種、第二種、又は第三種)も同様に電気工事施工管理技士の一次試験免除ならないので、一次試験から受ける必要があります。
まとめ
今回の記事では、電気工事施工管理技士と電気工事士と違いについて解説しました。
まずは電気工事士として現場経験を積むことで、将来的に施工管理技士へのステップアップが可能になります。
自分のキャリアプランに合わせて、段階的な資格取得を目指しましょう。
電気工事士や電気工事施工管理技士は、現場を支える重要な資格です。
その一方で、
- 責任が重い割に評価が低い
- 長時間労働が常態化している
- 将来の働き方が見えない
と感じている方も少なくありません。
資格を活かしながら無理なく働く選択肢について、転職・副業の両面から無料で相談を受け付けています。