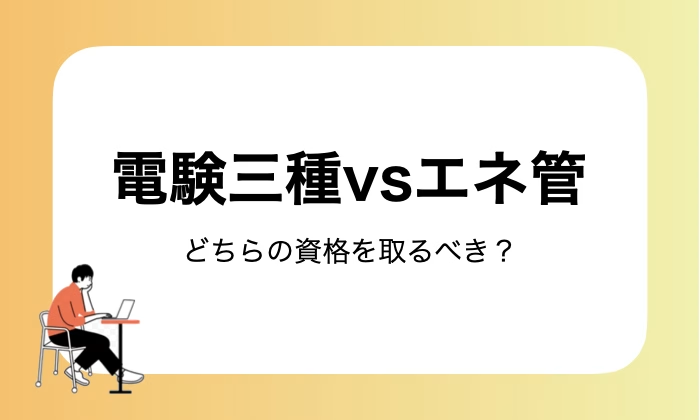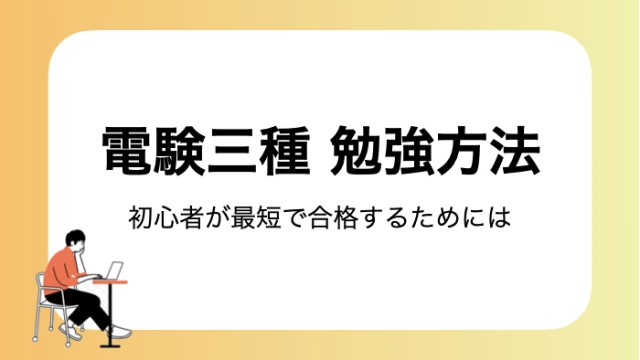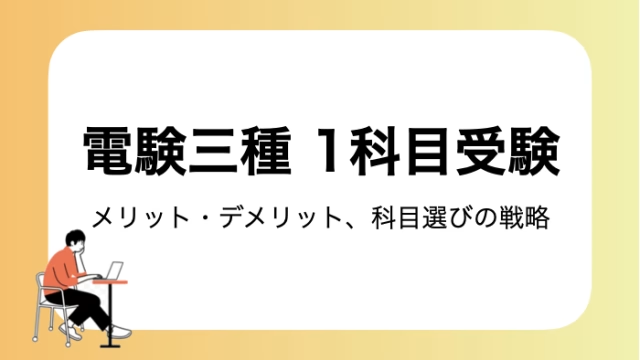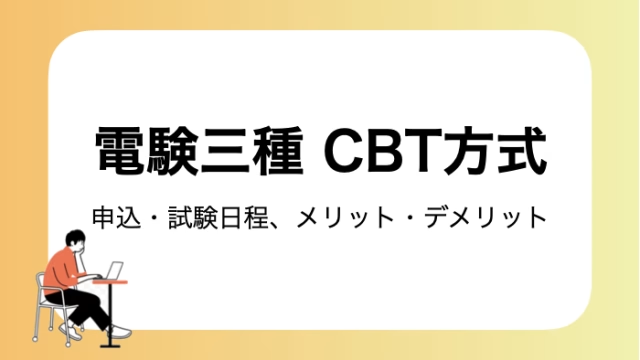電験三種とエネルギー管理士、どちらから資格取得を目指そうかと悩んでいませんか?
資格取得を目指すうえで「どちらの方が難易度が高いのか」「将来性があるのか」が気になって、どちらから勉強すべきか判断できない悩みはよくあります。
そこで、今回は電気主任技術者とエネルギー管理士の違い、難易度、取得の順番、ダブルライセンスのメリットについて解説します。
この記事を読めば、両資格の比較や自分に合った資格選びの判断材料がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
電気主任技術者とエネルギー管理士はそもそもどんな資格?
電気主任技術者とエネルギー管理士は、いずれも工場やビルなどの設備管理に欠かせない国家資格です。
両者は似ているようで役割が異なり、それぞれの職種で求められるスキルや業務範囲も違います。
以下では、資格の役割や業務内容、さらに活躍できる業界について詳しく解説します。
それぞれの資格の役割と業務内容
電気主任技術者は、電気工作物の「保安監督」を行うための資格です。
電気設備の点検・管理を通じて、火災や感電事故などを未然に防ぐ責任を担います。
なかでも「第三種電気主任技術者(電験三種)」は、ビルや工場、商業施設などの低圧・高圧設備(5万ボルト未満)を対象に業務を行うことができる資格です。
受験資格に制限がないため、比較的多くの人が挑戦しやすい国家資格となっています。
一方、エネルギー管理士は、工場などでの電力や燃料といった「エネルギー使用の合理化(省エネ)」を推進する責任者です。
業務内容は、エネルギーの消費量を定量的に管理し、効率化のための改善提案や実施を行うマネジメント業務です。
特に「エネルギー管理指定工場」においては、エネルギー管理士の選任が義務づけられています。
以下に、両資格の役割と業務を比較した表を示します。
| 資格名 | 主な役割 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 電気主任技術者 | 電気設備の保安監督 | 電気設備の点検、運転監視、指示・記録管理、保安業務全般 |
| エネルギー管理士 | エネルギー使用の合理化 | 消費エネルギーの分析・改善、数値管理、省エネ施策の立案 |
このように、電気主任技術者は「電気の安全」に特化しており、エネルギー管理士は「省エネと効率化」に特化した役割であることがわかります。
どちらの資格もインフラ・製造業にとって非常に重要な存在です。
活躍できる業界や職場の違い
電気主任技術者とエネルギー管理士は、いずれも設備に関わる技術者として多くの企業で必要とされる資格ですが、活躍の場には明確な違いがあります。
電気主任技術者は、法令で「一定規模以上の電気工作物」には有資格者の選任が義務付けられているため、電気を扱うあらゆる施設で活躍できます。
たとえば、商業ビル、病院、マンション、データセンター、製造工場、変電所、発電所などが代表例です。
特にインフラを支える業界では常に需要があり、就職・転職にも強い資格といえるでしょう。
一方、エネルギー管理士が活躍する場は、主に大規模なエネルギー消費施設です。
省エネ法により、年間エネルギー使用量が一定以上の工場などは「エネルギー管理指定工場」に指定されており、こうした施設では必ずエネルギー管理士を選任する義務があります。
対象となるのは、自動車・電子機器・食品・化学などの工場、さらにはガス・電力・熱供給といったエネルギー関連業界です。
以下に活躍が見込まれる職場を比較した表を掲載します。
| 資格名 | 主な活躍職場 | 備考 |
|---|---|---|
| 電気主任技術者 | ビル、病院、工場、発電所、データセンターなど | 電気設備を保有するあらゆる施設で選任義務あり |
| エネルギー管理士 | 自動車・電機・食品工場、エネルギー関連企業など | 省エネ法に基づき、一定の施設に選任義務あり |
このように、電気主任技術者は「設備を安全に使う」技術者、エネルギー管理士は「エネルギーを効率よく使う」技術者として、それぞれの専門性が発揮される場が異なります。
両者を取得すれば、より広範な業務に対応できる人材として評価されやすくなるでしょう。
電験三種とエネルギー管理士どっちが難しい?
電気主任技術者(第三種)とエネルギー管理士は、どちらもインフラ・設備系の専門資格として人気ですが、「どっちが難しいのか?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
ここでは、合格率や試験範囲、勉強時間などから両者を比較し、それぞれの難易度を明らかにしていきます。
合格率の比較から見る難易度
まず、試験の難易度を客観的に判断する材料として、合格率を比較してみましょう。
第三種電気主任技術者試験(通称:電験三種)の合格率は、年度によって差はありますが、近年は全体で約10~15%前後と非常に低い水準です。
特に科目合格制度があるにもかかわらず、1年で全科目に合格する受験者は少数派です。
一方、エネルギー管理士試験の合格率は20~30%前後で推移しており、電験三種に比べてやや高めです。
ただし、これは受験者の多くが実務経験者である点や、科目免除制度を利用していることも影響しています。
以下に、最近の合格率の比較表を示します。
| 資格名 | 最近の合格率(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 電験三種 | 10~15% | 全4科目/科目合格制あり |
| エネルギー管理士 | 20~30% | 全4科目/一部免除制度あり |
この表からもわかるように、単純な合格率だけで比較すればエネルギー管理士の方が易しく見えます。
しかし、試験の中身や受験層の違いを加味すると、一概に「簡単」とは言い切れません。
勉強時間と試験内容から見る違い
試験の難易度を判断するうえで、必要な勉強時間や試験範囲も重要な指標になります。
まず電験三種は、「理論」「電力」「機械」「法規」の4科目で構成され、電気工学の基礎から応用までを広範に問われます。
特に数学的な計算が多く、理系未経験者にとってはハードルが高い傾向があります。
合格までに必要とされる勉強時間は、一般的に800〜1,000時間とされます。
一方、エネルギー管理士試験は、「エネルギー総合管理」「電気設備」「熱設備」「法規」の4科目に分かれており、省エネや設備管理の実務寄りの内容が中心です。
数学的な要素はあるものの、電験三種ほど理論計算には偏っていません。
必要な勉強時間は、500〜700時間が目安とされています。
以下に、試験内容と勉強時間の比較表を示します。
| 項目 | 電験三種 | エネルギー管理士 |
|---|---|---|
| 試験科目 | 理論・電力・機械・法規 | 総合管理・電気or熱設備・法規 |
| 出題傾向 | 理論中心/計算問題多い | 実務寄り/知識問題が中心 |
| 必要な勉強時間 | 800~1,000時間 | 500~700時間 |
このように、電験三種は理論の理解と計算力、エネルギー管理士は業務知識と法規への対応力が求められる試験となっています。
「電験三種 エネルギー管理士 どっちが難しい?」の答え
「電験三種 エネルギー管理士 どっちが難しい?」という問いに対する答えは、目的と背景によって異なるというのが正確な回答です。
たとえば、電気の理論や計算が得意な理系出身者であれば、電験三種の方が取り組みやすい可能性があります。
逆に、実務経験が豊富な方や設備管理に携わっている方であれば、エネルギー管理士の方が合格への近道となることもあります。
ただし、一般的な難易度としては、「電験三種の方が難しい」とされるのが通説です。
これは合格率や必要な勉強時間、科目の内容などを総合して判断した場合の傾向です。
さらに、電験三種とエネルギー管理士は、互いに補完しあう関係でもあります。
両資格を取得することで、電気保安とエネルギー管理の両面からの専門性が身につき、キャリアの幅も大きく広がります。
そのため、どちらか一方を選ぶのではなく、将来的に両方を取得する道も視野に入れると良いでしょう。
特に「電験三種を先に取得し、その後エネルギー管理士に挑戦する」という流れが、実務経験や転職市場でも高く評価される傾向にあります。
両方取得するメリットと将来性
電気主任技術者とエネルギー管理士の両資格を取得することで、専門性と実務対応力が飛躍的に高まり、キャリアの幅が広がります。
ここでは、転職市場における評価や年収アップの可能性、ダブルライセンスの具体的な活用方法について解説します。
転職市場における評価
電気主任技術者とエネルギー管理士の両方を持っている人材は、電気管理とエネルギー効率化の両方に精通しているため、転職市場で非常に高く評価されます。
まず、電気主任技術者は電気設備の保安監督者として法令上選任が義務付けられており、電気を扱うあらゆる業界で必要とされます。
一方、エネルギー管理士は省エネ法に基づき、一定規模以上の事業所では選任義務のある資格であり、主に製造業や大型施設の設備管理部門でのニーズが高まっています。
この2つを保有していることにより、法定管理業務の両面をカバーできる人材として企業から重宝されます。
特に、省エネルギーへの関心が高まっている昨今、両資格を持つ技術者は、再生可能エネルギー導入やZEB(ゼロエネルギービル)対応など、先進プロジェクトにも携わりやすくなります。
また、ビルメンテナンス業界やエンジニアリング会社では、現場対応だけでなくマネジメントや顧客提案を担うポジションへの登用も期待され、資格の相乗効果は大きいといえます。
年収やキャリアアップの可能性
ダブルライセンスの保有は、年収アップや昇進のチャンスにもつながります。
以下に、資格ごとの平均年収と両方取得した場合の目安を比較表で示します。
| 保有資格 | 平均年収(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 電気主任技術者(第3種) | 500万〜650万円 | 設備保安・ビル管理系中心 |
| エネルギー管理士 | 450万〜600万円 | 製造・プラント・ビル系中心 |
| 両方取得 | 600万〜750万円 | 管理職登用や外部委託案件あり |
実際には、勤務地や企業規模により差はありますが、両資格を有することで年収600万円以上が見込めるケースも多く、さらに外部委託業務や副業的な収入源を確保することも可能です。
特に、資格手当が充実している企業では、それぞれの資格に対して月1万〜3万円程度の手当が支給されることもあります。
また、将来的には設備全体の管理責任者としての登用や、コンサルタント業務への転身も視野に入ります。
ダブルライセンスの具体的な活かし方
ダブルライセンスの活用方法は、現場だけにとどまりません。
たとえば、以下のような形でキャリアを広げることが可能です。
①工場やビルの設備管理部門での総合管理職
電気・エネルギー両方の知識を活かし、保守計画や省エネ戦略の立案に携わることが可能です。
②エンジニアリング会社での省エネ提案型営業
技術的なバックグラウンドを武器に、電力使用量の削減提案や補助金活用支援などを行うことができます。
③独立して外部委託契約を結ぶ
選任義務があるため、両資格の保有者は複数の施設と契約して収入を得ることもできます(いわゆる「兼任主任技術者」など)。
④自治体や公共施設での入札案件への対応
資格要件として両方の取得が条件になっているケースもあり、受注の幅が広がります。
このように、両資格の取得は単なる資格の足し算にとどまらず、キャリアの選択肢を広げ、専門性と収入面の両方で強力な武器となります。
今後の社会的な省エネ志向の流れを考えると、ダブルライセンスの価値はますます高まっていくでしょう。
電気主任技術者とエネルギー管理士はどっちから勉強すべき?
どちらも電気設備やエネルギー分野に関わる国家資格ですが、試験制度や出題傾向、学習の進めやすさに違いがあります。
ここでは、初学者がどちらから勉強すべきかをテーマに、順番や重複内容、教材の充実度などの視点から解説していきます。
初学者におすすめの順番
初学者が最初に取り組むべきなのは、一般的に電験三種(電気主任技術者)とされています。
まず、電験三種は理論・電力・機械・法規の4科目で構成されており、基礎的な電気理論や機器構造を網羅的に学べます。
この知識はエネルギー管理士試験にも応用が効くため、電験三種を先に勉強しておくと、後々の学習効率が大幅に向上します。
一方、エネルギー管理士は計算問題よりも暗記中心の傾向が強く、省エネ法や設備管理の実務知識が問われます。
そのため、ある程度電気の基礎がある人でないと、単なる暗記に終始してしまい、理解が伴わないことも多くなります。
また、電験三種は年2回(8月と3月)受験機会がある一方で、エネルギー管理士は基本的に年1回しか受験チャンスがありません。
この点でも、先に電験三種に取り組み、基礎を固めてからエネルギー管理士に挑戦するのが現実的です。
学習内容の重複と相乗効果
電験三種とエネルギー管理士の試験内容には重複している分野が多くあります。
これを活かすことで、片方の学習がもう一方の試験対策にもなり、相乗効果が期待できます。
例えば、電験三種の「理論」「電力」「機械」分野で学ぶ電気回路、変圧器、発電機、配電系統などの知識は、エネルギー管理士の「電気設備および機器」「電力応用」などの分野に直結します。
逆に、エネルギー管理士で出題される熱力学やボイラー制御などの分野は、電験三種にはあまり登場しないため、片方にしか役立たない分野も存在します。
したがって、共通分野を効率よく活用しながら、重複しない部分は計画的に個別対策を行う必要があります。
以下に主な重複科目とその内容の相関を表にまとめました。
| 共通分野 | 電験三種 | エネルギー管理士 |
|---|---|---|
| 電気回路 | 理論(直流・交流回路) | 電気設備および機器 |
| 電気機器 | 機械(変圧器・モーター) | 電力応用 |
| 電力供給 | 電力(配電・送電) | 電力応用 |
このように、先に電験三種を学習しておけば、エネルギー管理士試験の学習負荷が減少し、効率的にダブル取得を目指せます。
テキスト・教材の充実度を考慮
テキストや参考書の充実度という点でも、電験三種に軍配が上がります。
市販の書籍だけでなく、通信講座やYouTubeの無料講座、アプリまで、学習リソースが非常に豊富です。
一方、エネルギー管理士については、全体的に教材の数が限られており、特に独学向けの書籍は種類が少ない傾向にあります。
また、法令や省エネ技術に関する出題は年によって傾向が変わることがあり、過去問だけでは対策が難しいという声もあります。
テキストの比較例を以下の表に示します。
| 項目 | 電験三種 | エネルギー管理士 |
|---|---|---|
| 市販のテキスト | 多数あり(シリーズ化も) | 限られた出版社のみ |
| 過去問題集 | 豊富、年度別・分野別あり | 過去10年分など一部 |
| Web教材 | 動画・アプリ多数 | 限定的 |
このように、教材選びに苦労しない点でも、初学者がまず取り組むべきは電験三種といえるでしょう。
充実した教材環境の中で基礎を固め、その後エネルギー管理士に挑戦することで、着実にステップアップできます。
まとめ
今回の記事では、電気主任技術者とエネルギー管理士について解説しました。
どちらを先に取るか迷っているなら、まずは学習環境が整っている電験三種から始めましょう。
実際、電験三種は、取得するだけでも大きな価値があります。
一方で、その価値が十分に評価されるかどうかは、働く環境次第です。
- 今の職場で資格がどう扱われているか
- 将来的にどんな選択肢があるか
- 転職すべきか、副業という道があるか
無理な提案は行わず、電験三種を持つ方向けの選択肢整理を無料で行っています。