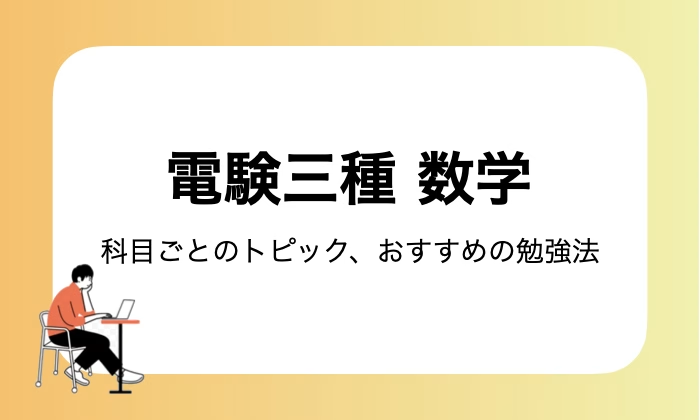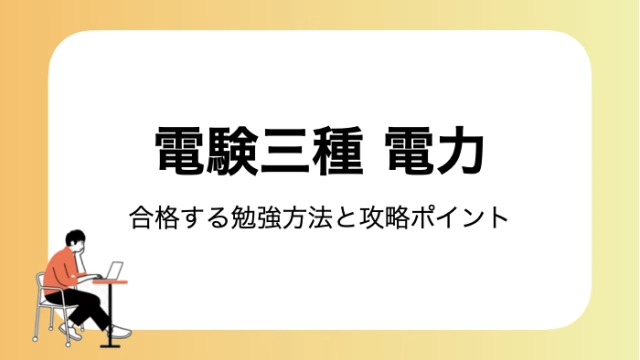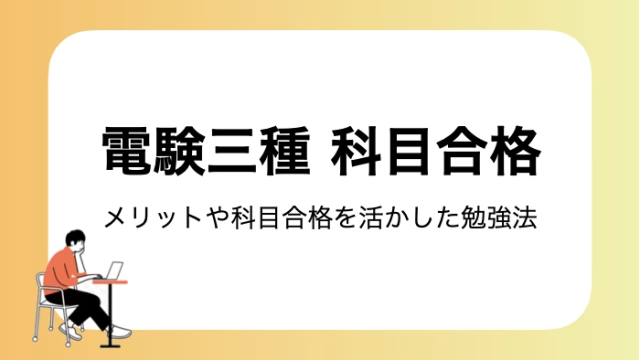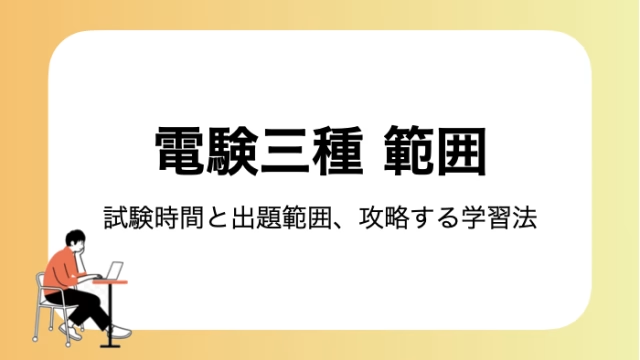電験三種の試験では、全科目において数学的な知識が欠かせません。
特に、「数学が苦手で不安」「どのレベルまで勉強すればいいのか分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では電験三種に必要な数学のレベルや分野、効果的な学習方法について詳しく解説します。
数学に苦手意識がある方におすすめの勉強法も紹介しますので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
電験三種で求められる数学レベルとは
電験三種に合格するために必要な数学のレベルは、「高校1年生程度」とされています。
数学が苦手な方でも、基礎から着実に学べば十分に合格を目指せる内容です。
以下では、どのようなスキルが求められるのかを具体的に解説します。
必要なのは高校1年生レベル
電験三種に求められる数学の範囲は、一般的に高校1年生までに習う数学が中心です。
つまり、文系出身の方や数学が得意でなかった方でも、基礎をしっかり復習することで対応可能な内容となっています。
具体的には、四則演算、分数、指数、三角関数、ベクトル、複素数といった単元が中心であり、それぞれが電気の計算問題に応用されます。
特に、四則演算や分数といった小中学校で学ぶ内容も頻繁に出題されるため、「数学が苦手だから無理」とあきらめる必要はまったくありません。
実際に出題される問題の多くは、公式を理解し使いこなすことによって正解できるものです。
複雑な証明や高等数学的な思考は求められておらず、「使える知識」として高校レベルの数学を運用できることが求められています。
また、通信講座や市販のテキストでも「高校1年レベルまでの復習」に特化した教材が多く出ており、学習環境も整っています。
焦らず、まずは基礎を固めるところから始めましょう。
特別な数学力ではなく、基礎を着実に身につければOK
電験三種で問われる数学力は、いわゆる「応用数学」や「高等数学」ではありません。
必要なのは、基礎的な数式を正しく理解し、計算ミスなく処理する能力です。つまり、公式の暗記とその使い方の習得が鍵となります。
例えば、交流回路では三角関数やベクトルが使われますが、その計算はすべて教科書に載っている基本的なパターンで解けるレベルです。
また、分数や指数は電気理論や電気機器の出題で多く使われますが、特殊な応用問題が出るわけではなく、定型的な問題が中心となります。
さらに、数学が苦手な方でも、インプットとアウトプットを繰り返すことで徐々に理解が進みます。
アウトプットを行う際には、問題集や過去問を繰り返し解くことで知識が定着しやすくなります。
とにかく「解いて慣れる」ことが大切です。
また、最近では「電気主任技術者 数学」対策として、計算問題に特化した参考書やドリルも多数出版されています。
これらの教材を活用することで、限られた時間の中でも効率よく勉強を進められるでしょう。
計算力と論理的な思考が問われる
電験三種の数学では、計算力に加えて「論理的な思考力」が重要です。
これは、ただ公式を覚えるだけでは不十分で、どの場面でどの公式を使うのか、なぜその計算が必要なのかを理解する必要があるからです。
たとえば、電圧・電流・インピーダンスを複素数で扱う問題では、ただ式を当てはめるだけでなく、交流特有の位相の概念を把握しなければ正解にたどり着けません。
ベクトルや三角関数の理解も、こうした論理的思考を伴ってはじめて使いこなせるようになります。
また、出題される問題の多くは、「与えられた条件から必要な値を導く」プロセスで成り立っています。
これは、電験三種が「電気主任技術者」としての実務に即した判断力を問うためです。
したがって、数学の知識は単なる計算のためだけでなく、思考の土台として機能しているのです。
計算力と論理的思考力の両方を鍛えるには、解法をただ暗記するのではなく、問題の意味を理解する学習が必要です。
「なぜその答えになるのか」を意識して問題を解くことが、合格への最短ルートとなるでしょう。
出題される数学分野と頻出トピック
電験三種では、四則演算や分数計算、指数のような基礎的な数学から、三角関数・ベクトル・複素数といった高校数学に登場する応用的な分野まで幅広く出題されます。
これらの知識は、電気回路の計算やインピーダンスの理解に直結しており、実務にも活かされる重要な基礎となります。
四則演算・分数計算・指数
四則演算は「足し算・引き算・掛け算・割り算」の基本的な演算であり、電験三種のあらゆる科目において不可欠なスキルです。
複雑な式を解く際にもこの演算能力が求められ、計算ミスを減らすためには正確性とスピードの両立が必要です。
また、分数計算は特に回路における抵抗の合成や電力計算などで頻出します。
並列接続された抵抗値の合成計算や、電力量の計算で繁分数が使われる場面もあり、分数の通分や約分の正しい理解が必要不可欠です。
指数に関しては、電圧や電流の値を計算する際に多く登場します。
特に指数法則(a^m × a^n = a^(m+n) など)を用いた式変形が問われる場面が多いため、中学~高校初級レベルの指数ルールを正確に理解しておくことが重要です。
これらの基礎的な数学スキルは、ただ解法を暗記するのではなく、手を動かして実際に何度も問題を解くことで初めて身につきます。
演習問題や過去問を活用しながら、確実に定着させていきましょう。
三角関数・ベクトル・複素数
三角関数は、交流回路の解析に欠かせない数学分野です。
電験三種では、sinθ・cosθ・tanθの基本的な関係式や直角三角形における辺の比の活用が問われます。
特に電流と電圧の位相差を求める問題では、三角関数の理解が解答の鍵を握ります。
ベクトルは、「大きさ」と「向き」を持つ量を扱う数学で、交流回路や三相交流系の問題で頻出します。
フェーザ図(ベクトル図)を用いた表現は、複雑な波形の合成や位相の分析に使われ、試験だけでなく実務でも重要なスキルです。
基本的な平面ベクトルの加減、ベクトルの直交性や内積の考え方を理解しておきましょう。
複素数は、電験三種の中でも特に「理論」や「電力」の科目で重要になります。
電圧・電流・インピーダンスなどを「a + bi」の形で表す記号法を用いることで、交流計算が非常にシンプルに処理できるようになります。
このため、複素数の加減乗除だけでなく、共役複素数や絶対値(複素数の大きさ)の概念も学んでおく必要があります。
三角関数・ベクトル・複素数の3分野は、いずれも一度理解すれば電験三種の多くの問題がスムーズに解けるようになります。
苦手意識を持たず、具体例と演習を通じて、確実に使いこなせるようにしましょう。
電気回路計算やインピーダンスの理解に直結
電験三種における数学の目的は、単なる計算力を試すことではありません。
特に理論分野で問われるのは、回路計算やインピーダンスの理解といった、電気の本質にかかわる数学的理解です。
例えば、直流回路ではオームの法則(V=IR)を基本とした電圧・電流・抵抗の関係が問われ、これに加えて並列・直列接続の知識やキルヒホッフの法則の理解が必要になります。
一方、交流回路ではリアクタンスやインピーダンスといった「複素数」を用いた表現が求められ、位相のずれを計算で捉える力が必要です。
また、インピーダンスは抵抗とリアクタンスを合わせた複素数表現であり、「Z = R + jX」で示されます。
この数式が扱えるようになると、交流の電力計算やインピーダンスの合成、電力因数の計算もスムーズに解けるようになります。
つまり、数学的な理解が電気工学の基盤と密接に結びついているのです。
実務においても、機器の選定やトラブルシューティングで数値計算は頻繁に行われます。
そのため、資格取得後も「電気主任技術者 数学」の力は求められ続けます。
試験対策の段階から、電気と数学の関係を意識して学習することが、理解を深めるコツとなります。
各科目ごとに必要な数学の知識
電験三種は4科目で構成されており、それぞれに必要な数学の知識が異なります。
「理論」では複素数や三角関数など高校数学の応用力、「電力」や「機械」では指数やベクトルといった基礎~中級の計算スキルが求められます。
一方で「法規」は比較的計算問題が少なく、対策次第で得点源にできます。
理論:交流回路・複素数・三角関数
理論科目は電験三種の中でも計算問題の比率が最も高く、全体の約8割以上を占めることもあります。
その中でも特に重要なのが、交流回路に関連する数学的知識です。ここでは、複素数・三角関数・ベクトルといった分野の理解が欠かせません。
交流回路では、電圧や電流の大きさと位相の関係を扱います。
これを数式で表現する際に用いられるのが「複素数」であり、電圧Vや電流I、インピーダンスZを記号法(a+bi形式)で表します。
複素数の加減乗除や共役複素数の利用などが問われ、数学的な操作ミスはそのまま失点につながります。
また、位相差を扱う問題では三角関数の活用が必要です。
例えば、cosθを用いて力率を計算したり、sin波形の重ね合わせで波形合成を行うといったケースがあり、単に公式を覚えるだけでなく、図やグラフから意味を読み取る力も必要です。
理論科目は他の3科目の基礎になる部分も多いため、ここでしっかりと数学的理解を深めておくことが合格への近道となります。
電力:指数・分数が中心。基礎知識で対応可
電力科目では、主に発電・送電・変電などの電気供給システムに関する問題が出題されます。
理論に比べて計算問題の比率は約4割程度とやや低めですが、数学の知識が不要というわけではありません。
特に頻出するのが、指数と分数の計算です。
指数は、送電損失やエネルギー量、電力の大きさを表す場面でよく使われます。
指数法則(a^m × a^n = a^(m+n))を使った簡単な計算が求められるので、中学校レベルの内容を正確に理解しておくことが大切です。
また、分数計算は変圧器の変換比率や、電力損失の割合などでよく登場します。
四則演算と組み合わせた繁分数の処理が問われることもあり、基本的なルール(通分・約分)をミスなくこなす練習が必要です。
電力分野は、数学が苦手な方でも基礎をしっかり押さえることで得点できる分野です。
理論のような複雑な計算式は少ないため、まずは基本公式を覚え、簡単な演習問題で反復練習を行うことが効果的です。
機械:分数・ベクトル・制御系の基本も必要
機械科目では、電気機器やパワーエレクトロニクス、自動制御など、実際の電気設備やその制御技術に関連する知識が問われます。
出題範囲が広く、計算問題もバラエティ豊かな内容が含まれています。数学的には分数、ベクトル、三角関数、さらには制御系の基礎までが必要です。
特に、同期発電機や誘導電動機といった回転機器に関する問題では、ベクトル図を用いた電圧や位相角の計算が出題されます。
ここでは、フェーザ表現とその合成によって各種電圧の関係を求める問題が中心となり、ベクトルの加減や三平方の定理が基本ツールとなります。
また、自動制御や論理回路の問題では、真理値表や論理式の変形(ブール代数)など数学的論理の理解が問われることがあります。
高校数学の範囲外と感じる受験者もいますが、基本的なルールさえ覚えてしまえば十分対応可能です。
このように、機械分野は単なる計算だけでなく、図解や概念の理解といった論理的思考力も試されます。
まずは頻出分野の過去問を分析し、得点しやすいパターンから優先的に学習するとよいでしょう。
法規:計算問題は少なめ。得点源として対策を
法規科目は、電気事業法や電気工事士法、技術基準といった法令に関する知識を問う内容です。
計算問題の出題割合は全体の1〜2割程度と少なく、基本的には文章読解や正誤判定、選択問題が中心です。
ただし、まったく計算が出ないわけではありません。
出題される計算は主に電力量の算出や定格容量の計算などで、指数、分数、四則演算といった初歩的な数学力が問われます。
内容としては理論や機械に比べて難易度が低く、正確に計算できれば確実な得点源となります。
法規の数学対策としては、特別な応用力は必要ありません。
むしろ、計算の手順を正確に守り、ミスなく答えを出すことが求められます。
また、条文の内容と計算条件の関係を正しく読み取る力も重要です。
限られた範囲の対策で高得点が狙えることから、数学に自信がない方でも比較的短期間で対策可能な科目です。
過去問に沿ってパターンを押さえ、得点源として活用しましょう。
数学が苦手な人におすすめの勉強法
電験三種の数学は高校1年程度の内容が中心ですが、数学に苦手意識がある人は基礎から段階的に復習することが重要です。
まず自分の現在地を把握し、苦手分野を明確にしましょう。
そのうえで小中学校レベルの計算力を固め、過去問演習や通信講座を活用して実戦力を養うのが効果的です。
まずは自分のレベルを把握する(模試や問題集)
数学が苦手な方にとって最初のステップは、自己分析です。
いきなり電験三種の問題に挑むのではなく、自分がどのレベルの問題まで解けるのかを把握することが、最も効率的な勉強計画の土台になります。
市販の数学問題集や、電験三種向けの入門問題集を使って演習し、どの分野が得意でどの分野が抜けているのかを確認しましょう。
特に「電気主任技術者 数学」において必要なのは、複素数や三角関数などの高校数学に加え、分数や指数といった中学数学の基礎です。
そのため、苦手な単元を放置せず、解けない原因を細かく分解して特定していくことが大切です。
また、模擬試験形式のテストを受けてみるのも有効です。
模試は自分の実力を客観的に測れるだけでなく、試験時間の感覚や解答順の工夫など、実戦的な経験にもつながります。
模試の結果を分析し、苦手を「見える化」することが、無駄のない学習につながります。
小中レベルから基礎を復習
電験三種の試験範囲には高校数学の内容が含まれますが、その土台となるのは小中学校で習う基本的な計算力です。
たとえば、分数の加減乗除、割合の計算、平方根や指数法則などは、試験のあらゆる場面で求められるスキルです。
特に、四則演算の処理速度が遅い場合や、約分・通分で時間がかかるようであれば、最初に取り組むべきはこの基礎部分の強化です。
具体的には、市販の中学数学復習ドリルや、YouTubeなどで無料公開されている講義動画などを活用し、短時間で繰り返し演習することが効果的です。
また、公式の暗記だけでなく「なぜその公式が成り立つのか」といった論理的な理解を心がけることで、他分野に応用が効く柔軟な思考力も育まれます。
これは「電気主任技術者 数学」として求められる論理的思考力にも直結します。
最終的には電験三種の過去問を解くことを目指しますが、その前に「解き方が理解できる状態」にまで基礎力を引き上げることが、遠回りに見えて一番の近道です。
過去問10年分を最低3周
電験三種の試験対策で最も重要なのが、過去問演習です。
なかでも数学的思考を問われる理論・電力・機械の3科目については、過去問を通じて出題傾向と解法パターンを体に染み込ませることが合格の鍵となります。
目安としては、直近10年分の過去問を最低でも3周することをおすすめします。
1周目は理解を重視してじっくり解き、2周目は時間配分や解答手順の効率化に注力、3周目は本番を想定した演習として行うと効果的です。
過去問を解くことで、自分の弱点がより明確になり、重点的に復習すべき分野が見えてきます。また、計算問題では同じような出題パターンが繰り返されるため、回数を重ねるごとにスムーズに対応できるようになります。
重要なのは「解けなかった問題をそのままにしないこと」です。
必ず解説を読み、どこでつまずいたのか、なぜ間違えたのかを分析し、再度同じ問題にチャレンジする習慣をつけましょう。
復習ノートを活用するのもおすすめです。
通信講座の活用も効果的
数学の基礎から応用までを効率よく学びたい場合、通信講座の活用も有力な選択肢です。
特に独学でのモチベーション維持が難しい方や、自己流の学習に限界を感じている方にとっては、プロによるカリキュラムと添削指導が大きな助けとなります。
多くの電験三種対策講座では、数学が苦手な受験者向けに「数学基礎講座」や「理系未経験者向けコース」が用意されています。
これらの講座では、複素数・三角関数・ベクトルなど試験頻出分野を重点的に扱い、動画やテキスト、確認テストを通じて理解を深めていく構成が一般的です。
また、わからない点を質問できるサポート体制がある講座を選べば、疑問をすぐに解消でき、挫折を防ぐことにもつながります。
自分のペースで学習できる通信講座は、時間の制約がある社会人や主婦の方にも適しています。
料金は数万円程度かかりますが、合格までの時間と労力を考慮すれば、費用対効果は高いと言えるでしょう。
信頼できる講座を選び、効率よく合格を目指してください。
よくある質問(Q&A)
電験三種の勉強において、「数学が苦手でも合格できるのか?」「文系出身でも大丈夫か?」「どんな参考書を使えば良いのか?」といった疑問は非常に多く寄せられます。
ここでは、これらのよくある質問に対して丁寧に回答します。
Q:数学ができないと電験三種に合格できませんか?
結論から言えば、数学が苦手でも電験三種に合格することは可能です。
実際、試験で求められる数学の範囲は高校1年生レベルにとどまっており、難解な微積分や高度な線形代数などは出題されません。
主に必要なのは、四則演算・分数計算・方程式・指数・三角比などの基礎的な項目です。
大切なのは、「難しい公式を覚えること」よりも、「基本的な計算を正確に、速くこなせるようにすること」です。
例えば、複素数を使った計算やベクトルの合成では、四則演算の正確さが結果に直結します。
つまり、特別な才能よりも、ミスなく処理するための“基礎力”が試される試験だと言えます。
そのため数学が苦手だと感じる方も焦らず基礎から復習していけば、十分に合格圏に到達できます。
Q:文系出身ですが大丈夫ですか?
電験三種は理系資格というイメージが強いため、文系出身の方にとっては不安が大きいかもしれません。
しかし実際には、多くの合格者が文系出身であり、理系でなくても十分に対応できる資格です。
必要なのは「難しい知識」ではなく、「丁寧に基礎を積み上げる姿勢」です。
数学についても、関数や図形といった内容を“論理的に理解”していけば問題ありません。
文系であることがハンデになるわけではなく、むしろ国語的な読解力や論理的な文章処理能力は、法規や計算問題において有利に働く場合もあります。
また、文系出身の方の中には、「電気系の知識ゼロからスタートして合格した」という成功事例も多く見られます。
最初から完璧を目指すのではなく、小さなステップで「できる」ことを積み重ねていくことが大切です。
自分に合ったペースで取り組めば、誰でも合格を目指すことができます。
Q3. どの参考書を使えばいいですか?
参考書選びは学習効率に大きく影響する重要なポイントです。
特に数学が苦手な方や文系出身の方にとっては、「どこから手をつけてよいかわからない」というケースも少なくありません。
そのような方におすすめなのは、以下の3段階に分けた学習教材の活用です。
まず最初のステップとして、中学レベルの数学ドリル(例:『中学数学をひとつひとつわかりやすく。』)を使って、分数計算や一次方程式といった基礎中の基礎を復習します。
次に、高校数学Iの入門書(例:『チャート式 基礎からの数学I』)で指数・三角比など電験三種に必要な範囲をカバーします。
そして最終段階では、電験三種に特化した問題集(例:『完全マスター 電験三種 計算問題徹底研究』)で実践力を磨きます。
これにより、基礎から応用への橋渡しがスムーズに進み、出題傾向に沿った対策が可能となります。
参考書は、自分の理解度や得意不得意に応じて選ぶことが重要です。
「何となく選ぶ」のではなく、「どの分野の理解を深めたいのか」という目的を明確にして選ぶことで、学習効率が大きく向上します。
まとめ
今回の記事では、電験三種を受験する際に必要な数学について解説しました。
今回お伝えした内容を参考に、ぜひ電験三種の取得を目指して頑張ってください。
実際、電験三種は、取得するだけでも大きな価値があります。
一方で、その価値が十分に評価されるかどうかは、働く環境次第です。
- 今の職場で資格がどう扱われているか
- 将来的にどんな選択肢があるか
- 転職すべきか、副業という道があるか
無理な提案は行わず、電験三種を持つ方向けの選択肢整理を無料で行っています。