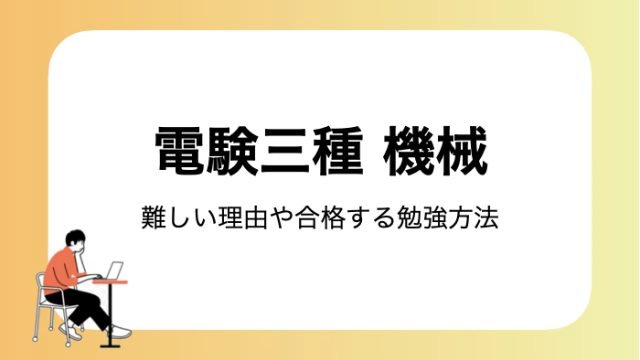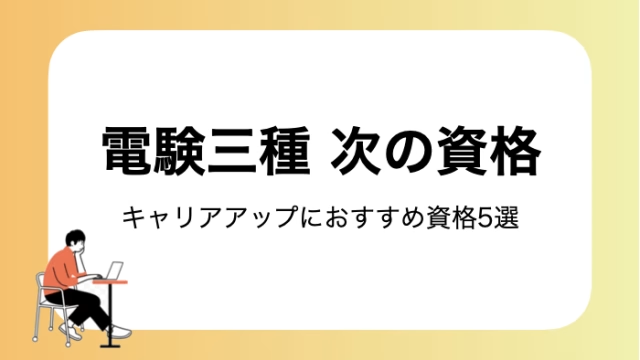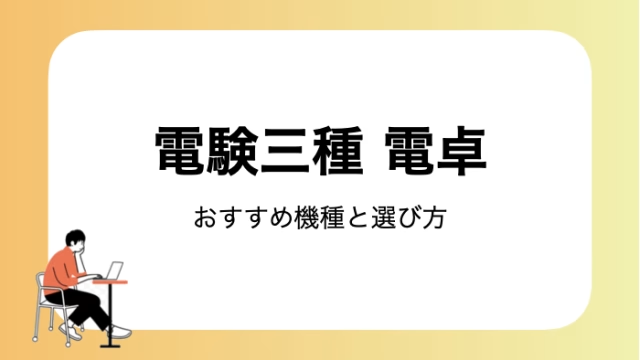「電気主任技術者の常駐って、結局どこまで必要なの?」とご疑問に思っているのではないでしょうか?
そこで、今回は電気主任技術者の常駐に関する基準や必要な勤務時間、法的要件、そして特別高圧設備での対応ルールについて解説します。
この記事を読めば、「常駐」の定義や実務での対応方法、外部委託との違いなどがわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
電気主任技術者の常駐とは
電気主任技術者に求められる「常駐」とは、単にその場にいることではなく、電気設備の安全を確保するための保安監督業務を継続的に行う勤務体制を指します。
常駐の時間については法律上で明確に「○時間以上」と定められているわけではありませんが、一般的な労働時間の基準にならい、週40時間程度の勤務が「常駐」とみなされるケースが多くあります。
これは実際の現場でも広く採用されている目安であり、受電設備に対する即応性を確保する観点からも重要です。
ただし、休日や夜間、盆休みなどは通常の就業時間と異なり、常駐義務の対象外となることもあります。
したがって「常に現場に泊まり込む」といった極端な勤務体制を想定する必要はありません。
電気事業法38条と常駐の法的位置づけ
電気主任技術者の常駐は、電気事業法第38条第4項を根拠としており、自家用電気工作物の設置者には電気主任技術者の選任が義務づけられています。
これは、電気設備の安全確保と事故防止を目的としたものであり、一定規模以上の電気設備を所有・運用する事業者には、資格を持つ電気主任技術者を配置する責任があることを意味します。
ただし、選任の義務がある一方で、「常駐」であるかどうかの要件は、設備の規模や種類によって異なります。
特別高圧以上の設備(22kV以上)では常駐が必要となる場合が多く、それ以下の高圧設備では外部委託や統括体制など柔軟な対応が認められることもあります。
近年では、遠隔監視技術の導入や業務のデジタル化が進み、必ずしも現場に電気主任技術者が常時いる必要はなくなりつつあります。
その結果、「2時間以内に現場へ到達可能な体制」であっても、事実上「常駐」とみなされるケースも増えてきました。
これにより、事業者の実務運用に一定の柔軟性がもたらされつつあります。
電気主任技術者の選任には、法令だけでなく省令や行政指導、そして事業場の実態に即した運用が求められるため、単に「常駐の有無」だけでなく、体制全体の整備が重要となります。
「専任」「兼任」「統括」の違い
電気主任技術者の選任には、「専任」「兼任」「統括」という3つの形態があります。
それぞれ対応できる設備の範囲や、常駐の有無、勤務体制などに違いがあり、選定に際しては設備の電圧・出力・規模などを総合的に判断する必要があります。
まず「専任」は、電気主任技術者が1つの事業場に常駐し、その設備だけに責任を持って保安業務を行う形態です。
常駐が基本となり、週40時間程度勤務することで常時監視体制を確保します。
特別高圧の設備など、リスクの高い現場ではこの専任形態が求められることが多いです。
次に「兼任」は、1人の電気主任技術者が複数の事業場を兼務する形態で、「専任1+兼任5」など一定の上限があります。
この場合、全ての事業場を常駐で管理するのではなく、必要に応じて巡回・点検を行う形になります。
「統括」は、170,000V未満の再生可能エネルギー設備(太陽光・風力・水力など)に対応する形態で、統括事業場に常勤しながら、被統括事業場の監督も行う仕組みです。
被統括事業場には常駐しない代わりに、「2時間以内で到達可能な距離」であることや、非常時に対応できる代理人の確保など、条件付きで柔軟な管理が可能です。
これらの違いを簡潔にまとめた表は以下の通りです。
| 選任形態 | 常駐の有無 | 対応設備の範囲 |
|---|---|---|
| 専任 | 常駐(週40時間程度) | 原則として制限なし(特別高圧含む) |
| 兼任 | 非常駐(巡回・点検) | 高圧以下、5000kW未満(太陽光)等 |
| 統括 | 統括事業場に常勤 | 170,000V未満の再エネ発電設備 |
このように、「常駐」が求められるかどうかは、選任形態と設備内容によって大きく異なります。
事業場の保安体制を設計する際には、これらの違いを理解し、最も適切な形態を選ぶことが求められます。
自社選任か外部委託か?最適な選任方法とは
電気主任技術者の選任においては、自社内で専任するか外部に委託するかの判断が重要です。
設備の規模や構成、運用体制などに応じて、どちらの方式が適しているかを見極めることが、コスト・保安品質の両面で有効な選任に繋がります。
設備規模・点数・要件に応じた選任パターン
電気主任技術者の常駐を必要とするか否かは、設備の規模や点数、電圧区分、そして法的な保安管理要件に大きく影響されます。
たとえば、特別高圧設備を持つ大規模工場やデータセンターでは、常駐の上での専任が求められるケースが多いですが、その一方で、中小規模の需要設備や再エネ発電設備などでは常駐義務がなく、電気主任技術者が常駐しない体制での運用が可能です。
これにより管理の柔軟性が高くなり、外部委託という選択肢も現実的になります。
選任形態には以下のような分類が可能です。
| 選任形態 | 主な適用場面 | 備考 |
|---|---|---|
| 自社専任(常駐) | 大規模な事業場や特別高圧受電設備 | 週40時間以上の勤務が原則 |
| 自社専任(非常駐) | 統括管理が可能な複数拠点 | 2時間ルールなどへの対応が必要 |
| 外部委託 | 再エネ発電所、小規模設備など | 外部管理技術者が要件を満たす必要あり |
企業としては、単に「常駐か否か」で判断するのではなく、保安レベル・コスト・技術者確保の実現性など複数の観点から最適な選任方法を選ぶ必要があります。
管理技術者による外部委託の条件
電気主任技術者を外部委託する場合には、委託先の管理技術者が法令で定められた条件を満たす必要があります。
これは単なる第三種電気主任技術者の資格保有だけでは不十分であり、対象設備に対応可能なスキル・実績・体制が整っているかが問われます。
たとえば、再エネ発電設備のように全国各地に分散している場合、常駐は現実的ではないため、複数の被統括事業場をまとめて管理する「統括管理方式」が採られます。
この場合、管理技術者は週40時間、統括事業場に常勤していなければならず、また緊急時に2時間ルールに従って対応できる体制も整備する必要があります。
外部委託を活用するにあたっては、以下のような点をチェックしておくことが重要です。
| 委託時の確認項目 | 内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 主任技術者の資格区分 | 設備の電圧に適合しているか | 第三種では高圧までしか対応不可 |
| 管理技術者の専任体制 | 統括事業場で週40時間勤務しているか | 電気事業法38条により義務 |
| 対応可能時間 | 2時間以内に現地到着できるか | 常駐しない場合の必須要件 |
また、近年は再エネの増加により、第三種電気主任技術者の活躍の場が拡大しているという点も見逃せません。
設備規模と選任要件に応じて、外部委託を柔軟に活用することで、人材不足やコストの課題を乗り越えた事例も多く見られます。
最終的には、自社の設備内容・拠点数・運用体制などを総合的に評価し、「どの形態が最も合理的で安全な保安管理を実現できるか」を基準に、選任方法を検討すべきです。
まとめ
今回の記事では、電気主任技術者の常駐について解説しました。
常駐の必要性は設備規模や運用体制により異なります。
誤解や思い込みで選任方法を決めるのではなく、法令や実態を正しく把握し、自社に最適な対応を検討しましょう。
実際、電験三種は、取得するだけでも大きな価値があります。
一方で、その価値が十分に評価されるかどうかは、働く環境次第です。
- 今の職場で資格がどう扱われているか
- 将来的にどんな選択肢があるか
- 転職すべきか、副業という道があるか
無理な提案は行わず、電験三種を持つ方向けの選択肢整理を無料で行っています。