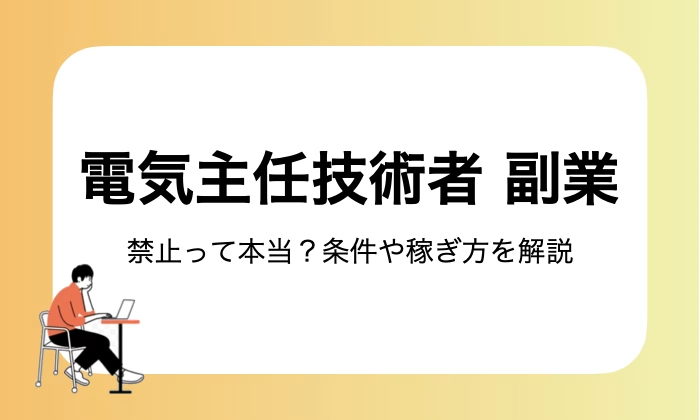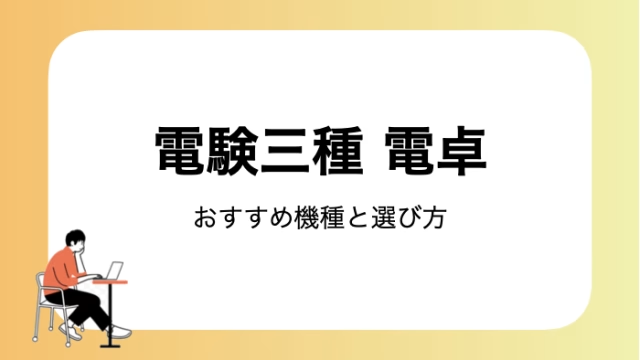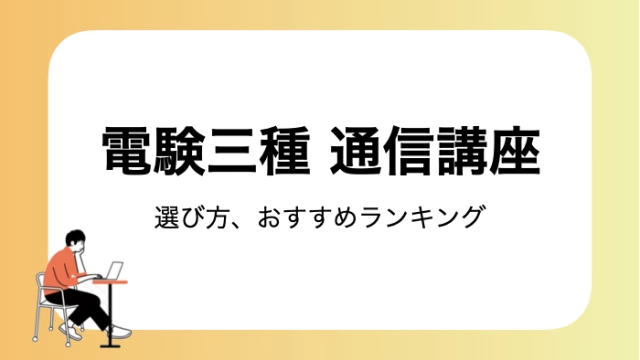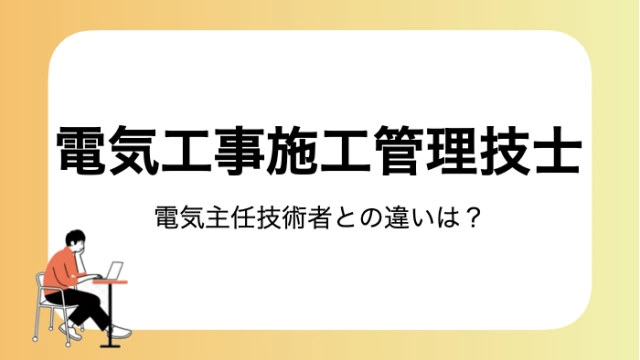副業したいけど「電気主任技術者は副業禁止」と聞いて不安…ということはありませんか?
そこで、今回は電気主任技術者の副業が本当に禁止されているのかどうか、所属先や働き方別に解説します。
この記事を読めば副業が可能なケースや注意すべきルール、実際にできる副業の種類がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
電気主任技術者の副業は本当に禁止されているのか?
副業を検討する電気主任技術者にとって「禁止されているのでは?」という疑問は非常に重要です。
ここでは、法的根拠や内規の条文から読み取れる解釈、そして経済産業省の実務的な運用まで詳しく解説します。
法的な根拠と内規(主任技術者制度の解釈及び運用)
電気主任技術者の副業に対する制約は、主に経済産業省が定める「主任技術者制度の解釈及び運用」に基づいています。
とくに注目されるのが「規則52条第2項」の内容であり、個人事業主として活動する電気主任技術者の副業について、以下のような文言が示されています。
保安管理業務の計画的かつ確実な遂行に支障が生じないことを担保するため、保安管理業務の内容の適切性及び実効性について厳格に審査するとともに、個人事業者が他に職業を有している場合には審査にあたり特に慎重を期することとする。
この条文からわかるのは、「副業・兼業が全面的に禁止されているわけではない」ものの、非常に厳しい審査があるということです。
とくに、保安管理業務の実効性に影響を与えると判断されれば、副業が認められない可能性があります。
また、法人に所属する場合でも「保安業務担当者は、保安管理業務以外の職務を兼務しないこと」というマネジメントシステムの規定があります。
つまり、雇用形態によって制限の程度が異なり、すべてのケースで一律に禁止されているわけではないことがわかります。
「電気主任技術者 副業禁止」は誤解?文言の真意を読み解く
「電気主任技術者 副業禁止」というキーワードで検索されることが多く、あたかも副業が法律で禁止されているような印象を受けがちですが、実際には誤解による部分も多いのが実情です。
先述の規則52条第2項は「慎重を期すこと」とされており、「禁止する」と明記されているわけではありません。
つまり、審査のハードルは高いものの、条件さえ満たせば副業は可能という立場です。
ただし、実際に副業が認められるかどうかは、以下のような要素によって判断されます。
| 判断要素 | 副業許可の影響 | 具体的な確認事項 |
|---|---|---|
| 業務時間 | 業務遂行に支障が出るとNG | 副業の拘束時間と本業との両立 |
| 業務内容 | 保安管理業務以外なら許容される可能性あり | 業務の類似性や競合リスク |
| 体制・実績 | 業務管理能力が問われる | 業務報告体制や過去の運用履歴 |
このように、制度上は「原則禁止」ではなく「慎重に審査される」という位置づけであるため、適切な手続きや業務体制を整えれば、一定の条件下で副業は可能です。
経済産業省の見解と実務上の運用
経済産業省は「電気主任技術者制度Q&A」などを通じて、副業・兼業に関する補足説明を公開しています。
そこでは、副業が全面禁止でないことが改めて示されており、制度の趣旨としてはあくまで「保安業務に支障を与えない限り認める」という立場であることが明らかです。
しかし、実務上は所轄の産業保安監督部によって判断基準に差がある場合もあり、同じ条件でも一部地域では通りやすく、別の地域では厳格に却下されることもあります。
このため、副業を検討する際には、個別に事前相談を行うことが極めて重要です。
また、現場では副業をしている電気主任技術者も一定数存在し、特に再エネ施設の遠隔点検や技術講師といった「低負荷・非競合」な副業が選ばれる傾向にあります。
こうした実例からも、副業は制度的に不可能というわけではないことが伺えます。
副業を行う場合は、以下の点を押さえておくとよいでしょう。
- 就業規則や所属組織のマネジメントシステムを確認
- 保安業務との両立可能性を具体的に示す体制を用意
- 経済産業省や保安監督部の最新ガイドラインを参照
これらを前提にした上で準備を進めれば、電気主任技術者でも法令を順守しながら副業を実現できる可能性があります。
勤務先による違い|副業が認められるケースと制限されるケース
電気主任技術者が副業を行う際は、所属する勤務先によって許可の有無や制限内容が大きく異なります。
ここでは「個人事業主」「電気保安法人」「一般企業・ビルメン」の三つの勤務形態ごとに、副業が認められる条件や注意点を詳しく解説します。
個人事業主・フリーランスとしての活動制限
個人事業主として電気主任技術者業務を請け負っている場合、副業に関しては特に厳しい制限があります。
根拠となるのは、経済産業省の「主任技術者制度の解釈及び運用」における規則52条第2項です。
この条文では、個人事業主が副業を行う場合、「保安管理業務に支障が出ないよう特に慎重を期す」と明記されています。
これはつまり、副業自体が直ちに禁止されているわけではないものの、業務の実効性を脅かすような副業は認められないという厳しい立場です。
副業の審査においては、「本業の業務遂行能力」「対応体制」「副業内容」「就業時間の重複」などが細かくチェックされます。
たとえば、平日日中に拘束される副業であれば、緊急対応が求められる保安管理業務に支障が出ると判断される可能性があります。
また、実際のところ産業保安監督部が承認するかどうかの判断には個別性が強く、地域差や審査官の見解にも左右されやすいのが現状です。
| 審査ポイント | 副業への影響 | 補足 |
|---|---|---|
| 副業時間帯 | 本業と重なる場合NG | 深夜・休日中心なら可能性あり |
| 副業内容 | 同業・競合の場合リスク高 | 教育・執筆は許可されやすい |
| 体制整備 | 緊急対応手段がなければ否認 | 当番制や連絡体制が必要 |
こうした点を踏まえると、個人事業主の電気主任技術者が副業を始めるには、実務体制の整備や事前相談、詳細な業務計画の策定が不可欠です。
電気保安法人に属する場合の規定
電気保安法人に在籍する電気主任技術者の場合、副業については社内規定と内規に基づく厳格な制限があります。
主任技術者制度の運用上、保安業務を担当する技術者に対しては「保安業務以外の職務(電気工作物の保安に関するものを除く)を兼務しないこと」という明確な方針が示されています。
これにより、実務上は副業が認められないケースが多く見られます。
ただし、副業の可否は一律ではなく、「保安業務を担当していない」「内部研修や事務職に従事している」などの特殊な立場であれば、会社内で許可を得て副業できる場合もあります。
また、電気主任技術者とは直接関係しない業務であれば、業務時間外に限り認められることもあるため、社内ルールの詳細な確認が不可欠です。
| 所属形態 | 副業可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 保安業務担当者 | 原則禁止 | 業務優先のため副業不可 |
| 事務・技術支援担当 | 条件付きで可 | 社内申請が必要 |
| 副業内容が教育・執筆 | 場合により可 | 勤務時間外・非競合であれば容認されることも |
このように、電気保安法人においては、本業と副業の線引きが厳格であり、申請プロセスやリスク管理体制を整えていない場合、副業はほぼ不可能だと考えておくべきです。
一般企業・ビルメン勤務での副業許可の実情
一般企業やビルメンテナンス会社、商業施設などに常駐する電気主任技術者の場合、副業に対する制約は比較的緩やかです。
副業の可否は「会社の就業規則」や「労務管理方針」によって異なりますが、働き方改革の流れから副業を容認する企業も増えてきているのが現状です。
とくに、電気主任技術者が本業の勤務時間外に行う「執筆活動」「講師業務」「リモート点検支援」などの非競合業務については、申請をすれば許可されるケースが多いです。
実際、ビルメン会社などでは就業規則で副業に関する申請ルールが整備されており、事前申告や承認制を取る企業が主流になりつつあります。
ただし、副業が原因で本業に支障が出たり、情報漏洩などのリスクが生じた場合には懲戒処分の対象となる可能性もあります。
そのため、以下の点を守ることが重要です。
| 副業時の注意点 | 内容 | リスク回避策 |
|---|---|---|
| 就業規則の確認 | 副業禁止規定の有無を確認 | 人事部に確認・相談 |
| 申請の有無 | 無許可で行うと問題に | 必ず社内申請を行う |
| 業務内容 | 同業他社との競合行為はNG | 非競合分野に限定する |
一般企業に所属する電気主任技術者にとって、副業は現実的な選択肢となり得ます。
ただし、あくまで「副業が本業に影響しないこと」が前提となるため、勤務時間、内容、会社への報告などをきちんと整えておくことが成功の鍵となります。
電気主任技術者に人気の副業10選
電気主任技術者の専門性は副業でも高く評価され、多様な働き方を実現する手段となっています。
ここでは、特に人気の高い副業を10種類紹介し、それぞれの特徴やメリット、注意点を具体的に解説します。
電験試験対策講師(予備校・大学・塾)
電験三種や二種の取得を目指す受験生向けに、講師として指導する副業は非常に人気があります。
予備校や資格学校では講義形式、塾やオンラインスクールでは個別指導形式でのニーズも高く、自身の試験対策経験を活かせる点が魅力です。
勤務時間が平日夜間や休日に設定されることが多く、常勤職と両立しやすい点も特徴です。
報酬は1コマ(90分)で5,000円〜10,000円程度が相場で、経験者や合格実績のある講師はより高額の報酬も期待できます。
また、電験に関する模擬試験の作成や解説資料の執筆といった業務も含まれることがあります。
実務経験を踏まえた講義内容は、他の講師との差別化要因となるため、受験対策に特化したスキルを磨くことで継続的な副業が可能です。
ブログやYouTubeなどの情報発信
専門知識をもとにした情報発信は、近年特に注目されている副業手段です。
電気主任技術者としての知識や試験対策、実務ノウハウをコンテンツにして発信することで、広告収益やアフィリエイト収入を得ることができます。
ブログの場合、記事内容を蓄積していくことで中長期的な収益源となり、1記事あたり数百円から数千円の収益が見込まれます。
YouTubeでは講義動画や設備解説、実務の現場紹介などが人気です。
登録者数や再生回数に応じた広告収益が発生する仕組みで、特に顔出し不要なスライド動画形式は初心者にも始めやすいでしょう。
情報発信は副業の自由度が高く、継続性と拡張性がある点がメリットです。
一方で、収益化まで時間がかかることや、SEOや動画編集といったスキルの習得が必要になる点には注意が必要です。
クラウドソーシングでの設計業務
クラウドワークスやランサーズなどのプラットフォームでは、「配電盤設計」や「変電設備の回路図作成」などの案件が多数掲載されています。
特にCADが使える電気主任技術者は重宝され、図面作成スキルがある場合は安定して案件を受注できます。
報酬相場は案件内容により異なりますが、1案件あたり2万円〜10万円程度が一般的です。
フルリモートで対応できる案件が多いため、空き時間を有効に使いやすい副業形態でもあります。
受注にあたっては、ポートフォリオや実務経歴の提示が求められる場合があるため、事前に資料を準備しておくとスムーズです。
また、クラウドソーシングは契約面のトラブルも起こりやすいため、業務内容や納期、報酬の条件を明文化することが重要です。
外部選任や遠隔監視対応の点検業務
外部選任による保安点検業務は、電気主任技術者資格の典型的な副業の一つです。
対象施設に月1〜2回巡回し、点検・報告を行うスタイルが多く、定期的な収入が見込めます。
1案件あたり月3万円〜5万円が相場とされ、2〜3案件掛け持ちするだけで月10万円超の副収入を実現可能です。
最近では、遠隔監視システムを活用した点検も増加しており、現場に常駐せずに対応できるケースもあります。
特に太陽光発電設備では、監視システムの導入が進んでいるため、PCやスマホで異常検知・報告作業を行う副業スタイルも現実的になっています。
ただし、点検業務は「選任」の扱いになるため、実務経験や報告書作成スキルが求められます。
また、産業保安監督部の承認を必要とする場合もあるため、事前確認が必要です。
再エネ関連設備の保守管理
太陽光や風力などの再生可能エネルギー設備の普及により、電気主任技術者の副業市場も拡大しています。
特に小規模太陽光発電所やメガソーラー設備における定期点検やトラブル対応、報告書作成業務が代表的です。
これらの案件は、月1回程度の巡回や、パネルの目視点検、発電状況の確認といった内容が中心で、物理的負担も少ない点が魅力です。
1件あたりの報酬は2万円〜4万円程度が多く、複数拠点を担当することで安定収入が期待できます。
また、再エネ関連の企業は副業者の受け入れに前向きな傾向があり、業務委託契約で柔軟に働ける環境が整っている場合もあります。
省エネ補助金の申請支援など、コンサルティング要素のある業務も副次的に発生するため、スキルの幅を広げたい方にも適しています。
法定点検の立ち会い(スポット案件)
法定点検の立ち会い業務は、比較的短時間で完了するうえに報酬単価が高く、電気主任技術者の副業として人気です。
スポット案件として単発で依頼されることが多く、定期契約に縛られない働き方を望む人には特に適しています。
仕事内容は、第三者機関による年次点検や定期検査の際に、現場の状況を確認し、必要に応じて技術的な補足を行うものです。
対応施設はオフィスビル、工場、太陽光設備など多岐にわたり、点検日が事前に決まっているためスケジュールの調整がしやすい点も魅力です。
報酬の目安は半日で1万5千円~3万円、1日拘束の場合で4万円程度のケースもあります。
業務委託契約となることが多く、事前に契約条件や保険の有無などをしっかり確認しておくことが重要です。
書籍・参考書の執筆
自身の知識や経験をもとにした書籍・参考書の執筆も、電気主任技術者の副業として注目されています。
電験三種や二種の試験対策に関する書籍、実務に即したハンドブック形式の解説書など、ニーズは多岐にわたります。
出版社との直接契約だけでなく、近年ではAmazon Kindleなどを活用した電子書籍の自費出版も広がっており、専門性を活かした個人出版も可能になっています。
報酬体系は印税収入(一般的には売上の5~10%)か、原稿料として1文字1~3円程度が相場となります。
文章力や構成力は求められるものの、一度出版した書籍が長期的な収入源となる可能性もあり、時間をかけてじっくり取り組む副業として適しています。
試験合格者の体験談や勉強法をまとめた入門書は特に需要が高い傾向にあります。
技術コンサルティング
豊富な実務経験を持つ電気主任技術者は、企業や工場の電気設備に関する技術コンサルタントとしての活動も可能です。
相談内容は多岐にわたり、設備更新の計画立案、配電設計の最適化、エネルギー効率の改善、法令対応などを含みます。
特に中小企業では社内に十分な技術者がいないケースが多いため、外部の有資格者に対するニーズが高まっています。
契約形態はスポット契約から月額顧問契約まであり、報酬も1時間あたり1万円以上、月額数十万円に達することもあります。
コンサルティングの経験がない方でも、初回は現地調査や現状分析といった簡易的な業務から始めることで、徐々に信頼を構築できます。専門性の高い分野で副業としての希少価値を高めたい方にとって有力な選択肢となります。
電気工事監督のスポット業務
電気設備の設置・改修工事において、施工管理や現場監督を担うスポット業務も副業先として人気があります。
建設業法に基づく施工管理技士の資格は不要な場合も多く、電気主任技術者としての技術的知識や安全管理経験が評価されるケースが増えています。
内容は、施工現場での図面確認、工事の進捗チェック、安全指導、完工後の試験立ち会いなどが中心で、プロジェクト単位での契約になることが一般的です。
報酬は日給ベースで2万円~4万円が目安となります。
ただし、工事現場は突発的な対応や休日対応が求められることもあるため、自身のスケジュールや体力面と相談しながら選定する必要があります。
スポット業務で実績を積めば、継続依頼や紹介も期待できる副業スタイルです。
中小企業の点検サポート
中小規模の事業所や店舗などでは、電気主任技術者の外部委託が難しいケースもあり、簡易的な点検や電気設備の相談を担える人材が不足しています。
そのようなニーズに応える形で、スポット的に点検や助言を行う副業も注目されています。
内容としては、分電盤や照明設備の状態確認、絶縁抵抗測定、老朽設備の更新アドバイスなどがあり、法定点検に該当しない範囲でも実務経験を活かせます。
依頼者との直接契約となるケースも多く、柔軟な料金設定や継続契約がしやすい副業です。
報酬は1回あたり1万円~3万円が多く、移動範囲が狭い地域密着型の働き方をしたい人には向いています。
副業としての社会貢献性も高く、信頼性を武器に口コミによる集客も期待できる分野です。
副業・フリーランスを始める前のチェックリスト
副業やフリーランスとしての活動を検討している電気主任技術者は、法令や企業ルールに違反しないよう、事前にいくつかの重要な項目を確認しておく必要があります。
ここでは、スムーズかつトラブルのない副業開始に向けて、確認すべきポイントを網羅的に解説します。
所属企業の就業規則と承認手続き
電気主任技術者が副業を始める際、最初に確認すべきは所属企業の就業規則です。
特に正社員として常駐している場合、副業を禁止している企業や、事前承認を求める企業も少なくありません。
仮に就業規則で副業が認められていたとしても、電気主任技術者は「選任」の立場にあるため、企業としても業務への影響を慎重に判断する必要があります。
副業を希望する場合は、直属の上司や人事部門に相談し、所定の手続きを経ることが不可欠です。
申請時には、副業の内容、勤務時間、報酬の有無などを明記した書類の提出を求められることが多くなっています。
また、口頭での確認だけでなく、書面による承諾を得ることで後のトラブルを防止できます。
とくにビルメンテナンス業界や病院勤務などの現場では、安全管理上の観点から副業を制限する企業も存在するため、業種・業態によって規定内容にばらつきがある点にも注意が必要です。
実務経験と必要書類の準備
電気主任技術者としてフリーランスや副業で外部選任を受ける場合、最低でも3年以上の実務経験が求められます。
これは電気事業法に基づく条件であり、業務委託契約を結ぶ際にも重要な判断材料となります。
よって、これまでの業務実績を客観的に示す書類をあらかじめ用意しておくことが重要です。
準備すべき書類には、以下のようなものが含まれます。
| 書類名 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 実務経歴証明書 | 選任先に提出する経験年数を示す書類 | 前職の上司や所属企業からの記載が必要 |
| 点検実績の記録 | 過去に担当した設備の点検・報告履歴 | フォーマットは自由だが記録性が求められる |
| 保有資格証の写し | 電験三種以上の資格保有証明 | 原本提示を求められる場合もあり |
書類の不備や記載内容の曖昧さは信頼性の低下につながるため、正確で明確な情報を整えておくことが案件獲得の鍵となります。
契約内容と賠償責任保険の確認
副業やフリーランスとして活動する際には、業務委託契約を結ぶケースがほとんどです。
そのため、契約書の内容を事前に十分に確認し、不利な条件や曖昧な条項がないかをチェックすることが重要です。
特に、トラブル発生時の責任範囲や報酬の支払い条件、契約解除のルールなどを把握しておく必要があります。
また、電気主任技術者は高電圧設備を扱う責任のある業務が多く、万が一の事故や損害発生に備えて、賠償責任保険への加入が推奨されます。
業務中に発生した損害に対して個人で賠償義務を負う可能性もあるため、保険に加入することで安心して業務に取り組めます。
以下は、確認すべき契約・保険のポイントです。
| 項目 | 確認内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 契約条項 | 業務内容、報酬、損害賠償の範囲など | 不明確な部分は事前に質問する |
| 契約期間 | 契約の更新・終了条件 | 自動更新条項の有無を確認 |
| 保険加入 | 賠償責任保険の加入有無 | 個人での加入が必要なケースも |
保険は民間の損害保険会社で年間1万円〜3万円程度から加入でき、特に外部選任や巡回点検業務を行う場合には必須といえます。
トラブル防止のための注意点
副業・フリーランスとして活動するうえで、最も避けたいのが顧客とのトラブルです。
契約書に基づく業務遂行は当然ながら、コミュニケーションや対応スピードも信頼獲得には欠かせません。
とくに電気主任技術者としては設備トラブルや不具合時の対応責任が重く、契約内容を超えた要求に発展する可能性もあります。
トラブル防止には、以下のようなポイントを意識しましょう。
- 初回契約時に業務範囲・責任範囲を明確に伝える
- 見積書・作業報告書などのドキュメントを都度作成
- メールやチャットなどの記録に残る手段でやり取り
- 不明点やリスクについては事前に説明・相談する
また、点検や設計業務などで法令遵守が求められる場合には、最新のガイドラインや内規の把握も欠かせません。
特に「主任技術者制度の解釈及び運用」に関する更新があれば即時対応し、常に適切な運用を行うことが信頼維持につながります。
副業を軌道に乗せるには単に技術力だけでなく、「誠実な対応」や「透明性のある業務運営」が鍵となります。
案件の探し方と継続受注のコツ
副業やフリーランスとして活動する電気主任技術者にとって、継続的な案件の確保は安定した収入と信頼構築に直結します。
ここでは、案件を効率的に見つける方法と、継続して受注を得るための工夫について解説します。
専門エージェントやマッチングサイトの活用
電気主任技術者が副業やフリーランスで案件を獲得するうえで、専門エージェントや業務マッチングサイトの利用は非常に効果的です。
近年では電気・設備系技術者に特化した人材紹介会社や、技術士・建築士などの有資格者向けの案件紹介サイトが多数存在し、単発の点検業務から長期契約まで幅広い案件が掲載されています。
以下は代表的なサイトやサービスの例です。
| サービス名 | 特徴 | 対応職種 |
|---|---|---|
| 建職バンク | 建設系専門の人材紹介サービス | 電気主任技術者、施工管理技士など |
| クラウドテック | フリーランス向け案件の豊富さが特徴 | ITエンジニア、設計士、技術者など |
| Bizlink | 士業・資格者向けのプロ契約サイト | 技術士、建築士、電気技術者など |
マッチングサービスを利用する際は、プロフィールに実績や資格、対応可能な業務範囲を明確に記載しましょう。
また、対応可能エリアや稼働可能時間帯を詳細に設定することで、受注率が高まります。
案件への応募時には、カスタマイズした提案文を用いると選考通過率が向上します。
元勤務先や業界ネットワークの利用
新規開拓だけでなく、過去に所属していた会社や協力会社、設備関連の同業者ネットワークを活用することも有効です。
特に電気主任技術者は、専門性が高いため、一度信頼関係を築いた関係先からはリピート発注が発生しやすい傾向があります。
退職時に良好な関係を維持しておけば、「点検業務の一部だけを委託したい」「資格者が不足しているから相談したい」といった相談が来る可能性が高まります。
中小企業や地方の工場では資格保有者の確保が慢性的な課題となっており、副業・フリーランスの技術者の存在は非常に重宝されます。
また、各種電気工事業者団体や電気保安協会の研修、セミナーなどを通じた横のつながりも、案件紹介や情報交換に役立ちます。
SNSやオンラインコミュニティでの発信を行い、顔とスキルを可視化することも、紹介されやすくなる要因です。
実績の見せ方と信頼の築き方
案件を継続的に受注するためには、実績を「見える形」で提示することが重要です。
過去に担当した施設の種類、対応した設備容量、保守点検の頻度、緊急対応の実績などを具体的にまとめたポートフォリオや実務履歴を作成し、クライアントに提示できる状態にしておきましょう。
特に、初回契約時には「この人に任せて問題ない」と判断してもらうための客観的な情報が求められます。
資格証明書、実務経歴、点検報告書のサンプルなどがあれば、説得力が高まります。
また、信頼構築には納期の厳守、丁寧な報告書の提出、適切なコミュニケーションが欠かせません。
トラブルが発生した場合にも、迅速に報告・相談する姿勢が再依頼へとつながります。
以下のような「信頼構築のポイント」を意識しましょう。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 実績の提示 | 業務範囲、対応設備、期間などを明示 | ポートフォリオや履歴書形式で可視化 |
| コミュニケーション | 報告・連絡・相談を丁寧に | メールやチャットで履歴を残す |
| レスポンスの速さ | 問い合わせ対応や見積もり提出を迅速に | 信頼度が大きく向上 |
これらの積み重ねにより、「またお願いしたい」と思われる存在となり、単発案件が長期契約へとつながる可能性が高まります。
まとめ
今回の記事では、電気主任技術者の副業について解説しました。
副業を始める際は、勤務先の就業規則や法令、内規を事前に確認し、トラブルを避けるためにも必ず許可を得てから行動に移しましょう。
実際、電験三種は、取得するだけでも大きな価値があります。
一方で、その価値が十分に評価されるかどうかは、働く環境次第です。
- 今の職場で資格がどう扱われているか
- 将来的にどんな選択肢があるか
- 転職すべきか、副業という道があるか
無理な提案は行わず、電験三種を持つ方向けの選択肢整理を無料で行っています。